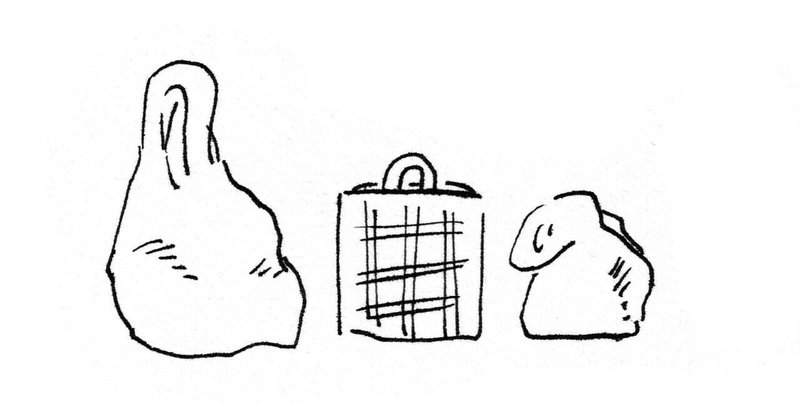
超短編小説 文化的スーパーマーケット
noteを始めたばかりの頃からずっと大好きで、すべての記事を読ませていただいている みたかの小さなプリン屋さんに、勢い余ってコラボ企画をさせてほしいとお願いしてみたところ快く引き受けていただき、この度「三題噺」で同時投稿させていただくことになった(狂喜)。
お題は「スーパーマーケット」「恋愛」「村上春樹」の3つです。それでは、どうぞ~!
僕には友達がいない。
僕の住む田舎町では、インチキなロゴがプリントされたトレーナーを嫌って父親のお古の深緑色のセーターを着たり、ブルーベリーの強烈な匂いがするガムを噛む代わりに祖父の仁丹をなめたり、BOØWYじゃなくてBeatlesを聴いたりしていると自然と嫌われる。
そして本当にそんなことばかりをしている僕は、同級生のほぼ全員から嫌われている。
最近好きな人ができた。
隣のクラスの芝山さんだ。3年生になってすぐに転校してきた背の高い女の子。
隣のクラスだから話したこともない。
彼女のことが気になり始めたのは、同級生の芋っぽい女の子たちとは群れずに、ひとりでいる姿をよく見かけたからだ。
ひと月ほど前の昼休み、何もすることがなく、なんとなくベランダに出てみると、芝山さんが隣の教室の窓の桟に腰かけて何かを熱心に読んでいた。その姿を見た僕は、なぜか心臓を鷲掴みにされたような気持ちになり、すぐに教室の中に戻った。
それから何週間か後、図書室で借りたある小説の貸し出しカードの自分の名前の上の欄に芝山さんの名前があることに気が付いた。
その瞬間、僕は自分が芝山さんに恋をしたということを完全に自覚した。
僕のノイローゼ(これは母が僕についてよく使う言葉だ)はますますひどくなった。
先週の日曜、両親が法事に出席するため昼飯代を置いて出ていった。
その日も朝からずっと芝山さんのことを考えていた僕は、彼女と僕が読んでいた小説に出てくるサンドイッチを作ることに決めた。
去年の誕生日に買ってもらったマウンテンバイクに乗って「文化的スーパーマーケット」に向かう。
家の近所にはもっと品揃えの良い、大手チェーンの店があるのだが、僕はちょっとした買い物をする時にでもバイクを20分以上走らせてこの店に行く。
スーパーマーケットと呼べるのか、もともと八百屋だった店が少しずつ他の食料品を置き始めたような店。
入り口で、褪せた黄色の買い物かごを手に取り、商品を選んでいく。
産地に近いからか、店にはいつでも新鮮な野菜が並んでいる。
レタスは巻きがゆるくて見るからにシャキシャキとしていそうだし、きゅうりからは独特の青臭さが立っている。そのうちの3本を選び手に取ると、表面のいぼが手に刺さって痛い。
パンについてはこの町に住む限りは妥協をしなくてはならない。パン売り場に並んだロイヤルブレッドの8枚切りをかごに入れる。
ハムは家の冷蔵庫に入っていたし、チーズは好きではないので買わない。
全ての食材がそろったところで、レジスターの列に並ぶ。
もちろん彼のレジスターの列だ。
村上春樹にそっくりな店長の列。
僕がこのスーパーマーケットに通う理由はひとつ。彼にお金を払いたいし、彼からお釣りを受け取りたいからである。
どんなことだっていい。村上春樹との距離は詰めていく。
それが僕のこだわりである。
家に帰る道すがら、芝山さんと地元のヤンキー高校のジャージを着た奴が並んで歩いているのに気が付いた。ふたりの手はしっかりと繋がれている。
芝山さんはそいつに話しかけるのに必死で、横を通り過ぎた僕になど全く気付いていなかった。
家に着くと、とにかく急いでサンドイッチを作った。丁寧に丁寧に作ろうと思っていたのに、それは出来なかった。
特にこのサンドイッチの命である「よく切れる包丁で切る」という鉄則も忘れてしまい、切り口がだらしなくなった。
そうなってしまうと、食欲もすっかり失せて、僕は大量に残ったサンドイッチをラップフィルムで包むと冷蔵庫にしまい、自室に上がった。
階下から僕を呼ぶ母の声が聞こえた。夕飯の時間になっていた。5時間以上も眠ってしまったらしい。
食卓にパックのまま並べられた出来合いの総菜の横には、僕が昼間に作った冷たいサンドイッチが置かれていた。
よろしければサポートをお願いします!いただいたサポートは今後の記事の取材費としてつかわせていただきます。
