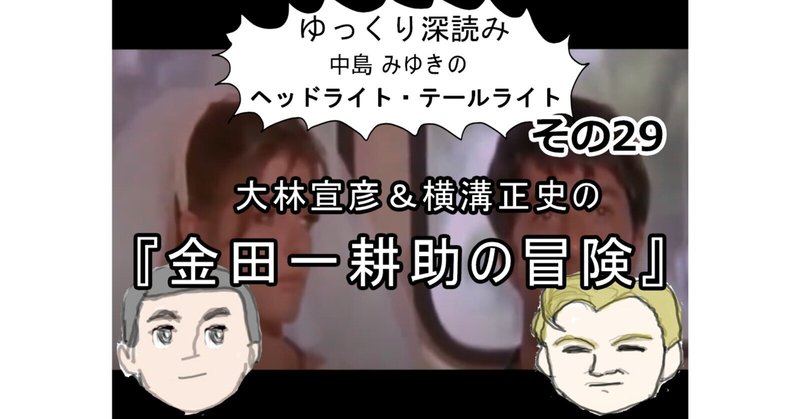
ゆっくり深読み 中島みゆきの『ヘッドライト・テールライト』その29「大林宣彦&横溝正史の 金田一耕助の冒険」
前回はこちら
A MOUSOU
(本作品は著者の身体に憑依した横溝正史の霊が世間で駄作の烙印を押されている大林宣彦の映画『金田一耕助の冒険』を種明かしするという妄想です。ネタバレどころか横溝文学の秘密の核心部分にも踏み込みますので予め御了承ください)

絵の中の少女…
つまり、美禰子を描いた「森の女」ですか?


「森の女」とされるこの絵は間違っとる。
そもそも漱石は最後にこう書いておるだろう?
「森の女という題が悪い」

え?

本当の「里見美禰子の絵」とは、これのことだ。


ええっ!?
フラ・アンジェリコ『サン・ジョヴァンニ・ヴァルダルノの受胎告知』!?

Fra Angelico

そして、こちらも。


美禰子を描いた『森の女』とは、フラ・アンジェリコの『受胎告知』だと言うのですか?

Fra Angelico

そうだよ。
美禰子が頭にかざしていた「丸い団扇」とは「halo」のこと。

ヘイロー… つまり後光(光背)のこと?

どちらの『受胎告知』もマリアに向かって光が差している。
そしてその光をマリアが「丸い団扇」で遮っているように見えるだろう?


夏目漱石はマリアの頭に描かれた丸い後光(光背)を団扇に見立てたというのですか?

西条八十『ぼくの帽子』や私の『傘の中の女』、そして映画『カサブランカ』や『人間の証明』などでは「帽子」に置き換えられている。
だいたいは「帽子」に見立てるのが定石なのだが、漱石はあれを「丸い団扇」に置き換えた。


確かに漱石は、扇子みたいな西洋団扇ではダメだと画家の原口さんに言わせていたような…
日本の丸い団扇でなければダメなんだと…

James Tissot

円形ではない扇子じゃ、円形の後光の代わりにならないからね。
だから漱石は丸団扇であることを強調したわけだ。

これは本当の話なのだろうか…

ふふふ。疑い深いねキミは。
『三四郎』最終章、展覧会のシーンを見れば一目瞭然だよ。
原口さんの絵はでき上がった。丹青会はこれを一室の正面にかけた。そうしてその前に長い腰掛けを置いた。休むためでもある。絵を見るためでもある。休みかつ味わうためでもある。丹青会はこうして、この大作に彽徊する多くの観覧者に便利を与えた。特別の待遇である。絵が特別のできだからという。あるいは人の目をひく題だからともいう。少数のものは、あの女を描いたからだといった。会員の一、二はまったく大きいからだと弁解した。大きいには違いない。幅五寸に余る金の縁をつけて見ると、見違えるように大きくなった。

原口さんの絵『森の女』の前には、長い腰掛、つまりベンチが置かれていた…

フラ・アンジェリコの絵『受胎告知』のマリアの前にも「長い腰掛」が置かれている。


ああっ!確かに!

そもそも展覧会の名前「丹青会」で気付くべきなのだが。
丹とはオレンジやピンクっぽい赤色のこと、つまり丹青とはマリアの服の色のこと。


なるほど…
確かに聖母マリアは「丹青」だ…

そして丹青会は「この大作に彽徊する多くの観覧者に便利を与えた」という。
観覧者たちは『森の女』が特別扱いされる理由を「絵が特別のできだから」「人の目をひく題だから」「あの女を描いたからだ」「まったく大きいからだ」と考えた。

「彽徊(ていかい)」は小説『三四郎』のキーワードの1つで、夏目漱石が好きな言葉ですね。
西洋人のようにモノゴトの意味や理由を深く考えたり突き詰めようとせず、何となく、ぼんやりと、流れに任せて生きていく東洋的な態度こと。

その通り。
大切なことほど言葉にしようとする西洋人と違い、日本人は「大切なことは言葉にならない」とか「言葉にできない」という考え方が好きだ。
大切なことを順序立てて論理的に伝えるのではなく、オブラートに包んだり他の何かに隠したりしながら伝えることが、おもしろい、趣があるとされてきた。
この歌『時の過ぎゆくままに』のように。

時の過ぎゆくままに、この身をまかせ、男と女が漂いながら…
まさに鴨長明『方丈記』の「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし」にも通じる東洋的思想、彽徊趣味ですね。

『時の過ぎゆくままに』は何を歌っている?

男女の愛ですが、その愛は世間では罪とされるもの…

具体的には、どんな?

おそらくこんなシチュエーションかと…
不幸な結婚生活に疲れた「あなた」が「わたし」に愚痴をこぼしながら悩みを相談し、憐れみの言葉をかけて同情してくれる「わたし」に心を許すだけでなく身体も許してしまい、流れで肉体関係をもってしまった…
というか「あなた」は最初からそうなることを期待して「わたし」と二人きりのシチュエーションを作っている…
よくある不倫のパターンです。
しかも「あなた」と「あなたのパートナー」との間で「お前もやったじゃないか」「あんたが先にやったから」とドロ沼化するパターン。

愛し合う行為が罪になる…
人間というのは実に不幸な存在だ。
だから人には究極の愛 Gesu が必要だった。

不幸な人間にはゲスが必要? ゲスは究極の愛?

君は Gesu を勘違いしている。

ゲスの極み乙女のゲスですよね?

『時の過ぎゆくままに』のジャケット写真…
なぜ沢田研二は「あんな場所」を走ってると思う?


あんな場所? おそらく表参道ですよね。

なぜ沢田研二は走っているのだろう?
しかも車ではなく自分の足で。

なぜ? どこかへ急いでいるのでしょうか?
何か車にトラブルがあったので、走って目的地へ向かっているとか?

そう。あの近くには教会がある。
沢田研二はそこへ向かっている。

教会? 何しに?

決まってるだろう。
花嫁を夫から奪うためだ。

ええっ!?

『時の過ぎゆくままに』のジャケット写真をよく見ると、中央分離帯と歩道橋が十字に交わっている。
そしてそのちょうどクロスしているところに「後光が差す人」が立っている。
あれは映画『The Graduate(卒業)』のオマージュだ。


なるほど…
確かにダスティン・ホフマンは故障した車を乗り捨てて走って行った…

沢田研二とそのブレーンは、阿久悠が書いた『時の過ぎゆくままに』の歌詞が何を意味しているのかを暗に示すため、マイク・ニコルズの映画『卒業』のラストシーンを使ったんだな。
同じ元ネタ、同じテーマを描いたものだから。

同じ元ネタ? 『時の過ぎゆくままに』と『卒業』が?

『三四郎』と『卒業』はよく似ている。
どちらも最初に「人妻の誘惑」があり、最後に「ヒロインの結婚」がある。
違うのは、それに対する主人公の行動だけ。

確かにそうですね…
三四郎はどちらからも逃げ、ダスティン・ホフマンはどちらも行動に移した…

彽徊趣味を好み、モノゴトを明確な言葉にしないのが日本文学だとした夏目漱石と、大切なことはハッキリと描かなければならないと考える西洋人マイク・ニコルズの違いだな。
『三四郎』の教会シーンで夏目漱石はこんなことをしなかった。


教会の中にいる人たちが出て来れないよう、門に十字架で鍵を掛けるって凄い発想ですよね。

あの描写は、教会の中の人たちが出られなくなったのではなく、罪を犯した男女が神の国から閉め出されたことを意味している。
つまり The Fall、失楽園を描いたものなんだよ。

え?

教会の中の「手」と、門を閉ざした「十字架」は、神の国(楽園)の「神の手」と「門番の天使」だな。
しかも罪を犯した二人の背後のガラスには鬱蒼とした茂みが映っていて、フラ・アンジェリコが描いたアダムとイヴそっくりになっている。


こ、これはいったい…

だから最後に女は男をジッと見る。
「私たち、これからどうなるのかしら?」みたいな不安な目で。


ああ… アダムを不安そうに見つめるイヴ…

The Graduate(卒業)とは The Fall(失楽園)のこと。
すべてが用意されていて何も苦労することのなかった世界から、すべてを自分たちの手で汗水たらして作っていかなければならない世界へ出て行くことだな。
ダスティン・ホフマン演じるベンジャミンと、キャサリン・ロス演じるエレーヌは、まさにアダムとイヴそのもの。

だから沢田研二の『時の過ぎゆくままに』のジャケット写真は『卒業』をオマージュしていたというのですか?

歌詞をよく考えてごらん。
ちょっと気になるフレーズがあっただろう?
「壊れたピアノで想い出の歌」とか「体の傷なら治せるけれど」とか「小指に食い込む指輪」とか。

確かに…
不倫なら指輪は小指ではなく薬指ですよね?
しかも「小指に食い込む」って、昔より太ったということ…
歌の出だしが「あなたはすっかり疲れてしまい」なんだから、昔より痩せて指輪がスカスカにならないと変…

その通り。渡哲也の『くちなしの花』みたいにね。

これはどういうことなのでしょう?

歌詞を順に解説しよう。
まず1番の冒頭、すっかり疲れてしまった「あなた」は、生きてることさえ嫌だと泣いた。
そして、壊れたピアノで想い出の歌を片手で弾いて溜息をつく。

壊れたピアノで弾く想い出の歌って何だろう?

「邪曲」だよ。

じゃきょく? 蛇の曲ですか?

よこしまな曲で邪曲。
視よ われ邪曲のなかにうまれ
罪ありて わが母われを孕みたりき

それは… 詩篇51?

そして「よこしま」と言えば、タイガース。

タイガーズは「たてじま」では?

ジュリーにとって「想い出の歌」といえば、ザ・タイガースのデビュー曲『MY MARY(僕のマリー)』でもある。

MARY… まさか…

MARY がいた場所には「朝の雨」が降ったという…
つまりそこには「水溜まり」があるということ…

そして唐突に出て来るフランス人形…

フラ・アンジェリコのことだな。
つまり MARY に会いに行った「ぼく」とは、天使ガブリエルのこと。


ジュリーの歌『時の過ぎゆくままに』の二人は失楽園のアダムとイヴだから、想い出の歌は『詩篇』であり、タイガースのデビュー曲『MY MARY』…
この2つの歌でフラ・アンジェリコの絵『受胎告知』を表現している…

そういうことだ。
阿久悠くんは本当に面白いことを考える。

そして2番の「体の傷なら治せるけれど、心の痛手は癒せはしない」とは…
寝ている間に脇腹から肋骨を抜かれ、起きたら何事もなかったかのように傷が消えていたアダムのこと…

Michelangelo(ミケランジェロ)

だな。

そして「あなた」の指輪があったのが「小指」だった理由は…
小指が「約束」の指だから…

アダムとイヴは神と「知恵の木の実を食べない」という約束をしていた。
さすがに指切りげんまんはしてないだろうけど。

だけどなぜ「あなた」は、すっかり疲れてしまい心労から痩せてしまうはずなのに「小指に食いこむ」なんだろう…

「小指に食いこむ」の「コユビ」と、そのあとに歌われる「この身をまかせ」の「コノミ」は、音が対応している。
つまり「コノミに食いこむ」だ。

コノミに食いこむ?
あっ! 木の実か!


阿久悠には有名な禁断の木の実の歌がある。
郷ひろみと樹木希林が歌ってヒットした『林檎殺人事件』。

つまりサビの「時の過ぎゆくままに、この身をまかせ、男と女が漂いながら」の「この身」とは、「アダムとイヴ」と「木の実」の駄洒落になっていた…

そういうこと。
そして「時の過ぎゆくままに」は、長い時間の経過を意味している。
だから最後は「もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう」というオチなのだな。

もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう…
つまり、二人が堕落の罪に絶望せず愛し合って子を残してゆけば、いつかその子孫の中からイエスが生まれ、自らの命と引き換えに原罪を贖って世界を新しいものに変えてくれる…

失楽園のアダムとイヴから見ると、受胎告知の天使ガブリエルと処女マリアは「窓の景色」に見える。
見事にフラ・アンジェリコの絵が完成した。


なんてこった… 信じられない…

ふふふ。「彽徊」から思わぬ長話をしてしまったな。
では夏目漱石『三四郎』最終章、丹青会の『森の女』に戻ろうか。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
