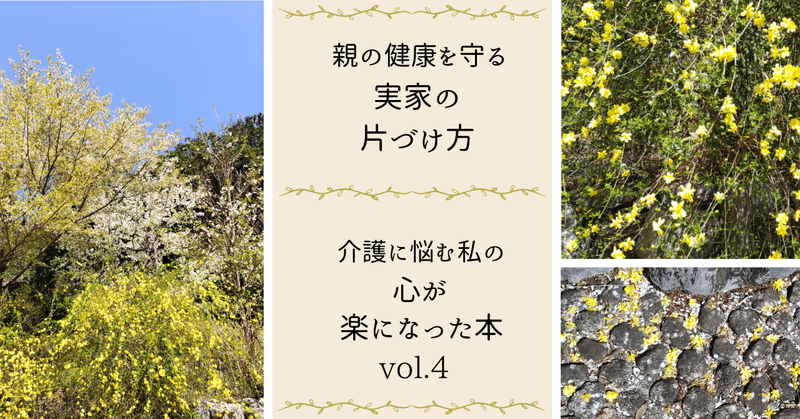
『親の健康を守る実家の片づけ方』 介護に悩む私の心が楽になった本 vol.4
2021年の春、母は入院していた。転んで骨折し、手術とリハビリを経て2ヶ月後に退院。もと通り動けるようにはならなかった。
入院中に要介護認定が下りていた。ちょっと位おかしくても、自力で暮らしていた母が要介護になるなんて。けど、これでやっと介護の相談ができると安心したことを覚えている。
介護保険を利用して住宅改修を行い、福祉用具を準備することになった。手すりを設置し、介護ベッドを借り、風呂場用の椅子を購入。これからは行政に助けてもらいながら暮らしていこうと思っていた。
でも現実は甘くなかった。退院直後の母は、いつも眉間にシワが寄っていて、口癖は『難しい』『困った』『おかしい』『分からない』だった。こそあど言葉が一気に増え、コミュニケーションが取れない。何に『困った』のかも言わない。
私は数年前から母の異変に悩んでいた。入院に伴って症状は更に悪化。めまい、頻尿、骨粗鬆症、肥満、高血圧、腰痛、脳動脈瘤、脚のムクミ、呂律、便秘、感情の波、認知症(グレー)。
一番の悩みは母に自覚がないことだった。『自分で出来ている』と思っていて、行政や医療機関に頼る考えは全く無い。無意識で娘を頼りにし、それが私の中で負担だった。
たくさんの悩みをケアマネさんに相談した。けれども『なんでも相談して』と言う割にパーソナルな悩みには応えてくれなかった。
あぁ、こういう相談は彼女の仕事の範囲を越えているんだ、と諦めた。既にある制度は教えてくれても、細かい悩み対応は対象外なんだと。
じゃあ、介護を必要とする人の暮らしを、誰に相談したらいいのか。私は介護予防とか改善とかも地域包括支援センターの管轄だと思っていたのだ。このままでは、この先もっともっと大変になるのに。
日本の介護保険制度の限界を知った。ただ、この点に関しては、以前のnoteで紹介した本を読んで、考え直した部分もある。
《 老いる不安や心配の行き先として 》
・まずは地域包括支援センターへ相談
・地域包括支援センター以外にも相談できる場所をいくつか作っておく
・相談相手の返事に一喜一憂せず、しっくりくる答えを探す
自分たちで工夫しようと思った。母の暮らし自体を簡単にしたらどうか。出来ることを減らさないようにしよう。
けれども、正直、30代の私に要介護60代母の暮らしを簡単にする方法なんて思い付かない。
2ヶ月の入院で浦島太郎状態になった脳で、普通の暮らしを続けようとする。自分に出来ること出来ないことが分からない。生きてるだけで危ない。あの頃は母が動く度にヒヤヒヤし、思い悩んでいた。
そんな悩みに答えてくれた本がある。

『親の健康を守る実家の片づけ方』
著者は永井美穂さん。日本初の片づけヘルパー。そんな職業があるのかと驚いた。彼女は、やさしい。とにかく寄り添う。
挿絵はイラストレーターの吉沢深雪さん。ご自身も介護を経験されている。絵本のようで読みやすいのは彼女のおかげ。
この本を読んで様々な考え方に救われた。抱えていた悩みとともに紹介したいと思う。
Question & Anser
① ベッド周りがグチャグチャに
母の退院に合わせてレンタルした介護ベッド。全長2mのベッドに対して、母の身長は146cm。50cm余る。そのスペースに物を置く。周りにも置く。そんな生活を続けて、ベッド周りはグチャグチャになった。
枕元に何を置くかというと、服、リモコン、ティシュペーパー、ペン、消しゴム、ノート、ハサミ、定規、裏紙、タオル、綿棒、本、紙コップ、ラップ、飲み薬、塗り薬、クリーム類、くし、手鏡、髪ゴム、輪ゴム、ガムテープ、割り箸、ピン、チョコ、バナナ、メガネ拭き、洗濯ネット。…書いていてビックリした…。こんなに置いてあったの…?
さて、永井さんのアイデアはこうだ。
→『介護ベッドの手すりにカゴを吊るす』
やってみた。カゴならある。S字フックで吊るすとのことだけど、家にS字フックは無い。ビニール紐でカゴをくくりつけてみた。
どうやら、ここにこれを置くと決めてしまえば母にはラクらしい。置き場所が決められないから、枕元に置くのだ。そして積み上げられる。
中には例外も。見た目は微妙だけど、そのままベッドにビニール紐でくくりつけた物がある。例えば、ハサミ。カゴに戻さず枕元に置きっぱなしにすることがあった。刃先が危ないので、刃先カバーをビニール紐でくくりつけてみた。ハサミをカバーに戻すようになり一安心。
少し改善されると、スッと気が楽になった。
② どこに服があるか分からない
母は服を袋に入れてベッドの周りに置く。外出着は枕元に置く。ここを正しい置き場だと思っているようで、いそいそと服をたたんで積み上げていく。ハンガーにかけられる服はラックに。
季節外の服は袋に入れて台所に置く。服が無い、又は着れないとなるとすぐ買う。そして、着ない服はどこに置いたか忘れる。見えない所の服は覚えられない。母の箪笥はスカスカか、着ない服を入れてある。引き出しを少し出して、ズラズラとハンガーをかけて上着を並べたりする。場所が勿体ない。
入院前の服は着替えが大変で、一気に服が増えた。どのくらい服があるか把握なんてできない。出かける前いつも何を着ようか悩んでいる。
服を袋に小分けにしてベッド周りに置く心理が私には分からないのだけれど、母なりのルールらしい。
この大量の服と収納を何とかしたいと思っていた。
永井さんのアイデアはこうだ。
→『吊り下げラックを使う』
買いに行ってみた。100均には無い。似たようなものを買おうか。ホームセンターに行ってみた。あったけど、1200円超え!! いったん保留。
形の似ているカラーBOXに服を詰めてみた。家で使っていたものがあったので、中身を移動させて再利用。
考え方は分かった。普段よく着る服を一目で分かるようにしたら良い、ということだ。いろんな所に服を置かない。把握できる範囲が適量なのだと。少しずつ服を処分しよう。
やさしい心と冷静な頭で
本当に小さな問題だけど、少し前進できると気がラクになった。なるべく自分のことは自分で。それがいかに難しいことか、母を見ているとよく分かる。
本全体に溢れているのは、やさしさと冷静さだった。自分の都合を優先しがちな片づけに対して、親に寄り添うことが一番なんだと教えてくれた。片づけは親が安全に暮らす為だと。そしてそれは、たくさんの現実を見てきたからこそ説得力が伴う。
やさしさなんて、すぐに忘れてしまう。イライラや怒りの種が、そこら中に埋まっているから。介護が必要な親を目の当たりにして冷静でいられる人は少ないと思う。忘れる前に定期的に読むようにしたい。やさしい心と冷静な頭で対策できるように。
高齢の親の様子が『少しおかしい』と思った方に、オススメしたい一冊だった。
春のことを少し
前回のnoteで、春を楽しみたい、と書きました。近くの寺へ桜を見に行ってみると

半分くらい葉桜になっていました。今年も乗り遅れてしまった…。例年よりも開花が早かったのもあります。でも足元を見てみると、黄色い花と桜が可愛いんです。花って散ったあとも美しいんですね。皆さんのnote記事を見て、私もやってみよう、と撮影しました。

昨年の今頃と比べると大きな変化です。風景写真を撮るというような楽しみが訪れるとは思いませんでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
おまけの一冊 『夢がかなう おとなの絵日記術』
手帖本とか日記本が好きで、色んな方の本を読んできました。これは先ほどのイラストレーター吉沢深雪さんの絵日記本です。

介護に直面した時期のことも書いてあり、一気に親近感を抱きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
