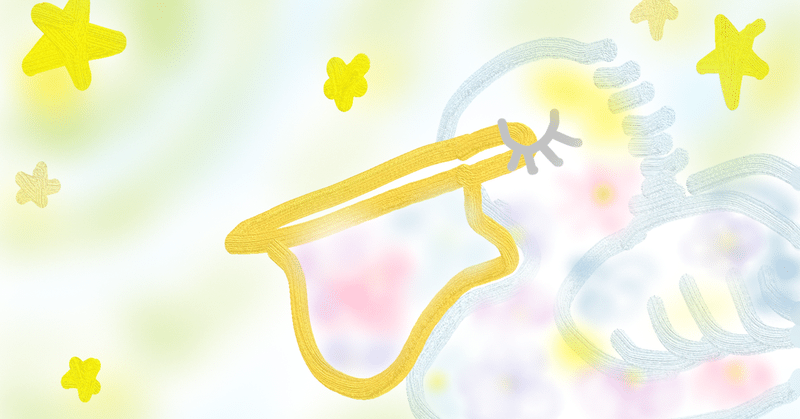
お仕事知識の身につけ方~my百科事典を作ろう~
はじめに
このnoteでは、業務マニュアルや引継書、商品知識が整理された資料などが用意されていない中小企業に中途入社した事務員さんに向けて、異なる業界で事務職に携わってきた私がこうした状況でより早く正確に仕事を覚えるにはどうしたらいいか? と試行錯誤してきた内容を紹介しています。
前回の記事では、『チェックリスト化のすすめ』を書きました。
次の記事で具体編を書きます、とお伝えしていたのですが、少し予定を変更。
今回の記事は、以下の記事で「このまとめ方に向かない」一例として紹介した、たとえば商品知識のような「業務に関連する知識」のまとめ方を紹介します。
商品知識のような情報は、「あれ、なんだったっけ?」と思った時に活用しやすいよう、検索のしやすさが重要です。また、後から追加する情報が多いので、シンプルかつ整理しやすいフォーマットが向いているように思います。フォーマット自体も難しい操作なく作れることも大切です。私はこうした観点から、ざっくりしたカテゴリごとに1つのExcelファイルで情報を集約することをおすすめしています
たとえば【卸売業 営業事務職さんの場合】
「業務に関連する知識」は、担当する事務処理によって異なりますね。ここでは、覚える仕事の範囲が多いと思われる、卸売業の営業事務職に就く事務員さんのお仕事を例に考えてみます。
こんな業務を担当しているとしましょう。
電話応対(商品知識や納期、価格に関する質問等に対応)
見積作成
仕入処理
この場合に必要となる情報や知識は大まかに、商品に関する知識、掛け率・出荷関連(仕入先、得意先ごとに)、仕入に関する注意点(仕入先ごと)、などが挙げられます。
商品そのものの知識(共通事項・メーカー別)
出荷関連(特定の得意先への出荷日が決まっている場合を想定)
掛け率(仕入先、得意先ごとに)
仕入先ごとの仕入注意点
“my百科事典”を作ろう”
こうした業務を覚えていくとき、入社した会社で必要な知識を体系的にまとめた資料があるととても心強いですが、中小企業ではこうした資料が準備されていないことが多いと思います。
次々と仕事を教わっていると、「聞いた気がするけど、どこにメモしたっけな?」「カタログを見てって言われたけど、どのカタログを見ればいいんだっけ」という場面に出くわすことがありますよね。
今、自分が必要な情報にアクセスすることが難しいわけです。
そこで、百科事典のように「困ったときは、このExcelを開けば大丈夫!」という資料があると安心しませんか。
たとえば、「〇〇についてわからない場合はこの資料を見る(リンクも貼っておく)」「このメーカーの商品について解決できない時は、コールセンターがある(コールセンターの電話番号を書いておく)」のように、力になってくれる資料や外部機関の情報も載せておくと、頼もしいです。電話応対のようなスピーディな対応が求められる場合も、情報は一箇所に集約されている方が頭の整理もしやすいですね。
部屋のお片付けをするように、情報もお片付けしよう
わたしは一時期、部屋のお片づけに凝っていました。お片付けもいろいろな流派(?)がありますが、カテゴリを分けたりモノの住所を決めたりと、共通していることもあります。情報にも、同じようなことが言えると思うのです。
たとえば、Excelにまとめる情報はまず大まかにカテゴリに分けて、シート分けすると良いです。「後でどんな風に検索したいかな」と想像しながら作るのがおすすめですが、初めは情報のカテゴリ分けが上手くいかずに苦労する場合もあるかもしれません。
そこで、先ほど例に挙げた卸売業の営業事務職さんの場合は、どんな資料を作ると自分を助けてくれるツール作りができるのか、これから徐々にお伝えしていきますね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
