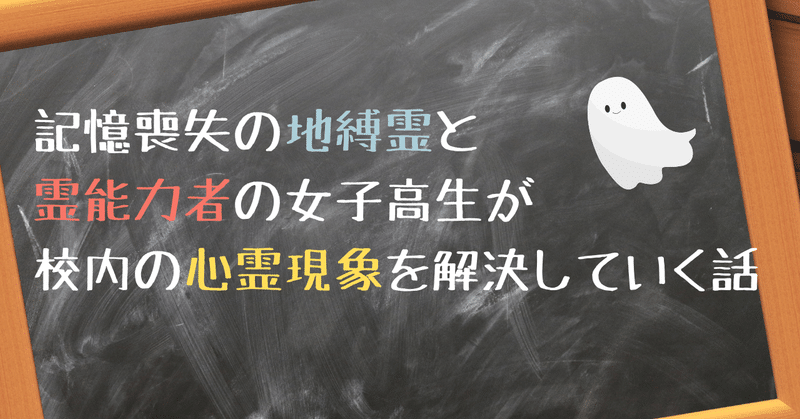
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #33
第5話 呻く雄風――(3)
土地神を探す、と宣言したものの、手がかりは皆無である。
この土地を守っている神様の癖して、社のひとつも構えていやしない。先生やアサカゲさんの記憶と感覚だけが、まだ在るのだと証明しているだけ。
だから、年々力が弱まっていったのだろう。
願いや信仰によって生まれる神様は、人間から忘れられれば、消滅はどうしたって免れない。ゆっくりと、人間からしたら気の遠くなるような長い時間をかけて、今も死にゆく最中なのだ。
であれば、仮に土地神を見つけ、この学校の人間に存在を認識してもらったところで、果たしてどれだけ期待できるのだろうか。
いや、土地神復活は駄目で元々の作戦だ。それに、もし浄化ができなくとも、せめてアサカゲさんと会うくらいはしてほしいと、俺は思う。
「おーい土地神ー。土地神様やーい」
翌日の昼休み。
アサカゲさんは手早く昼食を摂るや否や、校内で頻発するポルターガイスト現象の対応に向かってしまった。俺も同行しようかと思ったのだが、この状況下で〈よくないもの〉に近寄るのは危険だと断られてしまい、現在、澱みが比較的マシな場所にて、絶賛一人で土地神探し作戦を実行中の身の上である。
人が多いところは澱みも濃く、それは俺に直撃して蓄積していく。アサカゲさんへの道案内も、極力生徒の多い校舎には近寄らず、リストバンドを介しての案内に留めている。
〈よくないもの〉は人の意識や念の集合体だ。つまり、人が多ければ多いほど、その濃度は加速度的に増していく。既に昨日なんて比じゃないほど、澱みは悪化している。俺の身体は常に倦怠感と頭痛を訴えるほどになっていた。
「幽霊が頭痛って、なんなんだよ、もう……」
不甲斐なさと無力感も相まって、俺はその場にしゃがみ込んだ。
この学校のことを誰よりもよく知っているのに、誰よりも役立たずだ。
俺はいつもどこか蚊帳の外で。
それは幽霊だから、既に死んでいるのだから、仕方ないのだと自身を説得してきた。けれど、今回の件は、俺の活動時間がもっと長ければ、未然に防げたのかもしれないのだ。この学校から出られない地縛霊なら、それくらいできただろうに。
結果なにもできずにこんな事態に陥って、体調が悪いと愚痴を漏らす。
ああくそ、全くもって格好悪い。
「……ろむさん、ですよね?」
と。
頭上から聞き覚えのある男子生徒の声がして、俺はのろのろと顔を上げた。
心配そうにこちらを覗き込んでいたのは、春先に旧校舎の音楽室でピアノを弾いていたオオモモくんだった。
「具合、悪いんですか? ええと、朝陰さんを呼べば良いですか?」
「いや……もう大丈夫」
狼狽えるオオモモくんにそう声をかけて、俺は立ち上がった。
虚勢を張っているのではない。本当に、さっきまでの倦怠感や頭痛は幻だったのかと思うほど、気分がさっぱりしていた。
そういえば、彼の母方は神社の家系で、住んでいる家の庭では、神様を祀っているんだっけ。あれから、祠の掃除や供えものを欠かさずしているからなのか、彼の周りの空気は精錬としている。
「……あれ? なんで俺のこと視えてるの?」
首を傾げた俺に、オオモモくんも同様に首を傾けながら、なんででしょう、と不思議そうに言う。
オオモモくんは入学以来、一度も校内で幽霊の類を視たことのないという、この学校においては稀有な人物だったはずだ。
「二学期に入ってから、突然視えるようになったんですよ。クラスの子たちからはいまさらかよって笑われちゃいました。でも、こうしてろむさんに会えたんだから、塞翁が馬ってやつですかね。僕、貴方にもずっとお礼を言いたかったんです」
「お礼?」
「ほら、結城先輩を見送ったあと、朝陰さんは術を解いちゃってたし、僕は僕で涙が止まらなくて、あの日はぐずぐずのまま解散になったじゃないですか。だから、こうして会えて良かった。改めて、ろむさん、あのときはありがとうございました」
「べ、別に俺は、なにもしてないよ」
あのときの俺は、せいぜい緩衝材程度の働きしかしていない。
しかし、オオモモくんは、そんなことないですよ、と言う。
「ろむさんが先輩と朝陰さんの間に入ってくれなかったら、そもそも先輩は、話し合いに参加しなかったかもしれなかったらしいですし。僕が朝陰さんに呼び出されたときも、なにか言って場を和ませてくれてたじゃないですか。居てくれるだけで安心する人って、なかなか居ないですよ。だからお礼を言わせてください」
「……それなら、うん。こっちこそ、そう言ってもらえると嬉しいよ。ありがとう」
居てくれるだけで安心する。
オオモモくんの言葉に、とても胸の内が暖かくなるのを感じた。一般的には、これは『嬉しい』が故の反応だと思うのだけれど。どうしてだろう、喉から手が出るほど欲しかったものを、ようやく与えられたような気分だ。
「ろむさん? 本当に大丈夫ですか?」
「うん、平気へいき、大丈夫」
片手でぱたぱたと顔を扇ぎ、それよりもさ、と話題を変えることにする。
「オオモモくん、二学期に入ってから突然視えるようになったって言ってたけど、神様っぽいひとは見かけたりしてない?」
なにかと神様と縁のあるオオモモくんなら或いは、と思ったのだ。
「神様っぽいひと?」
「正確には、ここの土地神なんだけど。背が高くて、着物を着てて、長い髪を後ろでひとつに結ってるひとらしいんだ」
「それって――いや、なんでもないです」
明らかになにか心当たりのありそうなことを言い掛けて、オオモモくんは首を横に振る。
「そういうひとは視たことないですね……。だけど、どうしてまた、土地神様探しを始めたんですか?」
いくらオオモモくんといえど、そこまで都合の良い展開にはならないか、と心の中で小さく嘆息してから、俺は言う。
「二年生の子が校内でこっくりさんをした話は知ってる? 今、その影響が各所で出ててさ。たぶん、君がこうして俺とかの霊が視えるようになったのも、その影響のひとつなんだよ。とにかく悪いものが校内に集まり過ぎてて良くない状況だから、土地神の手も借りたいって感じ」
「ああ、こっくりさん禁止令は始業式のときに聞きました。なんだか僕の想像以上に大変なことになってるみたいですね。そういうことなら、任せてください」
そう言って、オオモモくんは自身の胸元をどんと叩く。
「僕、元運動部なので、結構顔は広いんです。二年と三年の陸上部になら声をかけられますし、最近は吹奏楽部と軽音楽部の子とも交流があるんですよ。目撃情報があれば、すぐに教えますね」
「助かるよ~……うん? 吹奏楽部と軽音楽部って?」
春先の時点では、オオモモくんは特にどこかに入部しているという話はなかったはずだ。
「僕、まだ楽譜がいまいちちゃんと読めなくって。吹奏楽部の子から、楽譜について教えてもらったり、お勧めのクラシックを聴かせてもらったりしてるんです。そうしたらどこからか、ピアノが弾けるフリーの奴が居るって聞きつけた軽音楽部の人から、キーボードとして参加してくれって声をかけられまして」
「青春してるねえ」
「はは、それもこれも朝陰さんとろむさんのおかげですよ。あ、そうだ。秋の文化祭には、僕の居るバンドも参加するので、良かったら聴きにきてくださいね」
「もちろん。楽しみにしてるね」
そんな話をしているうち、予鈴が鳴った。
オオモモくんは、それじゃ、と一礼すると、早足でこの場を去った。
彼が居なくなった途端に、それまでの清涼感が嘘のように、身体の至るところから不調を訴える声が上がってくる。もしかしなくとも、居てくれるだけで安心する存在というのは、俺ではなく、彼にそこ相応しい言葉なんだろうな、なんて思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
