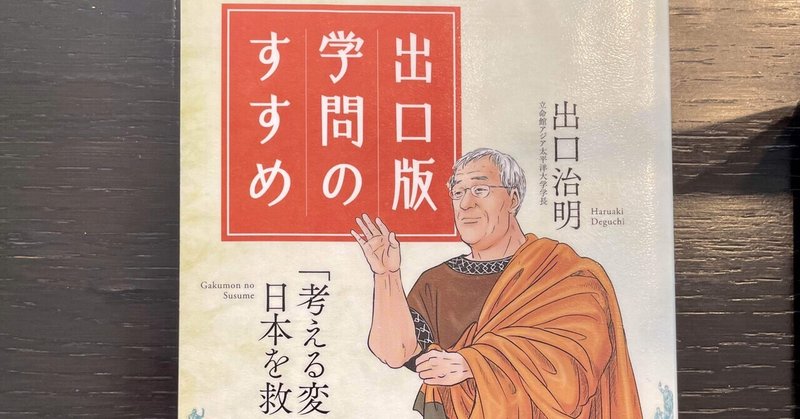
「ガリ勉」だった私と“出口式勉強法”
子供のころの私のあだ名は「ガリ勉」(笑)
「ガリ勉」「ガリ勉」といじられた子供時代。
「ガリ勉」になったのには理由があります。私には年子の妹がいるのですが、子供のころの妹は、顔が可愛く、愛嬌もあって、要領が良かったので、両親や周りの大人からチヤホヤされて愛される存在でした。
対して、可愛いという言葉には無縁だった私。妹がいつも羨ましくてしょうがなかったのです。ただ、勉強を頑張って良い成績を取ったときだけは「なおちゃんはえらいねー、すごいねー!」と教育ママだった母親にそれはそれは褒められ、喜ばれたのです。
なので、勉強を頑張って良い成績を取れば、(顔の可愛い)妹よりも私の方が可愛がられる!母親に喜んでもらえると思って「ガリ勉」と呼ばれるほど勉強を頑張ったという、そういう子供時代を過ごしました。
それが今でも沁みついて抜けきれないのか、いまだに何かしら勉強したり、試験を受けたりすることが好きだったりします。
余談でしたが、さて、最近読んだ、出口治明さんの著書『出口版 学問のすすめ』
出口治明さんは、ライフネット生命創業者であり、立明館アジア太平洋大学学長。世界1200都市を訪れ、1万冊超を読破したという稀代の読書家として知られています。
その出口さんが“出口式勉強法”として、
モノを覚えるとき、僕が実践しているコツは一つだけ。読んだり聞いたりしたことをそのまま覚えようとするのではなく、読み聞きしたことをもとに自分で考えて、考えた結果を他人に話すのです。
とおっしゃっています。そして、本を読んでも内容を覚えていられるのはせいぜい1日か2日だけなので、だから覚えているうちに、読んだものについてアウトプットすることが大切と明言しています。
面白い本を読んだら周囲の人に「これはおもしろいで」とその本の内容やおもしろかったポイントを話し、出口さんが教えていらっしゃる学生さんにも「人・本・旅で勉強して感動したら友だちにしゃべりまくれ」と話しているそうです。しゃべりまくるためには、聞いたり読んだりした話を、自分で咀嚼して、自分の言葉で再構築しなければならないので筋道を立てて覚えられるんだそうです。
ただ、アウトプットが大事なら読書日記をつければいいという意見もあるけど、これは効果がないそう。というのも、脳が無意識のうちに「これは日記用やな」「自分用のメモやな」と思い込んでしまうので脳に定着しないとのことで、書くのであれば読者のいるブログなどが良いそうです。「この文章は誰かが読む」と脳が意識するので、整理のレベルが格段に上がるんだそうです。
ほんの僅かででも読んでくださる方のいる、このnoteを活用して、学んだことを脳に定着させていこうと再認識しました。
ここまで、読んで頂いて本当にありがとうございました♡
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
