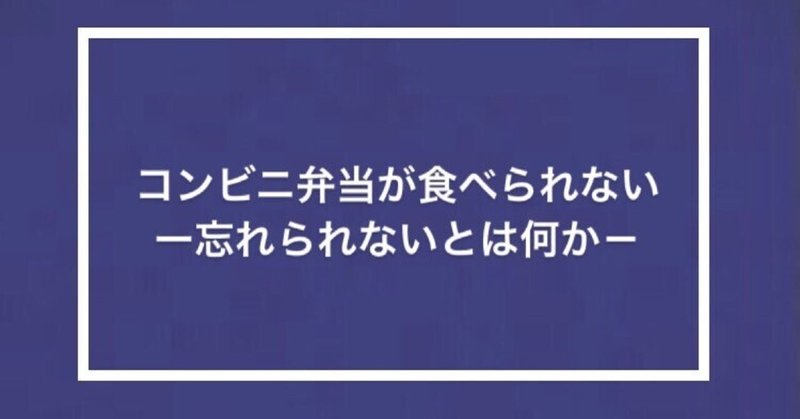
コンビニ弁当が食べられない
私がコンビニ弁当を食べられない理由
私は小さい頃からコンビニ弁当が食べられない。
もう少し言えば、スーパーのお惣菜コーナーに売れている、お弁当の形をしたものでさえも手に取ることが出来ない。
そのことが当たり前になりすぎて、なんとも思ったことがなかったが、ある時に、強烈に思い出された光景がこのような現象を生み出しているのではないかと思うようになった。
それは幼少期、母親が風邪をひいたか何かで体調を崩し、料理が出来なかった時、父親、私、弟、妹の四人でそれぞれスーパーで買ったお弁当を食べている光景だ。
その光景を母親が見てこう言った。
「お母さんがいないお家の食事風景で、なんか見窄らしい感じがするね」
この一言、この光景が事実ではなく、私の想像と忘却で構築された「真実」である可能性も十分にあり得ると思う。
夢の中で見たものを現実の世界のものとして認識してしまっている可能性も十分にあり得ると思う。
しかし、この時、私はなぜか泣いていた記憶がある。
泣きながら、お弁当を食べていた。
何を食べていたのかはも全く覚えていないくらいに。
私の涙は何がもたらしたものだったのだろうか。
この歳になって、事実かも分からないことを考えるのもどうかと思ったが、客観的に考えてみるに、やはり母の一言は大きかったように思う。
手作りのものがない食卓。食べ終わった後に洗うものがない食卓。
今でも私はそのような食卓を見ると、うっと泣きそうになる。
だから、いつだって自炊をする。
お惣菜は買うことが出来るため、お惣菜を買ったとしても、何か必ず一品は自分が作ったものを食卓にあげ、お惣菜も必ずお皿に出して食べる。
それがどれだけ疲労を生むとしてもだ。
自身の首を絞める行為になることもあるが、それ以上に捨てることが出来るものだけで構築された食卓を見ることのほうが、私にとっては後々、自身の心を締めつけるものになる。
もしかしたら、母がその一言を軽々しく放ったこと、父が黙々とお弁当を食べていた姿が、期待していたことを裏切られたような気持ちにさせたのかもしれない。
本当は父の運転で、どこかに食べに行きたかった。
風邪をひいているのならば、早めに言ってくれたら、私がご飯を作れたかもしれなかったのに、というように。
何気ない光景が今の私の食卓にまで引きずり込まれる。
それは、ある種のトラウマとも言えるのだろうか。
「忘れられないこと」とは何か
今、トラウマや記憶について興味をもち、本を読みながら学んでいる。
もともと目には見えない、けれどその人の言動に関与するものについては関心をもち、色々と調べてはいたが、改めて思うに、興味や関心の発端は必ず自分にあるように思う。
自分と距離のあるものに関心をもつことは私はあまりない。
とするならば、私にとって、興味関心について学ぶことは、自分を知ること、自分の過去の出来事を整理し、真実として再構築し、落とし込むことと同一なのかもしれない。
先日、とあるご縁で私の関心ごとと近い研究をしておられる研究者の方に出会った。あまりの共通点の多さに、声は出せなくとも、聞いているだけでとても興奮してしまった。
嬉しかった。
私の過去や今の状況を真実として、落とし込むことを手伝ってくれるかもしれない人に出会えたことが。
落とし込むことの出来ない、落とし込みたくないものを、混ざり気のあるままで、保存することを手伝ってくれるかもしれない人にまた一人、出会えたことが。
過去は不思議で、事実であっただろう、と推論でしか語ることが出来ない。
実際の出来事として記録があったとしても、真実にしかなり得ないと私は考えている。
それは忘却という機能が人間には備わっているからだと考えているのだが、忘却という力を凌駕して、それでも身体全身で覚えている出来事、感覚が存在するのはどうしてなのだろうかと考えている。
忘れられない
それが存在するのはなぜなのか。私は今、そのことを考えられる文章を書きたいと思っている。
上記に書いた研究者の方から、「とりあえず修論書くことだね」と言われた。
そのためには大学院に行く必要があるのだが、今は無理だとしても、自分が研究したいこと、考えてみたいことが生まれた時、その意欲が簡単に行動に移せ、興味を充足させることが出来るルートがもう少し、オープンに開かれていれば良いのにと思う。それは、どのような肩書きをもつこと(たとえば、妻、母、介護者など)になったとしてもだ。
すでに大人の学校的なところはあるのだろうが、学術的なことをしたいと思えばやはり、自身が師匠にしたい研究者の傘下で研究しながら、生活していくための仕事をするという二足の草鞋を履きたいと思う。
そんな人生を少し考えてみても良いのかもしれないと、ほんの少しだけ光を覗き込んだ気分でいる。
しかし、私はずっと自分で知っていた。
その希望は今に始まったことではなく、学生の頃から私がひっそりと心の中で抱いていた夢であったことを。可能性があるからこそ、夢として抱くことは出来ると考えると、それを思い出すことが出来ただけでも、私は今、とても幸せのように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
