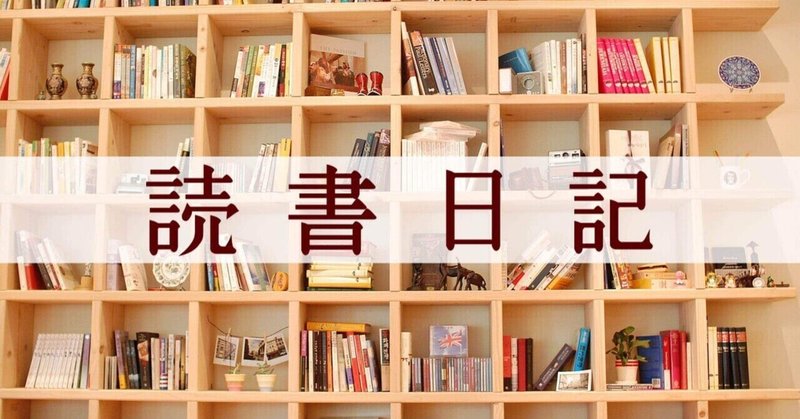
【木曜組曲】恩田陸
※インスタに投稿した記事より、一部加筆修正してお届けいたします。
耽美派女流作家の重鎮、重松時子がやや不可解な薬物死を遂げて四年……時子と深い縁のあった五人の女性は、毎年現場となった「うぐいす館」に集まり、時子を偲ぶ会を開催していました。
と言っても、堅苦しい「式典」ではなく、簡単に言えば「女子会」のようなものです。
偲ぶ会は、時子の命日ではなく、命日に近い「木曜日」に開催されます。というのも、日にちではなく、曜日を重視した集いだからです。
実は、生前の時子は木曜日を愛していたのです。
「木曜日が好き。大人の時間が流れているから。丁寧に作った焼き菓子の香りがするから。週末の楽しい予感を胸に秘めているから。それまでに起きたことも、これから起きることも、全てを知っているような気がするから、木曜日が好き」
本筋とは関係ないのですが、木曜日に対する時子のこの表現は、作中で一番印象に残りました。
しかし、その年は特別でした。
例年通り、前日の水曜日の午後、それぞれがうぐいす館に集まってくる所から物語は始まります。
この年がいつもと違うのは、皆の集合を見計らっていたかのようなタイミングでうぐいす館に花束が届けられ、謎のメッセージが添えられていたことです。そのことを機に、時子は本当に自殺だったのか? 或いは、他殺だったのか? という問題に、真剣に向き合う流れとなったのです。
実は、参加者全員が、心の中でその疑問をずっと拭えずにいたのです。
そうすると、もう、出るわ出るわ……告白と告発の嵐。
知っていること、黙っていたこと、知らなかったこと、思っていること、疑っていること、言えないことなど、皆で腹を探り合う席になったのです。
物語のほぼ全般通して、舞台はこの「うぐいす館」のリビングだけです。五人の喋くりも、ここだけで繰り広げられます。
登場人物も、回想で出てくる時子を除くと、集まった五人だけ。シンプルなステージの演劇を観てるような感じでした。
また、その五人の女性達も、時子と同じく、文筆業に携わっている「変わり者」ばかり。
ライターの絵里子、流行作家の尚美、純文学作家で受賞歴もあるつかさ、生前の時子の担当もしていた編集者のえい子、出版プロダクション経営の静子。
五者五様に時子と深い繋がりがありますが、絵里子とえい子以外は、時子の血縁者でもあります。こんな一筋縄にはいかない個性的な五人の女子会ですから、それはそれは、騙し合い、探り合い、暴き合いのオンパレードで、話は二転三転します。
ドキドキ、ハラハラの連続で、不穏な空気になったかと思えば、何事もなかったかのようにけろっと和解し、険悪になったかと思えば、理解も深まり……
合間合間に、凝った料理やケーキやお酒でリセットされ、張り詰めた心理戦が、一転して和やかなお喋りに。
まさに、緊張と緩和。
この辺りの構成力と描写力は、流石恩田陸さん! お見事としか言いようがありません。
そして、物語の根底となってる舞台は、やはり「女子会」なのです。
時に意地悪なのに、潔さもあり、大人の女性ならではのサッパリ感が清々しくもあります。逆に言えば、信頼とは別の意味で、互いに理解はし合っている関係なのでしょう。
ただ、その前提でも、何処までが本音で何処までが真実なのか、女性五人の会話劇と心象描写はとても生々しく、目が離せません。
肝心のストーリーは……これまた、とても秀逸です。
時子の死についても、沢山の伏線が綺麗に回収されていき、納得のいくフェアな解答が導き出されております。それが正解か否かはともかく、一つの解釈としてスッキリします。
そして、そもそもの告白大会は……
ネタバレになるので詳しく書けませんが、最後の最後に「そういうことだったのか!」と、それなりのサプライズが用意されております。
ある人の緻密な計画……こちらにも、全て作中に伏線が張り巡らされていたことに気付きます。
ミステリーとしてより、心理劇として、とても面白い作品でした! 個人的には、恩田陸さんの名作とされている、『夜のピクニック』や『チョコレートコスモス』よりも(全然タイプは違いますけど)好きかもしれません。
#木曜組曲
#恩田陸
#レビュー
#読書
#読書記録
#読書日記
#小説
