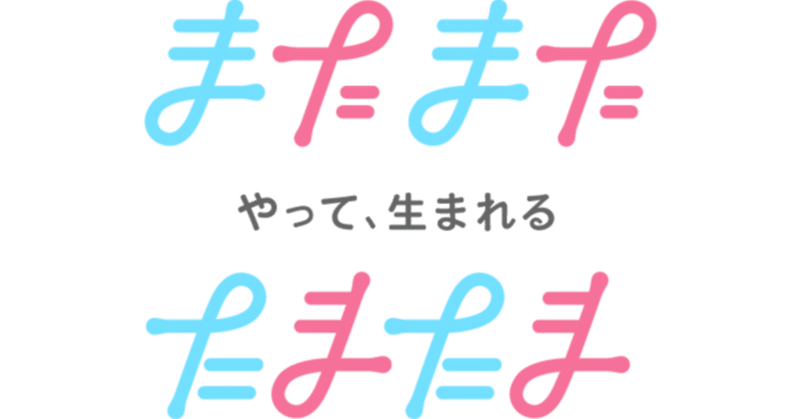
この旅は手法の探究とその言語化のためのプロセスでもある
『斗起夫』は映画的だ、と批評を受けたことがあった。その心は、書き手である宮澤大和のなかで明確なカメラワークとカット割りがあるように、小説を読んでいて感ぜられるからである、ということだった。
この批評は根本的に僕の思想(映画のほうが「小説」的であり、ドラマのほうが「戯曲」的であるのかもしれない)に通ずるところがあるかもしれない。あの作品はあの形態で発表することができてよかったとは思っている。悔いはまったくない。悔いのようなものがあるとすれば、一緒にクリエーションをしている俳優たちに対して適切に手を差し伸べてあげることができなかったということくらい。僕は演出家としての実力不足を痛感し自己嫌悪に沈んだ。けれどもいつまでもそこに沈んだままでは進歩の欠片もないし、あのときに多くの人たちに支えられながらつくりあげた2時間45分の大作からなにも学び得ていないことになってしまう。それでは申し訳が立たないし顔向けもできない、ので、ときどきこうやって後ろを振り返りつつも前を向いて進んでいかなくてはならない、と思うのだ。もし次に、『斗起夫』と同じくらいの規模で作品をつくれるとしたら、「戯曲」的な作品をつくってみたい。主人公だけじゃなく、その周縁にいる/ある人や物にもまた感情移入ができるような群像的な作品を。
今回のプロジェクト『「またまた」やって生まれる「たまたま」』はそのための準備と修行のタームでもある。
『条件の演劇祭 vol.1-kabuki』。ぺぺぺの会『太陽と鉄と毛抜』。捉え方によってはコミカルにも見えるけど、誠実な創作だと感じました。言葉を武器に世界を切り開く団体が、それ以外の武器も巧みに操り、結果としてシナジーを生む上演…に見えました。要は「俳優も身体もいいじゃん!」みたいな。
— 園田喬し/演劇ライター (@doughnutwork) July 9, 2023
演劇ライターの園田喬しさんとは、『斗起夫』の終演後にもあいさつをさせてもらい、たくさんの感想と助言を頂戴した。なかでも、僕が所属するぺぺぺの会のことを「言葉の団体」と評してくださったのはとても嬉しかったし、やはり自分たちの武器は言葉なのだ、と再確認する機会にもなった。思えば、ぺぺぺの会の前身の団体fukuroda no takiでの公演『獄中のユーチューバー』の頃から言葉は僕たちの重要なツールだった。
ぺぺぺの会の言葉の特異性はそのエクリチュール性にある、と自覚している。エクリチュールとは、簡単に言えば、「書き言葉」であり、その対照に位置するパロールが「話し言葉」と訳され説明されることが多いが、それだと細かいニュアンスがこぼれ落ち、また、例外的な事象が発生するのでエクリチュールはエクリチュールとして、パロールはパロールとして、表記することとする。
自分なりの解釈でエクリチュールを説明するとすれば「言葉そのものを尊重する姿勢」のようなものである。まぁ、だいたいそのようなニュアンスで読みとっていただけたら嬉しい。
少なくとも、ぺぺぺの会の台本はそのような姿勢で書かれて、そのような姿勢で発語される。それらは台本が文語体であるとか口語体であるとかそういうことではなくて、ただただ言葉と向きあう姿勢についてを述べている。
「現代口語、というジャンルの演劇があるせいで、口語=話し言葉、文語=書き言葉という誤ったイメージが、演劇界には定着していると思うんですよね」
とあるインタビューを終えたあと、雑談らしく語りあっていた。
同じ「話し言葉」を口語として捉えることもできるし、文語として捉えることもできる。それは捉える側の姿勢の問題なのだ。我々ぺぺぺの会はこの企画で同じインタビューを3回繰り返す。1度目は25つの定型質問をインタビュイーに対して投げ掛ける。インタビュイーが答えを返してくれる、その返答は純粋に「話し言葉」であるといえる。
どのような手続きで言葉が口をつくのかにはその人その人の特徴がある。
インタビューに協力してくださった方のなかには書き言葉的に話すなぁ、と印象を受ける人もいた(僕もその類型の人間だからよくわかるのだ)、けれどもそれがいくら書き言葉的であったとしても、インタビュアーとインタビュイーの会話のなかで、今まさに生成されている言葉である以上、純粋に「話し言葉」でしかない。
僕は、その「話し言葉」を文語に変換していくことはできないだろうかと考えたのだ。ぺぺぺの会が自らの特異・得意(エクリチュール的性質)をもとに「話し言葉」を表現するときに演出家や演者は、具体的にどのようなステップを踏んで自らの表現にたどり着いているのだろう?——この旅は、手法の探究とその言語化のためのプロセスでもある。
今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。 これからもていねいに書きますので、 またあそびに来てくださいね。
