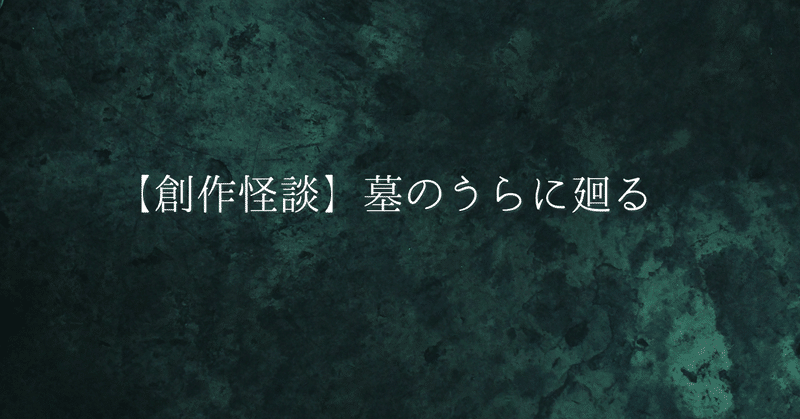
【創作怪談】墓のうらに廻る
子供の頃、僕は近所の寺で開かれる書道教室に通っていた。そこは江戸時代からの由緒ある寺で、地域の多くの家が菩提寺としていた。僕の家の墓もあって、寺は小さい頃から慣れ親しんだ庭のような場所だった。なので書道教室の時だけじゃなく、学校の帰り道にも立ち寄っては境内や墓地で鬼ごっこやかくれんぼをして遊んでいた。
いつもそこで遊んでいたのは、僕を含めて大体5人くらいだったと思う。だけど、たまになんとなく人数が合わない気がする時があった。顔は思い出せないが、誰か知らない子が混ざっているような感覚があったような、知らない笑い声が聞こえる日があったような。
***
ある夏の日のことだった。
「あかい墓のうらに廻ってはいかんよ」
僕が縁側でスイカを食べていると祖母が不意に話しかけてきた。祖母はその頃、少しボケてきたようで、日がな一日ぼぉっと仏間で過ごすようになっていたのだが、その日に限って妙にハッキリとした口調だったのを覚えている。
「おまえには話したことなかったなあ。寺で遊ぶのはいいが、墓には色んなもんがおる」
「あっこは良いも悪いも曖昧な場所だで。とくにな、盆は曖昧なことがようけある」
祖母は、ぼんやりと見つめる僕を諭すように話した。遠くのほうで蝉の鳴き声がする。
「なんで?」そう聞き返す僕に「なんでかは知らんでいい」「知らんでいいことは知らんことだ」とだけ言うと、急にまた、すとーんと肩を落として座り込んだ。
「あかい墓はいかん。いいか、あかい墓には廻らんような」
消え去りそうな声でボソボソと祖母はつぶやいた。
「あかい墓? そんなんあったっけ?」
僕が首をかしげると、祖母はうわ言のように「あかい墓はいかんで」と言って黙り込んでしまった。
カラン。
麦茶を入れたグラスの氷が鳴る。いつの間にか、蝉の声が聞こえなくなっていた。シンと静まる縁側で石のように動かなくなった祖母を見つめながら、僕はなんだか無性に居心地が悪くなり、適当な相槌だけして遊びに出かけた。
夕方、買い物から帰った両親が縁側で座ったまま事切れている祖母を見つけた。そこから数日の記憶がない。僕は祖母の死を知らされて、そのまま高熱を出して寝込んでしまったらしい。
以来、寺には用のない時は行かなくなった。
***
けたたましく蝉の鳴き声がする。
久しぶりに帰省した僕に「たまには墓参りでもして来なさい」と母が言った。あまり気乗りはしなかったが、うるさく小言も御免だったのでサンダルをつっかけながら散歩がてら懐かしい寺に来た。
じっとり汗ばむなか砂利道を歩く。そういえば今日は今年の最高気温を更新する可能性がどうとかニュースで言っていた。空には雲ひとつなく、焦げ付くような夏の日差しは薄っすら蜃気楼のような空気の揺らぎを作り出している。
その時、不意に忘れていた記憶が甦ってきた。
「あかい墓のうらに廻ってはいかんよ」
祖母の言葉が頭の中で木霊する。ゆわん、と目の前が揺れた。立ち眩みのような感覚に襲われて、少し頭を振って顔を上げると墓地の奥で何かがゆらりゆらり揺れていた。
瞬きすると、それは消えていた。なんだ、気のせいか。そう思いつつも言いしれない不安が押し寄せる。やっぱ帰るか。背を向け歩き出そうとした瞬間、声が聞こえた。
振り返ると、墓地の奥で祖母が手招きしていた。
あれ? ばあちゃんだ。
僕は歩き出していた。敷き詰められた玉砂利が、じゃっじゃっじゃと鳴る。祖母は見覚えのない赤い着物姿だった。幾重にも並ぶ墓石が太陽に照らされて、目の前が白く光るなか着物だけが鮮明に浮かんでいた。
どうして、僕は歩いているんだろう。
ばあちゃんなんていないじゃないか。
真っ赤な着物は目に入ってくるが、それ以外は陽炎がかかっているように揺らいでいる。
あかい。真っ赤だ。
陽炎のなかで真っ赤な着物が揺れている。ゆらり、ゆらり。揺れながら移動して行く着物だけが赤い。ゆらり、ゆらり、ゆらり。左右にゆっくり揺れながら、着物は墓石に広がり落ちた。
あ……
あそこになにがあるんだろう。
赤い……墓……真っ赤な……
僕はゆっくり墓のうらに廻る。
「やぁっと、きたわ」
そこには小さな人形が落ちていた。
真っ赤な着物に真っ赤な口紅。だけどそれ以外は真っ白な。目も鼻も髪の毛もない。真っ白な顔の表面に真っ赤な口紅がさしてある小さな人形。
僕は吸い込まれるように人形を覗き込んだ。
「やぁっと、よばれる」
鼻先で、とても厭な臭いがする。
真っ赤な口が、にちゃりと笑っていた。
「やぁっと。やぁっと、な……」
ああ……なんて……厭な臭いなんだ……
***
目を覚ますと僕は病院のベッドに居た。墓地で倒れているところを墓参りに来た人が助けてくれたらしい。熱中症だったんじゃないかと言われたが、特に体に異常もなくすぐに退院できると言われた。
僕を助けてくれた人は「墓地からおばあさんが手招きしていた」ので付いて行ったら僕が倒れているのを見つけたと言っていた。救急車を呼んで介抱している間、おばあさんは少し離れた墓石のそばで何かをブツブツと呟いていたらしい。「おばあさんは?」僕が聞くと、救急車が到着した頃には居なくなっていたようだった。
「でもね、なんか気になってさ。おばあさんが居た場所に行ってみたんだよ」「そしたら、地面にボロボロの赤い布が散乱してて」「ちょっと気味が悪くてさ」
そんな話を聞きながら、僕はいつの間にか手に握っている布の感触が気になって仕方なかった。
出典:尾崎放哉の自由律俳句「墓のうらに廻る」
全て無料で読めますが、「面白かった!」「すき!」なんて思ってくれたら気持ちだけでもサポート貰えると喜びます。
