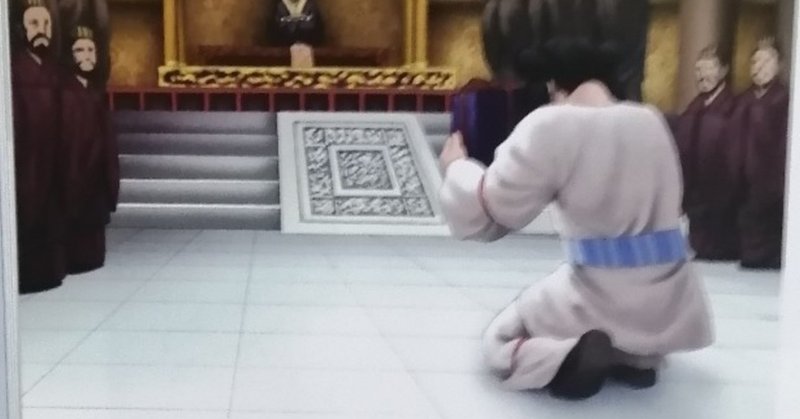
魏志倭人伝から邪馬台国を読み解く その14 中国への朝貢と年代
今回は、当時の日本と中国との国交の記録から、交流の流れや年代を追ってみたいと思います。
□倭国の朝貢
まず驚くのは、この時代で、既に倭人の国々から中国に朝貢している国が30ヵ国近くもあることだ。中国に使者を送れば、中国から自国の領土や王として正式に認められることや、その褒美として高価な物、貴重な物、金品等が与えらること等を韓国側などから情報として、得ていたのだろう。なお、実際に朝貢に来た国名が出ているのは、現存している資料では、『後漢書』の「奴国」、『魏志倭人伝』の「邪馬壱国(邪馬台国)」、その次の『晋書』以降の時代は「倭国」や「日本」になってくるので、30ヵ国は、中国側の誇張表現で、せいぜい数ヵ国だという見方もある。こちらの可能性もあると思う。
いずれにせよ、朝貢に行った最初は、隣国の韓国や朝鮮半島から移住して来た人達から話しを聞き、その真似をしたのだと思う。また、使者を送ることが、そのまま貿易にもなり、最新の中国の文化や技術を学ぶ機会になっていたと思う。我々が思う以上に、古代の倭人は、近隣諸国との交流が盛んだったのだと思う。当時の日本の船や渡航技術、陸路の長旅では、命がけの旅路であり、逞しくて勇気があり、凄いと思う。(なんといっても、中国側は、後漢から三国志の時代は、黄巾乱から始まる戦国時代なので、各国での戦乱だらけの戦時中です。)
補足ですが、朝貢とは、中華の皇帝に対して、周辺国が臣下の立場で貢物を持って挨拶に来ることです。その見返りとして、辺境の蛮族の国々に対して、中国の配下にあるという保証、中国における肩書きや、わざわざ遠方からやって来たことへの褒美として金品の品々などが貰えます。中国皇帝の持つ徳が、周辺諸国にまでおよび、その徳に慕ってやって来るという考え方です。
実際に周辺の国々が貢物を持ってくるとは言え、実は中国からみたら得る物は僅かな物で、実はその褒美に各国に与える恩賞の方がはるかに高額となります。中国側からみたら、朝貢は、体面、気分は非常に良いですが、実際は出費の方が高額で赤字です。実際に後の財政難な中国政権時代には、中国側より、各周辺諸国へ朝貢の停止や期間や回数の削減を命じたりもしたようです。(その場合も、もちろん財政難だからとは言わず、わざわざ毎年来て貰うのが忍びないからとか、これまでの忠節や忠勤への労いのためとかの理由づけになります。)
朝貢が、その際に貿易になったり、中国の学問や文化を得る機会であり、周辺国はメリットが多く、こぞって朝貢した時代もありました。この漢や三国志の時代もまだそんな時代だと思います。
なお、後の時代の遣唐使での渡航の成功率が約半分程や、有名な鑑真が失明までして六度目の渡航でやっと日本へ来た話し等から、弥生時代の渡航はもっと成功率が低いと思われるかもしれません。しかし、実際には遣唐使の時代は、日本は朝鮮半島を統一した新羅とは白村江の戦いをした対立関係があり、それ以降は、一番安全な朝鮮半島ルートでの中国への往来が出来ず、直接中国側へ行く長い距離を渡航していたからであり、この弥生時代の朝鮮半島への渡航は、間にあり渡航の目印や中継拠点となる対馬島と壱岐島のおかげで、もっと成功率は高かったと思います。
なお、古代より朝鮮半島諸国と倭国はずっと良好な関係だったわけではなく、友好の記録もあれば、争いの記録もあります。新羅の歴史書『三国史記 倭人伝 新羅本紀』などには、絶えず倭国が新羅に侵攻してきて、撃退されるような争いを繰り返していた事が記載されています。
いずれにせよ、海洋民族ならではの海の知識と造船や航海の技術により、偏西風、季節風、対馬海流などの向き先の状況に合わせて、倭国から朝鮮半島へ、朝鮮半島から倭国へ、それぞれの方向の渡航が可能な一番適した季節や海流のときに往き来していたと思います。渡航出来る時期を逃した場合には、一年や半年など、次の渡航出来るタイミングまで、その国に滞在して待っていたと考えられます
※朝鮮半島の三国史記については、以下に記載しました。
謎の古墳時代を読み解く その3 朝鮮半島の三国史記と倭王武の活動
※遣隋使については、以下に記載しました。
□前の時代の『後漢書』での朝貢
建武中元二年(57年)
倭奴國奉貢朝賀使人自稱大夫倭國之極南界也光武賜以印綬
安帝永初元年(107年)
倭国王帥升等献生口百六十人
57年に倭の奴国が朝貢した来た記録があり、このときに倭の奴国へ授けられた印が、出土した金印「漢委奴國王」だと考えらている。次の107年の倭国王「帥升(すいしょう、または、ししょう)」が日本人として記録に残る最古の人物名となっている。これは人物名ではなく役職名を表すという説もある。(分かりませんが、もし、古代中国側では他国の固有名を聞いたら、1音につき、漢字一文字を当てて書き表すような場合だと、帥升は、例えば、「すし、しし、しと」等と読むのかもと思います。もしかすると、倭人側が本当は、「すぃし」(水師や水司)などの3音ですが、中国人的に2音に聞こえるような名前や役職だったから、2文字になった可能性もあるかもと思います)。まさに約2,000年前の出来事であり、ロマンを感じずにはいられない。また、この後の邪馬台国の官の中には弥馬升(みましょう、みまし、みまと等)という官名が登場している。音が近い事例があることを紹介しておく。
王自らが中国に行く行動力も凄いと思う。ただし、王自らが行くとは思えないから、王の命令を受けた使者が行ったという見方もあるようだ。王自身がまだ若く父親から後を引き継いだばかりで、臣下や近隣諸国に対して自身の行動力や実力を示すために自らも行くことにした場合や、倭国連合全体の大王が邪馬台国等にいて、その中に各国の王がいたとしたら、大王に朝貢を命じられた国の王が自ら供を連れて行くのは、十分ありえると思う。
また、原文の読み方で別の解釈としては、「倭国の王の帥升等が」ではなく、「倭国王が帥升等を使わし」という意味だという考え方もある。この場合だと、記録に残る最古の個人名は王ではなく、その部下の使者だったことになる。いずれにせよ、確かめる方法はないが、記録上の最古の日本人を表す個人名または役職名であることには変わりはない。
余談ですが、『後漢書』の倭の最後には、会稽の東の海上に夷州(台湾)と亶州(沖縄?)があり、秦の始皇帝が、方士の徐福に、蓬莱の神仙を探しに行かせた有名な伝承のエピソードが書かれています。
□三国志時代の『魏志倭人伝』での朝貢
ここでは、献上品などの情報は割愛していますが、邪馬台国論争で有名な卑弥呼の銅鏡百枚は、この最初の朝貢のとき貰った品々の中に含まれる品物になります。他にも、印綬、刀、金、錦、真珠、采物などがあります。もし、卑弥呼や台与の時代のある墓や遺跡等から「親魏倭王」の金印が出土したら、少なくとも場所に関する邪馬台国論争は終了出来そうです。
私は、もし、親魏倭王(もしくは、親魏委王や魏委国王等)の金印がどこかの墓から見つかったとしたら、それは台与(壱与)の墓だと思います。金印を貰ったのは卑弥呼ですが、卑弥呼が亡くなったときにはまだ魏の時代で金印には効力がありました。その後、魏から晋の時代になり、266年の倭から晋への朝貢後に、金印の効力が無くなったため、その後に台与(壱与)が亡くなった際に一緒に墓に埋めたと思うからです。ただし、金印を墓に埋めるか埋めないかで言えば、国にとって非常に貴重な物のため、証として保持し、埋めない可能性の方が高い気がします。
景初二年(238年)六月
倭国の大夫の難升米と次使の都市牛利が献上
倭の女王卑弥呼を、親魏倭王とし、金印紫綬を与え、帯方太守の位を授けた。
難升米を率善中郎将とし、牛利は率善校尉とし、銀印青綬を与え、下賜品を与えた。
正始元年(240年)
帯方郡の太守の弓遵は建中校尉梯儁等を派遣し、詔書、印綬を捧げ持って倭国へ行き、これを倭王に授けた。
正始四年(243年)
倭王が大夫の伊聲耆、掖邪狗等八人を派遣し献上
掖邪狗等は等しく率善中郎将と印綬を受けた。
正始六年(245年)
倭の難升米に黄色い軍旗を賜い、帯方郡に付して授けた。
正始八年(247年)
倭女王の卑弥呼が載斯烏越等を帯方郡に派遣、狗奴国と戦争状態であることを説明
帯方郡の大守の王頎が、塞曹掾史の張政等を派遣し、張政は詔書、黄幢をもたらして難升米に授け、檄文をつくり、これを告げて諭した。
卑弥呼は死に、直径が百余歩の冢を大きく作った。
男王を立てたが、国中が従わず、卑弥呼の宗女、十三歳の壱与(台与)を立てて王と為し、国中が遂に安定した。張政たちは檄をもって壱与(台与)に教え諭した。
壱与(台与)は倭の大夫の率善中郎将の掖邪拘等二十人を遣した。
卑弥呼の使者に掖邪拘がいて、壱与(台与)の使者にも掖邪拘がいるので、この二人は同じ邪馬台国の政権基盤を引き続いでいることがみてとれる。少なくともここでは、倭国、邪馬台国の政権交代は行われていないと思う。
難升米の活躍も目立つと思う。このため、古くから、卑弥呼の男弟である説(卑弥呼が信頼、弟としては名前が出て来てないから)、伊都国の王(外交を担う重要国だから)、邪馬台国の男王(卑弥呼は倭国全体の女王だから)、邪馬台国の外務大臣に当たる人物、魏や帯方郡から派遣されてる人物(魏からの厚遇、信頼度が高いから)など、様々な解釈がある。私は、自然に卑弥呼が信頼していた邪馬台国の中心人物の1人(邪馬台国の外務大臣に相当)か、邪馬台国内での地位、力を持っていた豪族、実力者の1人だったと思っている。
倭国が最初に行き普段のやり取りしているのは帯方郡(朝鮮半島の北側の上部にある)の太守だ。仮に倭国の各国々から帯方郡に挨拶に来ていても、その後に中央の洛陽に皇帝に会いに行かなければ、最終的に集約される正史の記録には残らないのかもしれない。
ここで驚くのは、倭国側から一方的に中国に行くだけではなく、中国側からも使者が来ていることだ。中国側からも、授与する書や品々をわざわざ倭国に持って来るというのは、凄いと思う。はるか遠くの洛陽から帯方郡に運び、帯方郡が倭国に運んでいると思うが、かなりの労力と出費が発生する。単に返礼に品々を持って来ているだけではなく、倭国に対して、何らかの中国側の目的、興味関心事やメリットがあったはずだと思う。
例えば、始皇帝の徐福の神仙、不老長寿探しのような倭人の長寿の秘訣を探るなり、実際に倭国を帯方郡に組み入れて自国の領土にしようという国力、軍事力の偵察を兼ねていたり、倭国の珍しい産出物を入手して交易をして儲けようなりの中国側としての別の真の目的があると思う。でなければ、金印など製作に時間がかかる品物は、時間また翌年や数年後に来るようにと命じ、次回に会いに来たときに皇帝が使節と接見して回賜という形で授けて返礼品も一緒に渡せば良いからだ。
倭国→帯方郡→魏の都の洛陽
倭国→帯方郡
魏の都の洛陽→帯方郡
帯方郡→倭国
倭国は帯方郡の管轄であり、倭国にとって、帯方郡が外交上の重要な窓口であることが良く分かる。
□次の時代の『晋書』での朝貢
晋書 四夷伝 倭人
宣帝之平公孫氏也(238年8月) 其女王遣使至帶方朝見 其後貢聘不絶 及文帝作相 又數至
泰始初(265年) 遣使重譯入貢
晋書 武帝紀
泰始二年(266年)十一月己卯 倭人來獻方物
魏の司馬懿(三国志ファンには超有名なあの司馬懿仲達。曹操の部下、諸葛亮公明と敵対。後に魏を乗っ取り晋を興した司馬家の祖となる人物)が、遼東の燕王と名乗っていた公孫淵一族を滅ぼした(238年)。その後に、倭国女王からの使者が来たことが書かれている(まさに、公孫氏燕国が滅ぶような大戦乱中に、卑弥呼の使者が会いに行けるわけがないため、238年は間違いで239年以降と考える説もある)。これは、『魏志倭人伝』の卑弥呼が親魏倭王とされたときと年代が同じため、この使者は倭国女王の卑弥呼が送ったものと考えられる。265年には、倭国から度々、朝貢があった事が書かれている。継続して定期的に使者を送っていたものと思われる。
次に、266年に、倭よりへ晋へ使者が来たことが書かれている。ちょうど王朝が変わった次の年なので、帯方郡などから情報を得ていて、新しい王朝への挨拶にいったのかもしれない。女王という記載は無いが、こちらは、年代的に壱与(台与)が送った使者と考えられている。おそらく壱与(台与)の年齢的には、29~32歳くらいだと思う。特に記載がない以上、その可能性は十分あると思うし、また別の男王に変わっていたとしても不思議はない。
※『晋書』に関する記載は以下のリンクです。
謎の古墳時代を読み解く その1 晋書の倭国 太伯の末裔と朝鮮半島との関係
□魏志倭人伝から明らかになる年代
後漢書
桓 靈閒 倭國大亂 更相攻伐 歴年無主 有一女子 名曰卑彌呼 年長不嫁 事鬼神道 能以妖惑衆 於是共立爲王
後漢の桓、靈帝の時代(146~189年)に倭国大乱とある。何年間も王が不在だったという記載もある。
丁度このときお隣の中国でも、184年に黄布の乱が起きて、この反乱より漢が終焉を迎えていき三国志の時代に突入していく。
魏志倭人伝
其國本亦以男子爲王 住七八十年 倭國亂 相攻伐歷年 乃共立一女子爲王 名曰卑彌呼 事鬼道 能惑衆 年已長大 無夫壻 有男弟佐治國
こちらには、残念ながら時代を明記する情報はないが、元々は男子の王70~80年続いていて、この間に倭国が乱れて何年間も攻撃しあったいう記載がある。卑弥呼が王になったときに既に年長大だったのか、238年に朝貢してきたとき、記録を書いているときに年長大だったのかは、見解が別れそうだ。
これまでの中国正史に書かれている年代をまとめると概ね以下のようになる。文章の解釈次第な部分があるのと、『日本書紀』等の記載内容と照らし合わせて修正する解釈などもある。
57年 倭の奴国から漢へ使者
107年 倭国王帥升等が漢に朝貢
109、119~189年頃? 男の王で国が争い
146~189年頃? 上記と同じ、倭国大乱
190年以降? 卑弥呼が女王として共立
238年 倭国の卑弥呼が魏に使者を送る
243年 倭国の卑弥呼が魏に使者を送る
247年 狗奴国との争いを使者を送り報告
247~248年? 卑弥呼が死亡、百余歩の墓
247~248年? 男の王が立ち、国中従わず
248~250年頃? 壱与(台与)が女王になる
248~250頃? 壱与(台与)が魏に返礼使者
265年以前 倭からの使者がたびたび訪問
266年 倭人から晋へ使者が訪問
1世紀から3世紀の倭国の活動した情報が、現代にこれだけ記録に残っているのは、大変感慨深い。まさに中国側での歴史の記録と、その写本のおかげであり、大変ありがたい。
なお、この年代は、中国だと、漢(後漢)が25年~220年、魏呉蜀の三国志が220年~265年、晋が265~420年となる。
□卑弥呼の年齢は
仮に卑弥呼が王になったときは、壱与(台与)と同様に若いとき(15歳)に、190年に王になり、248年に死亡したと仮定すると、58年間の統治で73歳で亡くなったことになる。同様にいくつかの案を仮定すると以下となる。以下のような年齢だったと考えている方々も沢山いる。当時の平均寿命(40~50歳くらい)や、王としての行動力を考えるとちょっと高齢すぎる印象はある。なお、参考までに、年齢的には、三国志の曹操や劉備等よりは年下世代になり、呉の初代皇帝の孫権や先の魏の司馬懿仲達のような世代となる。
190年 15歳 58年間 248年 73歳
190年 30歳 58年間 248年 88歳
195年 15歳 53年間 248年 68歳
195年 30歳 53年間 248年 83歳
200年 15歳 48年間 248年 63歳
200年 30歳 48年間 248年 78歳
実は、『梁書の倭人伝』には、「漢の霊帝の光和年間(178~183年)に、倭国は乱れ、戦いあって年月を経た。そこで、卑彌呼という一人の女性を共立して王と為した。」という記載があります。
後の時代に後付けされた「霊帝の光和年間(178〜183年)」という情報が正しいのかどうか、なぜ急に年代が分かり書かれたのかは分かりません。もし仮に183年に15歳で女王になったとすると、魏に朝貢したのが70歳で、亡くなった248年は80歳となります。もし共立されたときに既に年長大だったとすると、仮に183年に30歳だと、亡くなった248年は95歳です。
かなり後の時代に後付けされた情報であり、卑弥呼がかなり長寿になるのと、70〜80年間の倭国大乱の時代もかなり短くなり『魏志倭人伝』の内容とも異なるため、ここでは、『魏志倭人伝』の内容で考えています。
仮に、238年や240年の親魏倭王のやり取りのときに丁度卑弥呼が年長大(30歳以上)だったと仮定し、248年の死亡だとすると、以下のようになる。こちらだと、当時の平均寿命のような印象になり、現実的に祭事を司る王として成立しそうな印象だ。このような年齢だったと考えている方々も沢山いる。なお、こちらだと、三国志では、曹操の孫で曹丕の息子である魏の二代目皇帝の曹叡や、蜀の武将の姜維などと同じような世代となる。
225年 15歳 240年 30歳 248年 38歳
220年 15歳 240年 35歳 248年 43歳
215年 15歳 240年 40歳 248年 48歳
210年 15歳 240年 45歳 248年 53歳
205年 15歳 240年 50歳 248年 58歳
個人的には、年長大の言葉のイメージが35歳くらいなので、上記の太字くらいではないかと思う。240年には実際に中国の使者にも会ったはずであり、それ以上の歳ならば、年老いて、老婆で、長寿でなど、もっと他の表現になる気がする。
一方の壱与(台与)はどうかというと、248~250年頃には壱与(台与)が返使を送っていて、265年以前にも度々使者が来ている記録があり、266年にも朝貢の記録があるので、普通に解釈すると、壱与(台与)の時代がそのまま続き、倭国からの訪問、両国間での交流、交易が続いたのだと思う。仮に壱与(台与)が四十代半ばから後半くらいまで生きて王だったとすると280年頃くらいまでが、その統治期間となる。
⬛次回は、邪馬台国が九州内にあった根拠について
最後までお読み頂きありがとうございました。😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
