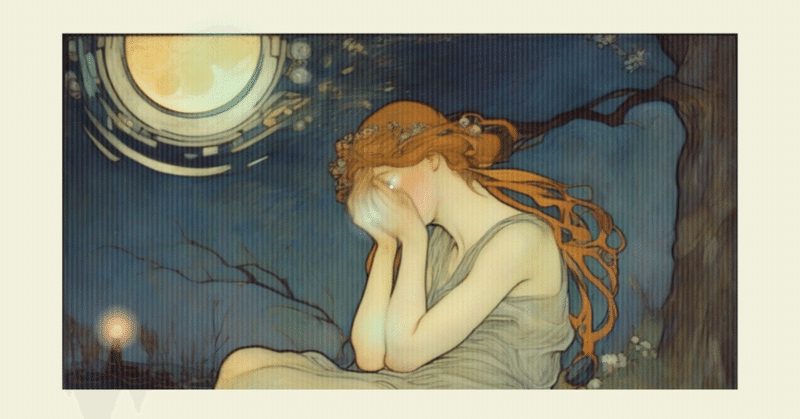
「女記者が見た、タイ夜の街」第1回:バンコク・タニヤ嬢に泣かされた夜
(注:このルポには、セクハラなど性的な描写が出てきます。タイ人女性の名前は全て仮名です)
■長い夜の始まり
2023年5月のある平日、私はタイに在住する3人の男性らと、成り行きでバンコクの歓楽街、タニヤのクラブに向かっていた。
3人のうち1人は、タイで事業を展開する50代の日本人男性で、タイ在住歴は30年以上のA氏。前職で取材させてもらったことを機に交流することが増え、会食に呼んでもらっていた。
その日、A氏から紹介されたB氏とC氏も、A氏と同年代の男性で、20年以上タイに住んでいるという。30代の自分にとって3人は、年齢的にも、タイの滞在歴でも「大先輩」であり、彼らの娘が私の年齢でもおかしくない面々であった。
会食の途中、自分が「タニヤの変遷を調べている」と話すと、3人とも目の色が変わり、話題がいつまでも尽きなかった。この手の反応を受けるたび、一部の日本人男性にとってタニヤという場所は、「語っても語りつくせない聖地」のような印象を受ける。
ワインボトルを一本あけ、すっかりできあがったA氏が、「話すより、行った方が早い!」と声を上げた。そうして私はその夜、ひさびさにタニヤに足を踏み入れることになった。
■コロナ禍を経たタニヤ通り
21年の厳しいロックダウン中に訪れて以来、夜のタニヤに来たのは2年ぶりだった。
飲食店の営業が制限されていたロックダウンの間、通りに人は誰もおらず、まるでゴーストタウンのようになっていたのを思い出す。
その時と比べると、タニヤ通りで飲食店の営業は再開し、女性らが椅子に座ってずらりと並ぶ光景が戻っていた。それでも、平日の夜ということもあってか、客の姿はほとんど見当たらない。なんとか客を確保しようと、私たち一向に通りの女性らから熱い視線が注がれていた。
A氏の行きつけのクラブの前にくると、いつも指名しているのであろう女性がA氏に駆け寄ってきて盛大にハグをし、満面の笑みを見せていた。
「キョウ、オキャクサン、ダレモイナイ!」
女性が大声でそう言うのがおかしくて、思わず笑ってしまった。
A氏以外は適当に女性がついて、計8人で狭いエレベーターに入り込み、店へ向かった。
その時である。酔いが回っていたB氏が、目の前にいた女性のお尻をおもむろにつかみ、「これがタニヤ流のあいさつだ!」と叫んだ。
女性はぎょっとした表情で振り返ったが、B氏が客である以上、もちろん「やめてください」とは言えない。
「今夜は長い夜になりそうだ・・」
そう思うと、不安は一気に高まっていくのだった。
■タニヤ嬢の苦笑いの理由
店内は、古びたシャンデリアや真っ赤なソファが飾られ、昭和を彷彿とさせる、バブリーなつくりだった。
確かに客は誰もおらず、私たち4人は真ん中の一番大きなボックス席に通された。ぐるりと見渡すと、私たち客1人につき女性2人がついていた。
初めに会話したのは、姉御肌のような雰囲気を持つビアさん(38歳)。普段は美容師をしているが、シングルマザーで子供2人を育てているため、経済的に苦しく、たまに出勤しているという。たどたどしい日本語ながらも、お姉さんらしく話をリードしてくれ、話がはずんだ。
しかし、「日本人に接客するのは好きですか?」と聞くと、「うーん・・・」と顔をしかめてしまった。
そのしかめっ面の理由は、すぐに分かることになる。先ほど女性のお尻をおもむろにつかんだB氏はどんどん暴走し、今度はビアさんの指をなぜか舐めはじめた。
一般的な感覚の女性であれば、ドン引きして逃げ出したくなる情景であることは間違いないが、タイ滞在中にこうした場面に幾度となく出くわしてきた自分には免疫があり(全くあっても得にならない免疫ではある)、ジャーナリストをやっている以上、この程度のことで逃げ出すわけにはいかないのである。
ビアさんは苦笑いをしながらその指舐めに耐えており、もちろん制止するようなことはしない。たまらず、「気持ち悪いので、やめてもらえませんか」と言ってみたが、行為に夢中になっているB氏の耳には全く届かないようだった。
「海外で毎日ストレスにさらされた男性が羽目を外せるのがこの場所なんだよ」と、A氏が言っていたことが脳裏をよぎる。
タニヤのクラブというのは、そういう行為が許される場所なのであり、女性たちも覚悟をもって働いているのだ。
ただ、ビアさんの本音は、先に私が投げかけた質問の答えが物語っていた。生きるということは、本当に大変である。
■女性だから打ち明ける本音
その後、女性らも酒がまわり、カラオケで歌ったり踊ったりして、場は盛大に盛り上がった。金づるにならない女性の私に対しても、「かわいい」「歌がうまい」とおだててくれるので、お世辞と分かっていても、とても良い気分になる。
普段は会社で重い責任を背負い、肩身の狭い思いをしているおじさん達が、綺麗な女性らにこんな風におだてられれば、舞い上がってしまう気持ちはよく分かる。
女性らと打ち解けてくると、おそらく男性客には言いづらいことを私に言い出すようになった。
ビアさんと入れ替わり、私の隣に座ったヌアさん(35歳)。目が大きく、肌が白く、日本人男性に人気のありそうな風貌をしていた。男性らの前では大人しくしていたが、私の隣に来ると、途端に饒舌になった。
例えば、カラオケで玉置浩二の「メロディー」が流れ出すと、「私この歌が大好き!でも、この歌を上手く歌える人ってあまりいないよね」といたずらっぽく笑う。
そして、実際に男性が歌いだすと、
「ほらね!」
やっぱり下手でしょう?といわんばかりに、目くばせしてくるのだった。
■ラリっても心配する友達
ヌアさんの次に隣に座ったのが、目鼻立ちのはっきりしたベルさん(35歳)。とても美人なのだが、少し様子がおかしいように見受けられた。先ほどまで指舐めに必死だったB氏もすぐこれに気づき、「この子は、たぶんラリっている」と指摘する。
確かにベルさんは少し挙動不審で、たまに支離滅裂なことを言いだし、酩酊しているというのとはまた違う印象だった。彼女が確実に薬物を利用しているとは断言できないが、こうした夜の街の女性たちが、生活や仕事の辛さを紛らわせるため、薬に頼ってしまう、というのはよく聞く話しだ。
様子がおかしいながらも、ベルさんはしきりに私に話しかけ、一緒に歌おう、一緒に踊ろうと誘いかけてくる。立って踊りながら一曲歌い終わった後、ぎゅーっと抱きしめられ、その後、右手を差し出してきた。
彼女の手のひらにあったのは、プラスチック製の髪留めで、「あなたにあげる」という。露店で、一個数バーツほどで売っているような代物だ。私に好かれるために贈り物をしようとしているようなその様子が、まるで幼い少女のようで、急に切ない気持ちになった。
ベルさんと席に着くと、今度はなんだかモジモジとしはじめ、私に何かを言いたげにしている。タイ語で「友達をここに呼んでもいいか?」と聞いているようだったが、真意が理解できなかったので、近くにいたママさんに訳してもらった。
「ベルちゃんの友達が、外で座って待機しているのだけれど、ここに呼んでもいいか?と聞いているみたい」
よく聞くと、ここしばらく客がなかなか店に来ないため、友達の収入を心配し、この卓に呼ぶことはできないか?というお願いだった。
すると、見かねたママさんが、「友達は呼べないよ。そんなことはお客さんに頼んじゃダメよ」とベルさんに注意した。怒られたベルさんは、子どものようにしゅんとしてしまった。
もし彼女が本当に「ラリった」状態だったとして、そんな中でも友達の生活のことを気にかけているのか――。酔いが回っていたのもあり、そう考え出すと、ふいに目頭が熱くなってしまった。
■暴走する男性を止めたのは――
感傷的になっていると、事件は起きた。
またもやB氏が暴走しはじめたのだ。
完全に酩酊してしまったB氏は、今度は私にターゲットを定め、執拗に絡んでくるようになった。はじめは少し離れた席から、訳のわからない言葉をわめいていただけだったが、そのうち席を立ちあがって、私の隣に座ろうとしてきた。
「隣にきたら、何かされそうだな」
危険を察知し、とっさにこちらが逃げようとした時である。店の女性らが3人がかりでB氏を制止し、絶対に私の近くにこないように食い止めてくれたのだ。
しかも、さっきまで指舐めされていたビアさんが、B氏に対し、「アナタ、ワタシの隣座る、カノジョの隣に行かない!」と、半ば声を荒げながら、私を守ってくれたのである。自分がセクハラされている時は、黙って耐えていたのに――。
女性らはその後も、B氏が私に近づかないように、見守り続けてくれた。先ほど会話したヌアさんが、また私の席にやってきて、「あの人、キモチワルイね。私たちがいるからダイジョウブ」と肩を寄せて、声をかけてくれた。タイ人女性というのは、本当に優しいのである。
やっと場がお開きになり、B氏と距離を取りながら、エレベーターで地上に降りた。時間は深夜の1時を過ぎていた。その場を一刻も早く立ち去ろうと、会計してくれたA氏にお礼を言い、配車アプリで呼んだタクシーを探していると、ママさんがそばに駆け寄ってきた。
私のスマホ画面を覗き込み、タクシーのナンバーを確認すると、少し離れたところに停まっていた車を見つけてくれた。
私を心配していたのか、手を取り、車内に乗り込むまで、ぴったり傍から離れない。その姿はなんとも男気があふれており、ママさんが男性だったら、惚れてしまうような状況である。見送られてタクシーが発車すると、ようやくほっとできた。
夜の街を取材する以上、こうしたトラブルは起こり得るし、自分でなるべく、リスク回避できるように心がけている。それでも、先ほどまで感じていたママさんの手の温かさと、最後まで守ってくれた女性たちの優しさに包まれ、私はまた、なんだか泣けてしまったのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
