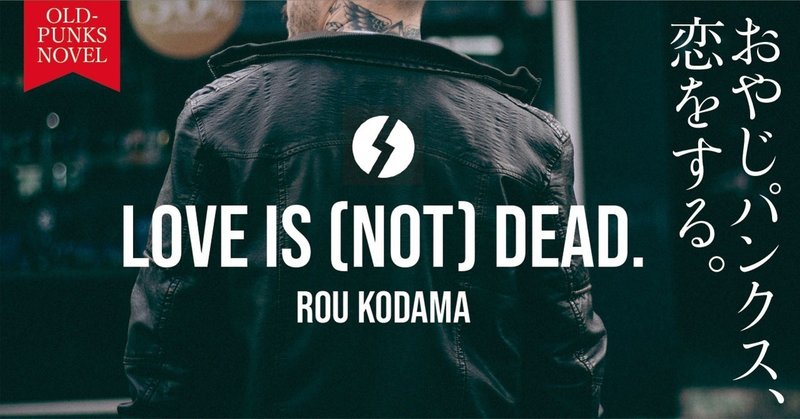
おやじパンクス、恋をする。#130
いや、ここ病室だろ。
絶句する俺を見てその老人は、へっと笑った。真っ白の髪はマッドサイエンティストみてえな感じでもじゃもじゃで、小柄な体格、病気のせいだろうか、浴衣のようなパジャマから覗く胸元はガリガリで、だけど、もうなんていうか、その精悍な顔つきだけでただもんじゃねえと分かるような老人。
「こりゃまた、トッぽいのが来たな」
ああ、風貌にピッタリのしゃがれ声。そしてこういう人たち独特の、なんていうんだろう、ある種の人懐っこさ。だけどその裏側には、近づき過ぎたら食われるかもしれないっていう恐ろしさが見え隠れしている。
俺は梶さんの傍まで行くと、両膝に手を置いて中腰になり、グレ始めたガキの頃先輩にしてたみたいに、「失礼します」とドスの利いた声で挨拶すると、自分の名を名乗った。自分から名乗るのは当然の礼儀だ。
「ああ、いやいや、そうかしこまられても困っちまう。よく来たな。まあ座れよ」
そう言って咥えタバコでベッドを降りると、自らの手でパイプ椅子を一つ用意してくれた。ちらと振り返ると、雄大はまるで若い組員みてえに、入り口んとこで後ろ手を組み、無言で立っている。くそ、話が違うじゃねえか。
俺は椅子に座ると、なにをどうすりゃいいんだとモジモジしていたんだが、そういう俺を眩しそうに見て、梶さんは柔らかく笑った。
「あのバカと、仲良くしてくれてるんだってな。ありがとうよ」
あのバカ、という時に梶さんは、顎で雄大の方を指した。いや、仲良くというか何というか。だけど無言で頷く俺。
「神崎んとこのせがれとも仲が良いんだってな」
神崎んとこのせがれ、ってのはカズのことだ。神埼和弘。俺はまた頷いた。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
