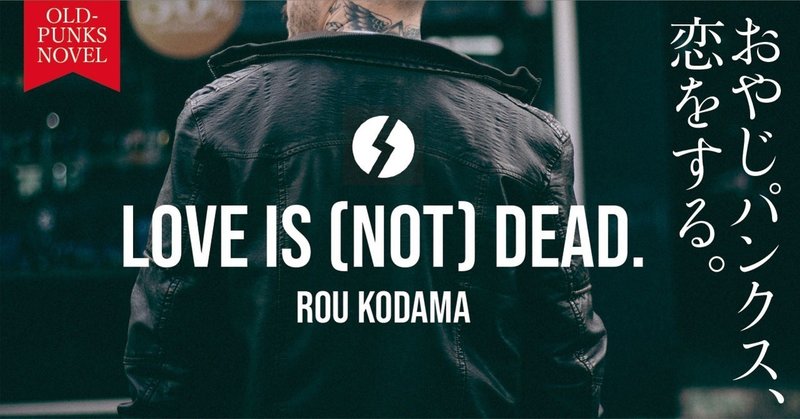
おやじパンクス、恋をする。#171
俺はぎくりと身体を硬直させると、恐る恐る振り返り、「なんだよ」と言った。
苦しげな表情をした彼女が、こっちを見てた。
「おい、どうしたよ」思わず駆け寄ろうとする俺を手で制し、「大丈夫」と彼女は言った。
「でも、もしかしたらさっきまでは、大丈夫じゃなかったのかもしれない。いろんなことに、追い詰められてたのかも。だから来てくれてよかった。ありがとう、マサ、また来てよね」
窓の外は既に暗かったが、照明をつけてない部屋の中はそれ以上に暗かった。むしろ、電飾をつけ始めた外からの光に、まるで彼女は逆光の中に立ってるようにも見え、それは俺が彼女と初めて言葉をかわしたあの日のことを思い出させた。
いや、涼介たちとこの部屋を覗いてたあの日じゃねえぜ。
三十年前、臭えドブ川沿いを歩いている俺に突然声をかけてきた、制服姿の、彼女のことさ。
―もしよかったら、あたしと友達になってくれないかな。
いや、彼女曰く、それは正確じゃない。
彼女はあの時、こう言ったんだ。
―もしよかったら、友達だと思ってていいかな。
そのときの声がまた聞こえた気がした。
俺は今度こそ涙が滲んでくるのを感じながら、「当たり前だろ、バカ」と言った。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
