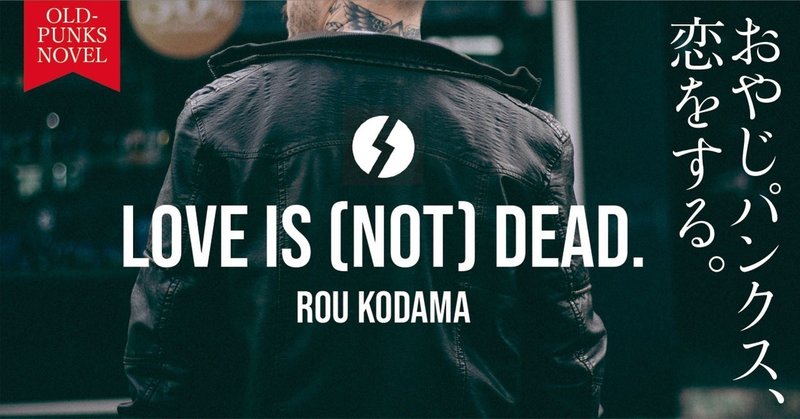
おやじパンクス、恋をする。#144
太陽をバックに立つ彼女は、群青色のシルエットになっていて、その顔はよく見えない。
だからこそなのか、彼女の発したその言葉が、コロナの尖った泡みてえに、ガシガシと俺に浸透した。
それで何となく、彼女の言ってることを理解した。
なるほどつまり梶さんは、自分のあと、彼女を支えてくれるような男の登場を待っていた。そして俺が登場した。梶さんは俺を、なかなか骨のありそうな奴だと褒めた。
俺は、自分でも気色悪くなるような穏やかな笑顔が、自分の顔の皮膚に浮かんできたのを自覚した。自分の好きな男から、男として認めてもらえることほど嬉しいもんはねえ。
「そうかよ。そりゃよかった」
彼女は俺の顔をじっと見つめた。俺が照れて視線を外すと、笑いとも溜息ともつかない声を漏らし、言った。
「あんた、女の趣味悪いんだね」
「おかげさまで」
俺は笑って言った。
俺らはそのまま公園で、ささやかな祝杯をあげた。口に出すのも恥ずかしいが、まあいわゆる、「記念日」ってやつだ。
人間勝手なもんで、自分の事がいい感じになると、自分以外の人のことを考える余裕が出てくる。そして俺が初めに思い浮かべたのは、あの小太りバカのことだった。
「ところで、雄大はこのこと、知ってんのか」
俺が言うと、彼女はあっけらかんとこう答えた。
「うん、ていうかあいつからそうしろって言われた」
「はあ? マジかよ」
「ありがとう。あいつ、なんか顔つき戻った」
「顔つき?」
「うん、今朝早くにあいつ私の部屋を訪ねてきて。スーツ着てたから、あれ、と思ってね」
「ああ、やっぱり会社行ってなかったのか」
「しばらくね。でも、妙にスッキリしたような顔で、マサさんと付き合えよって」
「なんだそりゃ。偉そうに」
「でも、最近あいつ、ずっと変だったから」
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
