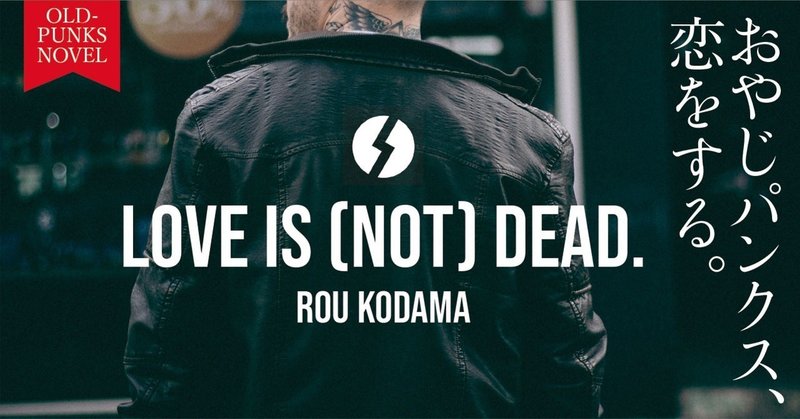
おやじパンクス、恋をする。#055
何度もそうやって自分をバカにしてみても、昨日、彼女と過ごした時間、彼女の微笑み、いちいち強気で断定的なあの言葉遣い、それでいて優しくて何でも受け入れてくれるような包容力、そういう全部が自分の好みで……
いや、今思えばこれって、俺の好みが彼女によって決定されてたってことなんじゃねえのか? 三十年前、あのレストランから盗み見ていた時に、学校帰りの夕方、突然話しかけられたあの時に、彼女が俺の理想の女性像になっちまったんじゃねえのか?
だけど、俺がこれまで好きになったり付き合ってきたりしてきた女は、彼女みたいなタイプじゃなかった。むしろ、正反対。
控えめで優柔不断で、厳つい俺の友達に怯えるような女、どっちかっつうと守ってやんなきゃというような気持ちになるような、頼りない女ばかりだった。
結婚していた嫁も、どちらかと言やそういうタイプだった。で、守ってやってるつもりが気付いたら間男との間に子どもまで作られちまったんだから笑えるが、いずれにせよ彼女みたいに豪快で姐さん的な女とはまるで縁がなかったんだ。
うーん、そう考えるとやっぱり彼女って俺の好みじゃない気がするんだけど、だけど、そんなこと言ったって仕方がねえ。
実際、俺は彼女にこれ以上ないってくらいビビッときちまってるわけで、初恋の相手が乳揉まれてるっていう衝撃の現場に立ち会ってしまったっていう事を差し引いても、やっぱり俺にとって彼女は何か、特別なんだ。
だからそんな彼女が連絡先も教えずに俺の前から去ったこと、水臭く金なんぞを置いていったこと(いやこれは感謝してしかるべきというか、常識的な対応なんだろうが、俺にはなんだかそれさえもムカついた)、そして何より、俺とこの先会う気がないってことに、ひどく傷つき、打ちのめされ、怒りを覚えた。
クソ、こだわってんのは俺だけか。
彼女からすりゃ、突然降ってきた小さなサプライズ、ちょっとした暇つぶしにはなったけど、程度の話なんだよな。
そんで、それが何て言うか、当然の反応だよ。
三十年ぶりの知り合いがいきなり目の前に現れて「初恋の相手でした」とか言われても、「はあ、そうですか」としか言いようがねえじゃねえか。そういう意味じゃ、彼女の反応はむしろ好意的だったと言っていい。
何しろ、笑顔で受け入れてくれて、店まで来てくれて、話を聞いてくれて、一緒に酒を飲んでくれたんだから。
そうやって楽しんで、次の日からはそれまでの日常に戻っていく。普段の生活に戻っていく。それが当たり前だよ。同窓会とかと一緒さ。
クソ、それなのに何なんだよ、俺は何をこんなにこだわってんだよ。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
