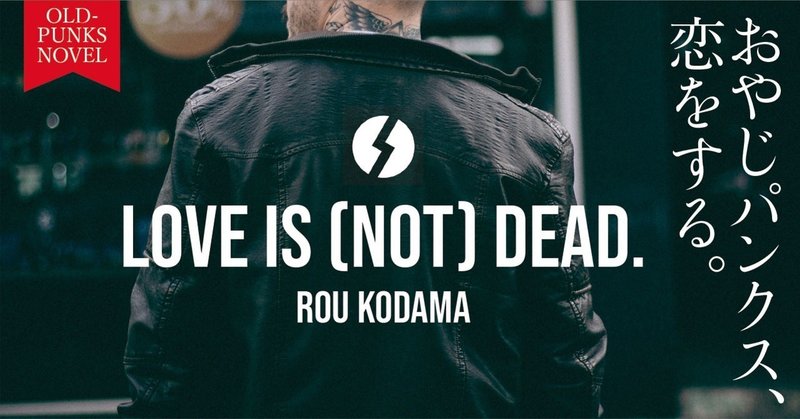
おやじパンクス、恋をする。#185
「ということは、お嬢の知り合いなんで?」
「ええ、そうよ。だから安心してちょうだい」
まあ、実際その通りなわけで、俺らは彼女の知り合いだし、問題を起こしに来たわけでもねえ。
ただ佐島さんの側からしたら、そう言われてはいそうですかと納得はできるはずもない。かといって彼女に対して反論することもできない。佐島さんは口をつぐんだが、その気持ちはよく分かった。
男っつうのは単純なようで複雑で、複雑なようで単純だ。
結局、佐島さんの俺らに対する不信感が、佐島さんの理屈に則って消えなけりゃ、心からの納得なんてできねえよ。
逆に言えば、梶パパは今までそういうことをいちいち気にしてこなかったんじゃないかという気がした。
よく言えばリーダーシップに満ちた、悪く言えば一方的で言葉足らずな方法で、彼らを動かしてきたのかもしれない。そしてそれを見て育った彼女は、疑いなく同じやり方で彼らに接しようとする。
……まあ、実際のところは分からねえ。けど俺の心はくるくると模様を変え、今度はなぜか、佐島さんや他の社員たちに、よくわからない同情をしてしまってた。彼女が放つピリピリした威圧感に、反発心さえ抱いてしまうくらいに。
俺も一応は、アウトローの端くれ。中学で不良業界にデビューして以来、それなりの揉め事を経験してきた。
こういう時の筋の通し方はわかってる。
俺は彼女の脇から佐島さんの前に歩み出た。
彼女が、そして佐島さんが、驚いた顔をした。俺は佐島さんの前で膝を落とし、中腰の姿勢になった。
俺らの業界じゃ、って何業界だって話だけど、とにかくこういう時は、挨拶するのも頼み事するのも謝罪するのも全部この体勢だ。
俺の様子を見て、佐島さんの顔が、ほっとしたように見えた。
この小説について
千葉市でBARを経営する40代でモヒカン頭の「俺」と、20年来のつきあいであるおっさんパンクバンドのメンバーたちが織りなす、ゆるゆるパンクス小説です。目次はコチラ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
