
「うつは心が弱いからなるのではない」の本当の意味
「うつは心が弱いからなるのではない」と言う時、「そうではなく、脳の病気である」と続くことが多い。
これに反論は一切ないのだが、なんだか感覚的にしっくりしなかった。
最近では「うつ病の原因物質を作るウイルス遺伝子」まで発見されていることからも、個人の内的なことが原因ではなく、外側に要因があることに納得感は増しているが、心の底から納得できない感覚だ。
実際に自分の脳は確認できないからかもしれない。
そんな中、『インテグラル心理学 ケン・ウィルバー (著), 門林奨(翻訳)』を読んでいて、この「うつは心が弱いからなるのではない」ということを違う観点から腑に落とすことができた。
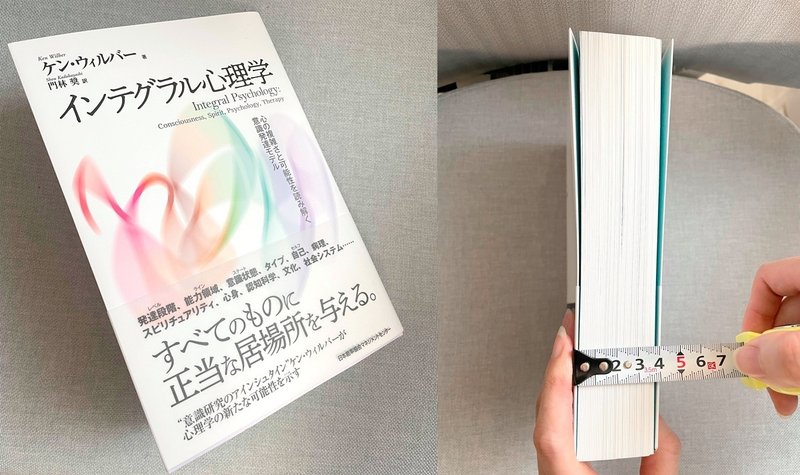
それを言葉で表すなら
「病理性は人間が発達の過程で誰しも持ちうる可能性があるが、発症するかどうかは環境(ある種、運のようなものも含む)による」
ということ。
加えて、
「病理が発生することさえも決して異質なことではなく、発達のプロセスという視点から見れば必然でありうる」
ということだ。
ここからはインテグラル心理学の内容も含めて発達理論に触れ、その意味を書いていきたいと思う。
自己の発達とは?
まず初めに私は専門家ではないので、正確でないことを書いてしまう可能性があり、かつ発達理論だけでも何冊も本が出ている分野のため、ここではかなり一部分だけを取り上げて書くことを前置きしたい。
その上で、ここに書かれている「自己の発達とは何か」を簡単に説明できたらと思う。
自己の発達とは「身体的な発達」のことではなく、「意識の発達」のことである。
「意識の発達」というと、とたんに抽象的になって想像もつかないかもしれないが、私なりの言葉でざっくりというと「感覚 / 認識 / 世界観の変化」といえる。
以前は良いと思えなかった歌や映画が時を経て、違った意味に解釈できたり、なぜか心に染みてきたり...そういった経験はあるのではないか。
このような感覚的・認識的な変化を個人レベルではなく、人間全体レベルで捉えたものが発達理論だ。
ちなみに『インテグラル心理学』の著者ケン・ウィルバーは先代の人々が確立してきた発達理論(ジャン・ピアジェ / ロバート・キーガンetc…)に普遍性を見出し、それをまとめあげた人物。
本書では人間が意識的にどのような発達を遂げていくのかが「支点1~支点9」までの段階で描かれている。
※支点という言葉は少しわかりにくいが、人間の意識の成長は様々な領域を含んだり、多様な面があり、必ずしも「あなたは発達段階☓☓のレベルにいます」と定義できるものではない。だが、自己の重心的な意識状態を表す単語として「支点」という言葉を使っている。
発達理論と病理の関係性
全体としては支点9まである発達段階だが、ここでは支点3までに焦点をあてたい。
「支点1~支点3」までの意識の状態だと世界をどのように捉えているのかはこのように書かれている。
最初の段階では、自己は、相対的に言って、周りの環境と未分化な状態にある。すなわち、どこまでが自分の身体で、どこからが物理的な環境なのか、容易には区別することができない(支点1の始まり)
次に、生後1年以内の何らかの地点において、子どもは、毛布を噛んでも痛くないけれど、親指を噛むと痛いことを学ぶ。
身体と物質のあいだには、違いが存在するのである。
こうして、子どもは身体と環境を区別(差異化)するようになり、子どものアイデンティティは、物質的世界と融合した状態から、情動的-感情的な身体と同一化した状態へと切り替わる(支点2の始まり)
やがて、概念を用いる心が出現し、発達を始めると(特に言えば3歳から6歳にかけて)、子どもは概念的な心(マインド)と身体(ボディ)を区別(差異化)するようになる。(支点3)
つまり、これを図にするとこんな感じになる。

ここで私が最も興味を抱いたのが発達段階と病理の関係性だ。
『こうした病理の諸段階は、部分的には、自己の発達における初期の3つの主要な段階(支点1、支点2、支点3)に対応している。
(中略)
たとえどの段階であっても、発達のプロセスに問題が起きると、その段階に対応する病理が生じる。』
具体的な病理はこのように述べられている。
支点1において、もし自己が物理的環境から自らを差異化させることに失敗し、物理的環境についての適切な像を統合することに失敗すると、精神病が生じる。
(どこまでが自分の身体で、どこからが周囲の環境であるか区別することができないので、例えば幻覚を見ることになる。)
支点2において、もし情動的な身体自己が他者の身体自己から自らを差異化させることに困難を生じると、自己愛性の障害(他者が自分の一部として扱われる)あるいは境界性の障害(他者が常に自分の脆弱な境界を侵犯し、破壊している)が引き起こされる。
支点3において、もし心が情動的自己から自らを差異化させることに失敗すると、そうした不安定な情動的自己との融合が続く。
他方、もし統合にすることに失敗すると、新しく出現した心的-自我的な自己によって、情動的な自己は抑圧(repress)される(典型的なタイプの神経症(※)である)。
(※)神経症・・・別ページにて例として不安、抑うつ、恐怖症、強迫性障害、過剰な罪悪感が挙げられている。
つまりこうなる。

一点、注意したいのは「発達段階における病理」は様々な原因の1つでしかなく、絶対的なものではない。
(冒頭述べたようにウィルス性の場合もあれば、外傷性の病因などもある。)
本書ではさらに、この支点ごとの病理に対応するセラピー(治療法)についても言及されている。この点も非常に示唆に富んでいるが、これはまた何か別の機会に書きたいと思う。
病理の深い意図とは
さて、最初の命題に戻るが「うつは心が弱いからなるのではない」といったときに抑うつは支点3<特に言えば3歳から6歳にかけて>にて、なんらかのまずいことが起きた場合に起きる病理である。
私はこの箇所を読んだときに「幼児の時の問題が大人になってから病理として現れる仕組みは何故なのだろう?」と思った。
そこで、知り合いの方を通じて発達理論に造詣の深い方に直接質問してみた。
そうすると次のような回答を得た。
「子どもの時の病理は大人になってもずっと内包し続けるもの。
それが、大人になって存在が揺さぶられるようなストレスがかかった際に、必要があって出てくる。
心の筋トレのやり直しをするようなものです。」
この時に、「うつは心が弱いからなるのではない」という言葉に対して身体の深いところから湧き上がるような洞察を得た。
もちろん様々な状況にめぐまれ発達段階を問題なく遂げてきた人もいると思うが、多くの人は家族や社会という関係性の中で多かれ少なかれ傷をつくるものである。
その傷を無意識化に沈め、大人になった人がほとんどなのではないだろうか。
その傷には幼い頃に感じたであろう「あなただけの主観性」が佇んでいる。だから必要性がある時に、「思い出してほしい」と病理として現れてくるのだ。
いわばそれは「意識の成長」を促すサインのようなものなのではないだろうか、と思う。
ちなみに発達理論では「後退」をすることは、とても大切なことであると述べられている。
例えば成人で支点5にいるような人でも次の段階に進む際には一度「後退」し、自分の弱い部分や傷を認め、地盤を強化する必要がある。
その後退をするタイミングを知らせてくれるのが「病理」なのではないかと私は思ったのだ。
「発達理論」と聞くとどこか難しく感じるが、シンプルに言うならば、発達段階が進むにつれて人間の意識は広がっていき「より多くのことに気づき、より多くの人(自分も含む)の視点にたてる」ようになる。
(注:発達することによるマイナス面もあり、発達=必ずしも善とは言えない)
今、何らかの病理が現れているのは、より多くの視点を得るために起きているような気がしてならない。
多くの視点には他者理解だけでなく「自己理解」も含まれており、支点3においては自分の傷、抑圧してきた感情などへの寄り添いが求められてくる。
※自分をより客体化してみれるようになり、他者のように自分に接することができるという意味での自己理解(自己に没頭する寄り添いとは少し異なる)
もちろん渦中にいる時(抑うつ症状など)はすごくつらいが、病理に隠されているのは人間の深い部分での意識の発芽のように感じる。
そして、それは「考え方の変化」や「自己受容」ひいては、「生き方の変化」につながってゆく。
冒頭で述べたように「うつは脳の病気」や「ウィルスによって引き起こされる」という側面があることを知るのも、もちろん大切である。
しかし、今まで述べてきたように「病理の裏にある深い内的な意図」に気づくことも、深い自己理解や治癒能力を高めるのにとても大切なことだと自身の経験から思っている。
最後にまとめるとこうなる。
======
● 病理(抑うつを含む精神的な症状)の種は自分自身でも記憶にない幼児〜幼少期にうけた出来事やキッカケにより誰でも内包している可能性がある(その出来事の悲惨さに客観的判断は必要がなく、あくまで主観的なものが尊重される)
● 病理が発生するかどうかは、環境やその人の生き方・必要性に応じて変わってくる
● 病理が発生したとしても、それは「人間的な弱さ」からくるものではなく、むしろ人間に宿っている根源的な意識の成長を促す「強さ(木々の芽が発芽し、成長していくような生命的なパワー)」からくるものかもしれない
======
私自身、10年以上精神的(時には身体的)な症状に悩まされてきて、それこそ初めのうちは混乱・悲しみ・絶望しか湧かず、病理を否定し続けてきた。
けれど、長年付き合っていくと少なくとも「私を悩ませる厄介な邪魔者」という側面だけではない気がしてきたのだ。
今まで述べてきたような「人間の生命が潜在的に宿している成長への衝動」と捉えた時に、病理にまた別の意味を見出すことができ、随分と生きるのが楽になった。
あくまで私の個人的経験からくる洞察であるが、同じような症状で悩んでいる方の何かヒントになれば幸いである。
▲インテグラル心理学の沼へようこそ
サポート頂いたら嬉しくてエクストリーム土下座します!!
