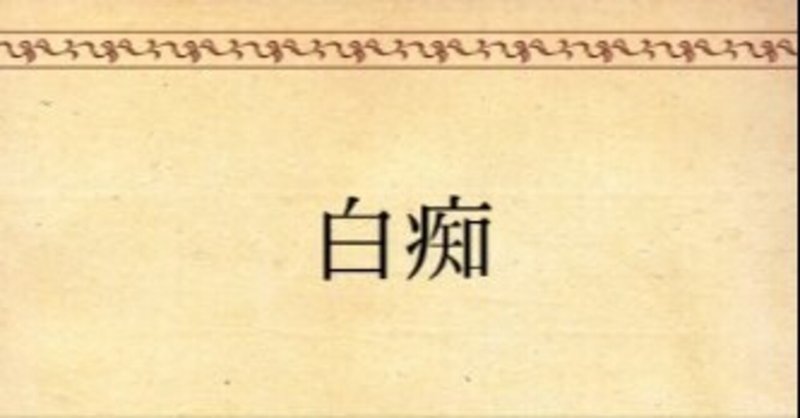
坂口安吾『白痴』について ~豚と私の背中にも光よそそげ~
無頼とかアナキズムという言葉には、なんとなく偏った極端なイメージがあるようにも思うが、よくよく考えればそれは逆で、これらの言葉が、あっちに極端に偏ったものを逆から攻めて調整する性質があるならば、むしろバランスを保つイデオロギーになり得る。
反権力、反体制、反秩序。
「反」というからには、反される側が当然あって、それが誰かに理不尽な状況をもたらしているからこそ、反されるのだろう。
ゆえに、現権力、現体制、現秩序がずいぶん偏ってるなと思えば、少しエッジを効かせて逆側から強めに主張することも必要になる。
そうすることでその時「反」だったものも、うまいことあっち方向に振れれば、そこからは「反」が取れてただのスタンダードになる。
スタンダードに不満がある方が常に「反」になるわけだから、現在常識として通用しているものが、時代によってはアナキズムと呼ばれる日が来るかもしれない。
常識的な価値観というものの軸は、行ったり来たり、左右に振れたり上下したりするもので、未来永劫変わらないなんてことはない。
諸行無常。絶対な本質などなく、ある意味、その法則だけが絶対と言える。
坂口安吾の作風の何が好きかって、私が思うところのこのバランス感覚の秀逸さというか、その行ったり来たりを、短い一つの作品の中で時に大きく、時に細かく、時に痛快かつリズミカルに繰り返すところ。
そこんところの絶妙なセンスが、安吾のアーティスト性だと(あくまでも私は)感じている。
とにかくあらゆる価値観に対して均衡をめざし(?)、あえて果敢にスクラップアンドビルドを繰り返す安吾のこんなマインドを、私は「逆説パンク魂」と呼んでいる。
坂口安吾という人は、「逆から攻めて偏ったものを正す」という至極真っ当な姿勢を持ちながら、たまたまその時に「反」であったから、結果的に無頼とかアナキストなどと呼ばれたに過ぎず、本当は誰より人間の有り様を冷静に、客観的に、そして純粋な心で見つめていた、頭抜けてバランス感覚の優れた作家なのだと思う。
さておき私は、『私は海を抱きしめていたい』の感想文のときも述べたが、振り子のように理屈に揺さぶられ、思考が行きつ戻りつしながら、結果的に極シンプルな答えにたどり着くという、なんだか騙された気分になるトリッキーな安吾の理論構造が好きだ。
複雑に絡まった先のド正論。
すべてを受け止め、すべてを飲み込んで、最後に一つの塊にしてしまう。
どれほど複雑な道筋を経ようとも、結局たどり着くゴールは一点だ。
つまり、最終的に全肯定。それこそ安吾のお家芸。
そしてこの全肯定を、彼は時にファルス(道化)と呼んでいる。
だから安吾作品には、あふれ出るユーモアがある。そこも好き。
『白痴』は、言わずもがなの坂口安吾の代表作であり、様々な人に語られ尽くされてもおり、今更私なんかが何かをあらためて述べるには少々敷居の高い作品でもある。
だから今回は、安吾独特の「振り子」がこれでもかと振れる様子にスポットを当てたいと思う。
イデオロギーとして大きなスケールで揺れている場合もあれば、ごくパーソナルな、ある種卑小とも言えるくらい、人間らしい揺れも数々ある。
そこらへんの人間らしい滑稽味の表現が、安吾特有のファルス芸であり、もしかしたら私が一番影響を受けたところかもしれない。
◇ あらすじ ◇
舞台は、第二次大戦末期の東京。
主人公の伊沢という男は、文化映画の演出家助手をしている27歳。
戦時下ゆえに軍のプロパガンダ映画ばっかり作らされて超ゲンナリしている上に、周りには、流行次第で右でも左でも節操なく傾くくせに、それを芸術だなどとのたまう勘違い野郎ばかりで憤りはマックス。そんな凡庸で無能な者らと自分とは根本的に違うと心密かに思っており、「本当は俺は、もっと意義ある芸術映画が撮りたいのだ」とクリエイター魂を胸の内でふつふつと燃やし続ける伊沢だが、しかし、月二百円の給料を貰うために、自我を必死で押し殺しながら生きていた。
そんな彼は自分のことを、まあまあインテリだし、若いわりにそこそこ社会の裏事情にも詳しい方だから多少のことでは驚かない人間だと思っていた。が、たまたま流れ着いて棲みつくようになった街が、想像を絶するほどのどえらいスラム化ぐあいで、さらにそこの住民も、もと人殺しやらスリの達人やら淫売やら妾やら気が違ってるのやらヒステリーやら白痴やらと、肩書きにしろ気性にしろ、とにかくフツーじゃない人間ばっかで、モラルなんかカケラも見当たらないほど破壊され尽くしており、超ビックリ、超ウンザリ。
ビックリ、ウンザリついでに隣家の白痴の女房がある日突然伊沢の家に転がり込んできて、とりあえず話し合いで解決策を見出そうとするも、いかんせん相手が白痴であるゆえ話にならず、結局、隣家の気のふれた夫と姑にバレないよう気をつけつつ、彼女と同棲を始めるというお話。
◇ 「芸術への情熱」と「現実(給料)」の狭間で ◇
この時代を生きる伊沢の心境の部分が、以下のように綴られる。
新聞記者だの文化映画の演出家などは賤業中の賤業であった。彼等の心得て いるのは時代の流行ということだけで、動く時間に乗遅れまいとすることだけが生活であり、自我の追求、個性や独創というものはこの世界には存在し ない。
伊沢は芸術の独創を信じ、個性の独自性を諦めることができないので、義理人情の制度の中で安息することができないばかりか、その凡庸さと低俗卑劣 な魂を憎まずにいられなかった。
軍の言いなりで、現実とは大きく乖離したニッポン礼賛フィルムを節操なく量産している会社のやり方を伊沢は心底軽蔑しており、その思いを周囲にダダ漏れにさせていると、皆からシカトされるようになった。
それでも自分の芸術に対する情熱は諦めきれず、日々鬱屈を募らせる伊沢。
そして彼はある日、以下のように社長に噛みつく。
戦争と芸術性の貧困とに理論上の必然性がありますか。それとも軍部の意思 ですか、ただ現実を写すだけならカメラと指が二三本あるだけで沢山ですよ。如何なるアングルによって之を裁断し芸術に構成するかという特別な使命のために我々芸術家の存在が――
しかし、間髪入れずに社長に切り替えされる。
お前はなぜ会社をやめないのか、(中略)会社の企画通り世間なみの仕事に精をだすだけで、それで月給が貰えるならよけいなことを考えるな、
いつの時代も変らないことがある。
それは政府とマスコミ報道の関係性。
この小説は、戦時下が舞台であるが、国のイメージとして不都合な真実は、忖度して報道をひかえ、そのかわりに、一体日本のどこにこんな現実があるのかと、まるでパラレルワールドにでも紛れ込んだかのような嘘くさい美談が広められるという現象は、現代日本でも頻繁に起こっている。
そしておそらくいつの時代も、そんな姿勢に反発する者はいるのだが、その者とはおおむね組織の中では弱者であり、立場とか給料といった「現実」を楯に脅され、黙らされるのが常だ。
◇ 「偉大なる戦争」と「卑小なる生活」の狭間で ◇
矛盾と葛藤を抱えながら、不本意で惨めな日々を送る伊沢の前に、ある日突然女があらわれる。
伊沢が自分の部屋に帰ると、押し入れの中にその女が隠れていたのだ。
よく見ればそれは、隣の一家の白痴の嫁、オサヨ。
どうやら、気が違った夫やヒステリー持ちの姑との暮らしに耐えかねて、伊沢の部屋に逃げ込んできたらしい。
深夜に隣人を叩き起して怯えきった女を返すのもやりにくいことであり、さりとて夜が明けて女を返して一夜泊めたということが如何なる誤解を生みだすか、相手が気違いのことだから想像すらもつかなかった。ままよ、伊沢の 心には奇妙な勇気が湧いてき た。(中略)どうにでも なるがいい、ともかくこの 現実を一つの試錬と見ることが 俺の生き方に必要なだけだ。(中略) 彼はこの唐突千万な出来事に変に感動していることを羞ずべきことではないのだと自分自身に言いきかせていた。
深夜に女を追い出すのもどうか?でも、このまま泊めてしまったら、隣家の気の違った亭主にどんな報復をされるだろうか?と逡巡。
一転。
ままよ。どうにでもなれ。
はい、安吾のあっちへ行き、こっちへ行ったあげくの「どうにでもなれ」宣言、出ました。これが好き。
さらに伊沢は、この唐突千万の出来事に感動しており、その感動しているという事実を恥ずべきではないのだと自分に言い聞かせる。
ただ、やはり女を家に泊めるということに関してつきまとう礼儀やモラルについて、伊沢も「普通の男」として悩むことはある。
つまり、手を出すか否か。
しかし女自身は、「普通の女」の貞操観念などはそもそも一ミリも備えておらず、むしろ求められることを当然としているようだ。
事態はともかく彼が白痴と同格に成り下る以外に法がない。なまじいに人間らしい分別が、なぜ必要であろうか。白痴の心の素直さを彼自身も亦もつ ことが人間の恥辱であろうか。俺にもこの白痴のような心、幼い、そして素直な心が何より必要だったのだ。俺はそれをどこかへ忘れ、ただあくせくし た人間共の思考の中でうすぎたなく汚れ、虚妄の影を追い、ひどく疲れてい ただけだ。
結局伊沢は、人間らしい分別など必要あるのか?白痴のごときピュアーな心こそ大事なのではないか?などと、上から目線で何やらご大層な言い訳をしつつ、欲望に身を任せるのであった。
とはいえ、一応伊沢もインテリ紳士という自負があるので、単に欲望にかられるだけの野獣には成り下がりたくないという思いもあってか、「人間の愛情表現は、決して肉体だけではないのだよ」などともっともらしいことを女に対して言ってはみるが、やはり相手はきょとんとするばかり。伊沢の言葉に反応はない。
伊沢はそこでまた、あらためてこう思う。
一体言葉に何の値打ちがあるのか?
こうして白痴の女を前にして、彼の抱いてきた常識やモラルが一つ、二つと失われていく。
そして、戦争にあらためて思いを馳せる。
この戦争はいったいどうなるのであろう。 日本は負け米軍は本土に上陸し て日本人の大半は死滅してしまうのかも知れない。それはもう一つの超自然 の運命、いわば天命のようにしか思われなかった。
こう考えた後、すぐに別の思いがよぎる。
彼には然しもっと卑小な問題があった。それは驚くほど卑小な問題で、しかも眼の先に差迫り、 常にちらついて放れなかった。それは彼が会社から貰う二百円ほどの給料で、その給料をいつまで貰うことができるか、明日にも クビになり路頭に迷いはしないかという不安であった。
お国に忖度してバカバカしいプロパガンダに勤しむ者達を徹底して見下し、時に上司に噛みつくくらいの反骨精神も持ち合わせているのに、たった二百円の給料をもらうごとに命を救われたのごとき幸福感を得てしまう伊沢。
そんな惨めな自分を直視することが、彼にとっては何よりの屈辱だ。
結局会社だとて組織を守るために国に忖度しているわけで、個人のそれと事情は変らない。
規模が大きかろうが小さかろうが、会社だろうが伊沢だろうが、金の契約で繋がっている以上、スポンサーには刃向かえないのだ。
伊沢の感情の振り子が、前後左右、時には上下に激しく振れる様を時系列で並べると以下のようになる。
突然白痴の女が家に来て「追い出すか」迷い、「泊めてやるか」迷い、「女に手を出さないことが本当に正義なのか」迷い、どっちかと言えば「白痴のごときピュアさが必要なのではないか」と自分の欲望に言い訳をしつつ、結局女を家に置くことに決め、気をまぎらわすために「戦争は運命だ」などと壮大なる感慨にふけった直後、「二百円の給料がもらえなくなったらどうしよう」と心配がつのり、だけどやっぱり「芸術は諦められない」という情熱にかられ、なぜかまた「女が欲しい」という答えに達するが、女との生活を思えば、再び「二百円を失うことが怖い」に戻る。(←今ここ)
◇ 「募る憎悪」と「沸き起こる愛情」の狭間で ◇
おそらく伊沢という男は、「俺は他の人間とは違う」と常に自分のアイデンティティを(内面で)逐一鼓舞するクセはあるものの、基本的には一般常識を忘れたことのないどちらかといえば気の小さい人間である。
いわゆる天才肌でもなければ天然でも変人でもなく、そういう基準で言えば、あくまでも普通の人。
なのでさんざん逡巡したあげく、お得意の「どうにでもなれ」精神で白痴の女を自宅に住まわせるようになったまではいいものの、結局伊沢は、バレやしないかと毎日ビクビクしながら日々を送ることになる。
女のことでビクビクしながら、また伊沢は戦争に思いを馳せる。
戦争という奴が、不思議に健全な健忘性なのであった。まったく戦争の驚く べき破壊力や空間の変転性という奴はたった一日が何百年の変化を起し、一週間前の出来事が数年前の出来事に思われ、一年前の出来事などは、記憶の 最もどん底の下積の底へ隔てられていた。
どうやらこの男は、些末で日常的なお悩みに気を取られそうになるたびに、戦争という「偉大な破壊」を思い、現実逃避する傾向があるようだ。
戦争の大きさを意識すると、なんとなく伊沢の気も大きくなるのだろう。しかし、またその直後に思う。
女がとりみだして、とびだしてすべてが近隣へ知れ渡っていないかという不安なのだった。(中略) この低俗な不安を克服し得ぬ惨めさに幾たび虚しく反抗したか、彼はせめて仕立屋に全てを打開けてしまいたいと思うのだった が、その卑劣さに絶望して、なぜならそれは被害の最も軽少な告白を行うことによって不安をまぎらす惨め な手段にすぎないので、彼は自分の本質が低俗な世間なみにすぎないことを咒い憤るのみだった。
伊沢は今度、戦争で世界が破壊されること以上に、隣の女房をこっそり住まわせていることが近所にバレることを恐怖し始めたのだ。
さらにその恐怖をまぎらわすために、いっそ家主にだけでもこの事実を打ち明けてしまいたいと思っていて、しかし、そんな自分の世間なみの低俗なマインドに憤ったりもして、今日も今日とてやっぱり葛藤に忙しい彼。
戦争なみの大きな恐怖には全然開き直れるのに、自分のちっぽけなプライドを傷つけられるかもしれないという小さな恐怖に対しては、常にジタバタ悪あがきする伊沢を見て、私は人間の悲しみを思う。
この愛おしい人間らしい滑稽味こそ、安吾の真骨頂だと思っているのだが、それが正解か否か私は知らない。
ともかく伊沢の矛盾と葛藤の振り幅は、女への愛情に関してよりいっそう大きくなっていく。
伊沢は映画芸術を志しているだけあり、基本「理論」ないし「言語」を拠り所として生きているようなところがあった。
これまでの彼の内面の「あーでもない、こーでもない」という逡巡、葛藤は、まさに人一倍理屈っぽい性格をあらわしている。
しかし、彼が唯一武器とするそのコミュニケーションツールも、白痴の女との間では一切役に立たない。
それゆえ生まれる憤りや苛立ちがあり、その一方で、不思議に幸福をもたらす瞬間もあって、それはそれは伊沢の振り子も激しく揺れるわけである。
この白痴の女は米を炊くことも味噌汁をつくることも知らない。(中略) 二百円の悪霊すらも、この魂には宿ることができないのだ。この女はまるで 俺のために造られた悲しい人形のようではないか。伊沢はこの女と抱き合い、 暗い曠野を飄々と風に吹かれて歩いている、無限の旅路を目に描い た。
伊沢は最初、この女のように意思を持たない、無駄に思考しない人間の方が、自分のように複雑に物を考える人間にとって、実は案外相性が良いのかもしれないとポジティブに考えた。
しかしそう思ったのも束の間、急速にその考えも変化し始める。
白痴の女はただ待ちもうけている肉体であるにすぎずその外の何の生活も、 ただひときれの考えすらもないのであった。常にただ待ちもうけてい た。(中略)在るものはただ無自覚な肉慾のみ。それはあらゆる時間に目覚め、 虫の如き倦まざる反応の蠢動を起す肉体であるにすぎない。
彼は見た。白痴の顔を。虚空をつかむその絶望の苦悶を。ああ人間には理智がある。如何なる時にも尚いくらかの抑制や抵抗は影をとどめているもの だ。その影ほどの理智も抑制も抵抗もないということが、これほどあさましいものだとは!
知性を宿さない、この女の無垢さのようなものに惹かれていたくせに、いつしか同じ理由のもとに「理知がない人間はあさましい」と言い始める。
女の孤独というものに対しても、伊沢はえらく辛辣である。
人間ならばかほどの孤独が有り得る筈はない。(中略)人は絶対の孤独というが他の存在を自覚してのみ絶対の孤独も有り得るので、かほどまで盲目的 な、無自覚な、絶対の孤独が有り得ようか。それは芋虫の孤独であり、その 絶対の孤独の相のあさましさ。心の影の片鱗もない苦悶の相の見るに堪えぬ 醜悪さ。
要は、
普通の人間は、他者との関わっているからこそ、他者と関われないことに寂しさ、孤独を感じるんであって、最初からそうした交流などあり得ない女が孤独を感じるわけないでしょ。もし孤独を感じているのなら、それはもう人間の孤独じゃないね、芋虫と一緒だね。
と言っているわけだ。
なかなか酷い。
かと思えば、本作のクライマックスである大空襲の際には、
伊沢は女と肩を組み、蒲団をかぶり、群集の流れに訣別した。 (中略)女 の身体を自分の胸にだきしめて、ささやいた。「死ぬ時は、こうして、二人 一緒だよ。(中略)この道をただまっすぐ見つめて、俺の肩にすがりついて くるがいい。分ったね」女はごくんと頷いた。その頷きは稚拙であったが、伊沢は感動のために狂いそうになるのであった。
というような、感動的で美しいシーンも展開される。
まったく意思疎通が叶わなかった女が、ただ一度、しっかりと頷くという意思表明をしてくれたことに、狂うほどに感激する伊沢。
ひしと抱きしめ、地獄の果てまで一緒だよ!という勢いである。
そして伊沢は、その勢いのまま、群衆とは逆の燃えさかる火の海へと女と二人で飛び込んでいくのだった。
ここで「逆」を行くところが、やっぱり安吾の小説の主人公らしいが、とにかく伊沢にとって、それは運試しだった。
文字通り、生きるか死ぬかの運試し。
まるでハリウッド映画のラストシーンのごとき、壮大なクライマックスだ。
もちろん、ここで終わればの話だが。
しかし、伊沢と女は生き残る。
◇ 「死の夜」と「再生の朝」の狭間で ◇
雑木林の中にはとうとう二人の人間だけが 残された。二人の人間だけが―― けれども女は矢張りただ一つの肉塊にすぎないではないか。女はぐっすりねむっていた。(中略)今眠ることができるのは死んだ人間とこの女だけだ。 死んだ人間は再び目覚めることがないが、この女はやがて目覚め、そして目覚めることによって眠りこけ た肉塊に何物を附け加えることも 有り得ないのだ。女は微かであるが今まで聞き覚えのない鼾声をたてていた。それは豚 の鳴声に似ていた。まったくこの女自体が豚そのものだと伊沢は思った。
要は、
こうやって寝転がってる女ってさー、まるで肉の塊じゃん。ってゆーか、この状況でよく寝れんな。フツー極限状態をくぐり抜けてきた人間なら、いくら疲れてたって興奮して眠れないもんでしょ。でもさ、この女は寝れちゃうわけ。本能しかないからね。神経が動物なみ。だからさ、結局起きたとしたって何も考えないわけ。動物ね。あ。言われてみれば、この女の寝息、豚の鳴き声っぽくない?つか、もはやこの女自体がほぼ豚。うん。間違いない。
って、言ってるわけでしょ?
おい伊沢よ、さすがに豚呼ばわりは酷くないか。
彼女こそが、手に手を取って戦火をくぐり抜けてきたいわば運命の女ではなかったのか!お前は、あれほどまでに感動に身を震わせ、命がけで壮大なロマンスに身を投じたのではなかったのか!
なのに、せっかく生き残って一息つけば、すでにこんなかよ。
瓦解。
安吾先生のメッセージがひしひしと伝わってくる。
キミね、これが人間というものだよ。
なるほど。
ドラマに酔い過ぎることなく、かといって現実に白け過ぎることなく、フラットに世界をとらえる目を持つことが大事なのですね、先生。
生きている限り、前後左右に心の振り子は揺れ続ける。
生きている限り、上に右に下に左に運命の輪も回り続ける。
夜が白んできたら、女を起して焼跡の方には見向きもせず、(中略)歩きだすことにしようと伊沢は考えていた。(中略)今朝は果して空が晴れて、俺と俺の隣に並んだ豚の背中に太陽の光がそそぐだろうかと伊沢は考えてい た。あまり今朝が寒すぎるからであった。
そして『白痴』を読むにつけ思う。
いかに理想と現実のギャップに絶望しようとも、いかに常識やモラルが崩壊し尽くそうとも、いかに盛大にロマンスの幻想が打ち砕かれようとも、いっそゼロになってくれたのであれば、清々しさもなくはない。
また一から築くのも悪くはないなと。
次に人生にやって来るものが、たとえ希望に満ちていなくとも、美しさに無縁であろうとも、まったく愚かで無意味な出来事であっても、そのありのままを受容し、肯定し、虚飾にまみれず己の本性に正直であり続けようとするならば、太陽の光は、こんな私の背中にもそそいでくれるだろうか。
(END)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
