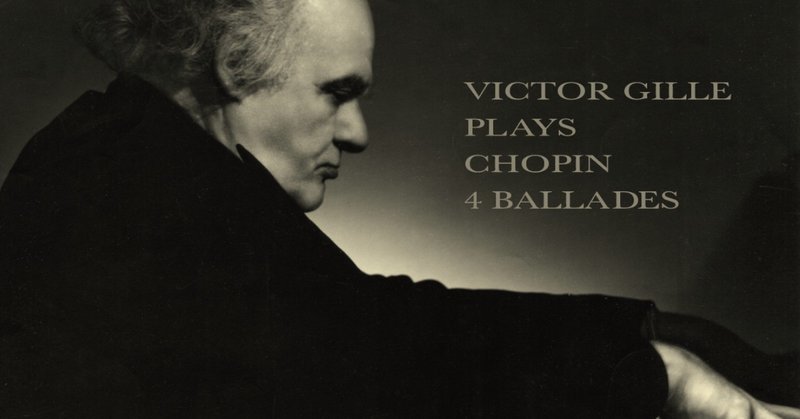
19世紀ピアニズム〜音のドキュメンタリー「ショパン伝統の継承者、ヴィクトール・ジル」
Fragments of History ~ ピアニストの黄金時代を担ったピアニストたち(4)
フランスの偉大なピアニストであり名教師ルイ・ディエメ門下のVictor Gilleは、ショパン自身の演奏を直接知る音楽家たちが出入りするサロンで沢山の助言を受け、それを最大限に生かした演奏で後世にショパン伝統の記録を残すことに成功した稀なピアニストであった。
ジルのレコードを聴くと、現存するピアニストと大きな隔りがある事に驚くだろう。そして、その隔たりこそが、失われてしまった19世紀的ショパン演奏なのである。現代に於いてそれは、ショパン演奏の可能性を取り戻す重要な「手がかり」ではないかと思う。
意外にもジルのレコードデビューは遅く、1930年に入つた頃に漸く残した仏オデオンの10インチ盤1枚2面が最初期の録音となる。選ばれた楽曲はショパン「夜想曲15-2」と「練習曲25-1」という凡庸なものであるが、まだ40代から50代のジルの技巧が衰えていなかった頃の隅々まで磨き上げた名演奏である。これをもってジルの実力を測る基準として捉えるべき出来栄えだ。ショパン自身の演奏は「最小限のルバートで最大の効果をもたらした」と伝えられているが、このジルの演奏は正にそれを具現している。それだけに、この時期のジルのレコード録音が他にないことが非常に悔やまれる。
その後、1940年後半から50年頃にプライヴェート・レーベルのSEPES ST.CLOUDの12インチ盤に1枚2面で「英雄ポロネーズ」を録音した。Disc Radiumに残した晩年の録音と音質も演奏内容も極めて似ている。恐らく当初はこの78rpm盤をコンサート会場で売り、途中からRadiumのLP盤に切り替えたのではないかと推測される。これらのレコードには、ほとんどすべてに直筆サインがある。
自宅の練習室での録音とおもわれるRadiumのセミプライヴェートLP盤、仏Acropoleにショパンのバラード全集と、それ以外の作曲家の演奏を最晩年に残したが、ミスタッチや記憶違いが数多くあり、厳格なリスナーでなくとも心穏やかには聴くことは出来ないだろう。ジル晩年の1960年代頃は、即物主義的なピアニストが中心的存在であり、あまり重要視されなかったことは想像に難くない。
こうして概ね忘れ去られていたVictor Gilleは、ようやくエーゲルディンゲル著「弟子から見たショパン」に、ショパン・サークル口伝の証言者として数か所に登場する。しかし、エーゲルディンゲルがVictor Gilleの証言を高く評価していなかった様で、それは実際に文章の端々からうことが出来る。ショーンバーグが「ピアノ音楽の巨匠たち」でパッハマンに低評価を下した事との類似性を感じさせる。
パハマンとジルはどちらもショパンの19世紀的演奏家として最重要なピアニストであるが、その見まごうような容貌の類似性とは裏腹に、演奏スタイルは一聴全く違ったアプローチに聴こえるだろう。パハマンのルバートは一定のテンポを保った伴奏の上でおこなわれる「ポーランド的」であるのに対し、ジルのルバートはいわゆる「盗まれたものを返さない」自由奔放でより即興的なスタイルであった。ダイナミクス幅の狭いショパン的なパハマンに対し、ジルは特にソナタやバラード、幻想曲などの大曲では、強弱の幅が広い大きなスタイルで演奏する。「葬送行進曲」の演奏を聴くと、かのアントン・ルビンステインが聴衆を魅了した演奏会での描写と酷似していることに気づ貸される。それは音楽を構造的に捉え再構築するニージェルスキのグランドスタイルと共に類まれなショパンと言っていい。
一見相反するアプローチのパハマンとジルの間にそれでも尚且つ偉大なショパン弾きに根源的な共通性を感じるのは、一般的な演奏概念から切り離されたショパン音楽の捉え方そのものではないかと思う。平易に言い替えるならば、ショパン解釈の未知なる「可能性」を指し示す存在という事である。古い録音に耳を傾ける楽しさは、忘れ去られたピアニズムに新鮮な驚きに尽きるのではないか。
皆様からいただいたサポートは、ピアノ歴史的録音復刻CD専門レーベル「Sakuraphon 」の制作費用に充てさせていただき、より多くの新譜をお届けしたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。
