
2022.2.8 日本人のDNAと市場経済システム
江戸時代といえば『鎖国』というイメージを持つかもしれませんが、では資源の少ない日本は外国との窓口を閉ざして、どのように自給社会を作ったのか?
現代の貨幣経済で用いられる仕組みや制度ですが、
・ケインズ主義
・変動相場制
・シンジケート融資
実は、これらは全て『江戸時代』から存在していました。
今回は、教科書が教えない高度社会だった江戸時代の真実について、書き綴っていこうと思います。
日本人のDNAに組み込まれた市場経済システム
アメリカがまだ植民地であった時代から、日本には固有の先進的な市場経済システムが存在し、世界に類を見ない百万人都市・江戸を成立させていました。
日本人のDNAには、過去400年以上にわたる市場経済システムの経験が、しっかりと組み込まれています。
経済史家である鈴木浩三氏の『資本主義は江戸で生まれた』は、私たちの祖先が、江戸時代にいかに高度な市場経済システムを作り上げ、その上で、たくましい経済活動を展開していたかを活写しています。
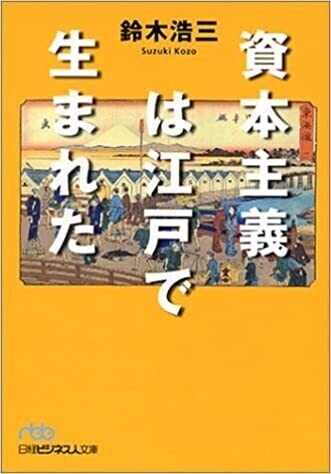
では、この本を頼りに、私たち自身に潜むDNAを思い出してみたいと思います。
そこに、日本経済再生のための重要なヒントが見つかることでしょう。
天下普請のケインズ政策
1590(天正18)年、三河や駿河を本拠地としていた徳川家康は、豊臣秀吉の命令で関東に移り、江戸に居を構えます。
当時の江戸は、海岸沿いは葦原ばかり、東は荒涼とした武蔵野に続く寂しい土地でした。
家康は関ヶ原の戦いで天下を取ると、全国の大名に命じて江戸城の城郭築造工事、江戸市街地や水路網建設に当たらせました。
このように、天下人が諸大名に命じて土木や建設工事をさせるのを『天下普請』と言います。
これは戦時の軍役と同じ扱いで、必要な資金や人員の一切を大名の石高に応じて供出させ、工事と役務を行わせるものでした。
数年に一度命ぜられる天下普請は、大名達に巨額の財政支出を強いました。
それは、幕府から見れば、敵対する可能性のある諸大名の経済力を予め削いでおくという防衛的な目的がありましたが、同時に、軍備に充てられるかもしれない経済力を、平和な『公共工事』に向けるという意味もあったのです。
また、天下普請の間、大名は多くの家臣と共に江戸に滞在したので、そのための大名屋敷や武家屋敷群が建設されていきました。
これらの建設工事が資材や労働力への巨大な需要を生み出し、さらに膨大な工事関係者の生活を支えるための食品や日用品、娯楽などの消費需要が生まれます。
江戸時代初期の70年間、このような公共工事が集中的に江戸で行われた結果、需要が需要を生み出す形で、江戸は高度成長を続けました。
これは、戦後の高度成長と同様に、公共投資を呼び水にして、需要が需要を生み出すケインズ政策でした。
参勤交代で盛り上がる消費需要
1635(寛永12)年に、参勤交代制度が始まりました。
大名達は一年を江戸、一年を国許で過ごします。
これも軍役と同様に、禄高と格式に応じた供揃いを義務づけられました。
供揃いとは、そのまま戦闘に移れる武装した行軍行列のことで、飲料水と薪以外は、武器・弾薬・食糧を全て持ち歩かねばなりませんでした。
参勤交代を含めた江戸在府に必要な経費は、大名の実収入の5~6割を占め、これが大きな負担となり、大名達は国許の米を売り払って貨幣を得て、それで江戸屋敷の生活費や諸経費を支払いました。
殿様に随行して地方からやってくる大勢の家臣団も、江戸での消費需要を盛り上げ、町人層を潤わせました。
そして、江戸屋敷での最大の支出は、幕府や他の大名との交際費でした。
江戸屋敷に常駐した『留守居役』は、天下普請の計画をなるべく早く掴み、思わぬ案件が自藩に廻ってこないように幕府の役人に根回ししたり、あるいは他藩と『談合』したりしました。
そのために吉原や高級料亭での接待や書画・骨董などの贈答が盛んに行われました。
こうした接待や贈答需要が、料理や服飾・工芸などの産業を発展させました。
江戸時代後半には、葛飾北斎や安藤広重などの浮世絵師が活躍し、『名所江戸百景』『東海道五十三次』などが盛んに出版されました。
これらは、参勤交代で江戸に集まった武士たちが、国許に持ち帰る土産であり、また道中のガイドブックでもありました。
さらに、江戸に全国から武士が集まることで、諸国の情報が集まり、また江戸の最新流行ファッションや長唄などの新曲が地方に伝わりました。
民間による商業航路の発達
天下普請のための石材など資材の運搬、さらに、動員した家来や土木作業員の食糧供給のために水運が発達しました。
江戸城の石垣築造では、西国大名31家が3千艘の運搬船建造とそれによる伊豆半島からの石材輸送を命ぜられます。
また東北の大名は、太平洋岸を南下する東回り廻船航路で、江戸まで米や資材を持船で運びました。
家康は東北大名達に命じて、1609(慶長14)年、その中継地点である銚子に港を築かせます。
このルートによる流通が盛んになるにつれ、民間による海上輸送の方が有利となり、東回り廻船航路での定期便が確立していきました。
また、江戸の消費需要が盛り上がるにつれ、日本全国から多種多様な物産が水運で運び込まれるようになりました。
清酒は、摂津国鴻ノ池(現在の兵庫県伊丹市あたり)の酒屋が、1610(慶長15)年に初めて江戸に持ち込みます。
当時、江戸では濁酒しかなかったため、清酒は飛ぶように売れ、初めは人が背負って運んでいたのが、駄馬による輸送となり、寛永年間(1624〜1643)になると船で運ばれるようになります。
醤油も正徳年間(1711〜15)に大阪から持ち込まれて、高級調味料として持て囃されました。
結果、上方の物産を江戸に運ぶために、大阪と江戸の間の民営の定期航路が発達しました。
二つの組織がそれぞれの定期便を運航して、明治に入るまで競争を続けました。
また、江戸時代以前に確立していた大阪と日本海経由で北海道を結ぶ北前船、大阪と瀬戸内、九州を結ぶ西廻り廻船と合わせて、日本列島全体を結ぶ民間による定期商業航路が完成しました。
変動相場制による取引
江戸時代の通貨制度は、『東の金遣い・西の銀遣い』と言われ、江戸の金貨と上方の銀貨が対等な本位貨幣として両立していました。
また、銅貨も少額の補助貨幣として使われていました。
しかも、これらの間の交換比率は変動相場制でした。
このような3貨制は、世界的にみても変動相場制だから、江戸の商人が上方に注文を出すには、銀相場が安い時、すなわち金高銀安の時に行うと有利でした。
例えば、現代日本の企業が国際市場で石油を調達しようとすると、石油の価格の動きと円ドルの交換比率の両方の変動を考えなければなりません。
江戸の商人たちは、すでにそういう世界にいました。
江戸と大阪、京都には、多くの両替商が繁盛していました。
貨幣の鋳造は幕府が行っており、度々金銀の交換比率を公定しましたが、ダイナミックな市場経済には幕府権力も及びません。
両替商たちは、日々の相場を見ながら金銀の両替や売買を行い、相場は『立合場』で決まりました。
大阪の北浜にあった金相場会所では、正月三が日と五節句を除いて毎日、午前10時から1〜2時間、『立合い』が開かれました。
両替商達が少しでも利益を上げようと、血眼になって取引に熱中します。
立会い時間が過ぎると拍子木を打って知らせますが、取引が過熱していて終わらない時には水を掛けました。
これを『水入り』といいます。
『立合い』『水入り』という相撲用語は、当時の商業用語でもありました。
現代のようにコンピュータこそないものの、取引の内容自体は、現代の通貨市場と本質的には変わりません。
両替商の銀行業務
両替商は、為替取引や預金、貸付け、手形取扱いなど、現代の銀行とほぼ同じ事業を行っていました。
江戸―大阪―京都の三都間では、本格的な為替取引が行われていました。
例えば、幕府の大阪御金蔵から江戸への公金輸送と江戸商人から大阪商人に支払われる商品代金を相殺する形で決済していました。
商人は両替商に預金口座を開いて、稼いだ貨幣を預けます。
現代の当座預金にあたるもので無利子でしたが、信用のある両替商と取引がある事は、その商人自身の信用を高めました。
両替商は、取引を希望する商人がいれば、身元や財産状況を徹底的に調べてから口座を開き、中には大名に貸付けを行うものもいました。
諸大名は、天下普請や参勤交代で出費が嵩む一方、年貢収入は頭打ちだったため、その財政状態は窮迫していました。
そこで、家老や留守居役が藩主の代理人として、両替商一同を料理屋などで接待し借金を頼みます。
両替商達は、その大名の信用状態によって貸出し総額を値切ったり、時には断ったりしました。
また、貸出しが焦げついた時の危険分散として、何人かの両替商がシンジケートを組み、貸付けを分担したりしました。
現代の銀行が大企業に融資するのとまったく同じです。
しかし、大名側は地位を利用して、借金の踏み倒しを行う例も少なくありませんでした。
肥後熊本の細川家などはその常習犯で、
「細川家は前々から不埒なるお家柄にて、度々町人の借金断りこれあり」
などと記録にも残っています。
こういうブラックリスト情報は両替商仲間にすぐ伝わって、組織的な貸し付けボイコットや年貢を担保に求められるようになりました。
大名の権威も、市場経済システムの前では形無しだったのです。
通貨政策による物価安定
諸大名は、領地でとれた米を大阪で売って銀を得ていました。
大阪の米市場では需給関係から米価が決まり、その変動を見越した投機や先物取引が行われていました。
近代的な商品先物取引が本格的に成立したのは、1865年のシカゴ商品取引所だと言われていますが、同所の発行する『商品取引便覧』には、
<1730年代に、日本の大阪において先物取引を含む商品取引所が存在していたことは驚くべき事である>
と、大阪堂島の米市場を紹介しています。
大名側が増収方策として米の増産に励んでも、米の供給が増えるほど米価が下がって収入は伸びません。
その反面、その他の商品の物価は上がり続けました。
幕府は米価維持のために、米の買い付けを大阪の豪商に命じたり、大阪御金蔵の資金によって自ら買い付けたましたが、それを売りに出すとすぐにまた米価は下がってしまい、幕府は困って大阪の両替商たちに米価維持策を相談しました。
両替商達は、米が安いのは通貨の質が良すぎるのと通貨供給量が少ないためだから、貨幣供給量を増やすようにと答えています。
この策を直接聞き入れたためかどうかは定かではありませんが、幕府は実際に貨幣の金や銀の含有量を下げる貨幣改鋳を行って、米価上昇と諸物価の安定にある程度成功しました。
現代でも円高を避けるために、政府が円売りドル買いをしたりしますが、幕府の米買いによる価格維持策はそれと同じでした。
また、両替商たちは、通貨の質や供給量が物価にどのような影響を及ぼすのかを既に理解していました。
通貨政策で物価の安定を図るという現代マネタリズム流の手法は、20世紀の社会主義経済での公定価格制などよりも遥かに先進的です。
問屋株仲間は業界団体
商品経済の発達につれて、幕府も年貢米を財政基盤とする体制から商品流通に財源を求めました。
江戸中期の老中だった田沼意次は、現在の同業者団体にあたる『問屋株仲間』を公認して独占を許すと共に、その対価として冥加金、運上といった『間接税』の徴収を始めました。
問屋株仲間は元々米、酒、塩、味噌、炭など、生活必需品12品目の高騰を規制するために、同業組合として幕府が結成を命じたもので、株とはその会員権を指しました。
田沼時代末期の大阪では、130にも上る問屋仲間が公認されていました。
問屋株仲間に入っていない業者が勝手に商売を行った場合は、幕府に訴えれば処罰してくれました。
また、株仲間の一部が幕府の規制に触れる行為を行うと、株仲間全体が連座して処罰の対象となったので、そのような事態を防ぐための自治活動が行われました。
新入りの仲間に対する厳しい選別過程はもとより、仲間の跡取りの品行をチェックして道楽者、怠け者を排除したり、嫁取り、婿取りに対しても全員の承認が必要でした。
問屋株仲間は、幕府の指導や統制を個々の業者に伝える『上意下達』だけでなく、業界としてのコンセンサスをとりまとめて、幕府に伝えるという『下意上達』の機関でもあったのです。
これは、現在の経済産業省が業界団体を通じて、間接的に各事業者を統制するという現在のやり方と同じです。
ただ、間接税も業界団体を通じて徴収するという点は異なります。
400年にわたる市場経済システムの進化
公共投資政策としての天下普請、需要喚起策としての参勤交代、通貨政策や需給調整を通じた物価安定策、高度な物流や金融のシステム、間接税、そして業界団体による間接的な事業者統制…。
こう見てくると、江戸時代に発展した市場経済システムは現代にそっくりです。
明治維新後の『文明開化』が急速に進んだのも、こうした近代的な市場経済システムが実態として既に江戸時代から存在したからです。
経済史的に見れば、明治維新や大東亜戦争敗戦という転機にもかかわらず、江戸時代から現代まで、日本の市場経済システムは環境変化に適応しながら、400年間に渡って連続的に進化してきたものです。
このあたりは、ロシアや中国とは根本的に異なります。
こう見れば、例えば政府(官)と個々の事業者(民)の間に業界団体(公)を設けて、業界としての自治を求めるなどという日本流のやり方が、アメリカ流の『グローバル・スタンダード』に欠落しているからと言って、一概に時代遅れの産物であるかのように見做すのはおかしい事が分かります。
歴史の浅いアメリカの市場経済システムが、まだそこまで到達していないだけの事かもしれません。
僅かここ10年ほどの経済の不振で、私たちの父祖が400年にわたって成長させてきた市場経済システムを弊履のように投げ捨てて、『グローバル・スタンダード』に走るのは、歴史から学ばない愚か者のすることです。
市場経済システムをどう新しい時代と環境に適応させ、その長所を強みとして発揮させていくべきかを考えていくべきでしょう。
今回も最後までお読み頂きまして、有り難うございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
