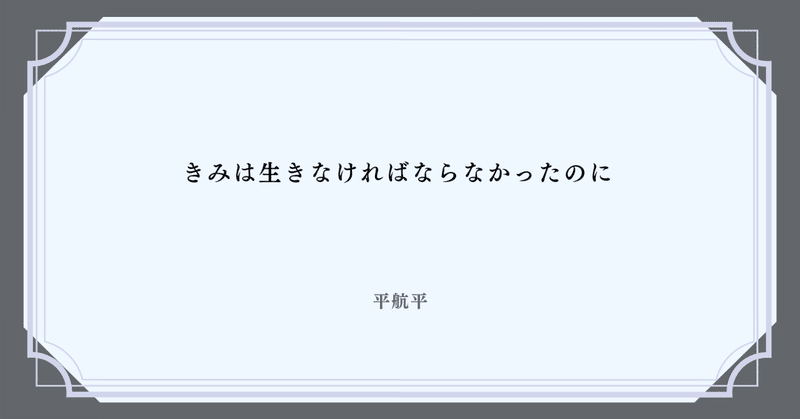
きみは生きなければならなかったのに
春月の微光が女の鼻筋を明るくした。虫の羽音さえ煩く思えてしまうほど静かな部屋、不幸な白いベッドで、女は上下の睫毛をぴったりと合わせている。そうしていたら、女は生きているのか、死んでしまっているのか、不明、しかしそれをどちらかに判断させるものも、ここには無い。
傍らには男がいる。音のしない呼吸を繰り返す女の、手を握ることもせず、髪を撫ぜることもせず、ただ見つめる。見つめる瞳は真黒、表面には女の中高の容貌をいっぱいに湛え、それでいて真黒のもっと奥の深い、暗いところには、執着、春情、あるいはそれに似た何か別のもの、それらを榾にした炎が何やら燻っている。
「わたしが死んだら、どうする?」
ふと、女は言った。小さく開いた薄桃の口唇からぷわり、浮かぶ言葉は童の吹くシャボン玉の如く。
その姿を瞳の中に捉えている男は、今しがた生まれたその浮遊する球体をうっかり壊してしまわないように文字の糸を紡ぎ始めた。
「真珠貝で穴を掘って、きみを埋めよう。そうしたら、天から落ちてくる星の欠片を墓標にするよ」
ほんとうに、糸を紡ぐようにゆっくりと言ったものだから、女の口角が徐に上がるのがはっきりとわかった。その時間を経て、男はこれが唯一つ、解答の存在する問であり、そして自分の回答は正解を貫いたことを覚った。純粋なる喜びが男の皮膚を走って、落ち着いた。
「漱石ね」
女の上機嫌を孕んだ声は、身体を取り囲む白い病室には似つかわしくない色をしている。しかし男は彼女の発するあらゆるものには何時でも果てしない死への諦念が漂っていることを知っていて、これも例外でなく、思わず、目を伏せたくなる。我慢。
「死ぬのかい」
その代わりに、男はもう何度も何度も発した五つの音をまた繰り返した。
「なんと書いていたかしら」
「漱石じゃない、きみが、死ぬのかと聞いているんだ」
「同じよ。わたしも」
しっかり閉じてもう二度と開かない瞼とは裏腹に、薄桃はおしゃべり、簡単に吐かれる絶望の、赤子の力でも打ち込めそうな杭は、男のこころが柔なのか、女の言葉が堅牢なのか。
「でも、あなたは、違うわね」
女はくらくら笑った。それは哀切の笑声、欣喜の笑声、不如意の笑声、解脱の笑声、汎愛の笑声、不条理に向けられた、深い土留色。
途方も、理由も無い。男は思った。この女は死ぬのだ。いや、もう死んでいるのかもしれない。なぜなら、なにがこの女の生命を証明し得るのかわからない。これは、もう、呼吸だとか、鼓動だとか、そういったものは無く、もともとそんなもの、ありもしなかったのに。骸を被った花嫁、輪郭だけの人間、多くの手が作りあげた紙粘土の命、太陽を拝むことを許されなかった室内の向日葵。そんなものなのに。
僅かに開いている窓から、遠くの踏切の音が吹き込んだ。微かな風が吐息のように舞った。男はやはりぴくりとも動かない睫毛から遂に目を離した。真黒は女以外に何を映すべきかしばらく彷徨った。
「きみが死ぬところは見たくないな」
言い訳のような台詞が不幸な白の床に落ちる。割れるような音がした。
男はこの絶望の海に沈んだ哀しい箱を後にすることにした。そうしなければいけなかった。男にはこれ以上、女の傍に寄りそう自信が無い。
立ち上がる身体は、夜闇によく似ている。
「でも」
女の呟きは月の光、後背に刺し込んだ一筋の光、眩しさには振り向かずにいられなかった。二度と瞳に映るまいとどこか安心していた胸の内側が、毒を注射された動物のように暴れた。窓から白い壁に反射する衛星が、変わらず彼女の血色のよい顔を照らしていた。
「死ぬんですもの、仕方がないわ」
男ははっとした。漱石。
玉響――。
女はぱっちりと眼を開けた。
黒い眸のなかに鮮に見えた自分の姿が、ぼうっと崩れて来た。静かな水が動いて写る影を乱したように、流れ出したと思ったら、女の眼がぱちりと閉じた。長い睫の間から涙が頬へ垂れた。……
近い将来に、女は死んだ。
屋上への階段を昇る足音は、永久に止まないノックのように感ぜられた。ドアノブを回す自身の手がやけに青白く気味が悪い。
女の唇によく似た艶の扉の向こうには藍の布が敷き詰められていて、それを横に裂くように落下防止の柵がある。いつもなら興味ありげにこちらを覗く無数の星は、雲の目隠しに遊んでいた。
「おや。めずらしい」
先客がいた。丸い背中を柵に預けて、見知らぬ人間は言った。
「あの女は死んだね。なに、悲しいことではないさ。時代は変遷するのだから、近代生まれの古くさいものには去っていただかねば」
見知らぬ人間の言葉は女と違う。醜い。
男は漏れたインクのようなその言葉から耳を背け、煙草に火をつけた。
落ち着かない。女がこの世界にもういないことを、受け入れるのは困難だ。
「おい、何とか言ったらどうだい」
女の所作は、発する文字は、身に纏う気配は、どうしてあのように美しかったのだろう。珠のように丸く、光を放っていたあの瞳を、忘れられるはずもない。
女は、あの存在は、生きなければいけなかったのに。
悔恨、されど意味は無い。
咥えた紫煙の先からほろり、薄いグレーの灰が落ちて、さらさらと霧散した。
見知らぬ人間がまだ男を見ている。
「死んだ。おまえたちが殺したのだ。そしてもう二度と、漱石は生まれない」
顔面全部で驚愕を現した見知らぬ人間と女が、まるで形が同じだけ、別世界の生物のようで気分が悪かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
