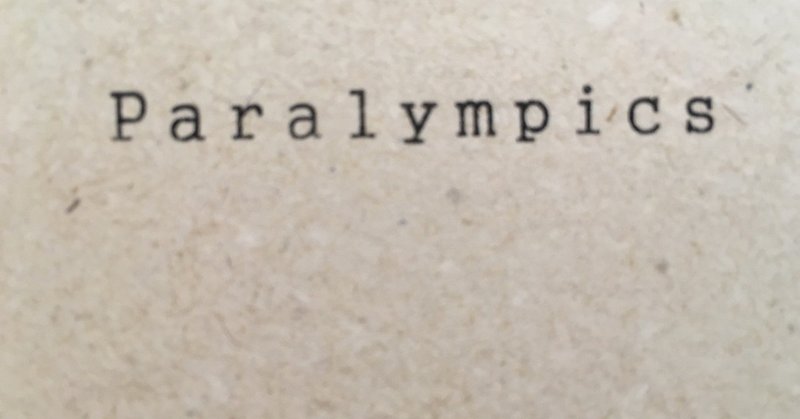
スポーツがもつ社会性を再考する
「失ったものを数えるな。 残されたものを最大限に生かせ」
こんな言葉をご存知だろうか。
これはパラリンピックの父と言われるルートヴィヒ・グットマンが残した言葉だ。グッドマンのこの名言は、パラリンピックの精神を支える言葉として、今では世界中の人に知られるようになっている。
僕とパラリンピックの出会い
僕がはじめて障害者スポーツに出会ったのは、2008年の北京パラリンピックの時だった。NHKで放送された競泳のダイジェスト映像を見て、身体の震えが止まらなくなった。ハンデを抱える人たちが、残された自分の身体を目一杯に使って、一心不乱にゴールを目指す姿が、とにかく僕の心に響きまくったのだ。
あれから数年の時が経ち、パラスポーツの環境も大きく変わった。競技者が増え、装具の機能が向上したこともあり、競技レベルは格段に上がっている。
きっと、2020年は東京でも、僕たちの想像をはるかに超えるパフォーマンスが繰り広げられることだろう。
パラリンピックの発祥
パラリンピックは、元々、リハビリテーションから誕生したスポーツイベントだ。その発祥は、ロンドン郊外にあったストーク・マンデビル病院の医師だったグットマンが、1948年に開催した院内のスポーツ大会だといわれている。
第二次世界対戦中の1944年に、イギリスのチャーチル首相らが、戦争で脊髄損傷する兵士が急増することを見越して、ストーク・マンデビル病院内に脊髄損傷科を開設した。この科の開設は、兵士の治療と社会復帰を目的としたもの。この時に初代科長に就任したのがグットマンだった。
グッドマンは、脊髄損傷の治療にスポーツを積極的に取り入れ、身体機能の強化と回復において、高い成果を上げていく。さらに、スポーツの催しをリハビリの柱の一つと位置付け、院内でスポーツ大会を開催した。この催しこそが、パラリンピックの発祥だと言われているのだ。
この院内大会は毎年開催され、参加者は多様化し、競技種目も増えていった。1952年にはオランダが参加。この年から「国際ストーク・マンデビル大会」として国際大会に発展した。さらに1960年のローマオリンピックに合わせて開催されたローマ大会から「パラリンピック」と呼ばれるようになったのだ。この第1回のローマパラリンピックには23ヵ国・400名が参加している。ちなみに、2016年に開催されたリオデジャネイロパラリンピックには、159の国と地域から、4342人が参加するまでになっている。
初瀬祐輔選手の例にみる、スポーツの持つ社会性
障害者の中でも、特に、事故や疾病が原因で後天的に障害を負った人々は、身体機能の喪失により、生きる気力を失ってしまうケースが非常に多い。
僕が過去に取材した複数のパラアスリートも、例に漏れず、障害を負った直後は「なんで自分だけ」「これなら死んだほうがマシ」と、自暴自棄になる経験をしている。
ここでは、そんな経験をしたパラアスリートの一人、視覚障害者柔道の初瀬祐輔選手のケースを紹介したい。
初瀬さんは、大学2年生の時に、緑内障によって両目の視力を失った。その日を境にして、それまで不自由なく出来ていたことが、一切出来なくなったという。親や友達の顔を見ることはおろか、お箸を持つことも、トイレに行くこともできなくなってしまい、その結果、半ば引きこもり状態になってしまう。
そんな初瀬さんに再びチカラを与えたのが、柔道だった。
知人から視覚障害者の柔道があることを聞き、その世界に足を踏み入れた。その当時のことを初瀬さんはこう語る。
「あの頃は、何かやらなきゃって思っていても、何もできずにいた時期。だから、藁にもすがる思いだったのかもしれません」
視力を失った当初、初瀬さんの周りには障害者は誰一人としていなかった。そのため、自分だけが取り残されたように感じていた。だが、視覚障害者柔道の世界に足を踏み入れてみると、そこは、障害があるのが当たり前の世界だった。中には就職してバリバリ働き、結婚して幸せな家庭を築いている人がいることも知った。
「目が見えなくても、社会で活躍している人がたくさんいるということを知りました。障害を抱えているのは自分一人じゃないって思えたのは大きかったですね。そのとき初めて“視力を失った自分の人生をもう一度生きてみよう”と考え方をシフトすることができました」
障害によって、一度社会のレールから外れてしまい、塞ぎ込んでしまった人間が、スポーツと出会う。スポーツをキッカケにして、似た境遇の人たちが前向きに生きている姿に勇気を持つ。彼らから生きる術を教わり、社会へ復帰していく。スポーツで作り上げたコミュニティには、こんな素晴らしいチカラがあるのだ。
このように障害者スポーツは、社会と密接に結びつきながら、障害者の運動機能の回復や社会復帰の手段として、活用されてきた。この歩みこそ、スポーツが持つ社会性だと言えるのではないか。
スポーツを社会に活かす
このようなスポーツの価値を僕たちはどのようにして活かすべきか。
日本の社会が、東京オリンピックパラリンピックをどのように活用しようとしているのか、については平成27年11月に閣議決定された「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の 準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」をみると良いだろう。
https://www.kantei.go.jp/jp/topics/2015/2020olym_paralym/20151127olym_kihonhoshin.pdf
この基本方針では、2020年のオリンピック・パラリンピックを契機として、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う「心のバリアフリー」を推進することや、ユニバーサルデザインの街づくりを進めることで、共生社会を実現し、障害のある人等の活躍の機会を増やしていくことが明記されている。
僕らは果たしてその意味をどれくらい理解しているだろうか。
「東京パラリンピックを正しく活用して、自分の生きる社会をどのように変えていくか?」
と考えると壮大なことのように感じる。
だが社会を構成する最小単位は一人の人間だ。例えば、僕らが、引きこもっていた人に少しだけ優しくなって受け入れるだけで、社会のあり方はわずかでも変化する筈だ。 一人一人が、小さく変わるだけでも、社会は、変わっていく。
2020年8月25日のパラリンピック開催まであと約1年。果たして、東京パラリンピックの後に、日本はどんな社会が作られているのだろうか。
瀬川泰祐の記事を気にかけていただき、どうもありがとうございます。いただいたサポートは、今後の取材や執筆に活用させていただき、さらによい記事を生み出していけたらと思います。
