
3-3-5. 近世ヨーロッパの学問と思想(1) 新科目「世界史探究」をよむ
奴隷とパンノキ
1775年、北アメリカの13植民地によって構成された大陸会議は、さる4月にイギリスとの戦闘(アメリカ独立戦争)がはじまったことから、9月以降、西インド諸島にすべての商品の輸出を停止することを決議した。
当時の西インド諸島といえば、イギリスが黒人奴隷をつかってサトウキビのプランテーションを展開していたエリアである。

そこへの食料供給がストップしてしまえば、奴隷に食べさせるものがなくなってしまう。農園主たちは危機感をつのらせた。
そこでイギリスが目をつけたのは、探検家ジェームズ・クックが南太平洋のタヒチで発見したというパンノキだ。
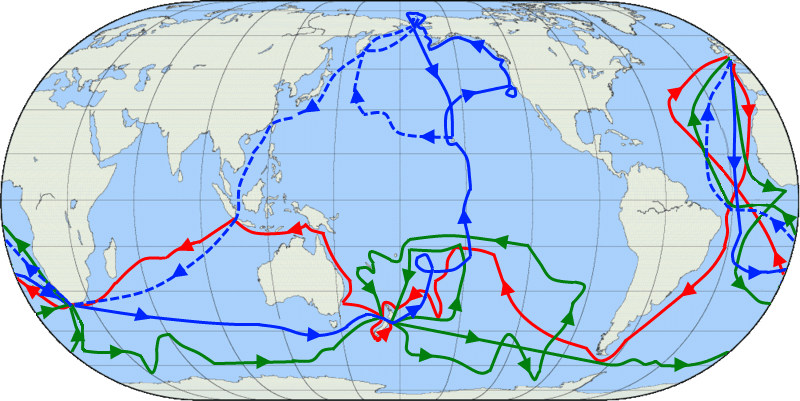
「パンノキをタヒチで獲得し、それをカリブ海に移植すれば、黒人奴隷を養える!」ということで、イギリス海軍の軍艦バウンティ号が派遣され、1789年にタヒチに到着。ところがこのバウンティ号は、タヒチからの帰路で水兵による反乱に見舞われてしまう。これはこれで有名な「バウンティ号の反乱」だ。
とにもかくにも生還したブライ船長は、ふたたび命令を受けて航海を行い、1793年に600本の苗を無事西インドに輸送することに成功したのである。
パンノキは、期待通りカリブ海の気候でよく育った。しかし、それが食料として、ただちに奴隷たちの間に定着することはなかった。現実に食料の不足が起こり、餓死者さえ出たというのに、である。その理由として、奴隷たちがヤムイモなどでかろうじて自給したこと、そしてほぼ同時期にかれらの故郷、西アフリカから導入されたアキー[中略]のほうが好まれて、パンノキは嫌われたことが考えられよう。飢餓のなかでさえ、食習慣や味覚は容易には変わらない、ということだろうか。
熱帯産の有用植物を、別の熱帯地域に移植する。そのような取り組みが、18世紀には盛んに行われるようになった。
パンノキの場合はカリブ海のセント・ヴィンセントとジャマイカの植物園で栽培されてから配布されたが、やがていきなり別の地域に移植するのではなく、ロンドンの王立植物園(ロンドンキューガーデン(1759年設立))に集められ、品種研究がほどこされた後に植民地に移植されることが一般化した。

パンノキの移植にせよ、奴隷への食料供給にせよ、生命を増やすという点では共通している。
そして生命を増やす行為は、すなわち国力を増大させる営みに直結していた。
これから見ていく近世ヨーロッパの学問と思想の動向にも、少なからずそうした背景が色濃く関わっている。
プランテーションの奴隷たちは、農園主の思惑を十分に察していた。子どもに同じ思いをさせたくないと、土地に伝わる薬草を用いて中絶する女性奴隷がいたことも明らかになっている。
「誰が科学をするかは重要な問題である。旅する植物学者がほとんど男性であるがゆえに見落とされる薬草もあった。たとえば、1687年にジャマイカに向けて航海し、のちに王立協会会長になるロンドンの内科医ハンス・スローンが、西インド諸島で探し求めたのは有用な薬草であったが、中絶用の植物に関心が向けられることはなかった。そもそも男性の学者たちは、中絶という薬効に関心がなかった。そうした知の状況を象徴するのがオウコチョウである。西洋では中絶はもちろんのこと避妊も禁止されていたが、女性たちは密かにそうした知識を長い歴史を通して伝承してきていた。(小川眞里子)」(『歴史を読み替える(世界史編)』2014年、154頁から引用)
中絶薬について:メリアン『スリナム産昆虫変態図譜』(1705年)オウコチョウの記載
「オランダ人の主人からひどい扱いを受けていたインディアンは、子供が奴隷になるくらいならばと嘆き(この植物の)種子を用いて中絶を行っています。ギニアやアンゴラから連れてこられた黒人奴隷は、子供をもつことを拒む素振りを見せて、少しでも境遇が良くなるように願ってきました。・・・彼女たちの中には耐えかねて自らの命を絶つ者もいました。」(『植物と帝国』より)
しかし、「産めよ増やせよ」の掛け声のもとで国富を増強しようとしていたヨーロッパ諸国にとって、中絶薬は都合の悪い存在にほかならない。
その研究は、やがて男性を中心とする科学者共同体により、良からぬものとされるようになる。

このように、純粋に学問的な研究や国家の政策とみえる営みであっても、その根底には、その次代の人々がよって立つ世界観や価値観(世界における物をどのように認識するかをめぐる知的な枠組み(エピステーメー))に、色濃く規定されるものである。
ここで少し時間軸をさかのぼり、近世ヨーロッパの学問や思想の特徴を、その経緯をたどりながら明らかにしていくことにしよう。
科学革命の時代
16世紀にアジア・アメリカに乗り出し“視野”をひろげたヨーロッパ世界は、17世紀になると「科学革命」なる時代を迎える。
1609 ガリレイ(伊)望遠鏡を利用
1609 ケプラー(独)惑星運動の第一法則、第二法則を発表
1623 シッケルト(独)計算機を発明
1628 ハーヴェイ(英)血液循環説の発見
1653 パスカル(仏)「パスカルの原理」を発表
1660 ボイル(英)ボイルの法則を発見
1665 フック(独)顕微鏡で観察した記録『ミクログラフィア』刊行
1675 ホイヘンス(蘭)実用的な機械時計を発明
1687 ニュートン(英)『プリンキピア』を刊行
“わけがわからない”ことを“わけがわからない”ままにするのではなく、“キッチリわかるところまで、理詰めや観察で突き詰める考え方(近代合理主義)が確立されていったのだ。
池上俊一氏の近著の説明を引いておこう。
資料 科学革命について
絶対主義が風靡し資本主義が本格化した時代のヨーロッパには、また近代科学が生まれました。一七世紀の科学者らはこぞって近代科学を基礎づけようとして、ギリシャ人とアラブ人が考えだした幾何、算術、代数を自家薬籠中のものにし、さらに発展させていきました。数学の利用は正確さ・精密さをもたらしますが、ヨーロッパの科学はこれを「自然」研究に適用し、また「実験」を重視して実用的な科学を開発していったのです。科学革命の旗手の名は、ガリレオ、デカルト、ボイル、ニュートン、ハーヴィらです。
そう。
科学革命のベースにあるのは、前にも紹介したようにイスラーム科学の業績だ。
その上でヨーロッパが独自に発展させていったのは、世界の成り立ちを数学的に記述していこうとする方向性だった。
天体の動きを観測し、すべての物体の間には、その質量に応じて引き合う力が働いているのだという「万有引力(ばんゆういんりょく)の法則」を導いたイギリスのニュートン(1642〜1727年)は代表的な自然科学者だ。中世以来の研究の進んでいた錬金術(れんきんじゅつ)にも手を出していたものの、観察した結果を「数式」で表すことで、目には見えない力の存在を導き出した点は画期的なもの。中世においては天上は地上とは別格の神に近い世界と考えられていたのだが、ニュートンは両者を区別することなく、いずれにおける運動も数学的に説明することに成功した。そこがすごいところである。
一定の条件におけるさまざまなケースを観察し、そこから法則を導き出す方法を帰納法という。
世界の物事を認識するためには、なにより世界の物事についていろんなかたちで経験することが重要だとしたイギリスのフランシス・ベーコン(1561〜1626年)の発想は、ニュートンをはじめ多くの人々に影響を与えた。
では、彼ら科学者は、どのような場で研究をしていたのだろうか?
以上、この時代の代表的な科学者の業績を紹介しましたが、彼らはルネサンス期の学者のようにパトロンの庇護にあずかることなく、むしろ学会や協会に守られる存在になりました。一六六二年にロンドンの「王立学会」、一六六六年にはパリに「科学アカデミー」が創立され、次の世紀にはヨーロッパ中に君主保護下のアカデミーが広がります。こうした新たな位置づけをうながした要因は、科学が国家のなかの本質要素となったという事実です。また科学革命では「ヨーロッパ」という枠組みが、非常に重要になります。ルネサンス文化もイタリアから北方ヨーロッパ各国に広がっていきましたが、科学革命は、ガリレオからニュートンを経てフランスの数学者・天文学者のラプラスまで、真に国際的(汎ヨーロッパ的)な知的活動が展開されたのです。ポーランド、イタリア、ドイツ、フランス、オランダ、イギリス、スイス、デンマーク、スウェーデンなどきわめて多くの国々の科学者が、この活動に参加しました。彼らは出身国を離れて活躍することもあり、国を超えて交流してもいました。一七世紀が、ナショナリズム、国家理性のぶつかり合いの世紀で、ヨーロッパの一体性でなく分裂が目立つ世紀だと述べましたが、それとは裏腹の文化的統合・協調も広がっていたのは印象的です。
池上氏の説明するように、科学革命は、科学者たちが自国を強国にしようとする国家の庇護を受けながらも、「ヨーロッパ」を単位とするアカデミックな交流のひろがっていく、その2つのベクトルの中で展開していった。
むしろ、国による庇護を嫌い、自由な思索をもとめて国をまたいで活動する思想家もいた。
その代表は『方法序説』(1637)・『省察』(1641)をあらわしたデカルト(1596〜1650年)だ。
彼の人生はまさに流浪そのもの、フランスでイエズス会の学校の中世スコラ学的な教育に飽き飽し、卒業後は「世間という大きな書物」において学ぼうと旅に出た。
折しも三十年戦争(1618〜1648)が始まろうとしていた。
1618年に志願将校としてオランダ軍に入ったと思えば(そこでオランダ人の医師から物理や数学に関する知識を得て開眼する)、三十年戦争が勃発すると1619年にドイツでカトリック側の軍に入った。ドイツでの従軍中での思索をきっかけに、これまでの学問を改革してみようとする意志を固め、1620年に軍を離れて旅に戻る。オランダ、フランス、イタリア、フランス…ヨーロッパ中を経巡り、最終的にオランダに移住し、研究に没頭する。そんななか、1633年に勃発したのが、地動説を支持したガリレオ・ガリレイに対するローマの宗教審問所による有罪宣告だ。
純粋に自然科学の論文を執筆したかったデカルトだが、ガリレイを支持しただけでも異端宣告を受けてしまうような時代である。1637年には自然科学に関する3つの試論と『方法序説』、1641年には『省察』、1649年には『情念論』を著すも、悪目立ちしてしまったデカルトは、自由の国オランダでも肩身が狭い思いをすることとなる。
そんななか、哲学に関心を寄せるスウェーデン王国のクリスティーナ女王の招きに応じ、1649年からストックホルムに滞在するも、翌年死去。まさに旅のような人生だった。
そのような中「じゃあどうすれば真理に迫ることができるのか?」ということを考えたときに、彼は「われ思う、ゆえにわれあり」(いま自分が頭を使って考えている。考えている自分がいるということ自体は、少なくとも疑うことはできない。この考えている私こそが、真理に至る出発点だ)ととらえた。
「なーんだ当たり前のことじゃないか」と思うかもしれないけれど、『聖書』の記述や信仰、迷信や悪弊などにとらわれず、「頭を使って合理的に考える方法を考えよう!」というのは、当時の人々にとっては、まさに“革命的”だったのだ。
自然法
この時代の人々の好奇心は、人間社会そのものにも向かった。
その背景にあるのは、ヨーロッパ人がアメリカやアジアの見知らぬ人々との出会いだ。

たとえばアメリカ大陸の人々の扱いをめぐり、16世紀のスペインで論争が起きたことはすでにこちらで紹介した。
一方、16世紀から17世紀にかけて、イエズス会の宣教師が赴いた中国に関する情報も、ヨーロッパの人々を驚かせていた。
「むしろ中国のほうがはるかに先進的な制度を発達させているのではないか?」
18世紀にはシノワズリ(中国趣味)と呼ばれる中国ブームが巻き起った。
ライフスタイルも価値観も違う人間同士に、共通の「決まり」があるとしたら、それはいったいどんなものなのだろう?「人間なら、いつの時代もどんな場所でも、守るべき不変のきまり」(自然法)というものはどんなものだろう?
そんな議論が盛り上がっていった背景には、キリスト教によるつながりを重んじる中世の価値観の崩壊と、主権国家体制の形成があった。
資料 自然法について
この時代、「自然法」(実定法と異なり、時空を超えて普遍妥当すると考えられる法)思想でも重要な貢献がありました。一七世紀から一八世紀までは、いわゆる近世自然法論の時代ですが、プロテスタントの法学者、グロティウス、プーフェンドルフ、ヴァッテルらは、いかなる状況下でどんな理由があれば戦争が正当化されるかを解き明かし、また戦争が始まった後に軍隊が──戦争に正当な理由(大義)があろうとなかろうと──守るべき規範と、平時に諸国家の外交や通商関係が重んずるべき規範を分けて、それらを自然法にもとづいた「国際法」によって明文化しました。とりわけ有名なのは、国際法の父と呼ばれるオランダの自然法学者、フーゴー・グロティウスです。自然法の根源が人間本性のなかにあり、自然を本質的に社会的かつ合理的だとするグロティウスは、自然法は、疑いを入れない不公正、社会を明確に破壊する行為のみを禁じ、社会的平和を単に保存することのみに向ける戦争があることになります。彼の記した『戦争と平和の法』は、自然法の諸規定と諸国の実定法の法則を説明し、それらの関係を定義できる柔軟な理論システムを構築するという野心的な試みです。中世的なヨーロッパの精神的統一、換言すれば「キリスト教世界」がくずれ、複数の国家の緊張に満ちた共存となった時代に、それぞれの国家の固有の法の有効性をなるべく肯定した上で、諸国の法に服さないいくつかの諸関係、とりわけ国際関係を律する法のあり方が模索されたのです。それは実定的ではないものの、あくまで合理的であるべきでした。そうした国際法の精神が、事実上、先述の「ウェストファリア条約」と「ユトレヒト条約」に結実したのです。
16世紀には各地で王権が権力を強め、それぞれの領域を囲い込み、富国強兵に邁進した。
かつてのローマ教会や神聖ローマ帝国のような、普遍的な権威はもはや通用しない。
そのような現実のなか、王権を支える新しい理論が求められた。
その典型例が、フランスのジャン・ボダン[ボーダン]の『国家論』だ。
史料 ジャン・ボダン『国家論』(1576年)
主権とは、国家の絶対的[訳者注より:ここで言う「絶対とは、あらゆる法の制約の外にあるという意味。]、永続的な権力である。[中略]ひとつの国家の人民や領主たちは、志高にして永続的な権力を、純粋かつ単純に誰かに与え、彼の思うがままに財産と人身と国家全体を処分させ、次いで、彼が好む者に国家を委ねることができる。[後略]
ボダンは、国王といえども、法に従うべしとの中世的な考え方を明確に否定し、国王は法よりも優位にあると主張する。
特に宗教戦争が苛烈をきわめたフランスにおいては、王権の強化は国内の秩序のための至上命題であったのだ。
ただ、どの国も同じような行き方をすれば、行き着くのは果てしない戦争だ。
実際17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ諸国は、ヨーロッパ内の領土と海外の植民地をめぐり熾烈な抗争をくりひろげた。
かつては、各国の主権よりも上位にローマ教会があって、普遍的な権威を及ぼすことができた。
それがもはやなくなった以上、それに代わる新たな法が求められたのは無理もない。
中世以来の議論を引き継ぎながら、「自然法」を持ち出し、国家の法を超える「国際法」について論じたのが、17世紀前半のオランダで活躍したグロティウスだ。
史料 グロティウス『海洋自由論』(1614年)
第1章 われわれの目的は、オランダ人[中略]が、自由に、今までどおり東インドへと航行し、その地の住民と交易を行うことができるということを、簡潔明瞭に論証することである。[その際]われわれは、万民法という確実かつ明白で普遍の規則(これは第一の最も特別な規則と呼ばれる)を論拠とするであろう。すなわち、すべての民族は、他の民族のもとを訪れ、彼らと取引し、商売をすることが許されるということである。[後略]
第5章 [前略]空気は2つの理由で万人共通のものである。第一に、それは占拠したり所有したりすることが許されないからであり、他方、それは人々に共通に奉仕すべきものだからである。同じ理由で、海洋もまた万人共通のものである。[中略]ポルトガル人は(いわば)2つの世界のあいだに横たわっている全海域の領有者と称しているようなものだ。[中略]もしもこれにカスティーリャ人[中略]の分け前を付け加えるならば、ほとんど、この大洋の全体が2つの民族だけの領有となり、他の数多くの国びとは北海の狭い海域に押しこめられてしまうだろう。[後略]
彼はこの『海洋自由論』の中で、スペインがオランダ人の航行を認めないことに対して、「海は誰の所有物でもない」という”自然の命令”をもとに反論しようとしたわけだ。
社会契約説
もうひとつ、この時期に流行った学説に、社会契約説がある。
先ほど言ったように、16〜18世紀は、ヨーロッパ各地の君主が国を統一的にまとめようとしていく時代だ。
しかし、君主も人間である。
なかには人々のことなど考えない邪智暴虐な君主も現れかねない(いわば君主ガチャである)。
なかには君主の権力をキリスト教の神によって説明する学説(王権神授説)も生まれたのだが、それに対抗し、人々(人々といっても、現在のように必ずしもすべての国民を指すものではないことに注意)の権利を確保しようとする思想家が現れた。
彼らの議論は「そもそも国というものは、どういう事情から生まれたものなのだろうか?」というところからスタートする。国家成立の事情から、「どのような国家のあり方が望ましいかを議論するのだ。
もちろん、はるか昔の時代のことなんてわからないからフィクションではあるんだけれど、さまざまな人が「自然状態」(国がまだなかったころの人間たちの状態)を想定した。
でもそんな状態、どうやったらわかるのだろう?
たとえばイングランドのホッブズ(1588〜1679年)という人は、人間の本性を合理主義的にとらえ、 その謎を解き明かそうとする。
史料 ホッブズ『リヴァイアサン』冒頭(光文社新訳文庫より引用)
自然とは、天地を創造し支配するために、神が用いる技のことである。人間の技術はさまざまな事柄において自然を真似る。そうした模倣によって人工的な動物を作ることもできる。「人工的な動物」という言い方は奇異に聞こえるかもしれない。だが、生命とは四肢の運動のことであり、その運動は内部の中心的な部分から起こる。それを踏まえるなら、「すべての自動機械(たとえば、腕時計のように発条と歯車によって自動的に動く機械)は、人工的な生命を持っている」と説明したからといって、何の差し障りがあろうか。なにしろ、心臓、神経、関節に代わるものとしてそれぞれ発条、線条、歯車があり、それらのおかげで全体が制作者の意図したとおりに動くのだから。 人間の技術はそれにとどまらない。模倣の対象は、理性をそなえた被造物、すなわち自然の最高傑作とも言うべき人間にも及ぶのである。実例を挙げよう。まさに人間の技術によって創造されたものに、彼の偉大なるリヴァイアサンがある。リヴァイアサンは国家と呼ばれている(英語ではコモンウェルスまたはステイト、ラテン語でキウィタス)が、実は一種の人造人間にほかならない。自然の人間よりも巨大かつ強力であり、自然の人間を守ることを任務としているところに特徴がある。
この人造人間は主権を人工の生命としている。それは全身の活力と運動の源泉である。為政者や司法・行政を担当する官吏は、人工の関節である。賞罰は、関節や器官を一つひとつ主権という中枢部に結びつけ、それぞれの義務を遂行させるので、神経に相当する。その働きは人体における神経と同じである。個々の構成員が蓄える富や財宝は、生身の人間であれば体力に相当し、人民の安全を図ることは、人間で言うなら職務に相当する。国家にとって知る必要のある事柄を漏れなく教えてくれる顧問団は、[脳内の]記憶装置の役割を果たしている。公平と法律は、いわば人工的な理性と意志である。国内の調和は人体の健康、騒乱は病気、そして内戦は死に相当する。
どうだろうか。
人間社会ってのは機械みたいなもんであり、その運動によって成り立っているのが国家だ。
つまり、国家を理解するには、その“部品”たる人間とは何かが分かればよい。
…というわけで、ホッブズの考察は、人間の心理へと進んでいく。
おもしろいのは、ホッブズが「人間の思考や感情は相互に似かよっている」と言っていることだ。
人間ってのは、だいたいみんな似たようなものだから、難しく考える必要はない。自分自身を知ろうとすれば、それがほかの人々を知ることにつながるというわけである。心の作用が国家というよくわからない人工物を生み出すのだとすれば、そのメカニズムを深掘りしよう。ホッブズはそのようにアタリをつけた。
すなわち、まず自分自身の内面を見つめることである。そして、自分自身の思考・推論・期待・恐怖が究極的に何を意味しているのか、また、何に根ざしているのか、それを考察するがよい。そうすれば、自分と同じ状況にある人間の胸中を読み取り、知ることができよう」。 念のために言っておくが、私が述べているのは、欲求・恐怖・希望など万人に共通する感情の仕組みが似かよっているということであって、感情の対象──平たく言えば、何に欲求・恐怖・希望を感じるのか──が似かよっているということではない。
こうしてホッブズは、自然状態を「国がなかった頃の人間たちは、自分や味方ことばかりを考え、限られた富を奪い合う状態(万人の万人による闘争)だった」との推論に至る。でも、それじゃあ怖い。だから人間はその状態を避けようとする。そうして自主的に自分が生まれつき持っている権利を「ひとつの存在(主権者)」に委ねる形で、「国家」があらわれてくる。
ようするに「国家」というのは、個々にバラバラな「個人」という要素が集まってできたものなんだという発想だ。
ホッブズの『リヴァイアサン』の表紙には、たくさんの人々が集まって「リヴァイアサン」という強大なパワーを持つ怪物(たった一人の主権者)を構成しているイメージ図が掲載されている。
ホッブズの世界観は突飛に聞こえるが、機械論的に世界をみようとする当時の潮流に根差したものだったといえるだろう。
一方、違った方向から国家の成り立ちについて考えた思想家もいる。
イングランドで名誉革命が起きた時に活動したロック(1632〜1704年)だ。
彼は、「もともと人々は、自分たちの自由や財産を守るため、それを保護してくれる政府に支配を“任せる”契約を結んだのだとする。
史料 ロック『市民政府論』
確かに、自然状態に置かれているとき人間はそのような権利を持っているが、しかしその権利を思いどおりにできるかというと、はなはだ不確かであり、ほかの人々から権利を侵害される危険が絶えずつきまとっているからである、と。考えてもみよ。万人がこちらと同じように王である以上、相手は皆こちらと対等であり、しかも大半の人々は、公正と正義を厳格に遵守しているわけではない。したがって、このような自然状態にある所有権は、ひどく危ういし、心許ない。だからこそ人間は、自由があるとはいえ不安と絶え間ない危険に満ちている現状に、終止符を打とうと積極的になる。したがって、人間が私の言う所有物(生命・自由・財産)を互いに保全するために共同体を求め、そこに加わろうとするのは、もっともなことである。
でも万が一、政府が勝手なマネをして、人々と結んだはずの約束を守らなくなってしまったらどうすればよいのだろう?
これについてロックは、次のように説明する。
史料 ロック『統治二論』
もし立法府が[中略]人民の生命、自由および財産に対する絶対権力を、自分の手に握ろうとし、また誰か他者の手に与えようとするならば、この新任違反によって、彼らは、人民が、それとは全く正反対の目的のために、彼らの手中に与えた権力を没収され、それは人民の手に戻るようになる。人民は[中略]新しい立法府を設置することによって、彼らが社会を作った目的である自分自身の安全と保障の備えをするのである。
各人には、社会を結成することによって確保しようと考えている事柄があり、また、国民には、みずから設立した立法部に服従する見返りとして求めている事柄がある。そうした狙いや願いをそこなう権力を立法部が持つなどということは、国民の願うところであろうはずがない。したがって、国民の所有するものを奪い取り、台なしにすること、あるいは、恣意的な権力のもとで国民を格下げし、奴隷の状態におとし入れること──このようなことを試みようものなら立法部は、国民を相手に戦争状態に突入したことになる。そうなると国民は、それ以上服従する義務はなくなる。そして、共通の逃げ場に身を寄せる。そのような逃げ場は、暴力から身を守るために神の計らいにより万人に用意されているのである。したがって、立法部が社会のこのような基本的な掟を破ったとしよう。そして、国民の生命・自由・財産を思いのままにする絶対的な権力をみずから握ろうと試みるか、あるいはそれを、ほかのだれかの手に握らせようと試みるとしよう。それは、野心または恐怖心に駆られてのことかもしれない。あるいは、短慮のゆえかもしれない。あるいは、倫理感を失ったせいかもしれない。いずれにしても、立法部が右の暴挙に出たときには必ず、信託を裏切ったことによって権力を剝奪される。その権力は、もともと国民がまったく別の目的で立法部に預けておいたものなので、国民の手に回収される。なぜなら国民は、本来の自由を取り戻す権利をそなえているからである。そして、(自分たちにとって妥当と思える)新たな立法部を設立することによって、自分たち自身の安全と安心を確保する。安全と安心こそ、人民が共同体を結成する目的にほかならない。
ロックにとってもっとも大切なのは、所有権をはじめとする自身の安全と安心の確保だ。
そりゃあ、国家などつくらずに、のほほんと暮らせたら、そもそも国家による自由の侵害なんて考える必要はないのだが、人間の社会はそんなに甘くない。所有権が脅かされるおそれがある。だから自ら立法府を設立し、自分たちの共同体を樹立する。だが、その共同体の意志が、常に人々の意志と同じであり続けるとは限らない。だからこそ、人々の意志を履き違えた立法府を倒す権利(革命権;抵抗権)を、人々に確保しておく必要があると、ロックは考えたのだ。
ホッブズにせよロックにせよ、人間の本性や社会について、じつに緻密な吟味をくわえていることがわかるだろう。
しかし、これらホッブズとロックのいずれにも与しないの異色の思想家・作家が、18世紀フランスに現れる。ジャン・ジャック・ルソーである。
その主著『社会契約論』の冒頭は、まさに、人間の自由をどのように確保するかという問いから始まる。
人民が自由を回復するための根拠
人は自由なものとして生まれたのに、いたるところで鎖につながれている。自分が他人の主人であると思い込んでいる人も、じつはその人々よりもさらに奴隷なのである。この逆転はどのようにして起こったのだろうか。それについては知らない。それではどうしてその逆転を正当化できたのだろう。わたしはこの問いには答えられると思う。もしも力と、力によって生まれる効果だけについて考えるならば、わたしは次のように答えるだろう。「ある人民が服従することを強いられて服従するならば、それはそれで仕方のないことだ。人民がその軛を振りほどくことができ、実際に振りほどこうとするのなら、それは早ければ早いほうがよい。人民は、人民から自由を奪った者と同じ権利をもって、みずからの自由を回復することができる。というのも人民には自由を回復するだけの根拠があるし、そもそも人民から自由を奪うことそのものが根拠のないものだったからである」と。ところで社会秩序とは神聖なる権利であり、これが他のすべての権利の土台となるのである。しかしこの権利は自然から生まれたものではない。合意に基づいて生まれたものなのだ。それではこの合意とは、どのようなものだったのだろうか。ただしこの問題を検討する前に、ここまで述べてきたことを証明しておくことにしよう。
ホッブズの場合は、人々はまず自分たちの国家をつくる契約を結び、その上で第三者との間に主権を認める契約を結ぶ理屈になっている。
だが、それでは第三者が、人々の意志と食い違うおそれがあるのではないか。第三者に主権を譲り渡してしまったら、その時点で人々は主権者ではなくなってしまい、自由を失うのではないか。
ルソーの批判はそこにある。
社会契約の課題ここで、さまざまな障害のために、人々がもはや自然状態にあっては自己を保存できなくなる時点が訪れたと想定してみよう。自然状態にとどまることを望んでいる人々はこうした障害に抵抗するのだが、この時点になると障害の大きさが、人々の抵抗する力を上回ったのである。こうして、この原始状態はもはや存続できなくなる。人類は生き方を変えなければ、滅びることになるだろう。人間は[何もないところから]新しい力を作りだすことはできない。人間にできるのは、すでに存在しているさまざまな力を結びつけ、特定の方向に向けることだけである。だから人間が生存するためには、集まることによって、[自然状態にとどまろうとする]抵抗を打破できる力をまとめあげ、ただ一つの原動力によってこの力を働かせ、一致した方向に動かすほかに方法はないのである。このまとめあげられるべき力は、多数の人々が協力することでしか生まれない。しかし各人が自己を保存するために使える手段は、まず第一にそれぞれの人の力と自由である。だとすればこの力と自由を拘束して、しかも各人が害されず、自己への配慮の義務を怠らないようにするには、どうすればよいだろうか。この困難な問いは、わたしの主題に戻って考えると、次のように表現できる。「どうすれば共同の力のすべてをもって、それぞれの成員の人格と財産を守り、保護できる結合の形式をみいだすことができるだろうか。この結合において、各人はすべての人々と結びつきながら、しかも自分にしか服従せず、それ以前と同じように自由でありつづけることができなければならない」。これが根本的な問題であり、これを解決するのが社会契約である。
また、ルソーはロックの学説も次のように批判する。
主権は譲渡されえず、代表されえない主権は譲渡されえない。同じ理由から、主権は代表されえない。主権は本質的に一般意志のうちにあり、そして意志というものは代表されるものではない。一般意志は一般意志であるか、一般意志ではないかのどちらかで、その中間というものはないのである。だから人民の代議士は人民の代表ではないし、人民の代表になることはできない。代議士は人民の代理人にすぎないのである。代議士が最終的な決定を下すことはできないのだ。人民がみずから出席して承認していない法律は、すべて無効であり、それはそもそも法律ではないのである。イギリスの人民はみずからを自由だと考えているが、それは大きな思い違いである。自由なのは、議会の議員を選挙するあいだだけであり、議員の選挙が終われば人民はもはや奴隷であり、無にひとしいものになる。人民が自由であるこの短い期間に、自由がどのように行使されているかをみれば、[イギリスの人民が]自由を失うのも当然と思われてくるのである。代表という考え方は近代になってから生まれたものだ。
人は一人では生きることができない。しかし、共同体をつくったとたん、自由を支配者が登場するかもしれない。その危険を防ぎながら、人々の自由を守るにはどうすればよいのか。
ルソーの用意する答えは「一般意志」を実現する直接民主制である。
一般意志と全体意志の違い
これまで述べたことから、一般意志はつねに正しく、つねに公益を目指すことになる。ただし人民の決議がつねに同じように公正であるわけではない。人はつねに自分の幸福を望むものだが、何が幸福であるかをいつも理解しているわけではない。人民は腐敗することはありえないが、欺かれることはある。人民が悪しきことを望むようにみえるのは、欺かれたときだけである。一般意志は、全体意志とは異なるものであることが多い。一般意志は共同の利益だけを目的とするが、全体意志は私的な利益を目指すものにすぎず、たんに全員の個別意志が一致したにすぎない。あるいはこれらの個別意志から、[一般意志との違いである]過不足分を相殺すると、差の総和が残るが、これが一般意志である。
結社の否定
人民が十分な情報をもって議論を尽くし、たがいに前もって根回ししていなければ、わずかな意見の違いが多く集まって、そこに一般意志が生まれるのであり、その決議はつねに善いものであるだろう。しかし人々が徒党を組み、この部分的な結社が[政治体という]大きな結社を犠牲にするときには、こうした結社のそれぞれの意志は、結社の成員にとっては一般意志であろうが、国家にとっては個別意志となる。その場合には、成員の数だけの投票が行われるのではなく、結社の数だけの投票が行われるにすぎないのである。こうして意見の違いが少なくなると、意志の一般性も低くなる。ついにはこれらの結社の一つがきわめて強大になって、他のすべての結社を圧倒した場合には、もはやわずかな数の差異の総和もなくなり、差異は一つだけになる。こうなるともはや一般意志は存在しない。ただ一つの個別意志が、一般意志を圧倒することになる。だから一般意志が十分に表明されるためには、国家の内部に部分的な結社が存在せず、それぞれの市民が自分自身の意見だけを表明することが重要である。
このようにして社会契約説は、ルソーの理論により、最終的に「人民主権」にもとづく新しい国家理論へと発展することになる。
(続く)
このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊
