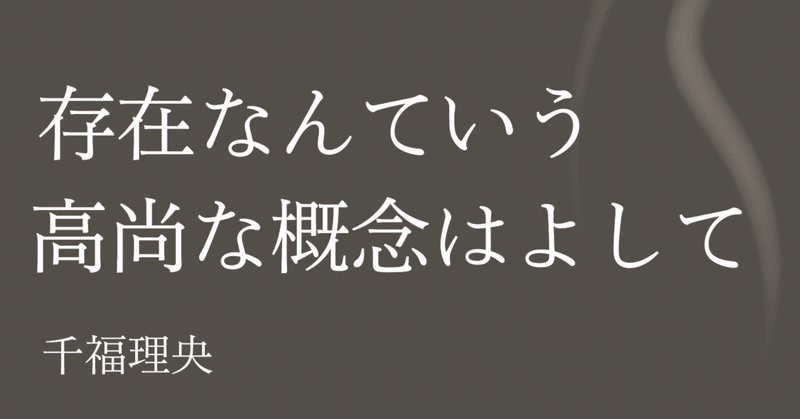
【小説】存在なんていう高尚な概念はよして
ピーが死ぬ時は、僕にも何となく分かった。ピーの元気のない様子を見て、僕は戸惑いながらおじいちゃんに相談したと思う。ピーが変わっているんだとか、そんな感じの、漠然とした言葉を選んだ筈だ。おじいちゃんは、後悔のないように面倒を見てやりなさいと言った。普段は僕に優しいおじいちゃんの、その時の顔は、世界で一番怖かったから、それで僕は、事の重要さを理解した。
僕はお父さんと一緒に、鶏小屋でピーを見守った(言い忘れていたが、ピーは小鳥ではなくて、ふくよかな鶏だった。ふくよかなのは、僕が餌を毎回沢山与えていたからであって、勿論ピーは卵用鶏だった)。夏の蒸し暑い日だった。お父さんがしきりに僕に、お茶を飲ませた。おかげで僕は頻回にトイレに行かなくてはならなくて、その間にピーがいなくなってしまったらどうしようかと僕は心配だった。お漏らししてもいいかと、父に聞いたと思う。父は、まだ大丈夫だから、今のうちに行きなさいと答えた。
夜になっても、僕は鶏小屋にいた。父もずっと一緒にいた。寝る時間になっても、家の外にいるのは、僕には新鮮で、不思議な気分だった。正直に言えば、新しい体験に少し興奮していた。でも、その気持ちを誰かと共有する事は出来なかったし、共有する気にもなれなかった。興奮は、現実を前にしてひっそりと呼吸していた。僕も深呼吸を繰り返した。眠くならないように、大げさに。
父はタバコに火を付けた。それで、父が今朝買ったタバコの箱が、遂に空になった。父は、不満そうに溜息をついた。けれどもタバコを吸うと、心が落ち着いたのか、穏やかな顔をした。それまでの間、僕と父の間に会話はなかった。お互いに、それほど話し合う関係ではなかったから。しかし、堪えきれなくなったのか、暫くして、父が僕に語りかけた。
「なあ」
僕は父を見る。父は、外に頭だけを出し、星を身上げていた。
「ピーはどこに行くと思う」
僕は、父の後頭部に付いている草を見つめながら、ぼんやりと考える。その草をピーにあげる事はもう出来ない。むしろ、ピーが土に帰って、草の元になるのではないか。
そうか、閃いた。ピーは草になってしまうのか。
「草?」
父は振り返って僕の方を見た。じっと僕を見る。その目が厳しく、僕は、間違えたかな、と思った。やがて父は、身体ごと僕の方を向いて、重く口を開いた。
「確かに、草だな」
僕は、褒められたと感じて、満足した。小さく頷いた。けれども父は頷き返さず、次の質問を僕にした。
「今、ピーはどうしている?」
目を離していた僕は、慌ててピーの様子を確認した。触ると、まだ温かく、呼吸をしている事が分かった。
「元気」
「そうか」
父は、タバコの吸い殻を足で踏み潰して、それから、立ち上がった。
「ちゃんと、ピーの事を見てあげなさい。難しい事だけれど、出来るね?」
僕は、大きく頷く。もう、手を離したりしない。父は、言葉を続ける。
「考えれば考えるほど、見る事が疎かになる。存在とか命とか、高尚な事を考えるのはよして、ピーの事を見てあげなさい」
僕は、父を数秒見てから、ピーに視線を移した。父が、僕の分からない言葉を、僕に対して使うのは、この時くらいだった。父は、息を吸ってから、誰にも聞こえないように吐いて、鶏小屋を出て行った。
それから僕は、ピーを目と手で確かめ続けた。伝わってくる熱が少なくなっていくのを、ちゃんと感じた。目に見える変化は、決して大きくはなかったけれど、僕には捉えられた。その時の僕に、感情の変化はなかった。自分の感情を、見ても触れてもいなかった。
もう、ピーが何も変わらなくなってしまってから、僕は鶏小屋で寝た。それでも、コケコッコーという大きな声が近くで聞こえて、直ぐに僕は起こされた。日が昇っていて、ピーではない鶏が盛んに太陽に叫んでいた。ピーを僕は探した。すぐ横にいた。けれど、もうピーはぐったりとしていた。僕は目を擦った。とても痒かった。そして目の下の頬も、非常に痒かった。
昨日の事を思い出した。一瞬で思い出せたが、思い返すには何時間もかかった。
そして、僕は泣いた。泣く時に1人だったのは、思えばこれが初めてだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
