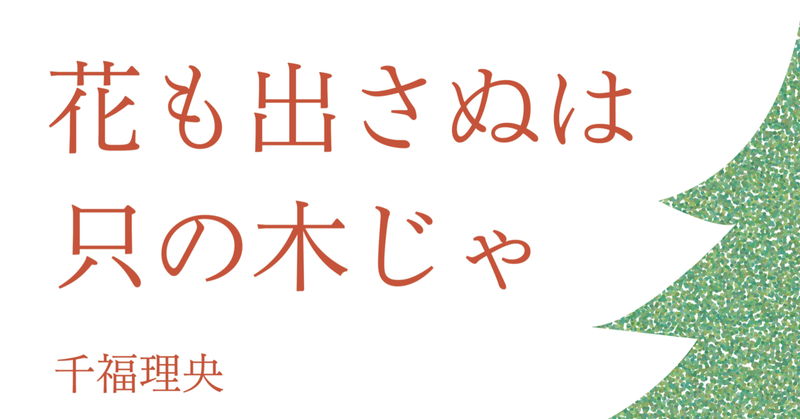
【小説】花も出さぬは只の木じゃ
実家でクリスマスを迎えた。情けないのか、情けなくないのか、分からない。親に帰ってこいと言われたから帰ったのだが、断ろうと思えば断れたはずだ。少なくとも、正月まで伸ばしてもらうくらいは、出来ただろう。断る理由がなかったのは、家族にどう捉えられているのか、僕は考えないようにしている。
家族は帰ってきた僕の事を特段歓迎しなかった。まあ、それは問題ないのだ。家族にはいろいろな形がある。僕の家族は、割合それぞれが独立に生きている節がある。帰ってこいなどと言ったのも、そうでも言わないと家族としての形が守れなくなってしまうからに違いない。確かに、僕から帰省しようなんていう発想は出なかったし、今後一生、出ないだろう。
けれどもおじいちゃんだけは、それなりに喜んでくれたので、僕は嬉しかった。誰かが自分の存在を意識してくれるというのは、やはり嬉しいものだ。おじいちゃんはクリスマス・イブの夕食をせっせと作ってくれた。毎年のように僕がモミの木に飾りを付けようとすると、おじいちゃんは、花も出さぬは只の木じゃと言った。その言葉の意味について僕はそれから1時間は考えたのだが、おじいちゃんが僕をからかったのかどうかさえ分からなかった。おじいちゃんはと言えば、けらけらと笑って料理の続きに戻っていた。僕は飾りという名の花をモミの木に付けた。
夕食はとても美味しかった。僕達はテレビを見ながら、さして会話もせずにたくさん食べた。おじいちゃんの食事の量が去年より減ったような気がして、僕は少し心配になった。けれどもおじいちゃんはよく笑った。僕も、元気なそぶりをする為によく笑った。尤も、元気がなかった訳ではないのだが、僕は元気だろうとあまり笑わないのだ。
就寝前に、僕がモミの木の飾りの照明を消そうとすると、おじいちゃんが、付けておいてくれと言った。僕には、その時、おじいちゃんが怖がっている事が、分かってしまったから、おじいちゃんに言われた通りに照明を付けたままで、おやすみなさいを言って部屋を出た。
おじいちゃんが僕に、けらけらと笑う方法を教えた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
