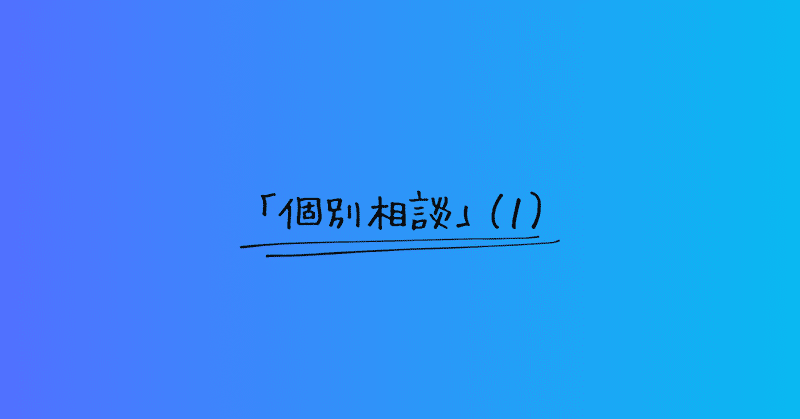
「個別相談」(1)
「橘先生」
突然名前を呼ばれて返事が不自然にワンテンポ遅れた。初めて先生と呼ばれた新任教師のように。
「個別相談。今日の放課後、一件入ってますよ」
教頭はその事実をまだ理解できていない様子を隠すこともなく言った。目力の出し方を忘れ去っていたように見えていたその目は、自分の前世を思い出したかのように見開かれていた。
不登校生徒の保護者からのクレームに対する施策である個別相談システムの導入以来、教師側としては、なんとなく共通認識としてあった生徒からの人気、不人気のラインが明確になったこと以外は何も起きていなかった。良いことも悪いことも。人気のある教師は貴重な隙間時間を個別相談の予約で埋め尽くされ、不人気な教師は知りたくもない評価を突き付けられた。なお、これの導入以降も不登校の生徒の数は加速度的に増え続けている。
橘には導入以来一件も個別相談の予約が入ったことはなかった。人気教師は予約が取りづらいため、急ぎの相談がある生徒の中には希望教師欄に「橘以外」と書くものもいた。彼の徹底的な不人気は彼を含め、この学校に所属する全員にとって予想通りの展開だった。彼の顔は表情を作ることが極端に少なく、石像のように硬い無表情で固定されている。最も人を寄せ付けないものは無なのだ。顔のパーツや配置を見ると非常に整ってはいた。ただ無表情なだけであれば、女子からクール路線での人気が出てもおかしくはない。しかし、彼の顔は本来人間が必ず備えているはずのもの、あえて言えば生気のようなものがあまりにも欠如していた。あるはずのものがないとき、人間は恐怖と混乱を覚える。その恐怖故か、彼の授業ではいつも生徒は非常に静かだった。というより静まり返っていた。
教頭が頼りない足取りで橘の机まで近づき、橘の名前が書かれた予約票を彼の机に置いた。警察に銃を向けられた犯人が手を挙げて凶器を置くときのように恐る恐る。橘はゆっくりとそれを手に取り予約者の名前を確認する。朝倉省吾。二年二組。二番。橘の記憶にその名前の存在は確認できた。そしてそれが、彼の脳をかすかに揺らすのを認識した。橘はゆっくりと席を立った。そしてゆっくりと歩き、ゆっくりと職員室のドアを開けた。彼の動きをその場にいた全ての人間が、その一挙手一投足を見逃すまいとでも言うように監視していた。
何か自分に対する文句だろうか。橘は朝倉がこの予約票に彼の名前を書いた目的を考察する。仮にそうだったとしたら思い当たる節は山ほどある。橘はまるで他人事のように自分に対する仮の不満を正当なものだと評価した。
「社会科準備室」と所々消えかかった文字で書かれたドアの前に立つ。社会科準備の準備が要りそうだなと橘は思う。中に入ると、埃のせいか景色が少し白んで見える。そこが使われているのを目にした記憶はない。しかし、学校にはおそらくこういう場所がいくつか必要なのだ。例えば、学校一の不気味な男が面談でもするときのために。
このままではこれまで縁のなかったぜんそくを発症しそうな気がしたので、窓を開けることにした。無事に開いてくれるかいささか不安だったが、意外にすんなり開いてくれた。自分が開閉可能な窓としてそこに存在しているのを忘れてはいないようだった。冷たい風と共に雲の切れ間からやや控えめな西日がその部屋に差し込んだ。
(続く)
僕の文章を読んで口角が上がってしまった方。よろしければサポートお願いします。サポートいただけた暁には、あなたのその口角。下がらないように書き続けます。
