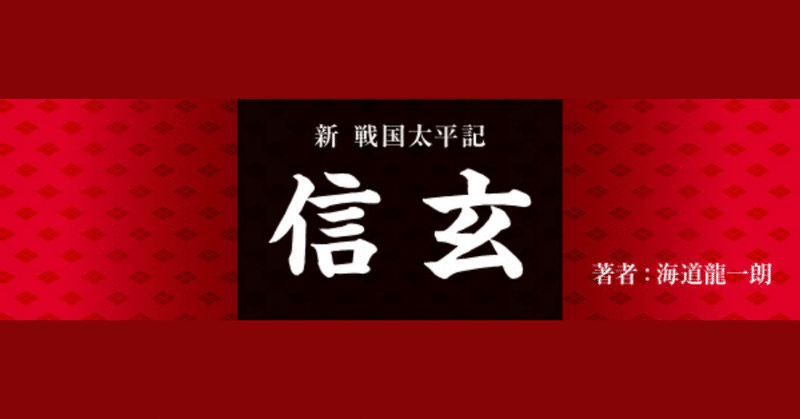
新 戦国太平記 信玄 第七章 新波到来(しんぱとうらい)12(下)/海道龍一朗
この軍評定が行われた翌日、十月八日の払暁から、先陣の三増峠の登坂が始まる。
真田信綱と昌輝が先頭を行き、それに馬場信春の本隊が続く。
武藤昌幸は浅利信種が率いる先陣殿軍に同行し、そこには検使として曽根昌世もいた。
山縣昌景が率いる赤備衆は、小幡隊の先導で志田峠を目指して出立している。
信玄の率いる本隊は麓を固め、小田原から追撃に備えた。
先陣第一隊が三増筋を進んで一刻(二時間)ほどが経ち、薄暗かった山中もすっかり陽光に照らされていた。
真田兄弟の先鋒は中腹の辺りまで進んでおり、どこで敵と遭遇してもおかしくなかった。
兵たちの緊張は極度に高まり、枯葉を踏む音が響くだけで軆が反応してしまうほどだった。
「昌輝、そろそろ周囲に斥候を出した方がよいかもしれぬな」
真田信綱がもう一人の弟に告げる。
「承知した。兄者、この身が美濃守殿に伝えてから物見に出る」
真田昌輝は馬場信春の処へ行き、自ら斥候に出ることを告げ、「兵に休憩を与え、敵の急襲に備えてほしい」と具申した。
昌輝は兵を二つの組に分けて斥候隊を編成し、自らは一の組を率いて右手側に見える雑木林へ向かう。
斥候隊一の組は右手側の木立の中へ入り、そこからは隠密行動を取り、慎重に雑木林の中を進む。
ひんやりとした大気に包まれた山中にもかかわらず、時が経つにつれて槍を握る手が汗ばんでくる。
他の兵たちも額にうっすらと汗を浮かべ、息を殺しながら周囲を見回していた。
雑木林を抜けると小さな沢があり、さらにその向こうには、さほど高くない尾根がある。真田昌輝と一の組は、それを越えて先へ進む。
──中へ入ってみるとわかるが、この峠の両側には、小さな沢と尾根が繰り返し現れ、それが幾重にも続いている。軍勢が身を隠して潜むには、格好の地勢だ。敵はこの「地の利」を知っており、待ち伏せに使うつもりだろう。
昌輝が見抜いたように、三増峠の山中は小さな沢と尾根が交互に現れ、麓まで幾筋もの起伏が波打っている。
──怪しげな人影は見当たらぬな。
小さな沢と尾根を二つほど上り下りしたが、敵らしき姿は見当たらない。
「あまり深入りしすぎても、本隊の行軍を遅らせるだけか。よし、そろそろ戻るとするか」
そう言った真田昌輝に、足軽頭が進言する。
「御大将、だいぶ歩いて喉が渇きましたゆえ、この先の沢で水を吞んでから戻るというのは、いかがにござりましょうや。尾根の下から水の音が聞こえておりまする」
「それもそうだな。では、この尾根を下りて何事もなくば、喉を潤してから急ぎ引き返そう」
「御意!」
足軽頭が率先して尾根登りを再開する。
頂上に辿り着くと、足軽頭はいきなり身を伏せ、右手で後続を制した。
何かを発見したらしい。
真田昌輝をはじめとする後続の者は足を止め、身を低くして備える。
匍匐で前進し、沢の様子を覗き込むと、そこには先客がいた。
腹当を身につけた足軽と思しき者たちが沢を流れる清水を呑んでいる。
その数、ざっと五十余というところだった。
向こうも山中を歩き回り、よほど喉が渇いていたのだろう。何度も両手で水をすくっている。
──やはり、待ち伏せか。傍らに槍を置いているところを見ると敵の槍足軽か。あやうく、こちらの姿を見られるところだった。
敵の姿を捉えた昌輝は素早く思案する。
──ここから急いで本隊へ帰り、応援を連れて戻るか。それとも、敵を見つけたことを全隊に伝え、待ち構えるか。
すると、沢から野太い声が響いてくる。
「おい、いつまでも腰を下ろしているな。行くぞ!」
敵の足軽頭と思しき者が手下を叱咤し、槍を杖代わりにしながら尾根を登り始めた。
それを見た昌輝は小さく舌打ちする。
──しまった! こちらへ向かってくるぞ。まずいな……。
思ったよりも早足で、敵の一団が近づいてくる。
──落ち着け。判断を間違えば、われらだけではなく本隊までが一気に不利となる。
昌輝は己に言い聞かせながら、視界の中に敵を捉える。
──ここから急いで戻ろうとしても、われらが沢から次の尾根を登る時に姿を見られてしまう恐れがある。ゆえに、撤退は下策。とにかく、本隊へ伝令を走らせることが先決か。それに登ってくる者どもが物見なのか、先陣なのか判然とせぬ。ならば、あえて、ここで敵を捌いて後続がいるのか、いないのかを確かめるべきであろう。よし、決めた!
肚を括った真田昌輝はすぐに足軽頭に命じる。
「そなたはもう一人誰かを連れ、本隊へ走れ。美濃守殿と兄上に敵の足軽隊を発見したと伝えよ」
「御意!」
足軽頭は踵を返し、二人で弾かれたように走り出す。
その姿を確かめてから、昌輝は残った兵たちに言い渡す。
「敵はまだ、われらがいることに気づいておらぬ。それゆえ、頂上に身を隠し、敵が登ってきたところを槍衾で迎え撃つぞ。相手は五十ほどだ。登ってきた者から順に倒していけば、捌けぬ数ではない。敵を倒したならば、ここから迅速に撤退するぞ。よいな!」
「はっ!」
兵たちは険しい面持ちで声を発する。
「くれぐれも槍を振り回すな。最小の動きでまっすぐに突き、素早く仕留めよ!」
「はっ!」
「では、参るぞ!」
真田昌輝の号令で一の組が駈け出し、先ほどの尾根へと登る。
同じ頃、先陣殿軍の浅利信種が苛立った面持ちで物見の報告を待っていた。
「遅すぎるな……」
信種が隣にいる浦野重秀にぼやく。
「それがしが見てまいりましょうか?」
「ふぅむ……」
浅利信種が顔をしかめて思案する。
その刹那だった。
右手の林で夥しい数の火花が明滅し、豆を煎るような乾いた音が響く。
一番近くにいた浅利信種、さらに浦野重秀と数名の足軽が吹き飛ばされるように倒れた。
「う、うわぁあ……」
異変に気づいた足軽が叫ぶ。
「……て、敵じゃあ!」
悲鳴を上げながら腰を抜かす。
「鉄炮がいるぞ! 敵の待ち伏せじゃ!」
その声を聞いた殿軍の兵たちが一斉に這いつくばる。
少し離れたところにいた武藤昌幸と曾根昌世も身を低くした。
「地面に這いつくばるな! 狙い打ちされるぞ!」
武藤昌幸が兵たちに向かって叫ぶ。
「身を低くして、沢へ下りよ!」
昌幸は曽根昌世と一緒に沢へと滑り下りる。
その視界の端に、敵と思しき槍足軽の姿が入った。
「昌世殿、まずい! 鉄炮の攻撃で、浅利殿と浦野殿が倒れるのを見ました。……かなりの深手かもしれませぬ」
武藤昌幸が叫ぶ。
「……やられた。まさか、北条が鉄炮隊で奇襲を仕掛けてくるとは」
曽根昌世の顔から血の気が引いている。
「昌幸、そなたは美濃守殿のところに戻り、この件を伝えてくれ。それがしは殿軍の検使として、残った兵をまとめ直し、援軍が来るまで持ち堪えるゆえ」
「承知! すぐに、援軍を連れて戻りまする。昌世殿、どうか御無事で!」
武藤昌幸はそれだけを言い残し、先陣本隊がいる峠の上に向かって走り出した。
曽根昌世は浅利隊の者たちを呼び集め、敵の襲来に備える。
鉄炮隊の奇襲で先手を奪った北条勢は、槍足軽の隊を押し出してきた。
勢いに乗った敵の圧力は凄まじく、少しでも自軍の隊形を崩されれば、一気に貫かれるおそれがある。
「開扇の陣だ! 総力を上げて押し返すぞ!」
曽根昌世は兵たちを緊密な陣形に導き、斜面を下ってくる敵方の出鼻を挫こうとする。
──なんだ、この寄手の重圧は!? ……北条の兵とは、かくも屈強だったのか。
昌世は敵兵の士気の高さに驚愕しながら槍を構える。
──まさか、これは地黄八幡、北条綱成の手勢なのか!?
その勘は当たっていた。
沢の上に現れた敵の足軽は、八幡の旗指物を背負っている。
潜んでいた北条勢の中で、いちはやく殿軍に鉄炮を撃ちかけたのは北条綱成が率いる一隊だった。
敵方からも大声で下知が飛ぶ。
「怯むな、者ども! この隊の敵大将はすでに討ち取った。余勢で、敵の中央を崩すぞ!」
ひときわ軆の大きい敵将が命じた。
その胴には金泥で三つ鱗の紋が刻まれ、四十八間の筋兜には八幡大菩薩の前立が輝いている。眼庇の下には浅黒い顔があり、燐光を放つが如き双眸があった。
──地黄八幡! 北条綱成に相違あるまい!
曽根昌世は眼を見開く。
──ここを凌がなければ、われらの隊は全滅するやもしれぬ。されど、凌ぎさえすれば……。
昌世の眼前で、敵がいったん後方に下がり、長蛇の陣形に変化する。
再び勢いをつけ直し、扇状に開いた自陣を崩そうとしていた。
「来るぞ! 敵の足許は、沢の手前で滑りやすくなっている! 沢を挟んで、槍衾で迎え撃て! 今が踏ん張りどころぞ!」
曽根昌世が檄を飛ばす。
沢を渡って陣形を整えたところに、敵の第一波が押し寄せる。
すぐに互いの兵が入り乱れ、激しい戦いとなった。
こうした乱戦では、瞬時に相手の動きを読み取り、素早く兵を動かさなければならない。その駆け引きに敗れた方が一気に不利となる。
北条勢は東の林から続々と現れ、曽根昌世の先陣殿軍は沢を挟んで迎え撃ち、援軍が来るまで時を稼ごうとしていた。
しかし、大将の浅利信種と副将の浦野重秀を討ち取られた衝撃は大きく、武田勢がじりじりと押され始める。
この時、先陣の別働隊であった山縣昌景の赤備衆は、志田峠から三増峠の西にある志田山へと登っていた。
その山裾まで物見に出ていた斥候が戻ってくる。
「ご注進! 三増筋に戦いの気配がありまする!」
「どの辺りだ?」
山縣昌景が険しい面持ちで訊く。
「殿軍のいる辺りから、怒声が響いてまいりました」
「さようか。下山に際しては、そなたが先導をせよ」
「畏まりましてござりまする」
「殿軍に北条勢の奇襲があったようだ。総軍、山を下りて救援にまいるぞ!」
山縣昌景が赤備衆に命じる。
志田山から三増峠までは半里(二㎞)ほどの距離だった。
経路の大半が下り坂であるため、急げば四半刻(三十分)もかからずに駆けつけることができる。
先陣の別働隊は敵の奇襲を察知し、三増峠へと向かった。
同じ頃、武藤昌幸が黒備衆の本隊に戻っていた。
「ご注進! 火急の件にて、ご容赦を!」
昌幸が叫びながら、馬場信春に駆け寄る。
「さきほど、突如として殿軍に鉄炮が撃ちかけられ、浅利式部少輔殿をはじめとする数名が撃ち倒されました」
「北条の奇襲か?」
馬場信春が聞き返す。
「間違いないかと! 鉄炮隊の強襲ゆえ、避けようもなく……。おそらく、浅利殿は……」
「討死か」
「お命があったとしても相当の深手かと」
「その鉄炮はいずこから撃ちかけられた?」
「東側の雑木林からにござりまする。射手は身を隠しており、どれほどの数かはわかりませぬ」
「やはり、東からか」
そう呟いた馬場信春が昌幸に訊く。
「して、昌世は無事か?」
「……わかりませぬ。検使として残った兵をまとめて防戦していると思いまするが……。美濃守殿、殿軍を救援に行き、残った兵を退かせとうござりまする。兵をお貸しいただけませぬか」
昌幸の進言に、馬場信春は大きく頷く。
「そこの一隊を連れて行け。先鋒でも何やら怪しい動きがある。このまま殿軍を崩されると危ない。頼むぞ、昌幸!」
「承知いたしました!」
武藤昌幸は三百余の足軽を連れ、殿軍の救援に向かった。
馬場信春が言ったように、黒備衆の先鋒でも動きがあった。
斥候に出た真田昌輝が、兄の信綱のもとへ戻ってくる。
「おお、昌輝。伝令から『敵を見つけた』と聞いた。詳しい状況は?」
真田信綱が駆け寄る。
「兄者、敵の槍足軽、五十余が東からこちらへ向かうところだったので、やむなく三十近くを討った」
「さようか。でかしたな」
「いや、討ち漏らした敵兵が戻ったことで、われらがいることも知られてしまったであろう。あれは単なる物見ではなく、いくつかに分けられている伏兵のひとつだと思う。周囲にかなりの数が潜んでいる気配がある。おそらく、敵はわれらの東側にいくつかの伏兵隊を置き、隊列が伸びたところで横腹を狙うつもりだったのではないか」
弟の昌輝は冷静に状況を読んでいた。
「われらの進軍と併走するが如く、北条も伏兵を置いているということか」
「おそらく、そうだと思う」
「すぐ近くに敵がいるならば、戦うまでだ。兵たちに応戦の構えを取らせ、他の隊にも触れを出すぞ!」
「わかった。美濃守殿にも、このことを知らせておこう」
真田昌輝が動こうとした時、伝令の足軽が駆け込んでくる。
「ご注進! 先陣殿軍が敵の奇襲を受け、浅利信種殿と浦野重秀殿が深手を負われたとのこと! 敵は東側に潜んでおりました」
「その件は美濃守殿もご存じなのだな?」
真田信綱が伝令に訊く。
「はい。先陣本隊も東側に物見を放ち、臨戦の態勢を取っておりまする」
「さようか。われらの物見でも東側に敵の伏兵を確認し、三十近くを討ち取った。これより、先鋒は全方位で索敵を行いながら前進し、退路を確保すると美濃守殿に伝えてくれ」
「承知いたしました」
伝令の足軽が踵を返した。
「昌輝、そなたが本隊に行く必要はなくなった。ここからは先手必勝の戦いとなる。そなたは東側を警戒せよ。それがしの隊が前方と西側の敵を見つけ出す!」
「了解した、兄者」
「われらは正面と西側を索敵するぞ。敵はかならず峠の上にもいる。油断いたすな!」
真田信綱も隊を率いて前進を始めた。
「われらは先ほど敵を見つけた辺りまで出張るぞ!」
真田昌輝が配下の将兵に命じる。
──先に敵を見つけ、先手で攻撃を仕掛けねばならぬ。
東の林へ入り、尾根を登りながら慎重に先へ進んだ。
──陽が昇り、逆光になっている。眩しいな……。
昌輝は兜の眼庇に右手をかざし、尾根の上から下の沢を見つめる。
その逆光の中に、数十躰の影が現れる。
胴丸に描かれた三つ鱗紋を見て、敵の足軽頭であると確信した。
その刹那、だった。
己の軆が自然に動いてしまう。
「敵だ、一斉にかかれ!」
真田昌輝は兵たちに命じると、自ら斜面を駆け下りはじめる。
「我に続け!」
素早く先頭の敵の前へと躍り出て、昌輝は閃光の如く槍を放つ。
狙いすました一撃が、相手の喉仏を貫いた。
素早く切先を引き抜くと、敵の足軽が呻声を発しながら頽れ、辺りに血煙が舞い上がる。
──先手を取った!
真田昌輝は躊躇いなく得物を繰り出し、立ち竦んだ三人の敵を連撃で倒す。
そこへ、さらに後続の味方が現れた。
敵の足軽は咄嗟に何が起こったのかわからず、骸になった味方を見下ろしながら固まっている。
先鋒の武田勢はすかさず左右から槍衾を見舞い、次々に北条勢の足軽たちを倒してゆく。槍兵たちは皆、大将の動きを手本にして一撃必殺を狙っていた。
機先を制した武田勢が有利になり、北条勢を東に押し込んでゆく。
この時、真田昌輝が遭遇していたのは、北条氏邦が率いる軍勢だった。
一方、三増峠の頂上を目指し、前方に進んでいた兄の真田信綱も索敵の報告を受けていた。
「峠の頂き付近に、北条勢の物見と思しき兵を発見いたしました」
透破頭の蛇若が伝える。
「どのくらいの数であったか?」
「それがしが見ましたのは、十数名の姿でありました」
「敵の斥候か。ならば、すぐ後方に先鋒の隊がいるな。ご苦労であった」
「はっ!」
蛇若が素早く下がる。
「さて、どう攻めるか……」
真田信綱は半眼の相で思案した。
──敵は高所の地の利を生かして戦うつもりだ。されど、これしきの勾配ならば、騎馬で駆け上がり、その余勢をもって戦えば、大した不利にはならぬ。兵を伏せて敵に迫るよりも、虚を衝いた騎馬の突破が有効ではないか……。
そう考え、信綱は足軽大将の加藤景忠を呼ぶ。
「景忠、よく聞いてくれ。これより峠にいる北条勢に攻め寄せるが、まずは騎馬五百で敵の正面から中央突破を狙う」
「まことにござりまするか!?」
加藤景忠が驚く。
「まことだ。高所に陣取る敵の裏をかき、中央を破って敵を左右に散らす。一気呵成に駆け上がり、敵の布陣を突き破るつもりだ。肝心なのはそれに続く、そなたら足軽隊の動きだ。足軽隊は三列の縦隊を組み、左右に分かれた敵勢を攻撃しつつ、中央の隊はわれら騎馬隊の背に追いついてもらいたい」
「なるほど。敵の中央に割って入り、分断してからの各個撃破にござりまするか」
「さようだ。騎馬隊は必ず敵を突っ切って反転するゆえ、足軽隊の中央は何とか背後に付いてきてもらいたい。ぎりぎりまで敵に迫った後、一気に勝負へ出る。先手を取り、敵を押し切るぞ!」
「承知いたしました」
策を理解し、足軽大将の加藤景忠が大きく頷いた。
「では、景忠。足軽隊の指揮は、そなたに任せる。頼んだぞ」
「はっ!」
「騎馬の者どもは、こちらに集まれ!」
真田信綱が騎馬隊を集め、策の要点を説明した。
すべての準備を終え、信綱の一隊は慎重に前方へと進み始める。峠の頂きが見えた時点で、動きが速くなった。
「騎馬隊、行くぞ! まずは全力の速歩で鋒矢の陣形をとれ!」
真田信綱が命令を下す。
「足軽隊、三列の縦隊で遅れを取るな!」
足軽大将の加藤景忠も叫ぶ。
五百騎あまりが坂道を登り始め、駈足から速歩へと移る。
「鋒矢から、衝軛! 二列になおり、敵の中央を破れ!」
真田信綱の号令を受け、騎馬兵たちは段違いの二列縦隊に変化する。
衝軛とは、牛車などの前方に伸びる二本の轅と牛の頸にかけるために横木を渡した軛のことを指し、隘路などで敵を打ち破るための縦列を意味している。
正面からくる相手にぶつかっても力負けしないための陣形だった。
愛駒を駆る真田信綱の視界に峠の頂きが入り、北条勢の姿を捉える。
敵方は狭い道幅いっぱいに広がっていたが、速歩で駆け上がってくる騎馬隊に驚き、眼を見張って立ち竦む。
敵襲だと気づいた北条勢は左右から包もうとするが、充分に勢いをつけた武田勢の騎馬隊は、それをものともせずに突進してゆく。
「敵を左右に捌いて中央を突破せよ!」
中段にいた真田信綱が命じる。
その言葉に従い、二列縦隊の騎馬は北条勢の陣を左右に切り裂いていく。
「討ち漏らしなど気にするな! 後続の足軽隊が始末してくれる! とにかく、突っ切るぞ!」
騎馬隊の背を追い、三列縦隊を組んだ武田の足軽勢が、左右に分断された北条勢に追撃を加える。
左右の足軽隊が怯んだ敵兵を隘路から脇の林に叩き落とし、中央の足軽隊は先行する騎馬隊の後方を守っていた。
真田昌輝の戦闘開始に同調し、兄の信綱も苛烈な攻めを開始する。
こうして先鋒全体でも激しい戦いが始まり、乱戦へと突入した。
一方、馬場信春から援軍を預かった武藤昌幸は、交戦中の浅利隊のところまで戻る。
「浅利隊の皆、馬場隊の援軍が助けに参ったぞ! 坂を登って戦いながら、こちらにまとまれ!」
昌幸は同じことを何度か繰り返して叫ぶ。
その声を聞いて警戒したのか、北条勢の寄手が動きを止めた。
そして、救援に気づいた浅利隊の兵たちが、敵の攻撃を凌ぎながら昌幸の方へ集まり始める。
「昌世殿! 曽根昌世殿はおらぬか!」
武藤昌幸は辺りを見回しながら叫ぶ。
「昌幸!」
頬を血で汚した曽根昌世が駆け寄ってくる。
「ご無事か、昌世殿!?」
昌幸は不安げな表情で同朋を見つめた。
「大丈夫、これは返り血だ」
「よかった」
昌幸は安堵し、すぐに今後の手立てを説く。
「昌世殿、兵をまとめて戦いながら先陣本体がいるところまで退きましょう。直に、赤備衆の援軍が参りまする」
「承知! 背合だ!」
今度は曽根昌世が味方に向かって叫ぶ。
「二人の背を合わせて守りながら、正面の敵を槍で討ち取れ!」
浅利隊の兵たちは隣にいた者と背を合わせて槍を構える。
曽根昌世は残った味方を呼び集めながら敵と戦う。武藤昌幸も三百余の足軽を率いて北条勢を押し返そうとした。
援軍を得たせいか、味方が勢いを盛り返す。
しかし、先手を奪った北条勢の勢いも止まらない。
八幡の旗指物を背負った兵たちが武田勢を包囲しようと、一斉に攻めかかってくる。
それに対し、武田勢は坂の上に退きながら応戦した。
武藤昌幸は坂の下から雲霞の如く群がってくる敵の足軽を次々と突き倒す。その隣で曽根昌世も同じように奮戦している。
辺りに血風が吹き荒れ、怒号が渦巻く。血の臭いが否応なく鼻腔を震わせ、すでに敵味方の判別がつき難い乱戦となっていた。
絶え間ない敵の攻撃を捌き続け、武田勢の兵たちも息が荒くなる。
「行けい、者ども! 武田を一気に潰せ!」
後方から北条勢の大将と思しき巨軀の漢が命じる。
「来るぞ! 怯むな! 浅利殿の敵を取るぞ!」
曽根昌世が声の限りに咆吼を上げ、兵たちを鼓舞した。
その時、再び大きな変化が訪れた。
西の方角から鬨の声が上がり、深紅の具足に身を包んだ一隊が現れる。
待望の援軍、赤備衆だった。
「行け! このまま敵の横腹を突け!」
山縣昌景が叫ぶ。
赤備衆は坂道に並んだ北条勢に横槍を入れる。
思わぬ方角からの攻撃に、坂の上だけを見ていた敵に激しい動揺が走った。
立ち竦む北条勢を、赤備衆の槍隊が容赦なく討ち取っていく。
「東の林は、滑りやすい斜面だ! その中へ追い落とせ!」
山縣昌景は勢いに乗った兵たちに命じる。
三千余の援軍が駆けつけたことで、瞬く間に形勢が逆転した。
この光景を目の当たりにし、残った浅利隊と武藤昌幸の援軍も勢いを取り戻す。
隘路の上から攻勢に転じ、槍衾で北条勢を追い落とし始める。
この動きに呼応し、赤備衆も激しい攻撃を繰り返し、敵を東側の斜面へと追い詰めていく。
「おのれ、伏兵か! 半原山の方角へ、いったん退き、陣を立て直すぞ!」
北条勢の大将が東側にある半原山への退却を命じる。
しかし、東側には栗沢や深堀と呼ばれる難所があり、崖になっているところも多い。加えて、中津川の急流もあり、渡ろうとすれば流される危険があった。
北条勢にとっては決して楽な退却ではなく、武田勢にとっては追撃の好機となる。
「敵は背を見せたぞ! 容赦いたすな!」
山縣昌景が赤備衆に追撃を命じた。
そこへ曽根昌世が駆けつける。
「山縣殿、まことに、ありがとうござりました」
「昌世、無事か?」
「……何とか、掠り傷で」
「浅利殿は?」
山縣昌景の問いに、曽根昌世は力なく首を横に振る。
「さようか。無念であるな……」
武藤昌幸も二人のもとへ駆け寄ってくる。
「昌幸、そなたも殿軍にいたのか?」
「はい、浅利殿が敵の奇襲で討ち取られましたゆえ、本隊の手勢を率いて助太刀に参りました」
「さようか。遅くなってすまぬ」
「いえ、持ち堪えている間に来ていただき助かりました」
武藤昌幸は頭を下げる。
「何とか凌げたようだな」
山縣昌景は無言で何度も頷く。
「ええ。されど、最後はまことに危のうござりました」
曽根昌世が苦笑する。
「敵の大将は、やはり、あの者か?」
「おそらく、北条綱成にござりましょう。尋常ならざる手応えにござりましたゆえ」
昌世は思わず頭を掻く。
「昌幸、そなたもよくやってくれた。傷は大丈夫か?」
「掠り傷にござりまする。それよりも、ここは山縣殿にお任せし、兵たちを本隊に戻しとうござりまする」
武藤昌幸が進言する。
「美濃守殿に、よろしく伝えてくれ」
「承知いたしました」
「昌幸、礼を言う。そなたの救援がなければ、ここまで持ち堪えられたかどうか……。かたじけなし」
曽根昌世は深々と頭を下げる。
「何のこれしきのこと。では、失礼いたしまする」
武藤昌幸は一礼し、残った兵に声をかける。
「者ども、本隊へ戻るぞ!」
足軽たちを率い、急ぎ坂を登り始めた。
志田峠に潜んでいた山縣昌景の赤備衆に横腹を突かれ、北条勢は半原山の方向へと逃げ、浅利隊は九死に一生の窮地から脱する。
こうした全局の動きは、使番からの報告によって次々と信玄の本陣へ伝えられていた。
「北条綱成と思しき将に率いられた敵勢に奇襲されました先陣殿軍は、武藤昌幸殿とわれら赤備衆の救援により、無事に立て直しをいたしました。ただいま、東に逃げました北条勢を赤備衆が追撃しておりまする。ただし、先陣殿軍の大将、浅利信種殿及び、同副将の浦野重秀殿は、無念のお討死にござりまする」
「さようか」
信玄は赤備衆の使番からの報告に頷く。
「ご苦労であった。戻ってよいぞ」
北条勢との戦いは先陣の全体に及んでいたが、最も危うかった先陣殿軍が助かったことで、自軍が優勢に転じていた。
──先ほど、先陣先鋒からの報告もあった。真田兄弟が奮闘し、三増峠の頂きにいた北条勢を駆逐し、退路を開いたようだ。さらに、小曽根の尾根道を使い、津久井城に攻め寄せた小幡重貞と信貞も、首尾良く北条方の内藤景豊を封じ、動けぬようにした。これで甲斐への退却には何の支障もなくなった。あとは……。
そう思いながら、信玄は近習の三枝昌吉に問いかける。
「源八郎、南へ出た物見は、まだ戻っておらぬのか?」
「すぐに確認してまいりまする」
三枝昌吉が踵を返して確認に走り、間もなく戻ってくる。
「御屋形様、物見の者が戻ってきましたので連れてまいりました」
「おお、待っておったぞ。状況は?」
信玄が身を乗り出す。
「はっ、ご報告申し上げまする。われらは五組の物見隊を編制し、愛川の里から下萩野辺りまでをくまなく調べましたが、敵と思しき軍勢の姿はまったくありませぬ」
物見の報告を聞き、信玄が扇で膝を打つ。
「さようか! 源八郎、勝頼と保科を呼べ」
「はっ。ただいま」
三枝昌吉は武田勝頼と保科正俊を呼びに行った。
──われらが動くならば、氏康と氏政の父子は間に合わぬ、この機だ。
信玄はついに本隊を動かす決心をする。
「父上、お呼びにござりまするか?」
武田勝頼が保科正俊を伴って現れた。
「勝頼、本隊を三増峠に向かわせるぞ。そなたらには殿軍を頼みたい」
信玄の言葉に、勝頼が即答する。
「承知いたしました」
「先陣が敵の伏兵を捌いてくれたゆえ、この優勢の間に甲斐へ帰還いたす。小田原からの北条勢はまったく間に合っておらぬゆえ、本隊の殿軍が敵に喰いつかれることはあるまい。されど、充分に警戒しながら退却せよ」
「わかりました。お任せくださりませ」
「では、すぐに退陣だ!」
信玄の号令で本隊の旗本衆が動き始め、愛川の里から三増峠の頂きをめざして進発した。
本隊の旗本衆は、すぐに先陣殿軍がいる場所へと辿り着く。
緒戦の奇襲で優勢に立ったはずの北条綱成も、先陣別働隊の赤備衆に横腹を突かれ、算を乱して逃げ始めている。
北条勢は難所の崖から転落したり、中津川の急流に流されたりして、多くの兵を失っていた。
「深追いはせずともよい! 討ち取れそうな者だけを追え!」
信玄の命令で旗本衆も追撃に加わる。
一方、先手を取った真田兄弟の先陣先鋒隊を加え、馬場信春の黒備衆が峠の頂上にいた北条勢を攻撃し始めていた。
「敵方は津久井城へは逃げられぬ! 隘路から東の沢に追い落とせ!」
馬場信春が鬼相で叫ぶ。
すでに北条勢は峠の陣を崩し、ばらばらになっている。
武田勢の先陣先鋒隊と黒備衆は圧倒的な優位を築き、敵兵を討ち取っていく。
結局、三増峠に陣取っていた北条氏照と氏邦は、三千余の兵を失い、北側に位置する相模の八王子城へと撤退した。
「間もなく御屋形様の本隊が峠に上がってくる! 合流の態勢を整えよ!」
馬場信春が黒備衆に命じる。
「美濃守殿」
先陣先鋒の真田信綱が駆け寄ってくる。
「おう、信綱か。怪我はないか?」
「ありませぬ。すでに、この付近には北条勢は見当たりませぬ」
「さようか。ならば、信綱。そなたは弟の隊と一緒に津久井城へ寄せている小幡親子の援護に回ってくれぬか」
「承知いたしました」
「われらも御屋形様の本隊と合流したならば、すぐに先へ向かう。ここからは迅速な退却が肝要だ」
「わかりました」
真田信綱は弟の昌輝と合流すべく動き始めた。
馬場信春は峠を登ってくる本隊を待つ。
信玄の旗本衆と殿軍の武田勝頼は順調に登攀を続けていた。
この時、北条氏康と氏政の父子が率いる北条勢の本隊は、武田勢を挟撃するために小田原城から厚木の辺りまで出張っていたのである。
しかし、北条氏照と氏邦の敗走を聞き、そのまま厚木から動けなくなってしまったらしい。
武田勢の本隊は敵に追われることもなく、悠々と三増峠に到着した。
敵の挟撃を、さらに二重の挟撃で打ち破る謀撃の策。
これがことごとく当たり、終わってみれば武田勢の完勝だった。
日が傾く前に、武田勢の勝鬨が三増峠に響き渡る。
「もはや長居は無用だ。まっすぐ府中へ戻るぞ!」
信玄が全軍に退却の命令を出す。
武田勢は上野原から大月を抜け、甲斐へ帰還した。
信玄が躑躅ヶ崎館に戻ると、朗報がもたらされる。
別働隊として駿河で動いていた秋山信友が、北条方の蒲原城を囲んだという一報である。
今川家が潰滅した今、蒲原城は武田家と北条家が衝突する最前線であり、相模と駿河の境目の城として重要な拠点だった。
前回の戦いでは落とせなかったが、今回は北条勢のすべてを三増峠の戦いに引きつけたため、手薄になった蒲原城を秋山信友の別働隊が一気に攻め寄せた。
実は信玄が小田原城にまで攻め寄せたのは、裏にこうした目論見があったからであり、北条勢が籠城することを読み切った上での策だった。
この年、永禄十二年(一五六九)十月、信玄は手切れとなった北条家にすぐさま戦いを挑み、三増峠の勝利でその力を見せつけた。
第七部 <了>
(第八部に続く)
プロフィール海道龍一朗(かいとう・りゅういちろう)1959年生まれ。2003年に剣聖、上泉伊勢守信綱の半生を描いた『真剣』で鮮烈なデビューを飾り、第10回中山義秀文学賞の候補となり書評家や歴史小説ファンから絶賛を浴びる。10年には『天佑、我にあり』が第1回山田風太朗賞、第13回大藪春彦賞の候補作となる。他の作品に『乱世疾走』『百年の亡国』『北條龍虎伝』『悪忍 加藤段蔵無頼伝』『早雲立志伝』『修羅 加藤段蔵無頼伝』『華、散りゆけど 真田幸村 連戦記』『我、六道を懼れず 真田昌幸 連戦記』『室町耽美抄 花鏡』がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
