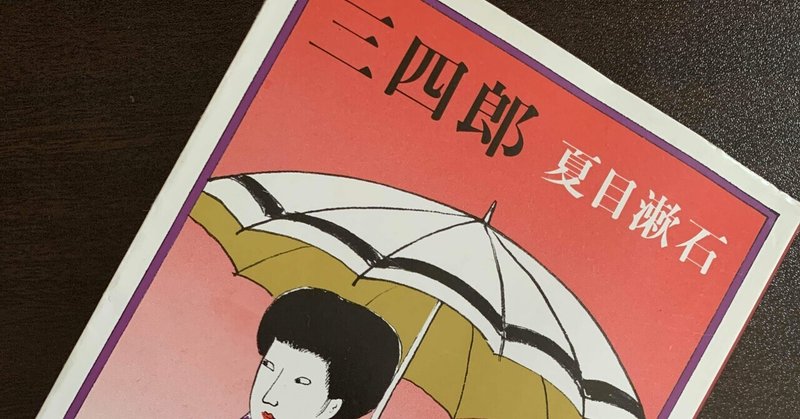
第十六回読書会:夏目漱石『三四郎』レポート(感想・レビュー)
新潮文庫でも337ページと長編で、まずは読了できただけでもエライ!
ご参加の皆さんも、一様にお疲れ気味だった気が……(@_@;)
夏目漱石の前期三部作のトップバターを務める本作は、とくに大きな事件が起こるわけでもなく、淡々と物語が流れ最後は「?」となりかねない、ちょっともやもやする作品です。
果たしてここから何が読み取れるのか?
淡々としていながらもいつのまにか引き込まれていく軽妙洒脱な筆致
まずは読書会参加者の感想として、
・もっとはっきりしてほしい
・三四郎はどっちやねん!
・語りが淡々としている
・余韻を持たせる終わり方
などと淡白な物語展開に対して戸惑う感想も多く、実際に私も読後はモヤモヤするところがあり、読書会当日までそのモヤモヤの正体が分からずにいました。一方で、
・今読んでも新しい
・一気に読める
など、長編ながらも読了できたのはやはり、ぐいぐいと引き込む漱石の筆致によるのは明白で、その手腕に唸る感想も聞かれました。今読んでもクスっと笑ってしまう文章が何箇所もあり、ユーモアを通して登場人物に向けるは優しい眼差しを感じる作品です。
その他の感想として、
・漢詩のリズムが伝わってくる文体
・音や色など五感に働きかけてくる言葉が多用されていて、登場人物の心の内を表現しているように感じた
など鋭いご意見も聞かれました。
三角関係の織りなす恋愛小説なのか?はたまた主人公の成長譚なのか?
私は主人公三四郎の思い詰めない性格が気に入って、この小説に明るい印象を持っています。
たとえば東京へ向かう途中で、同じ部屋で一夜を共にするはめになった女性から、『あなたは余っ程度胸のない方ですね』と云われ、狼狽し困惑し、しょげているところをうじうじと引きずっている場面があります。
けれども突然、
「三四郎は急に気を易えて、別の世界のことを思い出した。――これから東京に行く。大学に這入る。」(夏目漱石『三四郎』新潮文庫P.16)
と、思考を止めて別のことを考えだしてしまうのです。
肩透かしを食らった気分です。ここからどんな結論に達するのかと構えていたら、おいおい、もうちょっと考えないのか???と。
ところがこの小説の最後の方では、三四郎の様子が変容してきます。最後の一文は
「迷羊(ストレイシープ)、迷羊(ストレイシープ)と繰返した。」(夏目漱石『三四郎』新潮文庫P.337)
と三四郎の意味深なセリフを引き合いにして締めくくられています。東京での単純ではない人間関係のなかで右往左往していた三四郎が洞察力を鋭くし、言い得て妙といった言葉でしょう。
また、もう一つの読み方として、三四郎と美禰子と野々宮との三角関係というものがあります。三四郎と美禰子は両想いだったのか、はたまた違うのか、野々宮は美禰子のことをどう思っていたのか……。
ちょっと脱線……新聞小説に担わされた重責について
『三四郎』は、明治41(1908)年9月1日~12月29日にわたって朝日新聞に掲載された新聞小説です。
少しここで当時の新聞小説というものに触れておきましょう!
ラジオもテレビもない時代、報道といえば新聞しかありませんでした。新聞社とは、売り上げがたたなければ経営不振に陥る民間企業です。実は新聞小説は、今でいうトレンディ―ドラマのように、読者獲得のための戦略として打ち出されたものの一つだったのです。
小森陽一先生はその著書『漱石を読みなおす(ちくま新書)』のなかで、「資本主義的なジャーナリズムの確立は、最も商品価値の高い死の情報を売る方向へと、日露戦争を契機として突入していくのです。」と喝破しています。
「加熱した戦争報道は旅順攻略で頂点に達しましたが、(中略)しかしまもなく戦争は終ってしまいます。新聞各社が莫大な設備投資を回収しないうちに、情報商品を提供する戦場がなくなってしまったのです。」と戦争情報が新聞社の主力商品であったことをつまびらかにしています。
講和が結ばれ窮地に立たされた新聞社が次なる主力商品として目を付けたのが小説でした。そもそも小説とは虚構の世界ですから、実際に事件が起こらなくても「いくらでも事件を生み出せる装置」(小森陽一『漱石を読みなおす』ちくま新書)というわけです。
新聞小説は読者の維持獲得のための主力商品として経営戦略上に打ち出され、そうした背景の中で夏目漱石は、専属の書き手として朝日新聞社に雇われたのでした。
『三四郎』に出てくる女性たちを通して見えてくる日露戦争直後の日本
『三四郎』では、日露戦争(1904年(明治37年)2月~1905年(明治38年)9月)後の日本の様子を、女性を通して垣間見ることができます。
まず一人目は、東京へ上京する汽車の中で出会った女です。
「五分に一度位は眼を上げて女の方を見ていた。」というほどジロジロ見ていたら、そりゃ、私に気があるのかしらと思わせるには十分でしょう。夫からの仕送りが途絶え、親の里へ帰る途中というこの女は、三四郎からジロジロ見られていましたが、名古屋で一泊する際に宿を案内して欲しいと、しきりに三四郎に言い寄ります。とうとう同じ部屋に二人で一枚の布団で寝ることになったのです。
もちろん支払いは全て三四郎でした。
次の女性は、電車へ飛び込んで自殺した若い女です。三四郎が野々宮の家を訪れた際に、野々宮は急遽妹の入院先に呼び出され、三四郎はそのまま泊まることになりました。宵の口に家の裏手より「ああああ、もう少しの間だ」という声が聞こえます。それから前の列車よりも高い音を立てて列車が通過していきました。嫌な予感がしているうちに人だかりができ、その提灯の下に轢死体があったのでした。
行きずりの男と一泊を共に過ごす度量がなければ、思い悩んで死を選ぶことにならざるを得ない。極端ですが当時の女性の苦悩や貧困、悲惨さが描かれている象徴的で対照的なシーンです。そうした女性を養うことのできない、稼げない男たち。日本社会の実態が、日露戦争に勝利した一等国というイメージから程遠いものとして描かれています。
美禰子と野々宮の妹よし子、この二人の女性も小説上で描かれているよりはずっと複雑な問題を抱えているといえるでしょう。この小説は描かれていないシーンを想像しながら読むと、違った景色が見えてきます。
小森陽一先生は『漱石を読みなおす』のなかで、野々宮が一戸建てを借りていながら下宿暮らしに戻る経緯を、美禰子との関係に結び付けて解釈されていて、なるほど唸りました。
つまり、一戸建ては美禰子との結婚準備のために用意したものであり、しかしながら妹の病気入院により家計がひっ迫し家賃が払えなくなり、全てを手放したということなのです。
美禰子は兄の恭介の結婚が決まり、自身の身の振りようの決断を急がなければならない身の上となるのですが、結局、よし子の縁談相手だった人と結婚します。
この顛末について、よし子の詳しい気持ちは書かれていませんが、自分の病気のために大金が必要になり、兄の野々宮と美禰子との縁談が白紙になったことを気に病んでのことのようにも感じます。常に本当の姉妹のように仲睦ましく描かれ、当時の厳しい世相を生きぬく美禰子とよし子の深い絆を感じるのは私だけでしょうか?
美禰子と野々宮の破局からはじまる物語。勘違いしたままの三四郎……「あの人僕のこと好きなんじゃね?」
石原千秋先生も、『漱石と日本の近代(上)』(新潮選書)にて、「三四郎と美禰子の淡い恋の物語とする読み方は、漱石研究の世界ではたぶんもう通用しないだろう。」としています。
私も最後までどっちなんだ、とモヤモヤしていたのですが、最後の最後で、決定的なシーンを見つけました。美禰子をモデルにして描かれた絵「森の女」の展覧会が開催されたシーンです。
三四郎は入口で躊躇するのに対して、野々宮は超然として這入っていきます。私はこの野々宮の態度に、美禰子の絵に対しある種の決意を持って対峙しようという気迫を感じました。
「色の出し方が洒落ていますね。寧ろ意気な画だ」(夏目漱石『三四郎』新潮文庫P.336)
と、野々宮はまるで描かれたその場面の「色」をすでに知っていたかのような評し方をしているではありませんか。
「森の女」は三四郎が美禰子に初めて会った池でのシーンであり、あの時と同じ出で立ちで団扇をかざし、その通りに描かせているものです。美禰子にとって池のシーンは大切であることが分かります。
なぜか。
三四郎と初めて会った場所だから?
いえいえ、実はそうとも言えないようなのです。
重松泰雄先生は、池のシーンを構内図を用いて解明し、しゃがんでいた三四郎からは見えなかったけれども、じつは美禰子の向こう側には野々宮がいて、美禰子のとった挑発するような態度は野々宮に対するものだった、とする説を唱えました。
この挑発を三四郎は、自分に対するものとして勘違いさせたままでいるのが、この物語のレトリックです。
まあ実生活でもこうした勘違いはあることですよね~
あの人、僕のこと(私のこと)好きなんじゃないか?みたいな(*^_^*)
一堂で菊人形を見に行った際に、小さな川の端で美禰子と二人きりになることに成功した三四郎ですが、四尺(約120㎝)ほど離れて座り、「水が次第に濁って来る。見ると河上で百姓が大根を洗っていた。」「「空の色が濁りました」と美禰子が云った。」など、とてもロマンチックとは言い難い情景描写になっていて、二人の関係性の隠喩として捉えることも可能です。やはり美禰子は三四郎のことをとくに何とも思っていなかったと解釈するほうが、こうした細かい描写からもすんなりします。
池でのシーンに戻りますが、美禰子たちが通り過ぎた後、三四郎の前に野々宮が現れます。その時に野々宮のポケットから女性の手蹟らしい封筒が半分はみ出していたことがしっかり書かれています。このときに美禰子から手渡されたものと考えるのが妥当でしょう。
その後の展開は物語のままです。
野々宮は「森の女」の絵の前でたまたまポケットに手を入れたときに、美禰子の結婚披露宴の招待状の葉書が出て来ます。もうすでに披露宴は執り行われていて、野々宮は出席した後だったのですが、それを引き千切って床に棄ててしまいました。
美禰子と野々宮は池での出来事を契機に、区切りをつけて前に進もうとしている姿が、清々しくもあり痛々しくもあり健気です。
三四郎池に行くことができたなら、池のシーンを自分の目で確かめるべく再現したいなと思いました。どなたかご協力ください!!笑
**********
【参加者募集中!】
「週末の夜の読書会」は毎月一回開催しています。
文学を片手にワイガヤで一緒におしゃべりしませんか?
参加資格は課題本の読了のみ!
文学の素養は一切必要ありません^^
ご参加希望の方は、以下の専用フォームよりお申し込みください。
【申し込みフォームはこちら↓】
【問い合わせ連絡先↓】
shuumatuno46@gmail.com
【会場情報】
【第16回課題本】
文学は人生を変える!色々な気付きを与えてくれる貴重な玉手箱☆自分の一部に取り入れれば、肉となり骨となり支えてくれるものです。そんな文学という世界をもっと気軽に親しんでもらおうと、読書会を開催しています。ご賛同いただけるようでしたら、ぜひサポートをお願いします!
