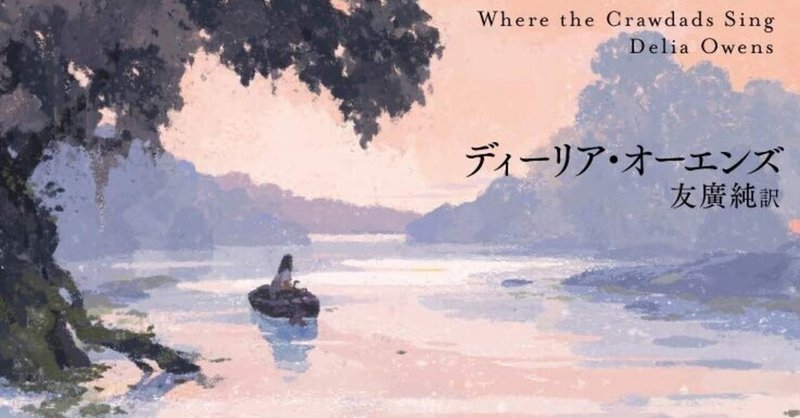
ザリガニはどこで鳴く?
Where the Crawdads Sing
『ザリガニの鳴くところ』って本をご存じですか?
昨年の3月に発売されたミステリーなのですが、タイトルが印象的だったので、読もうか、どうしようかと迷ってた本なんです。
家族に見捨てられながらも、広大な湿地でたったひとり生きる少女に、ある殺人の容疑がかかり…。みずみずしい自然に抱かれて生きる少女の成長と不審死事件が絡み合い、思いもよらぬ結末へと物語が動き出す。
発売されてから、けっこう経っているんですが、相変わらず話題になってるんですよね~。
それで、先日、ついに読んでみたのですが、今回はこの本について、”note” していきたいと思います。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
結論から言うと、話題になるだけあって、やっぱり面白かったのです!
タイトルにザリガニですからね~、最初は、どんな本なんだろうと思いますよね。しかも、ザリガニって鳴くの?みたいな感じです。
けっこう帯なんかに賛辞が添えられているんですが、そのとおりの印象なんで、安心して手に取ってもらえればと思います。
私的に面白かったポイントとしては、まず
①ヒロインの頼もしさ
湿地のほとりに住み着いた一家の幼い末っ子がヒロインとなるのですが、あらすじにもあるように、父親の暴力に耐えられなくなった母親を皮切りに、兄や姉たち、そして、最後は父親までも家を出ていって、見捨てられることになるのです。
そして、一人、家に残されたヒロインが、湿地のほとりでサバイバルしていくのが序盤になります。
一人ぼっちだったこのヒロインが、どんな人と出会って、どんな風に成長していったのか... という部分が物語の幹で、読んでいけばいくほど、成長していく姿に惹き込まれていくと思います。
②湿地の生態系
後書きやプロフィールによれば、作者の”ディーリア・オーウェンズ”は、この本がデビュー作らしいのです。しかも、執筆当時、すでに69歳!
もともと動物学者で、野生生物の行動生態学に関する研究などをしてた人物だそうです。
動物学者だけに、湿地で生きる様々な生物たちのことが、物語の中に散りばめられていて、舞台となった ”湿地” が生き生きと感じられるのです。
さらに、人間の行動についても、行動生態学的に語られる部分があって、その考え方自体がとてもユニークに感じました。
たとえば、男女の恋愛の感情や行動が ”求愛行動” 的に語られたり、自分を捨てた母親の心情を ”生態学的” に解釈する部分もあったりして、そこが、とっても興味深かったのです。
■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■
物語では、不審死を巡って、様々な憶測、捜査、そして裁判と、ミステリーとして展開していくのですが、私的には、このミステリー部分は、そんなに重要でない感じでした。
それよりも、何よりも、ヒロインの成長と湿地の物語だと感じられたのです。
で、タイトルになっている『ザリガニの鳴くところ』とは、どこなのかという点ですが、湿地の奥の方にある、人が足を踏み入れないような場所を指していると物語の中で説明されています。
ネタバレになる部分ではないのですが、作者が、なぜこのタイトルにしたのか、読み終わった後に考えてみると、なかなか味わい深かったりします。
*
物語としては、比較的ゆったりと進むような感じなのですが、ヒロインの成長譚、湿地の生態、貧富の格差やマイノリティに対する差別などの社会的問題、不審死とそれを巡る法廷劇、そしてロマンスと、いろんな要素が入った欲張りな作品となっています。
やっぱりデビュー作にはいろんのものを詰め込んでしまうのでしょうね。きっと、それがこの物語の長所であり短所でもあり、だからこそ、魅力的な物語になっているのは間違いないのです。
そして、最後に、ザリガニって鳴くの?って部分ですが、鳴き声とは若干違うかもですが、ジジジジっと音を鳴らすらしいです。
それが警戒音なのか求愛行動なのか、読み終わっても真相はわかりませんが、そんなことを想像してしまうあたり、この本の ”湿地” という場所に捕らわれてしまったのかもしれません。
*
