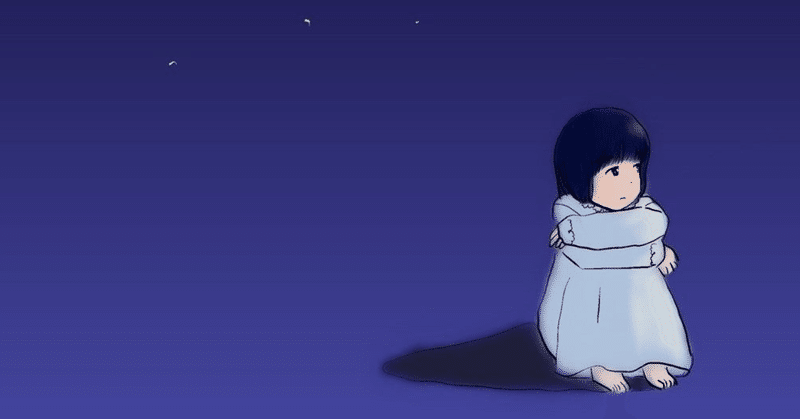
オリヴァー・サックス著『火星の人類学者』を読んだ話。
オリヴァー・サックスの医学エッセイ『火星の人類学者』を読みました。
サックスは脳神経科医なのですが、研究の中で出会った患者達を主人公とした七つの話が収録されています。
人間の脳みそってどうなってるんだろう……と思わされるエピソードばかりです。
まるで『火星の人類学者』
表題作『火星の人類学者』の主人公は、自閉症を持つ動物学者テンプル・グランディンです。
彼女は博士号を取得し大学の助教授として働く一方、畜産業にも関わっています。とても能力が高いのは間違いないのですが、自閉症の特性はグランディンの強みでもあり弱みでもありました。
グランディンは食肉にされる家畜達が幸せに生きられるように、最期の時に恐怖や苦痛を感じないようにと施設を設計します。実験に使った子豚に入れ込み、脳を調べるため殺さなければならなかった時は彼女いわく「おいおい泣いた」そうです。
しかし、彼女にとって人間は理解し難い存在であるようでした。
その場に相応しい言動、常識的に見える振る舞い、コミュニケーション方法などを、グランディンは周りの人間を観察し事例を頭の中に蓄積して日常に活かしています。それはまるで未知の生物を研究しているかのようです。
彼女はサックスの前で、何度も「私は火星の人類学者のようだ」と言いました。
障害の当事者が生きて行くと言う事
サックスとグランディンが出会った頃、2人の住むアメリカでは日本よりずっと発達障害についての研究が進んでいたでしょう。サックスも若い頃、重度自閉症の患者と勤務先で接していました。
それでも、当事者が自らの「障害」を語る事は珍しかったようです。グランディンは自伝を発表し、自閉症についての講演や啓発活動も行なっていました。
子供の頃から抱き締めて欲しい気持ちはあったけれど、誰かと接触するのが苦手だった事。
家畜を落ち着かせるための「締め上げ機」を知り、改良して自分専用の締め上げ機を作り上げた事(発達障害を持つ人は重いブランケットなどで圧迫されると安心するタイプが多いと言われています)。
締め上げ機への関心が科学に通じるきっかけとなり、今の仕事に繋がった事。
彼女の人生は、自閉症を持っているからこそ拓けたのかも知れません。
サックスは様々な患者と出会い、「障害」と呼ばれるものが患者本人と分かち難く結びついているのを目の当たりにします。
事故をきっかけに全色盲となった画家は、苦悩の末にモノクロフィルムや白黒テレビのような世界へ馴染んだ後、いくらか色覚が戻るかも知れないと薦められた治療を拒みました。
幼くして視力を失った男性は手術で「見える」世界を取り戻しますが、半世紀近く「見えない」人生を送って来た彼は酷く戸惑います。
そして、グランディンは講演でこう述べたそうです。
「もし、ぱちりと指をならしたら自閉症が消えるとしても、わたしはそうはしないでしょう──なぜなら、わたしがわたしでなくなってしまうからです。自閉症はわたしの一部なのです」
『火星の人類学者』
「障害」と呼ばれるものは、本当に全て治さなければならないのか。
「障害」とそれを持つ「人間」を切り離して考えてしまえば、何か重大な事を見失ってしまうのではないのか。
サックスとこの本に登場する人々は、そんな事を考えさせてくれます。
この記事では、私自身がASD(自閉スペクトラム症)の診断を受けた人間として表題作をメインに感想を書きましたが、他の話もとても興味深いので面白く読めると思います。
※ヘッダー画像は「みんなのフォトギャラリー」からお借り致しました。ありがとうございました。
ちょこっとでも気紛れにでも、サポートしてくだされば励みになります。頂いたお気持ちは今のところ、首里城復元への募金に役立てたいと思います。
