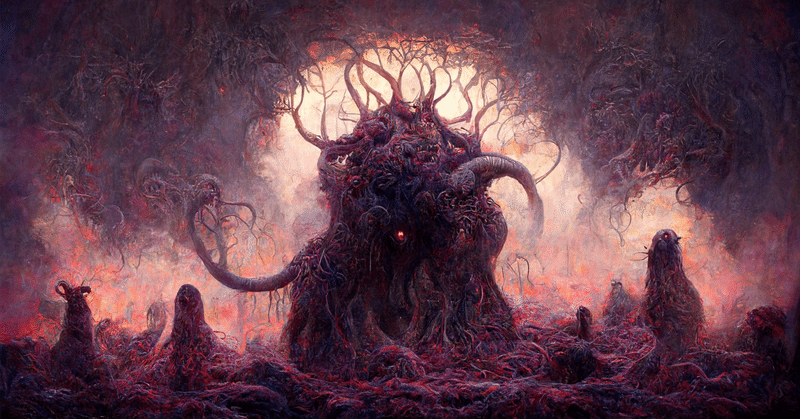
散裂Vol.03 世界 - 序文
世界とは、次の二つから成る系のことである。
[〔存在者―群〕=諸物]:すべての[存在するもの=存在者]の集まり
[〔法―群〕=秩序]:すべての[存在するもの=存在者]の振る舞いを規定する法の集まり
ここで世界とは、任意の経験データを体系的に解釈するための[模型=モデル]ではない。そのため、世界が実行的に実体化されているかぎり、[〔存在者―群〕=諸物]ならびに[〔法―群〕=秩序]は一意に確定する。
存在者は属性を所有する。属性とは存在者の部分であり、まさに存在者の所有するすべての属性を所有することによって、存在者は一体である。
[W:=〔世界―実体〕]において、ある対象[e1:=〔存在者―実体〕]と別の対象[e2:=〔存在者―実体〕]が隣接しており、その両者を不可分と見做せば、e1およびe2を属性とする一体[S:=〔存在者―実体〕]が構成される。このとき、Sにとってe1, e2は部分であり、Sが一体の存在者として扱われるとき、e1, e2は存在者ではない。しかしe1とe2を可分と見做すとき、e1, e2両者はそれぞれ存在者である。
このように、何が存在であるかを決定する、決定基準をスケイルと呼ぶとき、スケイルとは世界における存在者についての解釈の形式である。世界―Wの[〔存在者―群〕=諸物]は[S|e1, e2]であると解釈することも、Sのみであると解釈することも、[e1, e2]のみであると解釈することもできる。しかしこれらは単なる解釈であり、どれも世界―Wの実体を正確には表現してはいない。[〔世界―実体〕:W]とは、単に[〔世界―実体〕:W]である。
[実体|〔世界―実体〕]は、ただ[与えられる|生成する]ところのものである。
我々は与えられた〔世界―実体〕―Wを解釈することで[[W:=〔解釈世界―実体〕]|[W’:=〔解釈世界―構造〕]]を生み出す。解釈とは新たな実体の生成による近似である。解釈において世界を実体化する際には、初めから実体を生成することもできるが、まず構造を与え、それを実体化することもできる。構造とは、それが実体化されるときに、いかなる実体の性質をもつかを規定したものである。
解釈世界の構造について、おおまかに次の四つの方針を立てることで生成はおこなうことができる。
存在者が個々にあり、それらは敷かれた秩序に従って行為する。
存在者は全体として一者であり、敷かれた秩序に従って、その内部で部分が代謝をおこなう。
秩序はなく、存在者はただ行為する。
存在者と秩序は一体であり、存在者はただ行為する。
いずれの場合にも、存在者の振る舞いの規則性を抽象する解釈によって、擬似秩序を推測的に得ることができる。
解釈により生成された実体は、それが実行的に機能することによって[実質的=virtual]に実体として振る舞う。
例えば実在論においては、解釈によって生み出された〔世界―実体〕[との交感|からのフィードバックと自らの[意思決定・行動]との相互作用]によって我々の生活は成立しているのであり、誰も〔世界―実体〕そのものの姿を捉えることはできない。
[実質性=virtuality]とは、[架空・空想]のものの性質を指す語ではない。
解釈の産物として我々の前に立ち現れる実体は、先行する実体の[パラレル/オルタナ]にして、常に代替可能な実行である。〔解釈世界―実体〕は、[破綻・昏乱]なき[数学・論理]的な[系=システム]である必要はなく、存在者を引きつけて離さない[求心性・連続性]をもって、ただあるようにありさえすればよい。
先行する実体は常に絶対的なものとして[我々=解釈者]の前に立ち現れるが、しかしかといってこの実体が、実体自信にとって絶対的であるとは限らない。
人間はもとより自然の部分であり、本来的に人為と[自然=造化]に境界はなく、むしろ人為は[自然=造化]の部分である。
火山が熔岩を噴出して火成岩を生み出すように、植物が光合成をして酸素を生み出すように、人間は産業によって工芸物を生み出す。ここで[自然=造化]の環境は『破壊』されることはない。自らの代謝によって産み落とした人間によって資源が消費されることは、[自然=造化]の代謝の一部である。
物理界の外側に、代謝する論理空間を生み出すこと。それがもし電気信号によって成立する信号空間であるなら、内部の論理処理がいかに物理界から独立におこなわれていたとしても、信号機器の[錆化・風化]によっていずれ物理界に回收されてしまうことになるだろう。
もちろん、ここにはある程度の期間の実行性が担保されているため、何らこの論理空間の[実質性=virtuality]を毀損することにはならないが、しかしもし〔[自然=造化]―実体〕を生み出した造物主がいたとすれば、果たして[渠=かれ]は自らの存在する系の理と、完全に独立した秩序を敷くことができたのだろうか。
我々の前にあるこの[自然=造化]界が、[渠=かれ]にとって[実質的=virtual]であるにせよ、そうでないにせよ、重要なのはただ、これが実行され、我々のもとに与えられていること、ただそれだけである。
材料は何だっていい。
例えば文学は非空間の場にして、文字の羅列という〔存在者―群〕が、ある秩序によって確定している系であり、これは定義より世界である。
文学とは文学者の産み落とした一つの世界であるが、しかし[読解者=解釈者]による[読解=解釈]で実行されるのは、解釈の産物である[改変を含む複製=フォーク]された世界である。
文学という先行する世界は文字と紙面によって、読解という後行する世界は視覚と思考によって、それぞれ生成されている。
世界は、固着されたものに限らない。
ただ、その実行性のみによって、それは世界として認められる。
無数にある[オルタナ/パラレル]のなかから[一つ|幾つか]を選び取るか、あるいは自らそれを生成するための基準、すなわち、何を善とし、その世界においてそれを実現できるかどうかを判断し自ら選択する基準は、あなたを他の誰でもないあなたとするために必要な唯一の[倫理観=道徳観]である。
我々が『現実』を『仮想』に対置し、『仮想世界』と自嘲を込めて呼ぶものがすべて『現実世界』に従属し、『現実世界』における死を唯一の自己抹消として、『仮想世界』における死を死として認めないのは、ただ[情熱・執着]についての問題であり、[情熱・執着]によって、『仮想世界』における死をこそ唯一の自己抹消として自らに引き受けることは、人間が思考によって自身のうちに『仮想世界』を生成できるようになったその日からすでに可能である。
[物理・物質]への従属は単に惰性であり、この惰性を自身から[切断/脱離]することこそ、自ら世界を所有し、自らの生命をそこに灯すための、第一にして唯一の一歩である。この灯火が翳るときに自らが真に絶えること、そしてあるいは、新たな世界へ自らを産み落として転生すること、実行的に不滅となること、自らの生命を自らの手で摑むこと、真に所有すること、自らが神となること――生の[動躍=ドライヴ]はそこにある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
