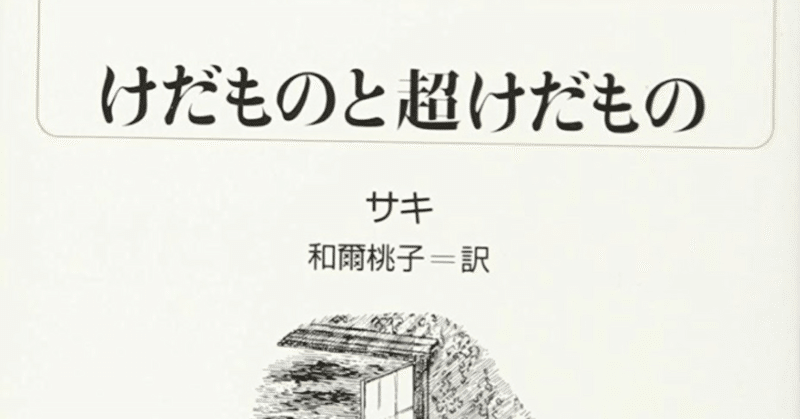
サキの短編は独りこっそり楽しむのがいい 〜サキ著「けだものと超けだもの」のこと
O・ヘンリーと並ぶ短編の名手と言えばサキ。O・ヘンリーが「陽」とするならばサキはまさに「陰」ですよね。ブラックジョークがちりばめられていて、読み終わるとつい口元が「ニヤリ」ってなるのが癖になってしまうのです。
さて、本書「けだものと超けだもの」はそんなサキの短編集。もちろんここでも彼一流のシニカルな物語がたくさん含まれています。
思うのですが、サキの短編はどれも短いものばかりなので、ついつい読み飛ばしていってしまいそうになるのですが、それはあまりにももったいない! 一編読み終わったら一度本を置いて、「ふぅ~」と一息ついて物語の余韻を楽しむ、そして物語を頭の中でもう一度思い起こして「思い出しニヤリ」、これこそが正しいサキの読み方ではないかと、僕はそう思うのであります。
てことで、その余韻を味わうってのがどういうことかを説明するために、一番最初に収められた物語「女人狼」について、ネタバレになりますがご紹介いたしましょう。
女人狼
レナード・ビルシタ―という男がいました。この男、悪い人ではないのですが、ちょっと「話に尾ひれをつける」癖のある人なのですね。そんな彼が東欧旅行に出た折、ロシア鉄道のストライキに会ってシベリアの奥地で二日間足止めされることとなりました。
帰国した彼はその時仕入れた伝承民話などを友人たちに話して回っていたのですが、その中でつい自分がシベリア魔術の秘術を伝授された、なんてことを言ってしまったのですね。
これが叔母のフープスさんの耳に入り、彼女がこの話を言い触らしてしまったものだから、もう彼は「シベリア魔術を伝授された男」として地元で有名人になってゆくのです。
さて、その話を聞きつけたのが近所のお金持ちメアリ・ハンプトン。彼女は自分のお泊りパーティにレナードを是非にと招待するのです。
そしてミセス・ハンプトンは言うのでした。
「もし魔術を使えるのなら、私を狼に変えていただきたいわ」
もちろんレナードはそんなことできるはずもないのですが、彼は言います。
「おふざけ半分にそんなことをおっしゃるのは、いかがなものでしょうか?」
肯定もせず否定もせず。シベリア魔術の可能性を巡ってパーティが盛り上がるなか、同じくパーティに招かれていたクローヴィス・サングレールという男が、ある貴族のパブハム卿にこっそりと話を持ちかけていました。
このパブハム卿というのは動物好き、それも野獣好きとして有名な人でした。
クローヴィスはパブハム卿に掛け合って、彼の所有する雌狼を借りるのです。
そして次の日、さらに来客が増える中、パーティも少し停滞した雰囲気になってきたころ。ミセス・ハンプトンはまたレナードに自分を狼にしてほしいと言いだします。
また話をごまかそうとするレナードにミセス・ハンプトンは憤慨し、「やれるものなら、やってみてごらんなさいよ」と言い捨てて庭の茂みの中へ隠れてしまいます。
困ったレナード。どうしたものかと考えあぐねているその時です。
なんとその茂みの中から狼が現れたのです。
辺りは騒然となります。ミセス・ハンプトンの旦那である大佐はレナードに向かって「早く元に戻してくれ」と言います。
でももちろん、レナードにはそんなことできるはずもありません。レナードは言います。
「ミセス・ハンプトンを狼に変えたのは絶対の絶対にぼくじゃありません」
そこでクローヴィスが言います。
「ですが、こうしてまのあたりにする眺めはご主張とはまるで逆ですよね、そこはご同意いただけますでしょ」
ミセス・フープスは涙交じりに言います。
「おまえがやったんじゃなくても、持ち前のすごい魔力で、みんなが噛まれる前にこの恐ろしいけだものを無害な何かに変えてくれない――兎とかに」
さてさて困ったレナード。すると、そこにミセス・ハンプトンが現れます。
「誰か、わたくしを催眠術にかけたでしょ」
そしてミセス・ハンプトンはレナードに「あなたは本当に魔術を使ったのね」と言うのですが、もはや焦燥しきったレナードは力なくかぶりをふります。
そこにクローヴィスが言うのでした。
「みなさん、実はあれは私がやったのです。実は私もシベリア魔術にちょっとした心得がありまして」
というお話。実はこれ、一見レナードがミセス・ハンプトンやクローヴィスに懲らしめられる話のようなのですが、実はそうではないのですね。
確かにレナードはちょっと悪い人なのだけれど、でも良く考えたらもっと悪いのはミセス・ハンプトンとクローヴィス、そしてパブハム卿。
彼らはグルになってレナードが得ていた名声を落とした挙句、代わりに自分たちがそのレナードの名声をすっかり頂いてしまっているのです。
勧善懲悪、と言うよりもむしろ勧悪懲悪。ああ憐れむべきレナード! ま、自業自得なんですけど。
賢い悪は憎めない
さて、本書には合計36の短篇が収められているのですが、大体ほぼこういう形になっています。
そして僕たちはこれらの物語を読み終わった時に、つい「ニヤリ」としてしまう。一番悪い人のした悪いことは書かれていませんが、ちゃんと読者にはそれが分かるようになっているからです。
まさにそれに気づくことこそサキの小説の醍醐味と言えるでしょう。
……実はですね、ここまで考えて、僕は今「ちょっと困ったなあ」と思っているのです。
何で僕が困っているのかを説明するために、今から三つの質問をするので、よかったらちょっと答えてみてくださいね。
一つ目の質問。「善」と「悪」だったら、あなたはどちらを憎みますか?
これはみんな「悪」と答えますよね。僕は自分でも性格が悪い自覚がありますが、それでもやっぱり「悪」を憎む心は持っているつもりです。(いやほんとに)
二つ目の質問。「賢さ」と「愚かさ」だったら、あなたはどちらを憎みますか?
これも簡単ですよね。僕は賢い人の悪口を言うのは好きですが、そんな僕でもやっぱり「愚かさ」を憎みます。(嘘じゃないって)
それでは三つ目の質問。「賢い悪」と「愚かな悪」だったら、あなたはどちらを憎みますか?
ちょっとひねった感もありますが、別に難しくはないですよね。理性を働かせれば答えは簡単。「賢い悪」を憎むべきでしょう。だってその方が被害が大きくなるのですから。
でも、だとするとですよ。僕がさっきまで語ってきた「サキの面白さ」とは矛盾することになりませんか?
つまり僕たちは本当は彼の小説を読んで、「いやだなあ」と思いこそすれ、「面白い」と思うのはおかしいのです。そんな風に感じてはいけないのです。「賢い悪」を喜んでることになってしまいますから。
でも、実際僕たちはそう感じてしまう。それはなぜでしょう?
もしかしたらそれは、こういうことなのかもしれません。
僕たちは「悪」を憎む。これは本心です。そして僕たちは「愚かさ」を憎む。これも本心です。
でも僕たちは「賢い悪」のことは、本心では憎んでいないのかもしれません。むしろ本当は好きなのかもしれない。
だけどそれは憎まないといけない、と思っている、ある種の理性という建前として。
サキという人はきっと、そのことに敏感な人だったのでしょう。彼が描こうとしたものは、僕たちの建前と本音の間にあるものだったのではないかと思うのです。
……でも、それは言ってはいけないこと。あんまり考えてもいけないこと。
だからもうこれ以上この話を進めるのはやめましょう。
その代わりに僕のここまでの話に共感しちゃったそこの貴方!
貴方も本書を読んで、そうして「ニヤリ」としませんか?
よろしければサポートお願いします!頂いたサポートは今後の創作活動のために使わせていただきます!
