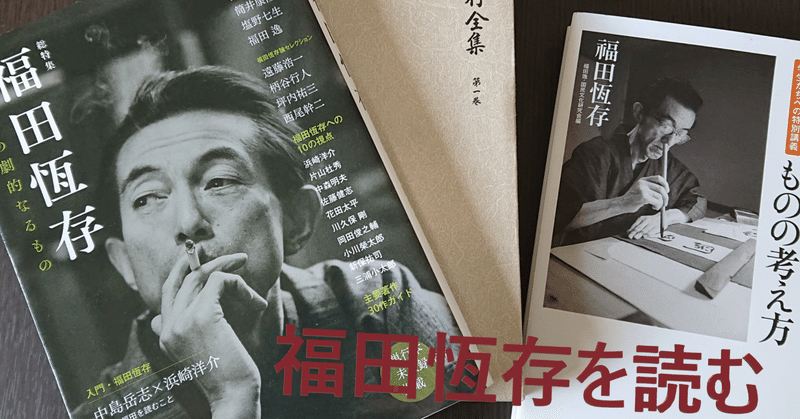
『文学の効用』書きつづけることによつて、その意思の突端がわづかに美にふれる
この論文は昭和二十二年に発表された。
福田は、文学の効用を考えるにあたり、まず芸術至上主義とは何を意味するかを問う。人はよく芸術のための芸術を批判して、人生のための芸術を説く。それに対して福田はこう反論する。
「冗談もやすみやすみいつてもらひたい。上は飛行機に乗ることから下は屁をひり、くしやみをすることにいたるまで、ぼくたち人間のなしうることにして、人生のためならざるものはない。」
屁だってくしゃみだって、身体の健康のために行っている行為なのだ。すなわち人生のために行っている行為なのだ。ただそれをいちいち意識していないだけのことである。つまり同じように、芸術のための芸術を追求することだって、本人が意識していないだけで、人生のために行っていることなのだ。
要するに、芸術家にして、芸術のための芸術を奉ずることは当然の態度である。商人は商売に勤しんでいるではないか。それを指して商売至上主義ということは出来ない。
だとすれば、本当の意味での芸術至上主義とは一体どのような態度を指すのか。
福田は言う。
「なんぴともひとと生まれた以上、芸術家たらざるべからずと盲信し、あるいは一人まへの人間たるためには、かならず芸術を鑑賞し理解する能力をもたねばならぬと強弁するものがあるならば、かれこそたしかに芸術至上主義者といふ非難に甘んじなければならない。」
芸術至上主義とは、言い換えれば、芸術万能主義のことである。あらゆる問題は芸術が解決しうると唱える態度のことである。
「ぼくたちがなんらかの障碍にぶつかつたとき、これを自然科学的技術によつて解決すべきこともあり、政治によつて解決すべきこともある。ときには社交や信用によつて、あるいは争いや借金によつて、ことを解決しなければならぬこともある。が、あらゆる障碍が文学によつて解決しうると考へるならば、あるいは文学はあらゆる障碍にたいして万能的効力を発揮すると考へるならば、それはとんでもない誤解といふべきであらう。」
では、このような誤解はなぜ文学において起こり得るか、起こりやすいか。たしかに、絵画をもって、「あらゆる問題は絵画が解決する」と叫んでいる人はあまり見たことがない。
福田によると、その理由は二つある。その第一は文学そのものの本質に関わるものであり、その第二は近代日本のみの特殊事情である。
第一の理由は、文学における「ことばの二重性」の問題である。
「ことばは文学といふ芸術を構成する素材であると同時に、現実生活における日常用語である。」
文学において言葉は二重性をもっている。
我々は文学において、日常生活で使用している言葉をなんら変改し整備することなくそのまま使用している。その点が、他の芸術と文学との異なる点である。たとえば、絵画は絵具をもっているし、音楽は音楽にのみ用いられる音階をもっているし、建築はそれ用に整えられた木材をもっている。
「が、文学においてのみ、ぼくたちは家といへば家を、山といへば山を、月といへば月を、そのままいちいち現実世界のそれらに検証して肯定するのである。で、ひとびとは実感といふことばを発明した。」
このことは、絵画や音楽と比較して、文学のみが負わされた不幸である。しかし一方で、その点において文学は他の芸術にたいする優位性をもっていると福田は言う。
文学は、誰もが一応は使える言葉というものを素材とするがゆえに、素材そのものからの抵抗はほとんどない。言い換えれば、言葉を使える人間なら誰でも一応は書くことはできる。その代わり、抵抗は直接に現実世界からやってくる。そこで、文学における美というものが問題となってくる。
「かれはすでに樹立しえてゐる美を表現するのではない—— 創作過程を通じて美に到達するのだ。書きつづけることによつて、その意思の突端がわづかに美にふれるのだ。かれは悪戦苦闘して現実の重荷を美の門口までもつてゆくだけのことである。あくまでことばの日常性とその論理とにしたがひ、そのうちに終始しつつ、作品の終結においてその論理の極限にまで到達するのだ。」
文学において、美は作品そのもののうちにはない。作家のうちにのみ存在する。福田の言葉で言えば、「作品の真実は現実の組伏せそのもののうちにあるのではなく、現実を組伏せる姿の美しさのうちに賭けられる」。
ここに様式という問題が出てくることになる。ひとつの時代やひとつの精神が真実であることを保証するものは、ただ一つしかない。様式の美である。
「もしひとつの時代がみづからの不安定性を真実にまで定着しえたとするならば、それはその時代がそれ自身の様式をもちえたことを意味するのにほかならない。(中略)それみづからの様式を獲得せずして、ひとつの時代もひとつの民族も、おのれを歴史のうちに位置づけることはできないのだ。すでにあきらかなやうに、時代や民族の精神的真実はまさに様式の美によつて証されるのである。」
事実と真実は異なる。事実は、様式の美を得て初めて、真実、すなわち歴史となるのだ。
地球が丸いという事実や、地球が太陽の周りを回っているという事実を知らなかった古代人は、真実をもっていなかっただろうか。そんなはずはない。彼らには彼ら自身の様式があった。その美しさが、彼らの精神を歴史に刻んでいるのだ。
たんなる過去を歴史に変えるものこそ、様式である。その美しさである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
