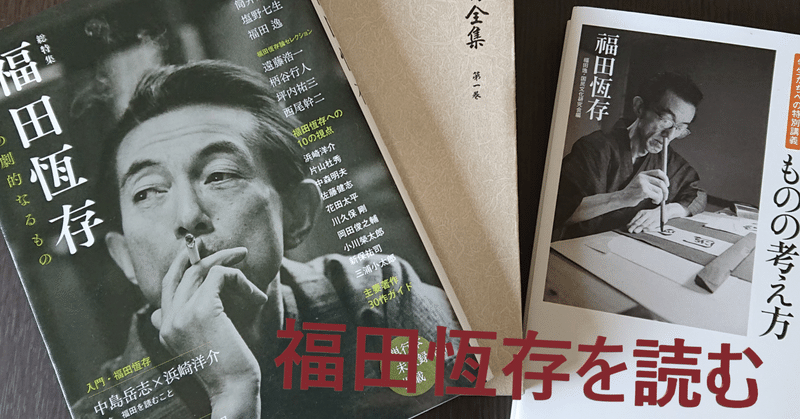
『一匹と九十九匹と —ひとつの反時代的考察』ペシミスティック・オプティミズムという生き方
この論文は昭和二十二年に発表された。
①まずは何よりも混乱に気づくこと
冒頭の引用から始める。
「今日、ぼくたちは混乱のただなかにゐる。といつてぼくはなにも敗戦後の現象的なさわがしさをいつてゐるのではない。有能な政治や思想的な啓蒙が解決しうる困難は知性にまかしておけばいい。ぼくたちのおちいつてゐる真の混乱は日本の近代とともにはじまつた。(中略)今日もしあたらしい時代がひらかれようとするならば、まづこの混乱をただし、この混乱をあきらめることからはじまらねばならぬ。いや、いまはなにより混乱そのものに気づくことがたいせつである。現代におけるあらゆる現象的なさわがしさは、この混乱に無感覚であることから生じてゐる。」
冒頭の一段落のなかに、「混乱」の語が九度も現れる。それだけ、当時の福田が混乱を身に染みて感じていたことが伝わってくる。福田は、混乱に慣れ過ぎて混乱のなかにいることを忘れている人々に対して語りかける。まずは混乱に気づくことから始めようと。
だれもかれもがおのれの立場を固執して譲らない。しかしそれは思想や信念の確かさから来るのではなく、むしろその逆であり、思想を持たないがゆえに、時々に変化する事象に捉えられているに過ぎない。
今日どこを見ても思想の片鱗すら見当たらない、ゆえに人間が見当たらない。存在するのはただ事実の断片のみである。なぜそうなってしまったのか。福田は問うて、自ら答える。
論争ばかりしているからだ、と。
「論争に参与するのは知性である。思想は論争しない。ひとりの人間の肉体がさうであるやうに、思想もまた弱点は弱点としておのれを完成する。(中略)ひとびとは論争において二つの思想の接触面しかみることができない。論争するものもこの共通の場においてしかものをいへぬ。この接触面において出あつた二つの思想は、論争が深いりすればするほど、おのれの思想たる性格を脱落してゆく。かれらは自分がどこからやつてきたかその発生の地盤をわすれてしまふのである。」
論争に関わるのは知性である。知性の最大の特徴は論理であろう。だが思想は、すなわち人間は決して論理だけでは成っていない。
論争とは思想を持たない焦燥から生まれるものだ。それは自己を成り立たせるために他者を否定することに過ぎない。しかし他者の否定は自己の肯定にはつながらない。
「他者を否定しなければなりたたぬ自己といふやうなものをぼくははじめから信じてゐない。ぼくたちの苦しまねばならぬのは自己を自己そのものとして存在せしめることでなければならぬ。この苦闘に思想が参与する。もしそこに犠牲がいるとするならば、それは自己そのものであつて、他人の存在をおびやかすことは許されぬ。」
思想に決着というものは存在しない。思想史とは二千年の矛盾撞着の歴史のことである。それはたがいに矛盾するものであるからこそ思想であり、思想であるからこそ今日まで生き残っているのである。老子の思想と孔子の思想、どちらが客観的に正しい思想だろうか。質問自体が馬鹿げている。
要するに、この世界には、知性や論理では決着のつかない領域が存在する。それは論争では永遠に解決できない領域である。
「すでにあきらかであらう ——ぼくのいふ今日の混乱とは、容易に決着のつかぬ問題をただちに決着しようとすることから、といふよりは、決済のできぬ問題を決済可能な場で考へることから生じたものである。」
明治以来、日本は容易に決着のつかぬ問題を無理に即座に決着させようとしてきた。それは近代化の波の中で、西欧に追いつくことを目指した必然的結果でもある。
それを認めた上で今もう一度、歩きだそう。まずは何よりも混乱に気づくことだ。
②政治と文学それぞれの仕事
「由来、ぼくたちの人生観を妙にあつさりとわかりやすいものにするひとつの危険な俗論があり、この俗論には知識人や思想家も案外たやすくまゐつてきたものである。といふのは人生がひとつの目的を有し、人間活動のあらゆる分野がそれぞれの分担においてこの目的にむかつてうごいてゐるといふ考へである。」
この俗論は所謂、歴史の合目的性である。文学も政治も、哲学も科学も芸術も、すべては同じひとつの目的に向かって営みを続けているという考え方である。人々がこのような考え方を好むのは、そのように考えれば互いの仕事を容易に理解できるからである。
だが、と福田は言う。「たがひに相手のいとなみを理解しようとし、また理解したとおもひこむ習慣が、相手をおのれの理解のうちに閉ぢこめてしまひ、その完全ないとなみを妨げる。政治は政治のことばで文学を理解しようとして文学を殺し、文学は文学のことばで政治を理解しようとして政治を殺してしまふ」。(『一匹と九十九匹と ——ひとつの反時代的考察』福田恆存全集第一巻)
『理解といふこと』でも福田は述べているように、安易に相手を「理解したとおもひこむ習慣」こそが、相手の十全な自己発揮を妨げることになるのである。
「ここにぼくは文学者として政治に反発する。政治がきらひだからでもなく、政治を軽蔑するからでもない。政治に対するぼくの反発は政治の否定を意味するものではない。それは政治の十全な自己発揮を前提としてゐる。」
政治と文学には別々の目的がある、そのように福田は考える。
「ぼくはぼく自身の内部において政治と文学とを截然と区別するやうにつとめてきた。その十年あまりのあひだ、かうしたぼくの心をつねに領してゐたひとつのことばがある。「なんぢらのうちたれか、百匹の羊をもたんに、もしその一匹を失はば、九十九匹を野におき、失せたるものを見いだすまではたづねざらんや。」(ルカ伝第十五章)」
この聖書の言葉を福田は自分流に解釈する。
「かれは政治の意図が「九十九人の正しきもの」のうへにあることを知つてゐたのにさうゐない。かれはそこに政治の力を信ずるとともにその限界をも見てゐた。なぜならかれの眼は執拗に「ひとりの罪人」のうへに注がれてゐたからにほかならぬ。(中略) ぼくもまた「九十九匹を野におき、失せたるもの」にかかづらはざるをえない人間のひとりである。もし文学も ——いや文学にしてなほこの失せたる一匹を無視するとしたならば、その一匹はいつたいなにによつて救はれようか。」
政治とは九十九匹のために、文学とは一匹のためにある。政治が十全に力を発揮したならば、九十九匹は救われよう。その期待があるからこそ文学は、また文学者は、残りの一匹を救うことに己れの仕事を全うできる。
仮にこの観点から日本の近代文学を顧みてみると、その薄弱さの原因を、文学者における政治意識の希薄だけに帰することはできない。
つまり、福田は日本の近代文学史を次のように考える。明治以来の政治は十全に力を発揮していなかった。そのため百匹のうちの十匹しか救えていなかった。そこで文学者は本当に救うべき一匹を探すために、残りの九十匹のあいだを探し回らなければならなかった。結果として、真に迷える一匹の所在を見失うことになってしまったのだ、と。
「ぼくの知りうるかぎり、ぼくたちの文学の薄弱さは、失せたる一匹を自己のうちの最後のぎりぎりのところで見てゐなかつた ——いや、そこまで純粋におひこまれることを知らなかつた国民の悲しさであつた。しかもぼくたちの作家のひとりびとりはそれぞれ自己の最後の地点でたたかつてゐたのである。その意味において近代日本の文学は世界のどこに出しても恥しくない一流の作家の手によつてなつた。が、かれらの下降しえた自己のうちの最後の地点は、彼等に関するかぎり最後のものでありながら、なほよく人間性の底をついてはゐなかつた。」
③二元論で世界を捉える
「ぼくはぼく自身の現実を二律背反のうちにとらへるがゆゑに人間世界を二元論によつて理解するのである。ぼくにとつて、真理は究極において一元に帰一することがない。あらゆる事象の本質に、矛盾対立して永遠に平行のままに存在する二元を見るのである。」
福田は、二律背反を含むかれ自身の人格の統一を信じている。それゆえに、知性によってあらゆる矛盾を一元的に解決しようとする営みに疑念を抱かざるをえない。
その代表的なものとして科学がある。科学というものは、生活を快適にするという効用性の領域でのみ有用である。しかしそれが高じて、人間の文化価値のすべてを科学の対象にしようとするならば、その行為は「知性の越権といふべきか、それとも知識人的事大主義といふべきか、いづれにしても自己を信じえぬ薄弱な精神の所為とせねばならぬ」だろう。(『一匹と九十九匹と ——ひとつの反時代的考察』福田恆存全集第一巻)
現実はあきらかに合理と不合理の領域を並立せしめている。だとすれば現実を認識するということは、この二つの矛盾を矛盾のままに把握することでしかない。要するに、この地点から先において科学は ——また政治も政治学も——無力である。
知性の解決しうる領域で知性を放棄することが神秘主義なのであって、知性の及ばぬ領域においては我々は潔く知性を放棄すべきである。
④ペシミスティック・オプティミズム
福田は、政治と文学の区別を主張している。しかし誤解してはならないのは、福田が言っているは両者の乖離でも、相互否定でもないということである。
反対に福田は、両者の完全な一致を理想とするがゆえに、その方法として、両者を区別するのである。両者がそれぞれの存在と方法とを尊重し合った上で、それぞれの持ち場にいることを願うのである。
これこそロレンスが福田に教えた「ペシミスティック・オプティミズム」であった。彼は文学者として一匹を救うことだけに己れの全てを懸ける、最後に百匹の救いが果たされることを祈りながら 。
「政治の目的達成をまへにして ——そしてぼくはそれがますます九十九匹のためにその善意を働かさんことを祈つてやまず、ぼくの日常生活においてもその夢をわすれたくないものであるが ——それがさうであればあるほど、ぼくたちは見うしなはれたる一匹のゆくへをたづねて歩かねばならぬであらう。いや、その一匹はどこにでもゐる ——永遠に支配されることしか知らぬ民衆がそれである。さらにもつと身近に ——あらゆる人間の心のうちに。」
あらゆる人間の心の内には、失われたる一匹が存在している。それは政治はもちろんのこと、哲学でも倫理学でも、社会学でも精神分析学でも救えない一匹である。
我々のうちにいるその一匹こそ、文学が訪ね歩く一匹である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
