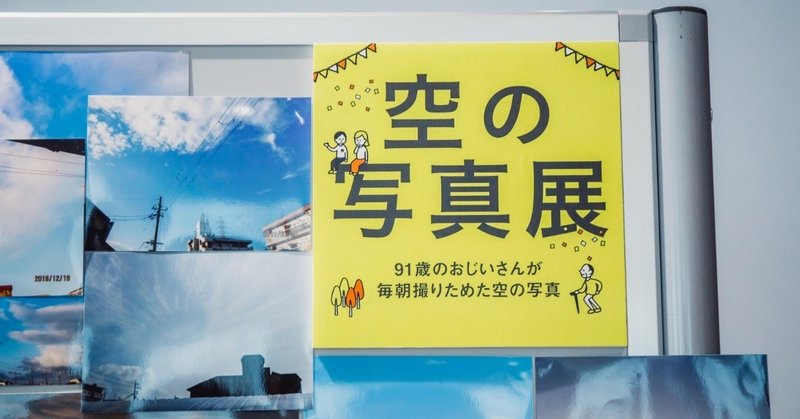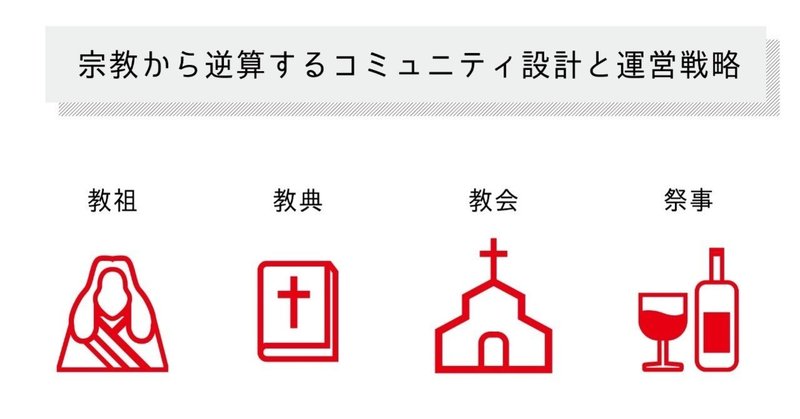#コミュニティ

喫茶ランドリーの憲法|6ヵ条:働くこと、共に生きること、あなたらしくいること、幸せになること、そのために必要なことをギュウっとまとめてみました!
喫茶ランドリーを考えはじめた当初、数多くカフェを運営されている方に何が一番大変ですかと聞いたところ、「それは人間関係ですよ」と答えて下さいました。むろん、そんな答えを聞いても、人一人雇ったことのなかった私たちには、何一つイメージが沸きませんでした笑。 そのような中で、気が付けば独自のお店をづくりをしてきたのだと思います。これまで喫茶ランドリーが、お客さんにとっても、また働くスタッフたちにとっても、他の場・お店にはない居心地を実現してきた背景には、人間らしい圧倒的な信頼関係が

「喫茶ランドリー」はやっぱりヤバい?コロナで来客3名!?になっても開け続けたら…地域に開くってそういうことだよ、と教わりました。
2018年1月5日にグランドオープンした「喫茶ランドリー」は、おかげさまで2年が経ち、3年目に突入しました。当時オープンしてまもなく書いた下の記事は、この2年間ずっと毎日誰かしかが読んでくださり、また、この記事をきかっけに全国各地からも来店してくださる方が絶えないので、本当に嬉しい限りです。 そして、ここをきっかけに喫茶ランドリーをつくり、運営しているグランドレベルという会社には、住宅や団地、マンションやスポーツジム、オフィスに市役所、広場や歩道など、さまざまな1階に人のい

コロナからのまちづくり03|利他主義とまちづくり|Eテレ超訳ジャック・アタリ(経済学者・思想家)から、田中と大西がグランドレベルの所信表明2020を!
先日、深夜にそれとなくテレビを付けたら、Eテレでジャック・アタリさんという経済学者で思想家の方の緊急インタビューが画面に映っていました。今回はそこから、私と田中元子で会話したことを、今回はそのまんま公開! (´・ω・`) 今、Eテレでジャック・アタリさんて人が、いつも我々が話しているようなことを語っとたよ! 冒頭のタイトルが「altruism・利他主義」。 (´・д・`) !!!でも俺ね、知ってんの。この「利他主義」って言葉、すっごい誤解されるんよね。英語のママが伝える