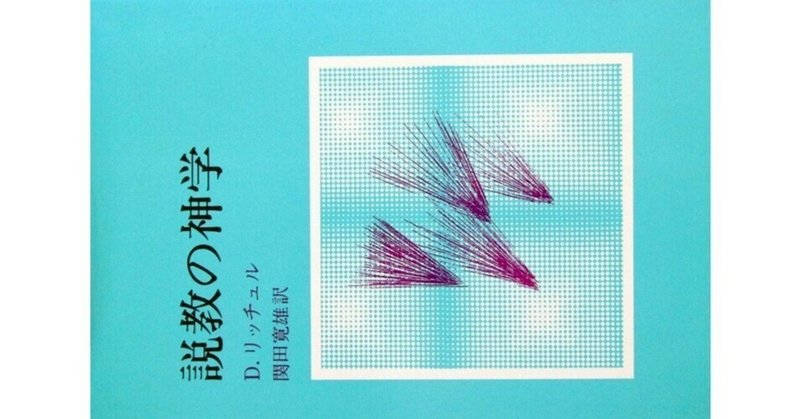
『説教の神学』(D.リッチュル・関田寛雄訳・日本基督教団出版局)
原書は1960年であるというが、実はその少し後から、翻訳の話があったのだという。だが、訳者が、青山学院大学の神学科廃止の問題に巻き込まれ、翻訳へ力を注ぐことができないまま、20年が経つ。そこでようやく日の目を見るようになった。私たちに、説教に対する力強い思想がもたらされた。
リッチュルは、1929年にスイスのバーゼルで生まれた。と聞くと、やはりカール・バルトとの関係がどうか、というところが気になるであろう。確かに、その影響は大きいと思われる。この辺りの事情を、「訳者あとがき」は簡潔にまとめている。バルトの「神の言の教理」に依存する形で出発した。それからレスポンスの重要性から礼拝について深く考えることをなすが、そのときに、信徒が受け身ではなく、礼拝をつくる積極的な役割を担っていることを軸としているのだという。
これは本書でも貫かれており、途中で、説教者が自由に語り信徒が聞くのだ、という図式を完全に破壊している。語るための聖書箇所すら、牧師が単独で決めるのではなく、信徒が決め、それに牧師が従って説教をつくっていくのだ、ということが非常に強調されている。これは私には非常に新鮮なことだった。そんなことができるのだろうか。
また、訳者は、説教者が聖書というテキストを自由に解釈し、解釈が主眼になってはならない、というリッチュルの考え方をも示していた。テキストに従うべきなのである。
そして、その説教は、言ってみれば歴史的に一回きりのものであるという。いつでもどこでも通用するような、見事な説教の見本のようなものを呈してはならないのである。カイロス的なその時のために与えられた、唯一必要な説教が語られるのだというのだ。
それだから、かもしれないが、説教にルールはない。説教はこうあらねばならない、とか、説教はこのようにして生み出されなければならない、という方法が決まっているのではないのだという。
このような姿勢を軸として、全体は、「教会と説教」とでも呼ぶべき世界を呈示している。どうして説教があるのか。教会があるためだ。教会に、神の言がもたらされなければならないのだ。そうして、訳者がまとめたようなことを、231頁まで述べる。説教の作り方のレシピではない。説教たるものが、教会においてどう扱われなければならないか、ということについて叫んでいる。確かにそれが「説教の神学」である所以であると言えるだろう。
こうして本論が終わった後、「付論」が掲載されている。わずか8頁に過ぎない。
方法論のアドヴァイスをしてこなかったのは、説教の方法に理想の形があるわけではないからだ、と弁明しているが、説教自体が最大限に神学の中心に位置することだ、と掲げてくる。
だが、それは、説教者のストイックなほどにまでの勉強や研鑽を要することなのだ、と著者は強調している。そして信徒もまた、同様に、自らが変わらなければならないと考えている。教会がうまくゆかないことを、他人のせいにしたり、政治のせいにしたりすることはできない。これはきつい指摘である。私たちは変わらなければならない。では、具体的にはどのようにか。
まず、問題にそれなりに長時間、集中して考える機会が必要だ、という。毎回手を替え品を替え説教を振り撒くのではない。一か月の間、一定の書に留まって語るとか、一定のテーマを問い続けるとかして、毎週深まる霊に導かれつつ、腰を据えて説教者は取り組まねばならない、というのである。このとき、原典との向き合い方や聖句の見つめ方、また黙想に入り、注解書の取り扱い方をレクチャーする。
しかしまた、一方では、世のことにも十分弁えておく必要が指摘される。「一人の教養人」として、広く自由に社会のこと、世の中のことを知らねばならない、というのである。この世界における教会の位置づけ、立ち位置を知るためには、この世界についての広く深い知識と理解が必要なのである。確かにそうだ。教会は、夢見るための場所ではない。地域の中での役割を担うことのできない教会が、如何に多いか。また、せっかく前任者が地域の中での役割に気を払い、運動を続けてきたのに、聖書も救いも知らない後任者が来てからは、地域になど全く目を向けないで、内輪だけなんとかしようともがいている教会もある。
しかし、世の文化と福音とは混同されてはならない。まさにこれは「聖」なのである。だから、妙にご機嫌を取って「分かりやすい」説教をする必要は全くない、という。人は、何か分からないことも、そのままに胸に秘め、熟すのを待つものなのだ。心に何か引っかかるものがあり、気になって仕方がない、というようなものを語るのが、私の理想である。誰にでも分かりやすい、いわば常識的な「お話」をして、ベタなオチで常に終わり、「いいお話でした」と言われるのがうれしくて、それでいてその話は誰の心にも遺らない、そして結局多くの人が、まともに聞きもしていない、というような「お話」については、私は辟易している。そういう教会が現にあるのである。
このように、私にとってではあるが、最後の「付論」が、実に感動的に心に響いてきた。冗長なところもなく、スパッと斬り込んでくる力があった。それだから、もしも本書に触れる機会があったら、この「付論」だけでも、教会の読書会に用いるとよいのではないか、と思う。教会が、生き返るかもしれない。それとも、死んでいるのに、生きているかのように、勘違いをしている場合であるだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
