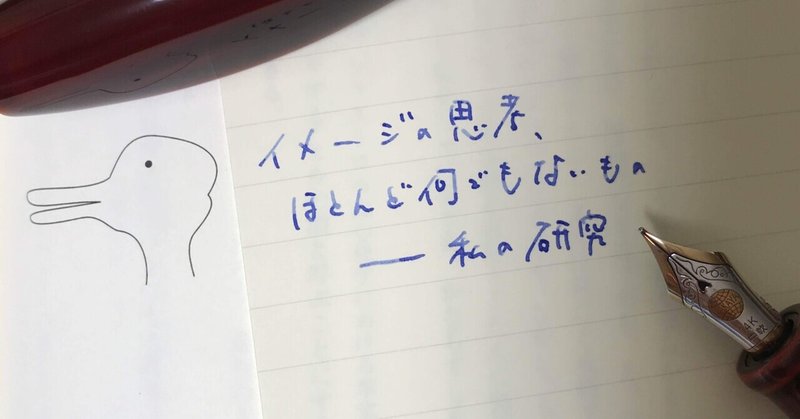
イメージの思考、ほとんど何でもないもの──私の研究
哲学は音楽のようだ。それはあまりにもわずかにしか存在していなくて、なしですませてしまうのもごく容易い。でもそれがなければ、何かが足りない。たとえその何かが言えなくても。……結局のところ、この何か知れぬものがなくても生きていける。哲学も、音楽も、喜びも、愛もなく、生きていくことはできる。けれども、それはあまりよいものではない。
──ウラジーミル・ジャンケレヴィッチ
哲学者たちはイメージに目がない。彼らはしばしば壁のごとき灰色の言葉の下にイメージを隠してしまうにしても、これほどイメージを必要とする職業はほかにない。彼らはよく知られたイメージを創造した。一つは洞窟だ。もう一つは、けっして二度と入ることのできない不吉な川だ。また別に、亀に追いつけずにその後ろで息切れしているアキレウスもある。合わせ鏡、松明をリレーする走者たち、そしてニーチェまでいけばその鷲、蛇、綱渡り師……。
──ポール・ヴァレリー
1 卒業論文がリュック・フェラーリの音楽作品を分析するもので、修士論文ではウラジーミル・ジャンケレヴィッチの時間論がとくに導きの糸になり、博士論文はジョルダーノ・ブルーノの人間論をめぐる考察であった。ミシェル・セールの哲学に共感を覚え、ユベール・ダミッシュの美術史学に感銘を受けてきた。ミシェル・ド・モンテーニュの書物に愉しみを見いだし、吉田健一の文章に寛ぎを感じる。
そこにどんな一貫性があるのかと尋ねられるたびに、いつも困惑した。一貫性などなく、ただそのときどきの興味にしたがっているまでと答えられたなら、気も晴れたかもしれない。でも、何かがそこにあった。何か知れない、曰く言い難きものがそこにあって、それは今でも変わることなくつねに思索の核心にありつづけている。
その何かを何と言えばいいか。空気の震えを音楽にし、布地の染みを絵画にするもの。風と音楽、布と絵画、そのあいだの差異は、ジャンケレヴィッチなら「ほとんど何でもない」と言うだろう──これはフェラーリによる逸話的音楽の代表作の題名でもある。あるいはウィトゲンシュタインに倣うダミッシュに倣って言えば、そこには「アスペクト」の差異しかない。けれども、このほとんど何でもないアスペクトの差異に、人間にとってのすべてが存している。音楽は空気が揺れているだけ、絵画は布切れが汚れているだけ、なんなら人間も蛋白質が反応しているだけ、と言ってしまうことは簡単であれ、それでも音楽、絵画、そして人間をそれとして感得させる何かが経験のただなかで働いている。それがなければ音楽はないし、絵画もないし、すべての芸術はなく、もっと言えば人間もなく、その文化も社会もなくて、生と死の差だってないことになろう。
そのように芸術を芸術にし、人間を人間にし、生と死とを分かつ、ほとんど何でもないアスペクトの差異はいったい何なのか、それはどこまで広がっているのか──これがつねに思索の核心にありつづけている謎だ。これは芸術の概念的定義の問題ではない。このほとんど何でもないような何かによって生じるすべてのことを、それがどこまで広がっているのかを、描き出すという課題である。この何かは理論と歴史の蝶番であり、そうして結び合わされる理論的文脈ならびに歴史的経緯があってはじめて芸術は芸術になるが、しかし結び目たるこの何かをそれ自体として把握することは叶わない。あのウサギ=アヒル図は、ウサギにもアヒルにも見えるが、同時に両方であるその図それ自体としては見ることができない。だからこそ、ブルーノはじめルネサンスの人々は──そして爾後のヨーロッパ人たちは──美の本質を「何か知れぬもの」、私には分からない何か、曰く言い難きもの、と呼んだのだろう。それをジャンケレヴィッチは人間にとってのすべてにまで敷衍して、「ほとんど何でもないもの」と言い直したのであった。
2 ほとんど何でもないアスペクトの転換から、一つのイメージが生じる。そうしたイメージはもちろん果敢ないものである。しかしその果敢なさゆえに、イメージは表象するものと表象されるものとの二項関係に閉じることなく、次々と転換しては連鎖していく。これが一つの思考になる。芸術作品がしばしば思考のモデルになるのは、そのために違いない。思考は無から生じることはなく、何かしらの対象から触発され、ときにはその対象のイメージが思考の内容のみならず思考の形式そのものになってしまう。比喩はその最たるものだ。概念を定義して体系化していくのとは異なって、喩え、擬え、象りながら思考が展開していくとき、そのような思考をさしあたり「イメージの思考」と呼んでいいだろう。もちろん伝統的に「想像力」と名指されてきたものでもあって、プラトンのミュトスからレヴィ=ストロースの神話論理までを覆っている。内包的真理を扱う論理学に対して美学は外延的真理を扱う、としたバウムガルテンの感性的認識もそこに連なっている。
実際的な研究主題をなしてきたのは、このイメージの思考のありようだ。ルネサンスと現代という二つの時代を調査地にして、ルネサンス人文主義のうちにイメージの思考の近代的な端緒を発掘するとともに、その今日的な帰趨を現代思想のなかに追跡してきた。
ルネサンス人文主義は、後世さまざまに語られた「ヒューマニズム」とはずいぶん異質なものに思える。ブルーノは人間の理想像を伝統的な「賢者」から「狂人」へと変えてしまい、理性よりも想像力を、主体性よりも関係性を軸にして、人間の多様性と社会の複雑性を論じている。この傾向は、ブルーノほど極端でなくとも、マキアヴェッリからモンテーニュまでにも見られる。人間は「カメレオン」(ピーコ・デッラ・ミランドラ)のように変幻自在の存在者になり、その思考も概念ではなくイメージにもとづいて融通無碍に繰り広げられる。ルネサンスというアナクロニズムが生みだしたヒューマニズムは、人間とその思考をアンフォルムに変えてしまったのだ。
このことの淵源には、当初は古典語の復興運動という一つのアナクロニズムとして始まったルネサンス人文主義が、中世スコラ学の論理学重視に対してむしろ文献学・修辞学を重視し、自由検討を真理探究の方法に据えたことがあるだろう。そのために言語・思考・真理の関係づけが根本的に組み替えられた。言語は概念的定義よりも歴史的用法にもとづくものになり、思考は論理的概念よりも修辞的イメージをもちいるものになり、真理は唯一の仕方ではなく多種多様にあらわされうることになった。
ここからルネサンスの哲学と芸術は「詩は絵のごとく」を掲げて互いを互いのパラダイムとし、イメージの思考の典型になった。モンテーニュは『エセー』を肖像画に、マキアヴェッリは『君主論』を風景画に擬えている。その極北がブルーノであって、彼によれば「真の哲学は音楽ないし詩にして絵画であり、同じく真の絵画は音楽でも哲学でもあり、真の詩にして音楽は神的な知恵であり絵画なのである」。
3 イメージの思考は、概念の思考のような抽象と定義という操作とは別の仕方で、つまりは交換と翻訳の操作によって、多様性から普遍性へと到達する。このとき多様性と普遍性がいかに結節されるのか──研究の実際的な問題機制をなしてきたのは、この問いだろう。何も新しいものではない。伝統的に言えば「多と一の関係」を問うているのであって、連綿たるプラトン主義の系譜がある。今日的にも、本質主義と構築主義の問題点を踏まえて多様性と普遍性を関連づける知的努力がつづけられている。
そのなかでルネサンス・プラトン主義は、フィチーノからブルーノまで、しだいに形而上学的基礎を超越から内在へと転倒させていった。世界の生成変化を超越した不変不動の一者は、世界を生成変化させる遍在的で内在的な一者へと反転した。この反転は、ハンス・ブルーメンベルクがクザーヌスとブルーノとのあいだに見た思想史的断絶と別のものではない。かくしてブルーノの無限宇宙は、ウサギ=アヒル図のごとく、多様でありつつ普遍であり、多様だから普遍で、普遍ゆえに多様であるものになる。多様性から普遍性が抽象されるのではない。多様性を包含し展開する普遍性を、ブルーノ哲学は存在論的に根拠づけるのである。
言うなれば「世界の複数性」というこの存在の描像が、ブルーノ以後、ジョン・トーランド、シェリング、またヴァールブルクへと、いかに反響したのか。現代にいたっても、たとえばマッシモ・カッチャーリにどれほど反響しているのか。あるいは、ミシェル・セールの〈大きな物語〉は、直接の出発点こそブルーノでなくライプニッツであれ、きわめて近しい描像でもって多様性と普遍性を結節していて、それがどこまでモンテーニュ──ひょっとしたら互いの著作を読みえたかもしれないブルーノの同時代人──に負っているのか……。こうした系譜の分岐を一つ一つたどっていくことで、多様性と普遍性とを結節するイメージの思考の、ほとんど何でもないような「アスペクト転換」(ウィトゲンシュタイン)にして「構造変換」(レヴィ=ストロース)の働きを、その広がりにおいて描き出せるだろう。ウィトゲンシュタインのアスペクト転換とレヴィ=ストロースの構造変換を重ね合わせたダミッシュの洞察は、つくづく天才的だと思う。
そのダミッシュが生涯こだわりつづけた画家ポントルモの言葉は──もともとの文脈からすれば別の意味合いではあるのだが──まさに同時に問いでも答えでもある謎々として響く。「絵画は表の毛が抜けてしまえば何の値打ちもない弱くて安物のどうしようもない布地のようなものです」。これがすべて、ほとんどすべてだ。
(2020年5月16日―2021年4月3日)
