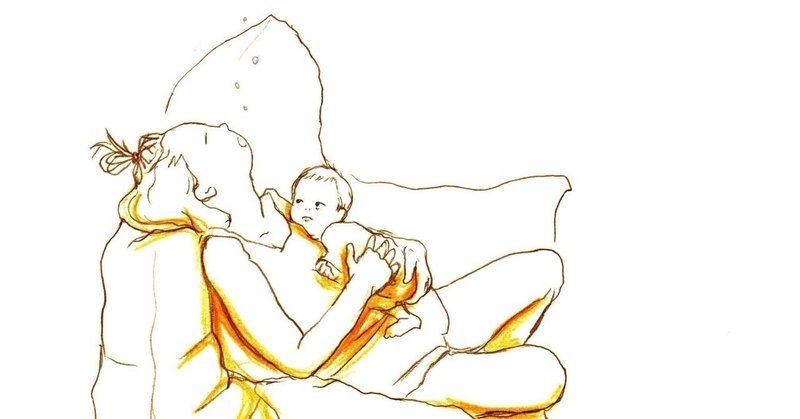
ゆる家事ゆる育児、自分をゆるめる。
家事育児は終わりがない。
家事と3人の子どもたちの世話を真面目に取り組んだら、1日が一瞬で終わると思う。
だから、家事育児は趣味として付き合っていこうと思っている。
「あー〇〇(家事育児の類)しなきゃなぁ・・」
と、こころがつぶやいたら即!!一回消す。
「○○したいなぁ」に変わるまで一回放置する。(又はあきらめる。笑)
たとえば
「ごはん作らなきゃ」と思ったら、
■「これが食べたい!作ろう!」って思うまで料理本見たりする。
(高確率でやる気が出る。作るよりも、料理本見てる時間が好き。)
■作らないで買っちゃうor外食しちゃう。
■夜ならちょっとプシュっとして(本絞り)とりあえずゆるむ。
■子どもに任せる(最近、平日の朝ご飯は子どもたちが準備して卵かけごはんとか、納豆ご飯とか、朝ご飯セットを出して食べてくれる。超助かる。(小4、小2、4歳)
■インスタントラーメンでもいっか。と一回許す。
こんな感じで、一回ちょっと時間を置いたり逃げ道があると思うだけで、
「やってもいいかな~」って気持ちなったりする。
なにより心の負担が軽くなってつらい方向に向かってしまうのを防げる。
ここに、自分の本心以外の何かが入ると苦しくなる。
作ったほうがいいかな
作らないとだめだよね
作らない母、妻なんてだめだよね
作らないと怒られる(恐怖・・!)etc...
誰か(夫や家族)や世間?の目を気にしたり、自分の本心「作りたくない、今は。」を無視すると、どんどんどんどん辛くなる。
《お母さんがごきげん》であること以上に、家族がハッピーになれることはないと断言する。
お母さんが辛そうだと、子どもが責任を感じてしまう。
だから家事育児は趣味だと思うとちょうどいいと思う。
趣味は、好きな時に、好きなだけ、好きなように、楽しんですること。
そう考えると「ねば・べき・かな」がなくなる。
「したい」だけになる。
家事が怠ったところで、家族の幸せに何の影響力も持たない。
家事育児は、お母さんだけがやるべきことじゃない。
一緒に暮らす人たちがみんなで協力して、できる範囲でするもの。
そうやって暮らすことで、思いやりのこころも育っていくはず・・・
「わたしがやらなきゃだれがやるのー!(キィーー!)」と、最初の1~2年は必死になって全力で家事育児してたけど、母親だけが抱え込んでいると家族(子どもも含む)は何も分からないので助けにくいということを学んだ。
子ども自身に、自分の事は自分で出来るようにする事も大事だし、
完璧を求めずすき間を作って助けてもらいやすくしたり、
出来ない時もある、って自分をゆるく見守ってあげることも、
きげんよく生きていくためには大事なことだな~と思う10年目のゆる母です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
