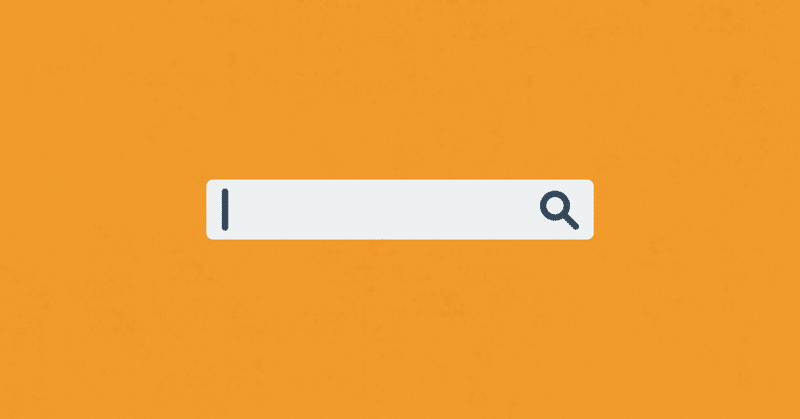
【介護保険改正】課題山積の総合事業、厚労省が新たな検討会を始動 今年夏に中間報告へ・・・という記事の紹介です。
今日は、張り切って一日中外回りをしてきました。
市役所の介護保険課や商工会議所には、事業所開設や創業についてのお礼もしに行く感じでしたが、これはもっと早くしておくべき事だったな、と反省です。
実際、創業直後は本当に忙しかったのでそういう頭がなくてちょっと落ち着いてようやく気が付きました。
あとは日本政策金融公庫さんの創業融資を受ける際に頂いていた助言で、地域の信金さんへの挨拶もあったので、近所の信金さんにも挨拶をしにいきました。
何かあったらいろいろ相談に乗ってもらえそうでよかったです。
地域の全居宅への改めての挨拶と営業も行いました。
まだまだ余裕あるので、という事をしっかり伝えました。
3月末までに職員が営業回りをしてくれていたので、それなりに認知度が高くなっているのは実感できて、結構話せたのでいい感触でした。
特に保険外でどういうサービスが出来るのか、いくらなのか、という部分での応対が多かったので、介護保険サービスでは対応しきれないケースが結構あるんだな、という実感です。
介護保険サービスについては、介護報酬次第でいろいろ変わる部分もあるので、保険外のサービスでどの程度の集客ができるのか、ニーズがあるのかをしっかりつかんでおく事は今後の戦略に生かせるので重要と考えています。
保険外で大きな利益が出るような料金設定ではないので、そこも踏まえて今後どう工夫していくかは実践の中で見極める必要がありそうです。
また、前職場にも軽く挨拶に行きました。
拠点全体がちょっとコロナ対策で気軽に入れる雰囲気ではなかったので、偶然外で見かけた顔見知りのケアマネさんに声をかけていろいろお話をしました。
地域が違うのと訪問介護も提供しているので競合するので、保険外サービスのみ売り込みましたが、ここでも保険外のサービスは好感触でした。
さてさて、今後どういう方向に流れていくかはわかりませんが、介護保険外で勝負する感じになるのであれば、それこそいろいろ自由にできるのでそちらの研究も必要だな、と感じましたし、複数の居宅からは、保険外で出来る事など具体的に書き出したものがあったほうが紹介しやすい、というドバイスも頂いたので、そのあたりの資料作成を優先ですすめようと思います。
そんな感じで忙しく地域を回ってあっというまの1日で、仕事終わったらランニングしようと思ってたんですけど、仕事終わって帰り支度していた職員とあれこれいろいろ話こんでいたら夜も遅くなってしまっていました。
そして、今度は僕の住民票と会社の印鑑証明書がまた必要になったので、明日は空知と札幌を日帰りで登別に戻ってくる事になりました。
もう必要ないかもですが、ちょっと多めに手元に置いておこうと思いますけど、発行後3か月以内のものという指定もあったりするので、どのあたりの匙加減も難しいなぁ・・・なんて感じています。
そして今日は、このニュースを取り上げたいと思います。
要支援の高齢者らを訪問・通所などのサービスで支える市町村ごとの「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」について、厚生労働省は10日、新たに設置した「充実に向けた検討会」の初会合を開催した。【Joint編集部】
地域で8か所目の訪問介護事業所になる僕らの事業所は、やはり後発なので紹介があっても要支援の方、要は総合事業の方の紹介が今のところ100%です。
どの地域でも同じですが、総合事業の利用者さんは人気がない傾向です。
これは単純に単価が低くなってしまうからなんですけど、そうはいっても選り好みできない状況ですので、どんなケースでも受けて信頼を勝ち取っていくのが正しい戦略と考えています。
このニュースでは、その総合事業の訪問や通所サービスについて、さらに充実させるよう検討する会議を始めました、という事なんでしょうけど、本気でやりたいなら報酬からきちんと見直すべきですし、地域まかせの制度設計にもメスを入れないとダメじゃないかと思います。
結局、国が思ってたような方向で進んでないからこういう検討会を立ち上げたんだと思いますが、簡単に言えばシステムや進め方が失敗しているわけですので、そこを変えない限りは充実させるのは難しいでしょう。
「多様な主体による多様なサービスの普及、という点で必ずしも十分に進んでいないとの指摘を受けている」
厚労省で介護保険を担当する老健局の大西証史局長は、冒頭の挨拶でこう問題を提起。介護予防の取り組みや生活支援サービスなどの重要性が一段と高まる今後を見据え、状況をなんとか打開していきたいとした。
多様なサービスの普及、という部分では当社でもある程度尽力できる事はあると思いますし、それぞれのニーズに対して出来る事をこれから創出していきたいと考えているので、そのための保険外サービスです。
ただ、保険外サービスはある程度お金がないと活用できませんので、幅広く手軽に使ってもらおうと思えば料金設定を安くしないと使い勝手がよくないですし、サービスも広がりませんが、そうなると提供できる人材を確保できません。
サービスを継続するのはそこで利益を生まないといけませんので、時給や経費を回収した上で多少なりとも利益が出ないとそれこそ多様なサービスとして存在できません。
社会保障というのはお金のあるなしに関わらずに必要であれば利用できるのが大原則で、それが基本的人権など憲法で保障されている事だと思うのですが、現実はそういう事すらお金で買う必要がある面があると思います。
事業者として利益を上げる必要がある一方で、社会保障制度の一端を担う会社として、幅広い方に使っていただけるサービスを作る必要もあり、そういう部分で非常に難しい判断が必要な内容だと思います。
結局、国はそういう事もまるっと介護関係事業者に丸投げして、何かあれば責任を追及してくる。そういう感じなんですよね。
守ろうとしているのは”制度”であって”社会保障”ではない、そんな感じがしています。
厚労省は今年夏をメドに、具体的な手立ても盛り込んだ中間的な報告書をまとめる予定。それに沿った工程表も策定し、総合事業の充実を計画的に進めていく構想を描いている。国の財政に余裕がなく、マンパワーの確保も難しさが増しているなど制約が多いなか、現場を後押しする改善策の展開によるブレイクスルーを目指す。
どんな案が出てくるのか興味はありますけど、それこそ異次元の提案が出てきそうで怖いですね。
お金はない、人もいない、だけど現場を後押しする改善策をつくるよ、という事ですので、結局は今現場で頑張っている人たちが”もっと頑張る”しかないような対策しか出てこない気がします。
そもそも総合事業の充実とはなんなんだろうか、事業所が増える事なのか、担い手が増える事なのか、何をもって充実とするのだろうか・・・という疑問があります。
介護事業全体でいくと、まだこの先5年10年はニーズが増加するはずなので、総合事業に限定しなくても全体のサービス量は充実してなくって足りてない状況です。当然、人手不足はずっと前から言われていたまま相当な介護職不足が発生しています。
少ない人員で事業を成り立たせるには、生産性を高めると同時に商品単価を高める事が必要です。
介護保険のサービスのニーズも増えるのですから、単価の高いサービスを事業者が選択するのは当たり前の事で、わざわざ単価の安い総合事業を受ける事業所はどんどん減るはずで、しかも自治体によって独自の価格設定が出来るんですけど、僕の理解が間違ってなければ国が示す単価より同じか低くする必要があったように記憶しています。自治体だって大変だと思いますよ、これ以上の工夫は出来ないと思いますし、たしか社会保障費用を減らしたら評価される仕組みだってあったはずです。(詳しく覚えてませんが、何かのニュースで見た気がしますが、あいまいな情報です)
どうにもならないでしょうに。
総合事業の特徴は、市町村がサービスの運営基準や報酬などを独自に決められるところ。相対的に状態の軽い高齢者の幅広い支援ニーズに応えられる体制を、地域の実情に応じてより柔軟に、より効率的に作れる制度設計となっている。
状態の軽い高齢者ですが、個人的にはここで介護予防をしっかりしないので介護度が上がっていってしまうんじゃないかと思っています。
なので、総合事業の段階かその前の段階でしっかり適切な介護予防につながるサービスを導入しておくことが重要なんですけど、実態は利用者さんを含めて、まだサービスを使う必要はない、という判断が多いです。
あまり介護予防のために総合事業のサービスを使う、という発想になってない気がします。
そのあたりの認識とかが変わるようになれば、総合事業の雰囲気も変わってくるのかもしれませんけど、結局、介護=困った事をやってもらう、という間違った認識が多いので、自立支援など出来るだけいつまでも自分でできる事を自分で行えるようにしておくために出来る事が多い時点から介護サービスを導入して、その出来ている期間を少しでも長くする、という発想や視点が広がらないと難しいと思います。
そして、その取り組みって結局結果として出てこないから誰も評価できないんですよ。
介護予防の実践をしたところで、その効果がどのていどあったのかを計測できない。サービスを使わないとこうなってました、という事実が示せないので、これについては本当に難しいところだと思いますけど、ここについては国や厚労省が思い切った評価基準なりを一定のデータの蓄積を元に示す以外はないな、と思っています。
ただ、本人の性格や生活歴、筋肉骨格のつくりだったり病気の有無や既往歴、周囲の環境に関わる職員や人との相性や人間関係、本人や家族や援助者の自立支援や介護に関する理解や認識、協力体制や使える資金の有無に量など、ざっと思いつくだけでもこんな感じで人間っていうのは多様性の塊なんで、他の人と同じような事をしても期待した効果が得られない事が多いので、本当に本当に難しいんですけど、そこが逆に人間同士の関わりの中でうまくハマった時が介護やケアマネジメントの醍醐味というか面白い所なんですよね。
介護保険の今後をめぐる議論では、より効率的な仕組みへ転換すれば給付費の膨張に一定の歯止めをかけられることもあり、要介護1と2の訪問介護・通所介護を総合事業へ移すべきとの意見がある。政府は2027年度の制度改正までに結論を出す方針。今回の新たな検討会は、そうした大きな動きにも影響を与えていくことになりそうだ。
あ・・・そっちの方向の話だったんだ・・・と思いました。
個人的な感想なので実際はどうなるかわかりませんけど、目先の社会保障費用を減らせたとしても、健康寿命が短くなって介護が必要な期間が延びれば社会保障費用は結果として増大する気がするんですけど、どうなんでしょうね。
必要になってから介護サービスを使っても手遅れですぐに重度化重症化して入院したり治療が必要になってしまうケースは散々見てきました。
介護費用を減らしても医療費が増大するんじゃないでしょうか。
コロナ5類の話と似たような感じで、5類になったとしてもウィルスの毒性自体は同じで、要介護1と2の通所と訪問を総合事業に変えたとしても、見た目の介護保険の費用は減ってるように見えるかもしれませんけど、必要とされるサービスの量と質は同じなんですよね。
どこがその費用を被るのかの違いなだけで、移行するのであればセットで別のシステムの構築も必要なんじゃないかなぁ・・・なんて思いました。
老健局の担当者は、総合事業の進捗・効果をどう評価するかも論点の1つになると説明。「総合事業だけで考えるのではなく、他分野のサービスも含めてどのように評価するのか。地域共生社会の実現という大きな目標へ向かうためにもそういう視点が重要」との認識を示した。
総合事業だからとかそういう事じゃなくて、本当に日本の介護保険制度をちゃんとしたものにするのであれば、ケアマネジメントの公正中立性の確保とケアマネの地位向上は必須課題だと思います。
制度的には本人が中心の制度でそれを公正中立の立場でマネジメントするのがケアマネなのに、ちゃんとそうなってるケースって少ない気がします。
ケアマネさんも、本人以外の関係者や書類に目が行ってしまいがちなんじゃないかなぁ、それはケアマネが悪いんじゃなくてちゃんとしたケアマネの地位や役割を作らないで制度を走らせ、山盛りの書類や会議をしないと認められないような制度設計をした国の責任だと思います。
公正中立の立場のケアマネが、いろんな角度から指摘され指導されている姿を見てきました。
介護保険制度の中核的な存在のケアマネの存在がこんな事では、そりゃ全体としていろいろ矛盾が出てもしかたないな・・・なんて思うに至る記事でした。
これからどうなっていくのかわかりませんが、やれることをやるまでなので少なくともこれ以上ハードルを上げるような事はしないで欲しい、というのが正直な所です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
