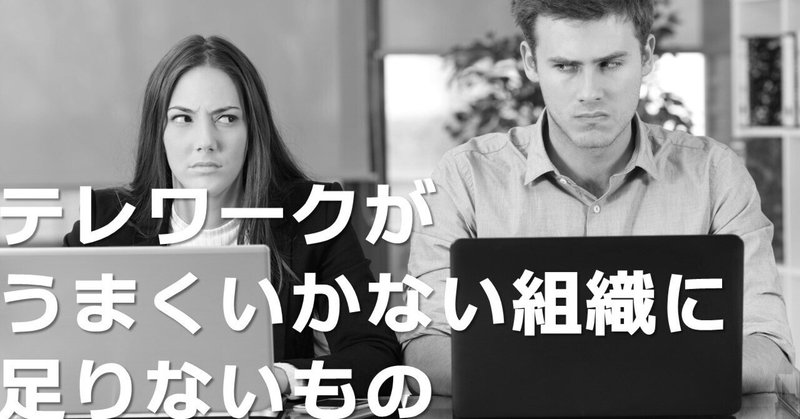
テレワークがうまくいかない組織に足りないものは?新しいチームの作り方3つのヒント
今回は、「テレワーク導入後の運用がうまくいかない」と感じるときに発生している3つのボトルネックについて紹介し、それを解消するためのヒントをお伝えします。
目次
1.テレワーク導入後の運用がうまくいかないときの3つのボトルネック
1-1.そもそも環境整備が不足している
1-2.ハイコンテクストな環境が邪魔をしている
1-3.一時対応としてのテレワーク導入にとどまっている
2.ボトルネックを解消するためのヒント
2-1.あいまいさを整え、メンバーの自律した行動を促す
2-2.業務やチーム体制を、目的から見直す
2-3.未来への投資志向でテレワークを味方につけよう
3.まとめ
テレワーク導入後の運用がうまくいかないときの3つのボトルネック
1.そもそも環境整備が不足している
テレワークを導入するためには、これまでの集約型のオフィス勤務では問題にならなかった環境の整備が必要になります。
東京商工会議所が2022年3月に発表した調査によると、調査対象の中小企業が抱えるテレワーク実施の課題は、「PCや通信環境の整備状況」が最多の62.6%となっています。次いで、「社内コミュニケーション」が62.1%、「情報セキュリティ」が60.2%でした。
(出典:https://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1029265)
いずれも前回の調査よりもポイントが上がっていて、導入した後の運用に課題を感じている企業が多いことが伺えます。
また環境整備とは、ICTツールのことだけを指しているわけではなく、就業規則や業務整理もテレワークの環境を整えるうえでは非常に大事なものになります。
環境整備が追いついていない場合、そのしわ寄せとして従業員の作業量が増えたり、従業員から会社の動きが見えづらくなったり、監視と感じる形で縛りが強くなったりと、不満・不安が増大していくことがあります。
2.ハイコンテクストな環境が邪魔をしている
顔が見えるサイズ感である中小企業の組織風土としてよく見られるのが、3つの「あ」です。
・阿吽の呼吸
・暗黙知での共有
・あいまいな目標管理、評価
これまではお互いに共通理解の多い(ハイコンテクスト)環境の中で、支えあいながらチームとして成果をだしてきたともいえます。
ただ、テレワークで物理的に個々の距離が離れ、空気が共有できなくなったときに、そのコミュニケーションでは難しくなるのは容易に想像ができます。
また、ハイコンテクストな環境の上で成り立っているマネジメントでは、あいまいな目標管理や評価になっていることもよくあることです。
3.一時対応としてのテレワーク導入にとどまっている
新型コロナウィルスのパンデミックを受け、十分な準備をすることなくテレワークの導入がスタートした企業も多いのではないでしょうか。
「いつかテレワークは終わり、出社ベースの業務に戻る」との認識で表面的なテレワークツールだけを整えて運用しているとするならば、それはあたかも北海道仕様の家を建てて沖縄で生活をするような、ちぐはぐさや機能を活かしきれていない状態が起こっているのではないでしょうか。
ボトルネックを解消するためのヒント
ここからは、ボトルネックを解消するための3つのヒントについてご紹介します。
1.あいまいさを整え、メンバーの自律した行動を促す
個々の働く場所が異なり、言語を中心としたコミュニケーション(ローコンテクスト)の必要性が増すテレワーク環境では、これまで持ちつ持たれつだった業務範囲のあいまいさは減らしていく一方で、個々の働き方についてはあいまいさをある程度許容していくことが必要となってきます。
あいまいさを減らしていくもの
・メンバー間のコミュニケーション
・個々の業務範囲
・個々の目標設定、評価
あいまいさをある程度許容していく必要のあるもの
・就業時間などの働き方
あいまいさを整えていくとどういう変化が起こるのでしょうか。ここから少し、ハイコンテクストな環境をもつチームが陥りがちなケースを紹介しましょう。
チームコミュニケーションの多くは、聞き手が相手の意図を察し、声のトーンや表情、会社に漂う空気を読み取りながら調整をすることで業務が遂行されます。話し手は多くを言語化せずに済みます。たとえば、「Y課長が言う『念のため確認しておいて』とは、Zさんに確認しておくことを指す」というように。
そんなチームでテレワークが導入されるとどうなるのか。ある日Y課長からAさん宛てに『念のため確認しておいて』とのメッセージが届いたとします。それを受けてZさんに確認の連絡を入れようと思ったときにふと思うのです。「Zさんに何を確認するんだっけ?」と。これまで対面のときは、Zさんに現在の状況を伝え、表情や相槌の様子をみて、懸念点は持っていなさそうか協力してくれそうかを肌感覚でつかんでいたのです。そして、言語・非言語含めて得た情報を持ち帰って課長に報告していたのでした。
では、テレワークの環境ではどうすればよいのでしょうか。答えは、言語化をすることです。
Y課長は、『Zさんに懸念点がないか確認して、協力を仰いでもらえる体制をつくってほしい』と伝える必要があります。依頼業務の目的、得たい情報までしっかりと言語化します。
するとAさんの行動はどう変わるでしょうか。目的を達成するためにはどのコミュニケーションツールがよいか考えます。それから、伝える情報を整理し、相手からはっきりと意思を示してもらうために働きかけます。
このケースでは主に2つのあいまいさが解消されています。1つめは、Aさんの業務目的(責任範囲)のあいまいさ。2つめは、Zさんに働きかけるときのAさんの言動です。
加えて、あいまいさが減ったことでAさんに起こっているもう1つの大きな変化は、業務に対して「どうしたら目的を達成できるか」を考える選択肢を持ち、自律的に動いていることです。
このように、あいまいさを整えていくことは、メンバーが主体性を発揮し、自律した行動をとるための土台づくりになります。テレワークでうまく成果をあげていくために必要なのは、まさにメンバーの自律的な業務遂行です。
2.業務やチーム体制を、目的から見直す
自律した個人の行動のうえに、チームとしての一体感が醸成されていくことが、テレワーク下での強いチーム作りの要となっていきます。
自律的な業務遂行ができる組織づくりを前提とすると、テレワーク下の環境整備や組織づくりをする際にも見え方が変わってきます。
これまでの業務のあり方を前提にするのではなく、新たなチームづくり・マネジメント視点をもって業務を見直していくことが大事になってきます。
たとえば、環境整備のツールや活用方法を検討する際に、マネジメント側から指示を出すという矢印で考えるのと、メンバーが主体的に業務を進め、マネジメント側はサポート、コーチングしていくと考えていくのでは、必要となる環境は異なります。
また、業務整理を行う理由が「隣同士で仕事をしなくなったから見える化する」だけではなく、「チームや個人の役割を明確にし、個人のパフォーマンスの発揮とチームの目標達成を見える化する」という目的で見直すことで、より有益な業務改善ができるのです。
3.未来への投資志向でテレワークを味方につけよう
環境変化への応急処置としてテレワークを導入した場合、以前の状態をありたい姿と設定し、現状とのギャップを埋めるための環境整備を進めてしまいがちです。
緊急度の高いタイミングではその方法も必要ですが、経営者の方々にとっては、「テレワークを導入することが未来の会社にとって何につながるのか」を意識したうえで運用することが非常に大切です。
テレワークの効用は社員の働き方改革の文脈だけではありません。テレワークが可能になると、顧客先や仕入先など様々な場所から即座に社内データを活用できたり、直接出向かなくてもあらゆる人がWeb会議ツールで繋がることができたりする環境を作ることができます。これらは顧客対応の質の向上や生産性の向上につながります。
また、今後人材の多様化、不足が加速していくことは間違いないですが、そのときに個別状況に合わせた働き方ができる企業なのか、仕事でパフォーマンスを発揮しやすい環境が整っている企業なのか、経営の姿勢が問われていくことにもなるでしょう。
まとめ
テレワークを導入したけれどうまくいかないと感じているなら、ぜひいったん、“ありたい姿”に立ち返ってみることをおすすめします。
弊社では、テレワークを戦略的に導入・運用していきたいと考えられている企業様のために、筋道を立て、伴走していくご支援をさせていただいております。
お気軽にお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
