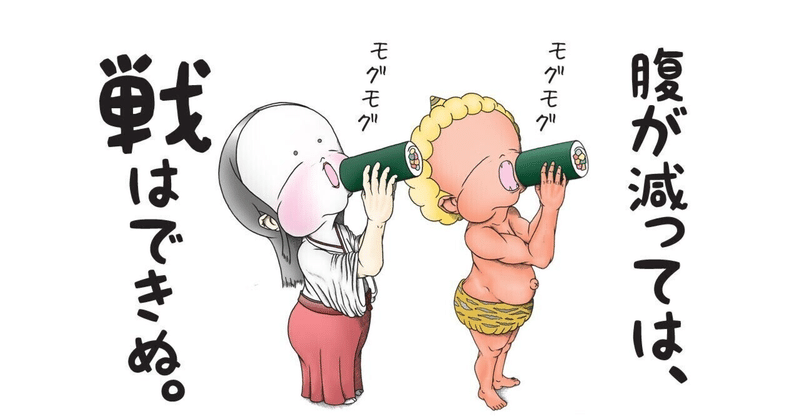
政治講座ⅴ696「国防費をめぐる増税論議」
中国に対抗できる自衛の軍事力を持つにはどれだけの費用が必要かの議論なしに増税論が先走っている。摩訶不思議な増税論である。吾輩の自論は国債発行を検討すべきである。
日本の領海には無尽蔵の資源が眠っている。日本の領海の海底に眠る資源の得べかりし利益(逸失利益)を考えると、守るべき領土・資源からどれだけ経済利益が上がるか、侵略・略奪された場合の経済的損失が防衛費の分岐点となるであろう。
そして、日本の領海の海底に眠る資源の得べかりし利益(逸失利益)を算定し、その領海の資源を担保に国債を発行する(仮称資源開発債)を開発費と防衛費に充当する案を提言したい。
その開発費と防衛費の人件費などは日本国のGNP・GDPとなり、国民の生活を潤わせる円滑資金となる。この様に相乗効果が期待できるので、国家予算の捻出が出来ないと悩んでいる財務官僚に是非提言したい。
皇紀2682年12月17日
さいたま市桜区
政治研究者 田村 司
お金は知っている 日本の国力衰退で聞こえる習近平氏の高笑い 国債発行を排除 デフレ脱却できないまま「緊縮財政」と「増税」防衛費増額分を捻出
11 時間前
岸田文雄首相が「防衛力強化」「防衛費増額」の財源として、安倍晋三元首相が提示した国債発行などを排除して、財務省主導の「増税」方針に固執していることへの批判が止まらない。閣内や与党内、財界だけでなく、ネット上でも「岸田増税」への怒りの声が噴出している。自民党の税制調査会は14日、非公式の幹部会合で、復興特別所得税と法人税、たばこ税の3税を税制措置(増税)の対象とする方針を確認したが、コロナ禍からの回復に必死な国民や企業を痛めつけるのか。産経新聞特別記者の田村秀男氏は「岸田増税」を強行すれば、日本の国力衰退を招き、中国の習近平国家主席(総書記)が高笑いすると喝破した。

岸田政権は月内に国家安全保障戦略など「安保3文書」を改定する。中国に関しては、「(国際秩序への)最大の戦略的な挑戦」と記し、これまでの「国際社会の懸念」にとどめていた対中認識を米国並みに近づける。
中国の習主席(総書記)による独裁体制が「異例の3期目」に入り、「台湾併合」など対外膨張策をエスカレートさせかねない状況のもと、当然だが、問題は中身だ。
古来、中国の支配層は言葉を政治手段とし、息を吐くように噓を並べ立てることがならいだ。彼らが真に気にするのは、あくまでも言葉を裏付ける実体、つまり軍事力のはずである。
グラフはドルベースの中国の国防費と国内総生産(GDP)を、日本のそれぞれと比べた倍率である。国防費は2006年に、GDPは10年に日本を抜き去り、いずれもぐんぐんと日本を引き離している。21年では国防費は5・4倍、GDPは3・6倍である。
日本は1976年11月に三木武夫政権によって防衛費を国民総生産(GNP=GDP+海外所得)比1%以内とする枠を決めた。86年12月に中曽根康弘政権が撤廃したものの、2020年度までは、ほぼ一貫してGDP比1%以内に抑え、21年度は補正予算後に同1%を若干上回った。
母数となる名目GDPは1990年代後半から始まった慢性デフレのために、現在までほとんど増えていない。従って防衛費も横ばいのままである。
対する中国の軍事費のGDP比は2003年以降2%以内で、21年も1・73%だが、GDPが高成長を続け、軍事費の膨張を支えてきた。
日本はGDP1%の墨守とGDP低迷のために、軍事力で中国に大きく水をあけられたことになる。「中国の脅威」なるものは、日本側の防衛に関する認識の甘さと、デフレ圧力、ゼロ経済成長を招く増税、緊縮財政という「政策の失敗」が招いたとも言える。
そして今、安保3文書の改定で、中国の脅威に対処しようとする。
防衛費を2027年度までに、現在の「GDP比2%以上に増額」というのが岸田政権の方針である。防衛費以外の財政支出を切り詰め、なおかつ足りない部分を「増税」に頼るという。基本的な考え方は、あくまでも「均衡財政路線堅持」で、従来の延長である。
繰り返すが、日本経済は25年以上の間、GDPが増えない。その背景はデフレにあり、「脱デフレ」は果たせないままだ。GDP全体の物価指数であるGDPデフレーターは21年度以降、今年7~9月期まで前年比マイナスに落ち込んでいる。
ところが、岸田政権はデフレが続くなか、「緊縮財政」と「増税」で、防衛費増額分を捻出するという。これでは、自ら「国力の衰退」を招いてきた四半世紀にも及ぶ財政政策を繰り返すことになる。
安倍晋三元首相は生前、防衛力増強の財源について、「防衛国債」の発行を提起していたが、岸田政権は均衡財政主義の財務省の画策通り、国債発行を否定した。習主席の高笑いが聞こえるようだ。
■田村秀男(たむら・ひでお) 産経新聞社特別記者。1946年、高知県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後の70年、日本経済新聞社入社。ワシントン特派員、米アジア財団(サンフランシスコ)上級研究員、日経香港支局長などを経て、2006年に産経新聞社に移籍する。著書・共著に『中国発の金融恐慌に備えよ!』(徳間書店)、『経済と安全保障』(扶桑社)、『日本経済は再生できるか「豊かな暮らし」を取り戻す最後の処方箋』(ワニブックスPLUS新書)など多数。
「岸田下ろし」が始まった!防衛費増税に「全面反発」高市・西村・秋葉らチーム安倍の目論見
FRIDAYデジタル - 昨日 18:00
防衛費の大幅増額。そのために必要となる財源は、法人税、たばこ税、復興所得税から賄うとして、最大1兆円2千億円の増税を打ち出した岸田文雄首相。統一地方選を年明け4月に控え、閣僚、自民党はこの「岸田政策」に猛反対の嵐となった。

岸田首相の強引な政策に「内閣の一員」である高市経済安保相が啖呵を切って「岸田下ろし」開幕のベルが鳴った 写真:つのだよしお/アフロ© FRIDAYデジタル
閣内からは、高市早苗経済安保相が、いち早く反対を表明。
「閣僚の任命権は総理にあるので、罷免をされるのであれば、それはそれで仕方がない。覚悟をもって申し上げています」
クビを切るならいつでもどうぞと啖呵(たんか)を切った。続いて西村康稔経産相は、
「法人税の増額は、企業が賃上げと投資をしようとする機運に水を差すことになる」
と、このタイミングで法人税増税という間の悪さ、流れが読めていない岸田首相のKYぶりに困惑と不信感をあらわにした。さらに秋葉賢也復興大臣は会見で、
「東日本大震災からの復興財源を、それ以外の目的へ流用することは断じてない」
と、顔色を変えて猛反発を示した。そもそも、防衛費の大幅増額について十分な議論がなされたとはけっして言えない。
「岸田下ろし」が不可避な理由
「岸田首相批判」の火の手はさらに広がる。13日、保守系有志議員20人が衆院議員会館で開いた会合では「内閣不信任に値する」という過激な声も飛びだした。
「増税方針を決めるまでのプロセスが乱暴すぎる。税調幹部だけで決めれば政局になる。そもそも、税の目的外使用は許されないルール違反だ」
政局、つまり内閣辞職か改造か、いずれにしても「このままでは済まない」というのが大勢の空気なのだ。党内では「岸田政権では自民党が潰れてしまう」という危機感が日々募っている。「この際、急先鋒の高市を担ぐ」と、「岸田下ろし」の具体的行動へ、容赦ない発言もあった。自民税調幹部がこう明かす。
「防衛費財源の増税案は11月下旬、岸田首相が麻生副総裁、菅元首相と相次いでサシの会談を行ったときに相談していた案件です。おそらく、萩生田政調会長にも事前に伝えられていたでしょう。いずれも、岸田首相に翻意を促しましたが、国防を“自分事”として国民に理解していただきたいと首相は主張、臨時国会終了後のタイミングで増税表明したのです。
しかし、防衛費を増額してその金で『何を買うのか』という中身を示さないまま、ただ『兵器を買う金をよこせ』では、みんな怒るのは当たり前。岸田首相にしては、やり方が、やや乱暴だった」(自民党幹部代議士)
岸田首相のトップダウンを受けて9日、緊急招集となった自民党政調全体会議は、50人以上の怒声、罵声が飛び交う大荒れとなった。
税制改正が選挙に直結する議員にとって、増税は痛い。それがなくても支持率が低落するばかりの岸田首相から飛び出した増税方針に議員らは危機感を募らせている。
今、関係者は、首相の乱心をなんとか力ずくでも阻止しようとしている。が、防衛費増額の本質を見なければならないと警鐘を鳴らすのは自民党リベラル派の重鎮だ。
「財源」など、どこにもないのに
「防衛費の積算根拠が示されないまま、不足の1兆円分の『増税』だけが争点になっています。しかし、残る3兆円の財源ですら確保されているのか怪しい。今回用意されるのは、外国為替特別資金特別会計やビルの売却などからかき集めた金で、恒久財源ではないのです」
岸田首相が当てにしている財源、『防衛力強化資金』は、外国為替資金特別会計、財政投融資特別会計、新型コロナウイルス対策費余剰金に加え、東京・大手町の政府保有分ビル「大手町プレイス」売却で「かき集めた」もの。2027年度以降の防衛費については、その財源はまったく確保されていないのだ。
「国債発行をしない方向であれば、財源は再増税に頼るしかない。鈴木俊一財務相は疲れ切っています。『なんとか工夫して、防衛費をひねり出すしかないな』とため息をついていました」(財務省キャリア)
財源に関する議論以前に、「防衛費の大幅増額」についてもっと議論を尽くす必要があることは言うまでもない。岸田首相は防衛費問題の年内決着を指示した。何があろうと通そうという態度である。経済を重視してきた宏池会の岸田首相が、中国、ロシア、北朝鮮の恐怖を煽り、有事を喧伝する政権運営は本意なのか。国民は、何が何でも戦争を回避する政治を求めているのではないだろうか。

今年2月、衆議院本会議。笑顔で語りかける高市に耳を傾ける岸田。首相の「聞く力」は、いつ失われたのか…© FRIDAYデジタル
取材・文:岩城周太郎
日本の防衛力強化「賛成」、日本68%・米国65%…日米共同世論調査
読売新聞 - 昨日 21:56
読売新聞社と米ギャラップ社は11月に日米共同世論調査を実施した。今後日本が防衛力を強化することについて、「賛成」は日本で68%、米国で65%といずれも「反対」を大きく上回った。米国民の間でも、アジアの安全保障における日本の役割の拡大を期待する声が多数を占めた。

(写真:読売新聞)© 読売新聞
自国にとって軍事的な脅威になると思う国・地域(複数回答)を挙げてもらう質問では、日米ともに「ロシア」が最多で、日本は82%(前回2020年調査57%)、米国は79%(同61%)だった。日本では、「北朝鮮」がロシアと並ぶ82%(同73%)で、次いで「中国」の81%(同77%)。米国は「中国」77%(同64%)、「北朝鮮」70%(同68%)の順だった。
中国が今後、台湾に軍事侵攻した場合、米軍が台湾を防衛すべきだと「思う」は日本で72%を占めた。一方、米国では「思う」48%、「思わない」45%と拮抗(きっこう)した。バイデン米大統領は米軍による台湾防衛に前向きだが、米国の世論は二分している。ロシアによるウクライナ侵略を巡って、米国は今後、ウクライナへの軍事的支援を強めるべきだと「思う」は、日本59%、米国55%と、ほぼ差がなかった。
現在の日米関係が「良い」との回答は日本で58%(前回51%)に上昇し、現在の調査方式となった2000年以降、15年と並んで過去最高だった。「悪い」は25%(同27%)。米国では「良い」51%(同50%)、「悪い」11%(同12%)でほぼ横ばいだった。
防衛財源に法人など3税、増税時期明記せず実質先送り-税制改正大綱
占部絵美 - 4 時間前
(ブルームバーグ): 自民・公明両党は16日、防衛力の抜本的強化に向けた増税措置を盛り込んだ2023年度の与党税制改正大綱を決定した。財源をねん出するために法人、所得、たばこの3税を組み合わせる方針を明記したが、増税実施は24年以降に実質先送りされた。

Fumio Kishida, Japan's prime minister, speaks during a budget committee session at the upper house of parliament in Tokyo, Japan, on Thursday, Dec. 1, 2022. The second supplementary budget for the year is set to fund measures to ease the impact of inflation on people and companies.© Bloomberg
ブルームバーグが入手した大綱最終案では、防衛財源として法人税額に4-4.5%の付加税を課す。所得税額に対しても1%の新たな付加税を課す一方で、復興特別所得税の税率を1%引き下げて相殺、たばこ税は1本3円相当の値上げを段階的に実施する。一方で、実施時期は「24年以降の適切な時期」との表現にとどめた。
岸田文雄首相は今月8日、財源確保の税制部分について税目、施行時期を含めて検討するよう要請したが、具体的な措置内容や課税時期の明示は見送られ、玉虫色の決着となった。
岸田首相は27年度に関連経費含む防衛費を現在の国内総生産(GDP)比2%に引き上げる方針を表明。財源については同年度までの5年間の総額を43兆円程度とし、27年度以降、毎年度約4兆円の追加財源の確保が必要と指摘。うち4分の1兆円強を増税で賄う考えを示した。
大綱に税制措置の詳細が来年の税制改正議論に持ち越された背景には与党内で慎重論が根強いことが背景にある。自民党金融調査会長の片山さつき参院議員は、新型コロナの感染拡大で影響を受けた景気の回復を見定めることが必要だとし、「景気条項的なものはあってしかるべきだ」と述べた。
慶応義塾大学の土居丈朗教授は、国債ではなく増税で財源を確保した点を評価する一方、「取りやすいところから取る」という法人税を軸とした結論を疑問視する。財政への影響について「追加増税も必要になるのではないか」とみている。
野村総合研究所の木内登英エグゼクティブ・エコノミストは、結論を1年延長したことで「議論は漂流しやすくなった」と指摘。来年は経済状況が悪化する恐れがあり、「24年度も増税は無理だという形でさらに後ずれし、結局増税されずに、なし崩し的に国債の発行で賄われていく可能性も相応にある」と分析した。
富裕層への課税強化
今回の税制改正では、岸田政権の掲げる「新しい資本主義」を実現するための目玉政策として、NISA(少額投資非課税制度)の抜本拡充が盛り込まれた。貯蓄から投資へのシフトを促す「資産所得倍増」を具体化するため、つみたてNISAの年間投資枠を現行の3倍の120万円、一般NISAは併用可能な「成長投資枠」に衣替えして240万円に倍増し、非課税となる生涯上限を1800万円に引き上げた。
一方、富裕層優遇との批判を避けるため、所得30億円を超える富裕層に対する課税強化策も盛り込んだ。所得が1億円を超えると実質の税負担が下がる「1億円の壁」解消は、岸田首相が就任前から提起していた政策課題。22年度改正では、株価下落や市場の批判を受けて見送られたが、「超富裕層」をターゲットにすることで決着した。
野村総研の木内氏は、「格差問題に多少目をつぶっても、個人の中間層の株式投資を促すために大盤振る舞いをした印象で、株式市場にとってはプラス」と指摘。NISA拡充は「新しい資本主義」の目指す企業と家計の好循環に向けた「第一歩であって、さらに推し進めるにはリテラシーの問題に加えて、成長戦略を合わせて進めていくということが必要」と語った。
NISAの大幅拡充を訴えてきた自民党の中西健治財務金融部会長は、資産所得倍増に向けた「器はできた」と評価。今後は「できた器にきちんと魂を入れていきたい」と述べ、金融教育の充実やお金が動く仕組みづくりを業界に働き掛けていく考えを示した。
主な税制改正項目NISAの年間投資枠360万円、生涯上限1800万円富裕層課税を2025年から強化、所得30億円以上を想定スタートアップへの再投資、20億円まで売却益課税を免除エコカー減税、現行制度を2023年末まで据え置き生前贈与の相続税対象期間、3年から7年に延長教育資⾦と結婚・⼦育て資⾦の⼀括贈与の非課税期間延長インフラファンド税制優遇措置を3年延長
More stories like this are available on bloomberg.com
©2022 Bloomberg L.P.
海保強化へ重点6分野、政府決定…尖閣警備・自衛隊連携など
読売新聞 - 6 時間前
政府は16日午前、海上保安庁の体制強化に関する関係閣僚会議を開き、「海上保安能力強化に関する方針」を決定した。沖縄県・尖閣諸島周辺の領海警備などの6分野を重点的に能力強化することを掲げ、海保予算を2027年度に今年度当初比で約1000億円増の3200億円程度とする方針を明記した。

(左から2人目)(16日午前、首相官邸で)=帖地洸平撮影© 読売新聞
岸田首相は会議で、「我が国の周辺海域を取り巻く情勢は緊迫度を増しており、体制を一層強化することが必要だ」と述べ、海保予算を大幅に増額する必要性を強調した。大型巡視船4隻を新たに整備し、遠隔操縦できる無人航空機を活用した監視体制を強化することも明らかにした。
強化方針では、安全保障で海保が果たす役割の重要性を指摘。尖閣周辺の領海警備を例に挙げ、「事態をエスカレーションさせることなく業務を遂行し、武力紛争への発展を抑止している」とした。
尖閣諸島周辺の領海警備については、巡視船などの整備で体制強化を図ることを盛り込んだ。近年、中国海警船の大型化や武装化が進んでおり、対処力を向上させる狙いがある。
「戦略的な国内外の関係機関との連携・支援能力」では、日本が攻撃を受ける武力攻撃事態に備え、防衛相が海保を統制下に置く手順を定めた「統制要領」を策定するとした。自衛隊との共同訓練も行う。法の支配に基づく「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、外国の海上保安機関との連携を一層推進することも打ち出した。
このほかの重点分野には、▽無人機などの新技術等を活用した隙のない海洋監視能力▽テロや災害などの大規模・重大事案の同時発生に対応できる強靱(きょうじん)な対処能力▽海洋権益を確保するための海洋調査能力▽サイバー対策などの強固な業務基盤能力――を挙げた。
政府が同様の文書を策定するのは16年以来。国家安全保障戦略など3文書の改定に合わせて見直した。
27年度防衛費は「8.9兆円程度」 岸田首相が明らかに
毎日新聞 - 7 時間前
岸田文雄首相は16日、首相官邸で開かれた政府与党政策懇談会で、2027年度の防衛費を「8兆9000億円程度」とする考えを明らかにした。

閣議に臨む岸田文雄首相(中央)=首相官邸で2022年12月16日午前9時27分、竹内幹撮影© 毎日新聞 提供
防衛力の抜本的な強化に向け、首相は27年度に防衛費と関連経費の合計を現在の国内総生産(GDP)比2%とする方針を示している。22年度のGDPを基準にすると2%は約11兆円となる見通し。政府は8兆9000億円程度の防衛費と、海上保安庁などの予算を合算し、約11兆円を確保する計算になる。【今野悠貴】
参考文献・参考資料
お金は知っている 日本の国力衰退で聞こえる習近平氏の高笑い 国債発行を排除 デフレ脱却できないまま「緊縮財政」と「増税」防衛費増額分を捻出 (msn.com)
「岸田下ろし」が始まった!防衛費増税に「全面反発」高市・西村・秋葉らチーム安倍の目論見 (msn.com)
日本の防衛力強化「賛成」、日本68%・米国65%…日米共同世論調査 (msn.com)
防衛財源に法人など3税、増税時期明記せず実質先送り-税制改正大綱 (msn.com)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

