
乗代雄介『それは誠』《砂に埋めた書架から》69冊目
名前は文芸誌でよく拝見していたが、作品は読んだことがなかった。けれども野間文芸新人賞や三島賞の受賞、芥川賞にも複数回ノミネートされるなど、評判の良さは耳に入ってくるのでとても気になる作家だった。四回目の芥川賞候補作となった『それは誠』で、私はようやく乗代雄介氏の作品を体験したが、それは、この小説をどうしても読んでみたいと思う理由があったからだった。
昨年の七月、第169回芥川賞が発表されたちょうどその日、著者がデビュー前から長年書き続けているという個人ブログ『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ』に、「Sに」という文章が投稿された。そこには今回の候補作だった『それは誠』を執筆するにあたっての、創作秘話とでも言うべき興味深い内容が公開されていた。
「現代の日本の小説で複数人の会話が描かれることは驚くほど少ない」という書き出しで始まるその文章は、ようするに、台詞を発する人数が多くなるほど長い会話場面は書くのが難しくなる、ということを、乗代氏は深く掘り下げて述べていたのだ。私はその部分を読んだとき、心の底から「同感!」と叫んでしまった。
いきなり自分の話で申し訳ないのだが、私は自作の短編小説をこのnoteに投稿させて頂いている。これまでに発表した四十編あまりを振り返れば、会話場面は圧倒的に「二人」の場合がほとんどだ。そこにもう一人が加わって「三人」になるケースもあるが、たった一人が増えただけでも、記述の難易度は上がる。私が三年前に書いた、カラオケルームで失恋の歌をみんなで歌いまくって傷心の仲間を救うという短編では、「四人」による会話に挑戦したが、これが私の実作における最高人数だった。非常に神経を使い、いくつか工夫を施しながら書いたことを覚えている。モブキャラは登場しないので、四人それぞれの性格や特徴が伝わるように書き分ける必要があるし、話し方も個人の特色を加えないと、混同して誰の台詞なのか読者に伝わりづらくなる。会話文を受けたうえでの地の文も、単調にならないように変化を盛り込まなければならないし、そういった書き手の苦労の跡が読者にバレないように、違和感のない滑らかな読み味に仕上げることも必要になる。つまり、会話に参加する人数が増えるほど、書くのが難しくなるのが、小説の会話場面なのだ。
そういったたいへんさを、私も素人なりに知っていたので、乗代氏の投稿「Sに」を読んだとき、深く共感してしまったのである。
乗代雄介氏は『それは誠』でその複数人の会話に挑んでいる。書くことの困難さを意識したうえで、会話場面に着手している。私はそれを知って、ぜひとも今回の芥川賞候補作を読みたいと思った。七月に本を買い、半年以上寝かせてから読んだ。私にとって初となる乗代作品である。そして実際に読んでみると、注目していた複数人による会話場面もさることながら、自分が期待した以上の面白さを備えた作品であることがわかった。結果から言うと、私はこの一作ですっかり乗代雄介のファンになったのである。
メインストーリーを簡単に紹介すれば、地方の高校に通う二年生の佐田誠が、修学旅行先の東京で、日野に住んでいる叔父さんに会うため、班で計画した自由行動のルートから外れる行動を起こす。もちろん学校には内緒で。複雑な家庭環境を持つ誠の単独行動に、同じ班の男子三人と女子三人が協力する流れになる。正規ルートを回る女子たちは、学校から持たされた男子の分のGPS端末を預かることで偽装に手を貸し、誠を入れた男子四人は、浦和から電車を乗り継いで、叔父さんが一人で暮らす日野のアパートに向かう。必ずしも叔父さんに会えるとは限らない中、誠たちは制限時間内に同じ班の女子たちが待つ新浦安駅まで戻らなければならない。果たして、誠の望みは叶うのか。学校にバレずに首尾良く女子班と合流し、先生たちの待つホテルへ帰還できるのか。そういったサスペンスを含みながら、同じ班の高校生七人の関係と心情の変遷を描いたのがこの小説なのである。
メインだけを紹介すると、単純なストーリーに思えるかも知れない。しかし、この作品にはさまざまな企みが仕掛けられており、読みどころはそれだけでは収まらない。そもそもこの小説自体が、修学旅行から帰ったその翌日に、誠が今回の思い出を文章に起こしてパソコンに打ち出している、という体裁なのだ。誠の記憶にあるたくさんの出来事や会話場面を盛り込んで、班分けが決まったときから東京での自由行動を終えた日までの経緯を、書くことで再現しているのである。それ自体がすでに驚異だが、特筆すべきは誠が書き連ねるその文体だ。J・D・サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』を模倣していることが、すぐにわかる文体を採用しているのだ。『ライ麦……』を読んでいる読者なら、『それは誠』の冒頭からわずか三行で、ホールデン・コールフィールドの口調であることに早々と気付く人もいるであろう。もちろん、これも作者の企みであり、深い思惑があってのことで、決して文体で話題づくりを狙った、というような、そんなチャチな理由ではない。私が注目したのは、先ほども述べたように、複数人の会話場面を作者がどう構築しているのかということだった。乗代氏は『ライ麦……』のホールデン少年が語るように、一人称の饒舌体で複数人の会話場面を、ひいては、この小説全体を書ききろうと試みたのである。
私は、この作品に一人称を採択したことは、最良の選択であったと考える。読み終えた今、改めてそう思い、感服している。佐田誠の主観が十分に入った視点だからこそ、彼を取り巻く人間の濃淡が、しっかりと心に刻まれる。三班のメンバー全員に、常に誠の主観が入るからこそ、彼ら彼女らの言動の重要度が増す。そして、みんなが誠をどう見ているか、仲間の反応がそのまま映し鏡となって教えてくれる。これらはすべて、佐田誠自身が採択した台詞であることが重要なのである。なぜなら、この小説は佐田誠がキーボードを叩いて打ち込んでいる文章だからだ。一人称小説ではあるが、ただの一人称でできているわけではないのである。
この小説が好きすぎて、語りたいことはたくさんあるが、これ以上文字数を増やすのは避けるのが賢明だろう。作者がどのような工夫を凝らして多人数がやりとりをする会話場面を書いたか、ひとつひとつ取り上げて説明するのも、これからこの作品を読んでみようと思っている人にはきっと興醒めになる。そのことに私は遅まきながら気付いたのだ。先日、何かのSNSで、『それは誠』を読んでみたが最初の方でやめてしまった、という投稿を見た。おそらくその人は、自由行動の行き先を七人が話し合う場面で匙を投げたのだろうと想像する。しかし、会話場面の構築に興味があって読み始めた私のような変態には、そこはたいへん面白いうえに読み逃せない場面だった。それに、『それは誠』の本当の面白さが始まるのはそのあとだ。井上奈緒、小川楓、畠中結衣の三人の女子が、そして、大日向、蔵並、松、佐田誠の四人の男子が、読者の心に自然な形で定着したあとからが、この小説の醍醐味を味わえる本当のスタートなのである。
今では、私はこの七人が好きでたまらない。この小説を読んでいる間、何度泣き笑いをし、笑い泣きをしたかわからない。美人の高村先生が語る宮澤賢治の言葉もこの小説の中で重要な役割を果たすが、私はこの三班のメンバーが松のことを常に気に掛け、温かく見守っていたことを忘れない。単純だなあと思われても構わない。私は松のお母さんの電話で泣いた。すごく心に残る言葉だった。
2024/02/26
書籍 『それは誠』乗代雄介 文藝春秋
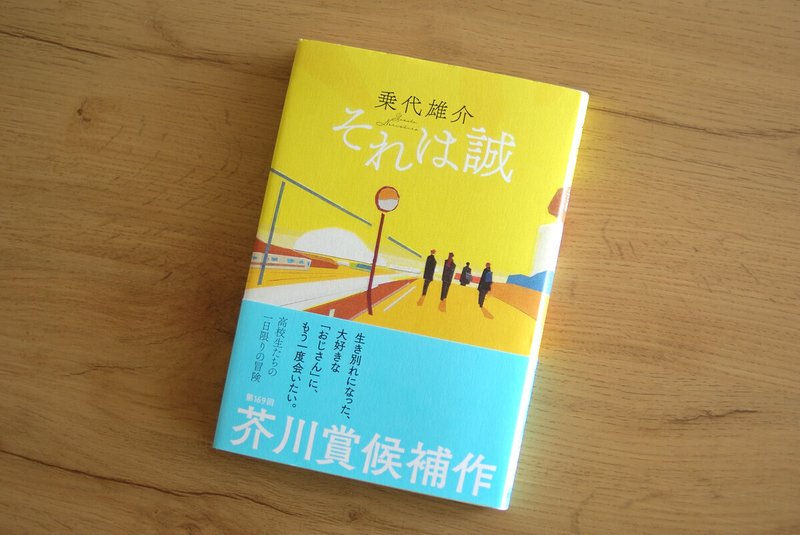
◇◇◇◇
■参考にさせて頂いた著者のブログ
「ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ」
Sに 2023-07-19
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
