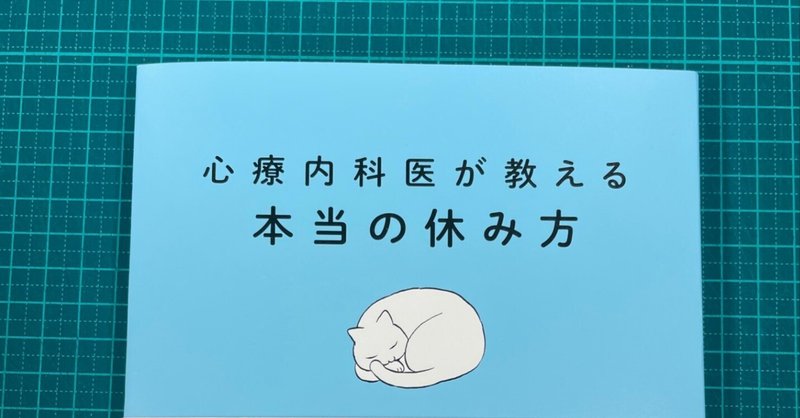
休むことが苦手な人へ 〜「動けない」を受け容れる〜
実に2年半ぶりのnoteであります。
なぜ2年半ぶりに筆を執っているのかというと、月末に「休むこと」をテーマにした書籍を出させていただくことになり、担当編集のKさんに「なんかいい感じで内容を紹介するnoteを書きましょう」と言われたからであります。
せっかくなので、本に込めた想いなどを振り返りながらこの文章を書いている次第であります。
こちら。
(「本当の〜」とかいうタイトルを背負うのはなんだか偉そうな感じがして荷が重いのだが、気がついたらこのタイトルになっていたのであります。)
これまでも休むこととか、休職のこととかについて書いていたのだけど、ここ数年で臨床の内容がとても大きく変化して、いろいろと新しい心理療法やその背景の神経理論などを学ぶ機会があって、前よりも踏み込んだことがお伝えできるかもなあと思っている次第であります。
なぜ休むことは難しいのか?
さてもさても、「休むこと」って、本当に難しいよね〜。
なんでそんなに難しいんでしょう?というのを、冒頭の方にこんな風に書いた。
なぜ「休みたくても休めない」「休みをとっても、心や身体が休まらな
い」「休んでいるつもりなのに、心身の疲れが取れない」といった状態が起こるのか。
その根本的な原因は、「休むこと」が、いかに難しさを伴う高等技術であるかが理解されていないことにあると私は思います。
人がうまく「休む」ためには、大きく3つのプロセスがあると考えています。
①休みが必要な状態だと自覚すること
②休むことができる環境を確保すること
③自分の状態にとって適切な休養活動を選択すること
「きちんと休む」「自分に合った本当の休みをとる」というのは、これらのプロセスをすべて成立させないといけない「総合芸術」のようなものだと考えています。
しかし、これらすべてのプロセスにおいて、非常に大きなハードルが存在します。
にも関わらず、私も含めて、ほとんどの人は「休む」ことについて深く学ぶ機会がありません。
よくわからないまま「テキトー」に休んでいるというのが現実かもしれません。
まずは「休むこと」について、改めてとらえ直していく必要があるでしょう。
休みが必要なほどダメージを受けていることに気づくのは難しい。
そして、「休みが必要だ」と周囲に訴えることも難しい。
休むという選択には勇気が必要である。
それを選ぶことで、何かを手放さないといけないかもしれない。
そういう選択をするのはとても難しい。
「つらすぎると、つらくなくなる」 〜「解離」という防衛反応〜
本の中でも、とくに知っておいてほしいなとおもうのは、大きなストレスがかかったときに作用する「神経的なブレーキ」の話だ。
防衛的な自律神経の働きで、身体や心が動かなくなる。
「つらすぎると、つらくなくなる」という機構が人間には備わっている。
心をすり減らす環境に対して、「感情が動かなくなる」ことで適応しようとするのだ。
次第に感情が動かなくなり、生活に現実感がなくなっていく。
あたかも脳に麻酔をかけるように、あらゆる痛みに鈍感になっていく。
これは、生物が古来より身につけている、「解離」という生存戦略である。
命がおびやかされるような危機的な環境をやり過ごしていくために、脳の機能の一部が低下させ、「私がいま、ここにいる」という自己感覚をぼやけさせる。
そうすると、心身が感じる痛みを麻痺させ、他人事のように感じることができる。
自分と世界の間にベールが張ったような感じになり、外からの刺激に影響を受けないでいられる。
こうなると、どれだけ過酷な環境であっても、そこまで「つらい」と思わずに日々をやりすごすことができる。
肉食獣に襲われた草食動物は、「死んだふり」をしてやりすごす。
多くの肉食獣は屍肉を食べないからだ。
外敵を撃退することも、逃げおおせることもできないとき、動物はフリーズし、生命活動を極限まで縮小させることで生き延びる可能性を高めようとする。
これは、動物が生き延びるために培かわれた非常にパワフルな生存戦略で、多かれ少なかれ、私たちはこの「解離」や「不動」といった防衛を駆使しながら日々を過ごしている。
とくに「うつ」と言われているような方のうちで、解離とまるっきり無関係の人はほとんどいないのではないか。
それだけではない。
たとえば、いじめやパワハラ、暴力を受けている時の「無抵抗」
学校にいくことに危険を感じている人が、朝になると動けなくなるといった防衛的な「不登校」
どう努力しても変化しない環境を生き延びるための「学習性無力感」
そして、大きな喪失を体験した直後の「現実味のなさ」
これらは、僕らが生き延びようとするために行われる神経レベルでの防衛プロセスであり、脊椎動物のDNAに蓄えられた叡智の結晶でもある。
生命の危機に直面している局面において、その場を動かずに、不感的・不応的でいたほうが都合が良い場面というのがあり、身体がそれを自動的に実行してくれているのだ。
ドラクエで言うところのアストロン(鋼鉄の塊になって、動けないかわりにすべての攻撃を受けつけなくなる防御呪文)のようなものだ。
この防衛的な「不動のプロセス」の恩恵を知り、もっと肯定的になる必要があるのではないか、というのが本書において僕が一番伝えたいことなのではないかと思っている。
不動は、生存戦略である
危機に対して「動けない」ことは、決して恥ではない。
むしろ、生命活動を守ろうとするために身体が導き出した選択である。
そのことをもっと理解して、「不動」の自分を肯定的にとらえられないだろうか。
多くの人は、休んでいる自分、思うように動けない自分、なすすべもなくフリーズする自分に対して、恥や罪悪感を感じるものである。
「本当の自分はこんなものではない」
「もっとやれるはずだ」
「動けない自分が許せない」
「こんなの自分ではない」
そんな風に感じて、どうしても否定的になってしまうことがある。
とくに、責任のある「降りられない」立場で、誰かのために活動的に動いている人ほど、そうした傾向があるように思う。
でも、「動けなくなってしまっている」ということは、おそらく今、危機的な状況にあって「動くべきではない」ということを身体が教えてくれているのかもしれない、ということだ。
頭でいくら「まだいける」「もっとやれるはずだ」「ここで動けなければだめになってしまう」と思い込んでいても、「動かないこと」を身体が選択していたり、本当に必要としているのだとしたら、それに身を任せて、ほんの少しの間でも、背負っているものや「思い込み」をいったん降ろして、「ぐったり」してみてもいいのではないか。
そうやって、必要なときに度々「ブレーキ」をかけてくれている身体の判断に、リスペクトを払ってみるのはどうか。
こうした話を、不登校の生徒が9割を占める通信制高校で話したときに、その日一番の反響があった。
奇しくも、本の発売日は8/31であり、一部の学生・生徒さんたちにとっては、最も精神的な苦痛が強い日のひとつかもしれない。
たとえば学校や会社に行く時間に、無気力、倦怠感、抑うつやぼんやり感を感じるとしたら、それは努力や気合いの問題ではなく、神経学的な「ブレーキ」による防衛のプロセスが強く関わっている可能性が高い、というのは声を大にして言いたいことだ。
不動であることには、合理性がある。
ただそれを知っただけで全てがどうにかなるわけではないかもしれない。
それでも、過剰な自責や自己嫌悪に苛まれることが、ほんの少しでも減ってほしいと思う。
そして、ぼく個人としても、この「防衛的な不動」の大きな恩恵をあずかっていた。
すこし前に、とても大きな喪失体験があった。
容易に立て直すことが難しいだろうことは明らかだった。
それでも、まあ仕事は詰まってたし、ある程度こなし続けることはできていたように思う。
最近になって、少しずつ整理がつき、浮上しているように思うが、つい先日、「あのとき、なんか意見を言える雰囲気ではなかったですよ〜」とスタッフに言われた。
そうだったのかもしれないな、とおもう。
やっぱり余裕がなかったんですね、と。そうですよね〜。
余裕がないときに、「余裕がない」と気づくことは難しいし、コミュニケーションが崩れだすのは、たいがいそういう時だよな。
「人にやさしくできない」といって嘆く人がいるが、そのうち95%は単にキャパシティが足りないことが原因なのではないかとおもう。
今回の体験をもってはじめて、ぼく自身が「ブレーキ」に入っていることをを、はじめて肯定的に受けいれることができたように思う。
普段はわりと活動的な方だから、思うように動けていない、ぐったりの自分をなかなか受け容れられていなかった。
それでも、ぐったりとして、現実味がなく、あまり心が動かない状態になっていたことで、大いに助かっていたのだということが今になって分かる。
もっと身体の反応に素直に、何もしない時間をつくって、ぼーっとして、積極的に引きこもってもよかったのかもしれない。
「身体に起きていることは、いったん正しいのかもしれない」という態度で、もうちょっと自分の反応に、耳を傾けていきたいものだなあと思っている。
というわけで、本の最後の章をちょっとリライトしたものを載せてみます。
なにかちょっとでも拾える部分や良き問いを受け取ってもらえたら幸いです。
与えられた役割を脱ぎ捨てて「ヒト」になる
これまで繰り返し、健全なものにはゆらぎがある、とお伝えしてきました。
休むことの真骨頂は、身体にとってあるべき「リズム」を取り戻すことです。
私たちは、さまざまな環境に応じて、いろいろな「モード」を切り替えながら生きています。
暑いときには汗をかいて体温を逃し、寒いときには血管を収縮させて熱を保つ。
リズムがあることが健全であり、ヒトらしい生き方なのです。
私たちは、社会的な役割を果たし、他者にとっての価値を生み出している自分(ニンゲン)と、その役割から降り、ただ生物として存在している自分(ヒト)でもある。
そのどちらもが「自分自身」であり、そこを行ったり来たりできることこそが、「人間存在」として、より健全な状態といえるのではないかと思うのです。
そして、「過剰適応」とは、他者や社会が期待する役割から降りることができずに、生物(ヒト)としての自分を犠牲にして、他者のために価値のある自分でい続けようとしてしまうことでもあるのではないでしょうか。
だから、本当に大切なことは、自らの社会的役割を一次的にでも「オフ」にできることなのではないでしょうか。
他者のニーズを引き受けすぎて、気を遣いすぎて、「コミュニケーション・オーバー」になったときには、ちゃんと「いっさいのコミュニケーション交流を中断して引きこもりたい」という身体のニーズが、神経系の反応としてあらわれてくれます。
そのニーズに応え、「不動のモードの自分」を引き受けて、積極的に、しっかりと引きこもることの大切さをここで強調したいのです。
精神科医でありミュージシャンでもある北山修(きたやまおさむ)先生は、人生を舞台とたとえたとき、安心してリラックスできる『心の楽屋』の必要性を語ります。
「実際の演劇には、観客に見せる舞台だけでなく、役から降りて素顔に戻ることのできる楽屋があります。そして、人生にも、この楽屋に相当する部分がぜひとも必要なのです」
「観客から見られている舞台から降りて、一人でホッと一息つける場所。人の眼を気にせずに素顔になれる場所。そうした『心の楽屋』が、現実の世の中においても必要なのです」
「この舞台は自分の意思で降りて、楽屋に撤退していいんだということを知っていれば、一時的に楽屋に戻り、態勢を整えて、また舞台に上がり直すこともできるでしょう」
さて、どこでそんな「楽屋」が得られるのか。
それは、友だちが担ってくれるのかもしれないし、カウンセラーなどのメンタルヘルスの専門家などが担ってくれるのかもしれません。
そもそも「人間なんてみんな等しくダメであり、みんな等しく尊い」ということを真に理解している人は、いたずらに他者をジャッジすることをしません。
そういう人に頼ったりもしつつ、ほんの少しの間でもいいから、役割から「降りる」ことができれば、「人間存在」としての健全なリズムを取り戻せる可能性が高まるのではないかと思います。
世間や社会というのは、思っているよりも絶対的な存在ではありません。
当たり前だと思っている社会的役割をオフにできるようにできることは、あなたの生存能力を大きく高めるでしょう。
「そんなものに応え続けなくてもいい」ということを、あなたの身体は教えてくれているのかもしれません。
「演じるわたし」と「降りているわたし」。
「社会的存在としてのニンゲン」と「動物としてのヒト」。
これらを行きつ戻りつしながら「リズムをもってゆらいでいること」が、人間らしさを取り戻すことであり、「休む」ことのもっとも本質的な効用なのではないかとおもいます。
いつも読んでくれてありがとうございます。 文章を読んでもらって、サポートをいただけることは本当に嬉しいです。
