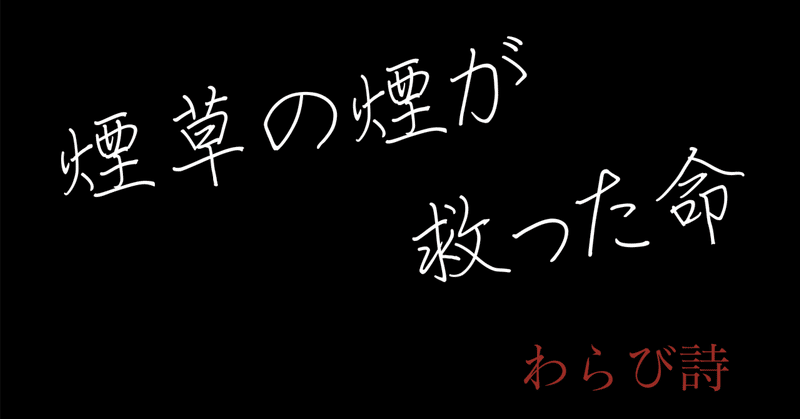
【短編小説】煙草の煙が救った命
深夜にうなされて目が覚める。
首筋にまとわりつく汗をぬぐっても、気持ち悪さは消えなかった。
恐ろしい夢だった気がするが、目覚めてみると内容を思い出せなかった。ただ、いつも煙草の匂いがする。
それは毎年、俺の誕生日に起こった。
枕元のスマホを見ると、時刻は深夜零時を少し過ぎたところで(あぁ……誕生日か)と納得した。
毎年のことなので、うなされる日イコール誕生日、と方程式が出来ている。嫌な方程式だが、おそらく死ぬまで変わることは無いだろうと予感していた。
夢の内容を覚えていなくとも、原因は明白だ。きっと見ていた夢もあの日に関連したものに違いない。
十年前、俺の三十五歳の誕生日の日、ある事故が起きた。
仕事帰り、駅のホームで誕生日を迎えた。しかし激務に追われていた時期だったので誕生日の事なんて頭の片隅にも無かった。
今日は早く寝付けると良いな、などと思いながらホームのベンチに身を沈めていた。
あまりに疲れすぎて、頭が働いていなかったのだ。視界の端にスーツを着た中年男性がいたことも、その人が禁煙のホームで煙草を吸っていたことも、ホームギリギリに立っていたことも――なんなら、飛び込みそうな気配もうっすら感じていたのに、俺は体を動かさなかった。
案の定、その人は快速電車に向かって飛び降りた。急ブレーキの音が耳に刺さり、ようやく意識を取り戻した気がする。
轢かれたのだろうと容易に想像できた。
あの日、どうやって帰ったのかは覚えていない。ただ何となく、このままこの会社にいたらあの人と同じ道を辿ることになる、それだけは分かった。すぐに会社を辞められたのは、あの人の死に突き動かされたからだ。
その後、転職活動は上手く行かず、派遣社員やアルバイトなどを転々として、どうにか食い繋いでいる。
あの人が煙草をくわえ線路に飛び降りた翌年から、俺は毎年自分の誕生日にうなされるようになった。柄にもなくお祓いに行ったり、お守りを買ったりしてみたが効果は無い。その内うなされるだけならどうでも良いか、と思うようにもなった。だって二度寝すれば忘れてしまうのだから。
そんな誕生日を十年続けた。きっとこれからも誕生日にはうなされ続けるのだろう。しかし今年、翌日の深夜零時過ぎに、俺は汗だくの状態で目を覚ました。
湿った寝間着。嫌な暑さがまとわりついて、心臓がドクドクと脈打っている。体を包むのは煙草の匂いだ。
「え……誕生日は昨日だろ?」
混乱しているが、首筋の汗も動悸もヤニ臭い匂いも、現実だった。誕生日は昨日終わったはずなのに、また今日もうなされた。
胸騒ぎがして二度寝する気になれなかった俺は、空気を変えたくて窓を開けた。ベランダから吹き込んでくる少し肌寒い春の風がカーテンを揺らし、ぬるく湿った体を冷やした。
煙草の匂いが外へ出て行く。それを感じて安堵し始めた時、あの音が聞こえた。
耳をつんざく甲高いブレーキ音。
俺は慌ててベランダに出た。しかし車どころか自転車一台走っていない道路を木造アパートの二階から見下ろしただけだった。
「……」
おかしい。これは明らかに今までのパターンから外れている。
だとしても、何で今更? あの人が幽霊になって憑りついてるとして、十年間何もしなかったのに。俺の誕生日――と言うより、あの人の命日にうなされるだけ。覚えていない怖い夢を見させられるだけだったのに。
俺は眠れぬまま朝を迎え、仕事に向かった。先日新しく紹介された派遣先は雑用ばかりやらされ、やりがいなんて全く無い上、空気も殺伐としている。それでもあの恐怖心を忘れるには十分だった。
しかしその夜、俺は絶叫しながら飛び起きた。
「はぁ……はぁ……」
恐怖に押しつぶされた体が小刻みに震えている。隣人が壁を叩いた。その音にまでビクついてしまう。
なにか大きな物に体を引き裂かれて絶命する夢を見た。大きな……四角い……電車みたいなものに。
(覚えてる……?)
今までは覚えていなかった夢。しかし、一部ではあるものの今は記憶に残っている。
どういう訳か、不味い事になった。このまま行けば明日はもっと克明な夢を見せられるんじゃないか? それどころか、追体験させられるに違いない。あの自殺の瞬間を。
俺は仕事を休んで、以前お祓いをしてもらった神社に向かった。前と同じ手順で申し込み、社殿に通され、祝詞のようなものを一緒に唱えた。
「悪いものはいませんよ。あまり気に病まないように」
などと言われたが、気休めにさえならなかった。
その夜、眠るのが怖くなった俺はいつもの時間が過ぎたことを確認してから布団に入った。
「そうだ。毎日こうすれば良いんだ」
あの時間に寝ていなければ夢は見ない。そう考えたが、眠りに落ちた直後、俺はまたしても絶叫しながら飛び起きた。
うるせぇぞ! と隣人の怒号が聞こえたが、それどころじゃ無い。
迫る電車のライト、冷たい線路と敷き詰められた石、くわえた煙草の感触が、気持ち悪いほどリアルに感じた。
時刻は深夜一時前。たった数十分しか寝ていない。
「嘘だろ、……何でだよ」
時間をずらしても、お祓いをしても無駄だと言う事か?
一刻も早く何か対策をしないと……とは思うがこれ以上何をすれば良いのだろう。
「……あ、そうか」
あの駅にお供えに行けば良いのだ。そうしたらこれも止むに違いない。と言うか、そうであって欲しい。
翌日の仕事終わり、久しぶりにあの駅に向かった。大きな変化は無いようだ。あの頃のまま少し陰鬱な雰囲気のあるホーム。
昔ながらの蛍光灯が辺りを照らしている。その寂し気な灯りの下、ちょうどあの人が立っていた辺りに、未開封の煙草を置いた。手を合わせ「もうやめてください」と呟いた。
――キキィィィィィ!
俺は咄嗟に線路に目を向けた。が、電車なんか来ていない。周りにいる人達も何食わぬ顔で立っている。
俺だけに聞こえた、あの時の音。あの人の命が消えた音。
俺は恐怖の余りホームを駆け下り、タクシーに飛び乗った。
「つ、次の駅まで!」
「次の駅ぃ? 電車に乗った方が早いですよ」「良いから! 早く出してください!」
タクシー運転手はぶつぶつ文句を言いながらも、車を走らせた。
「何かあったんですか?」
「……」
「幽霊にでも会ったみたいな顔してますよ」
「……会っては無いです」
「会っては無い? じゃあ、聞いたんですか? 声とか」
「……」
「音とか?」
「……何か知ってるんですか?」
訝る俺に運転手は半笑いで答えた。
「まぁ、あの駅はこの辺では有名な自殺の名所ですからね」
「……自殺の名所」
「足を引っ張られたとか、叫び声が聞こえたとか色々聞きますよ」
「……。あの、俺……十年前にあの駅で飛び降り自殺を見たんです」
「それは災難でしたね」
「それから毎年同じ日に、いつもうなされてたんです」
「あらまぁ」
「でもここの所毎日……電車に轢かれる夢を見て……、今日お供えに来たんですけど、幻聴が……あの人が轢かれた時の音が聞こえて……」
「お祓いに行ったら――」
「行ったんです! でも、無駄でした」
「……」
「もう、どうしたら良いんだ……」
頭を抱え項垂れる俺に、運転手はあることを提案してきた。
「お兄さん、五駅先くらいまで乗って行きませんか? そしたら良い拝み屋、紹介しますよ」
「拝み屋?」
「といってもうちの家内なんですがね。口が悪くて碌でもない奴なんですけど、霊感だけは本物なんですよ」
「……」
「どうです? まぁ、何か請求されるかもしれませんけど、高級食材でも渡しとけば大丈夫だと思いますよ」
「……」
「おっと、もう着いちゃいました」
運転手は俺が言った通り、隣の駅で車を止めた。あの駅同様寂れた気配を感じ、とても下りる気にはなれなかった。
「……乗ります」
「まいどありぃ」
罠だったとしても、これ以上自力でどうにかするのは無理だ。貧乏人には痛い出費だが、背に腹は代えられない。
悪夢はその後も毎日続いた。どんどん鮮明になっていく夢のせいでノイローゼになる。一度隣人が怒鳴り込んで来たが、俺のあまりの蒼白さにたじろぎ、そそくさと帰って行った。
夢は階段を上がるところから始まり、ホームギリギリに立ち、煙草に火を点け、このあとどうなるか分かっているのに、飛び降りるのをやめられない所まで来ていた。もう、煙草の匂いは四六時中感じるようになっている。
あの人の家とか職場まで知りたくない。知ったらたらきっと、俺は俺でいられなくなる。俺はあの人になって、本物の線路に飛び込んでしまうだろう。
次の日曜日、藁にも縋る思いで運転手の家に向かった。奥さんは、運転手が言った通りの人だった。
「また、こんな不幸の塊みたいなやつ連れて来て。あたしはタダではやらないよ!」
貫禄のある大きな体。ひっつめ髪のせいか、目がつり上がっている。
「あの、これを」
有名な高級フルーツ店のロゴが入った紙袋を差し出すと、彼女はあっという間に奪い取った。中を確認し、
「まぁいいわ、合格で」
と紙袋と共に家の奥へと消えた。
彼女の隣に立っていた運転手は苦笑いを見せた。
「ま、本物だから」
と家の奥に向かい、俺もあとに続いた。
八畳ほどの居間は、俺が言うのも何だが結構散らかっていた。洗濯物や新聞などが散乱し、良くも悪くも普通と言うか、特別な力とか神聖な感じは全く無い。
「で?」
ちゃぶ台に高級イチゴを置いてむしゃむしゃ食べている彼女は、赤い汁が流れた手をそこら辺にあった小汚い布巾で拭いた。
「電車に飛び降りる夢を見るって?」
「あ、そうなんです。その瞬間を実際に見てしまって……」
俺は何とかスペースを見つけて正座した。彼女はテレビを付け、ぐるぐるチャンネルを回している。
「冴えないサラリーマンのジジイ?」
「ジジイ……。その、憑いてるんですか?」
「憑いてると言えば憑いてる。でも別に祓う必要は無いわね」
「え」
「あんた今の仕事やめた方が良いわよ。そのジジイと同じ結末を迎えたくないならね」
「……」
「心配してるだけよ。あんた、そのジジイと同じオーラだもの。相性が良いのよ。だから憑いてるの」
「で、でも、俺派遣とか契約社員とか……職を転々としてて」
「あぁ、そんな感じするわ。ジメジメしてるものね、あんた」
「……。その、年齢的にも、新しい仕事を探すのは大変なんです」
「車の免許無いの?」
「免許? 一応、ありますけど……」
「じゃぁあんたの所で面倒見てあげれば良いじゃない」
と運転手に水を向けた。
「え? まぁ、人手不足ではあるけど、二種じゃないだろ?」
「あ、はい。普通です」
「そんなの会社負担で取らせれば良いでしょう! 人が足りない足りないってずっと文句言ってたじゃない」
「そうだけどさ……」
「あんたは新しい職が見つかる上に、うなされる事も無くなる。会社は人材確保できて一石二鳥でしょ! これが一番良いのよ! あたしの言う事が間違ってたことある⁉」
「……無いです」
(無いんだ……)
話は終わった、とばかりに彼女はまた別のものをばくばく食べ始めた。
圧倒されたまま家を後にした俺は、翌週タクシー会社の面接を受けた。あの運転手の紹介ということもあり、すんなりと合格を貰った。二種免許も、会社の人に教えて貰いながら何とか取れた。俺の経歴からすると、本当にありがたいことだ。
そして職場が変わった瞬間、びっくりするくらい安眠できるようになった。口は悪いけど彼女の力は本物らしい。
俺は改めて彼女へお礼に行った。勿論季節の果物は忘れずに。
玄関先で、彼女は例のごとく紙袋の中身をきちんと確認してから言った。
「うなされなくなったでしょ?」
「はい。すごいですね。俺がいた会社、今パワハラ騒動で話題になってる会社なんですよ」
「あら、あそこだったの? やっぱり碌でもない会社にいたのね」
「ははは……」
「あ、そうそう。まだあんたの後ろにいるから年一回うなされるのは変わらないと思うわよ」
「え!」
「良いじゃない。年に一回くらいあの人の事を思い出してあげたって。あんたとの思い出がそれしかないんだから」
「はい、そうですよね」
「素直で宜しい」
「……どうも」
「あと、今度会う時は焼き肉が食べたい気がするのよ」
「……え?」
「え? 誰のおかげで手に職がついたと思ってるの?」
「そ……そうですよね、ハハッ……」
「あの人と同じ、一年に一回で良いのよ」
「……はい、分かりました」
俺は否応なく頷くしかない。命の恩人は、つり上がった目で豪快に笑った。
「一年に一回か……」
俺はタクシーの中で呟いた。
あの人の家族は年に一回、あの人を思い出すんだろうか。知る術は無いんだけど、俺はもう少し思い出してあげたいな、と思う。だって何もできなかった俺を、あの人は救ってくれたんだから。
慣れた手つきで、未開封の煙草を助手席に置いてから、アクセルを踏んだ。
「お客さんが来るまで、ドライブしましょうか」
ふわりと煙草の匂いを感じ、俺は少しだけ目を細めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
