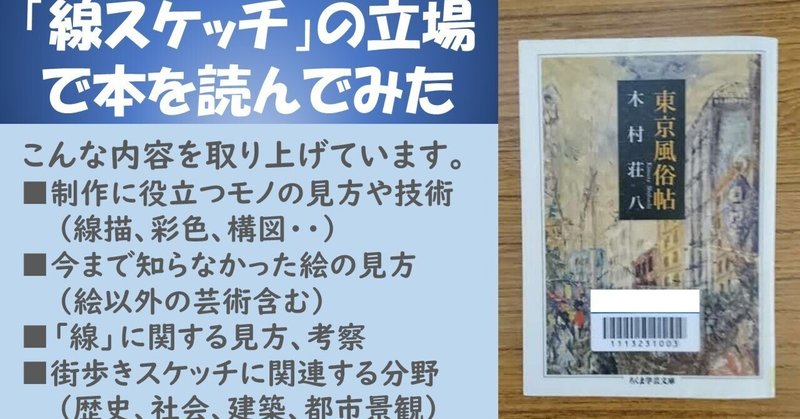
<東京風俗帖> 木村荘八 ちくま学芸文庫(2003) その2.
はじめに
本記事は、「<東京風俗帖> 木村荘八 ちくま学芸文庫(2003) その1.」の続きです。時間の余裕があれば一度読まれてから本記事をお読みいただければと思います。
時間の余裕のない方に「その1」の要点を以下に記します。
私が昭和30年代に訪れた東京の印象は「なぜ、東京の家並みの屋根は、うすっぺらなスレートやトタンばかりなのか?」でした。
これに対する10年前の私の解釈(仮説)は、以下の通りです。
・江戸期の瓦屋根は、関東大震災まで続いていたが、大震災により壊滅す
る。
・震災後、大正から昭和初期にかけて、コンクリート建築が増加、昭和初期
の東京の街並みが作られるが、太平洋戦争の空襲により壊滅する。
・戦後の復興の過程で、東京では即効性の、トタン屋根、スレート製の瓦が
応急的に用いられる。
・昭和30年代になり、高度経済成長の波に乗り、大量生産、安くて軽く、規
格が維持できる新建材による瓦が開発され、普及していく。
・東京オリンピック開催のため、この傾向はさらに強くなり、新型瓦が主流
になり、現在まで続く。東京では、もはや昔ながらの瓦が用いられること
はなかった。
木村荘八が見る明治、大正(震災前、震災後)、昭和(戦前、戦後)の街の変遷
本書は、明治の26年に生まれ、戦前の大正から戦後の昭和にかけて生き、高度成長期の昭和33年に亡くなった著者が、自身の挿絵を入れながら、著者が生まれる前の江戸、明治初期の東京の変化も加え、幼少期の明治、大人になってからの大正、昭和初期、戦後の高度成長期の東京の変化を直接体験、目撃して、生家「いろ牛肉店」があった両国広小路界隈、友人の岸田劉生が生まれた銀座煉瓦街、隅田川両岸から佃島、芝浦から築地までの都市の変貌を独特の視点で書いています。
本記事は、著書全体を紹介するのではなく、冒頭で述べた商家の瓦屋根に関する私の仮説に関連する部分を紹介するのですが、その前に画家である著者が本書で言いたかったことを画家らしい表現で記述した箇所がありましたので紹介します。
銀座煉瓦街と築地築地居留地は絵に例えて云って見れば、いずれも画室の、近世日本の野心的な習作品だったと考えるが、銀座は成功し、予想外の大作となって完成したに対して。居留地は製作半ばに仕事の見込みが立たず、中止した作品と思われる。いずれも外来を迎えるについて採った日本の応急「製作態度」であって、遂に完成作にはならなかったけれども、築地は、一時外来の受け入れ態勢として開国日本に無ければならなかった足がかりとなり、それだけの役割もすませ、もし築地近く(大川口)の水運が良く、品川の港湾が深かったならば、今ごろは――その後矢張り八十年の星霜――「東京港」の終着点・出口・入口として、世界的な築地になっていたことは明らかだった。
著者は昭和30年時点から遡って、築地や銀座が、明治維新直後の政治家の街の欧米化を目指す理想と現実(権力争い)や、大火、地理的条件、気候風土の違いなど各種要因に影響を受け、街(建物)が消失、変化していく様を振り返っています。
引用文の末尾で築地についての「たられば」を書いていますが、別の個所で銀座についても、振り返りと未来予想を書いています。築地がコロナ以前のインバウンドであふれかえる、世界に名のとどろく観光地として、また銀座の風貌、特に百貨店の盛衰を見たならば、著者は何と思うでしょうか。
江戸・明治におけるの商家の建築設計の変遷
さて、以下冒頭の私の仮説に関する著者の記述に焦点をあてることにします。
「定稿 領国界隈」の「両国・浅草橋真図」の中に次のような文章があります。
浅草橋から柳橋にかけての川岸は土蔵が並んで、山々型に、その屋根々々の相並んだ景色は、見る目に快いものだったが、土蔵には・・(中略)
旧江戸の町屋作りに――火災予防に対して――「土蔵」の奨励されたことは、それが幕末の政令でもあったが、この建築に対する十箇年月賦の恩借制度なども考えられ、通例云う「河岸蔵」という江戸府内の家並みは、此の地(江戸)独特の一つの建築景観であったとされる。(後略)
土蔵造りの商家に関する記述ではありませんが、浮世絵でよくみられる河岸に連なった土蔵群の話です。防火のために蔵造りの家が奨励されたのは現在ではよく知られていると思います。
上の引用文の後に、広重の「河岸蔵」の浮世絵について言及していますので、著者が想定していると思う広重の絵を参考までに下に示します。

次に土蔵そのものではなく、蔵造りの民家についての記述を紹介します。
以下に紹介する内容は、私がその1で挙げた疑問(関西の瓦屋根と江戸の瓦屋根の違い)に対する回答になっていると思うからです。
遡って考えると江戸の町も、万事の勢いが関西から東漸して「新興都市」としておこりかけたはじめ(慶長寛永の頃)には、建築物の有様など、従来の西に仿(まな)んで――云う迄もなく仿ぶべきものと云っては、西のやり方以外に無い――公私とも輪奐の大を競ったもののようだが、これは例えば屏風の無い畳の上へただ立てた人形のように、すぐ風に吹き倒されて了ったらしい。「関東平野」の性格に合わなかったものらしい。殊に「火」に敗北したようである。
「銀座煉瓦 七」の書き出しはこのように始まります。 要は、最初関西風の建て方が、関東平野のからっ風に合わなかった。特に「火災」にやられたというのです。それで、「経験」と「年功」によって、江戸独特の「姿」が出来上がった。 それは以下のように形容されています。
(前略)その外装は黒々と「火」を防ぐ為めに厚く土の塗りごめにされて、屋根は雨足の「滝」や「矢」に備えてとんがり帽子のように勾配を高く急に作り、家全体の棟、おおむね低く、云ってみれば、火事装束厳重に身ごしらえした男が、地にかがみ、かじりついて、待機したような、奇体な格好である。「江戸」の町屋以外には何処にも無い形ちで、それが此の地独創の、大屋根の鬼瓦には金(かね)の棒の熊手のような角をはやし、多くその片わきに、水瓶であるとか、土蔵(くら)を目塗りの用意に、ドロ桶が高々と載せてあった。いつでも来たれという、夜・昼無い常時戦闘の構えだった。
西の優雅に比べ、「奇妙な格好」と散々な言いようですが、実はここで記述しているのは、徳川家光が火災を防ぐために茅葺を禁ずる政令を出した頃の江戸の町の様子です。
まるで、その場で見てきたような書き方は画家ならではの目によるのでしょう。
茅葺の家がなくなった後、安政2年の大地震が起こり、頑丈な土蔵や土蔵見世に人々が籠ったところ、人、物共に打砕かれあるいは家財道具を厚く覆ったところから火災が起き、そのため安政2年の地震以降、土蔵建築作りに反動が来て、無傷の土蔵も壊して、以前の板屋作りを作る状況になった。その状況を幕府も見逃したが、当然のように毎晩のように火災が起きて江戸の人々は考え直したとその後の歴史の記述が続きます。
そこで又々江戸の人々は、一度見捨てた土蔵、土蔵見世、塗屋、瓦屋の・・・・工夫に、新規蒔直しに、追いまくられた。
そういう幾段階の「身」を曝した経験の末に出来上がったのが、此の地独特・独創の「戦闘態勢」成す黒い家だったので、明治時代の東京には、殊に目貫きの町々・筋々と云えば、ぎっしりとその、鬼瓦いかめしく鎧った、屋根瓦のだらだら急に前のめりな、見るから頑丈な、垂木や大黒柱の太い、外廻りはつやつやと、黒々と、クラの戸前仕立てにびっしりと塗りこんだ、「われわれの家」が充満した。
ここで幕末から明治、大正の大震災前での、土蔵造りの商家の立ち並ぶ様子の記述が完成します。最後に現代(昭和30年代)の人にも見せたいものだと続けています。
面白いのは、江戸の蔵造りの家については、独特、独創的と言いつつも、形態については好んでいるようには見えません。やはり、画家の美意識からは、江戸の独創的といえる蔵造りの家は武骨で好まないのかもしれません。
これで、関西の瓦屋根の家と江戸の蔵造りの家の印象が異なるのはなぜかという長年の疑問が、東京下町生まれの著者から説明を受けて納得がいきました。
もっともよく考えると、「戦闘態勢」を思わす、巨大な鬼瓦といかめしい瓦屋根、黒々とした色彩感覚は、火災を防ぐ構造とは直接関係がないと思うので、むしろ西の美意識と関東(東日本)の美意識との違いと考えた方がよいと思うのですが、いかがでしょうか?
この点については、我が国における「黒ベタ」の流行の記事と、10年前のブログに記事を書いていますので、もし興味ある方はお読みください。
さて著者は、蔵造りの壁の変遷についても画家らしく観察しています。明治初期の伊豆の海鼠(なまこ)壁のあと幕末後ヨーロッパ風の建築が入ってくると斜め十文字、最後には白の十文字を描くだけの形式に変わったと言っています。その様子は挿絵で示されています。(下図)

一方、
本格の御国振り塗り屋の壁・関東独特の壁は、土蔵ならば白一色、住居ならば黒一色、これを丹念に。テリがでるまで塗りこむ、「土蔵造り」が定法になって、コンクリート以前の、壁地の完全な塗籠手法が、ここに成立した。
以上が「銀座煉瓦」の章の蔵造りの家についての記述ですが、「東京繁昌記 東京の民家」にも関連する記述がありますので、紹介します。
佃島に残る堅牢な民家の記述の後、明治の東京の町についての長い記述が続きます。少し長いですが、以下に引用しながら紹介します。
そういう家々(注:佃島に残る堅牢な家)がこの土地に一杯あったのが、悉く焼けて、いまは一軒も満足なものは無いのである。僕はカブキ狂言で一ノ谷陣門の熊谷をみると、熊谷直実、この関東武者の黒糸縅(おどし)に、むかしの東京の家を懐うのであるが、僕がむかしの東京の「家」についてくどくも書くのは、それをすでに、見ることが出来ず、従って知らない今の若い人達(世代)に、「明治」中期までの、そのころは「東京人」がまだ東京を生活して居たといえる――「今」の東京は、日本人の東京であっても、東京人はその中枢に係るまい、――その時代のローカリズムを、とりあえず「家屋」を通じて、伝えたいと思うからである。
少しわかりにくい文章ですが、明治後期以降、大正に入って経済発展するに従い東京は地方からの人々の流入により人口が増大し、日本人の東京になってしまった。著者が生まれた明治後期より前に、江戸の下町で生まれ育たった「東京人」の比率が下がってしまった。だから、東京人は今の東京(注:昭和三十年当時)では、その中枢(注:政治や経済的発展)に係るまいという表現になるのでしょう。
実際、著者は別のところで東京下町生まれの自分たちにも故郷はあるという議論をしています。変わりゆく故郷を感傷的ではなく、変化を受け止め、けれども若干の寂寥と未来への展望を抱いて記述していくところに本書の魅力があると思います。
先ほどの引用文の中の「熊谷直実、この関東武者の黒糸縅(おどし)に、むかしの東京の家を懐う」について叙述が続きます。
小粒ながら強い黒糸縅の家がびっしり並んだ東京の町だったということを申し上げたい。江戸から東京にかけてのこの土地の生活は、家のみならず服装にも、小態(こてい)ながらウワずらない、材料に念を入れた質実堅牢が注意されて(多年の「火災」と「地震」がこの土地の人間をそう訓練した)、万事にも持ちの良さを貴ぶ土着東京人の「質実性」は、どうかすると吝嗇にさえ傾いたもの。都心はいうまでもなく、都西(青山辺)にも都北(本郷辺)にも至る所指摘されたカワラぶき・蔵造りのガッチリした町屋建築は、その「気質」の具象として見る場合に意義がある。
ここでは、明確に関東大震災以前の東京の街並み、町屋についての思いが現れています。
先に引用した「銀座煉瓦 七」の章では、見かけの描写は必ずしも好意的な表現ではなかったのですが、ここでは「黒糸縅」の様相は、「東京人」の質実性の気質の表れとして好意的に記述されています。
その後の東京は様相もガラリと変わったと見なければならないが、大正震災でまず「家」という旧東京の「残影」がほとんど全部滅亡した時期を、その交代チャンスと見てよいと考える。例えば卑近にむかしの町屋風俗についてうたわれた三味線端歌の〽ちょいと出るにも結城の着物」という、この「結城織」にしてもそれは今のようなシャレ糸の着尺地をいったのではなく、節糸の強い、持ちの良いフダン着の袖地をいったものである。
熊谷直実のような「家」・黒糸縅が、その後は東京に無いように、シブく強いシラ結城も無ければ、むかしの東京は、「東京」にはほとんど今何も無いということを申したい。その無くなったものの説明に僕は念を入れているわけである。
以上の文章の中で「旧東京の「残影」がほとんど全部滅亡した時期を、その交代チャンスと見てよいと考える。」と言い切るところに、大正の震災、東京大空襲、そして戦後の高度成長による街の消失・変貌を体験し、目撃してきた著者の姿勢が現れています。
実は、今回私の街歩きスケッチから取り上げた蔵造りの民家の話題は、本書の一部にしかすぎません。
著者の、消滅していくものに対する冷静な視線は、現在ではほとんど話題に上ることのない「銀座煉瓦」と「築地居留地」の誕生・消滅に関する章により詳しく記述され、そこに本書の中心があります。
明治政府の欧米化政策、全東京を洋風レンガの街並みに持っていこうとする政治家の思惑、それにかかわる人たち、そして最終的には、「東京人」は自然に東京の風土に合った蔵造りの家を選択していった過程を記述して、なぜ著者がそのような姿勢を取るようになったのかが理解できる内容になっています。
本書に関心を持たれた方は是非お読みください。
最後に
私の街歩きスケッチに関連して本書を取り上げました。
冒頭で述べた私の疑問に関する部分に焦点を当てたのですが、東京には今や無く、川越に残る大正以前の蔵造りの家と街並みについての印象(関西との違い)について、著者はの見方と私の印象が一致していたので納得できました。
これまで多くのスケッチャーが古い瓦屋根商家を描いています。基本的には、昔のままに描く、消滅してほしくない、といった気持ちが現れています。ある種のノスタルジーです。
しかし、5年前、関西の古い家屋を描くときの私の方針は、ノスタルジーではなく、変化を受け入れる、そして現代に合わせるでした。
具体的には、消滅した後の新しい開発された姿、古い家屋を現代に改装(リノベーション)した姿など、時代の変化を写し取ることでした。
もし著者が生きていれば、私と同じようにノスタルジーではなく今を写し取ろうとするのではないかと思います。
その意味で、昨年川越の商家群を見たときは、どう描いたらよいか分からず帰ってきてしまいました。(むしろ江戸よりも、昭和レトロの街並みが残っているのに興奮しました)
理由の一つは、それこそ「鬼瓦いかめしく鎧った、屋根瓦のだらだら急に前のめりな、見るから頑丈な、垂木や大黒柱の太い、外廻りはつやつやと、黒々と、クラの戸前仕立てにびっしりと塗りこんだ、「われわれの家」」の印象に圧倒されたのか、美しいとは思えなかったからです。
二つ目の理由は、現代を感じさせるものがなかったからです。いわば博物館的なのです。むしろ現代風に改装されていると、生きた生活を感じるのですが・・。
いずれにせよ、著者によれば、東京人の「質実性」を表しているということなので、次回は川越の商家を新たな目で見直すことにします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
