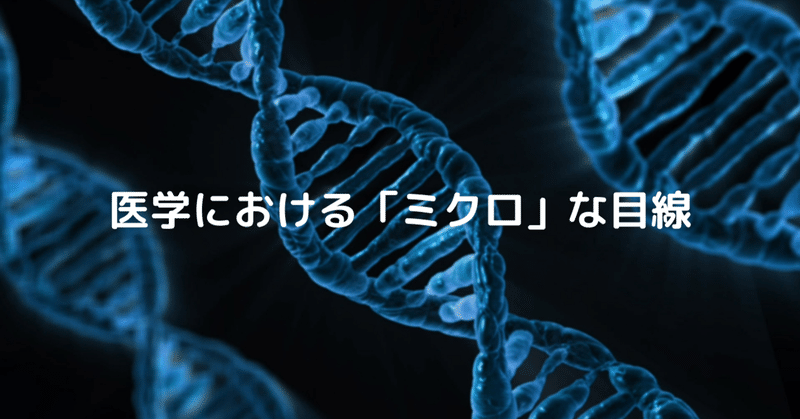
医学における「ミクロ」な目線とは?
では、医学部前半で学ぶ「ミクロ」な目線である「基礎医学」ではどんなことを学ぶのでしょうか?
難解でコスパの悪い「基礎医学の授業」
科目にするとたとえば「細胞生物学」や「生化学」、「分子生物学」とかになります。病気や治療に関する学問だと「薬理学」や「病理学」が該当します。これらの知識はヘルスリテラシーを高めるために有効だし、家族が患った病の知識を深め、医師からの病状説明や治療方針の説明を「納得感」をもって聞くために役立つでしょう。
ですが、個人的な経験から、これらの科目を「いかにも大学」的な場所で、「いかにも難解」な教科書で勉強することはかなりコスパの悪い行為だと思います。
でも、誰もが知っておくべき基礎知識もたくさん含まれる
また、これらの内容を一般向けに上手に説明した書籍はやはり残念ながら「多くはない」と思います。そしてさらに残念なことには、ちまたに普及しているのは、こういった背景知識のない一般人を「煽る」ことで収益を得ようとしている書籍だったりweb記事だったりします。その点は、新型コロナウイルスやそのワクチンを巡る混乱で多くの人は気づいたかもしれませんが、、、
過去記事でも絶賛した本書は、ガチですべての人にオススメなので再掲しておきます!
WING先輩のスタンス
WING先輩のスタンスは、これらの基礎医学的な内容を「ある程度厳密さ」は無視して、一般の方でも「肌感覚」で医療にかんする情報を理解し、医療を「納得感をもって」受けられるようサポートしていくことです。
で、この「ミクロ」な目が非常に「大事」にも関わらず「イメージしにくい」問題をどう解決していくか?それは、やはり「イメージしやすいマクロな目線」と紐付けしていくことです。つまり、最低限みんながイメージしやすい、「身近な病気」や「臓器」、あるいは健康診断で受ける血液検査の結果などと結びつけていくことですね。健康意識の高い方々であれば栄養・食事・運動などの知識も断片的にあるはずですから、そういった知識を「糸口」にして多少は基礎医学の「おいしいところ」をつまみ食いしてもらえるように鋭意、作文していきますよ!今後とも宜しくお願いします!
とりあえず、こんな感じで短い記事を細かく投稿できるよう頑張っていきます!
WING先輩の自己紹介や生い立ち?この連載をするようになった経緯などについてもいつか語ろうと思っています。お楽しみに!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
