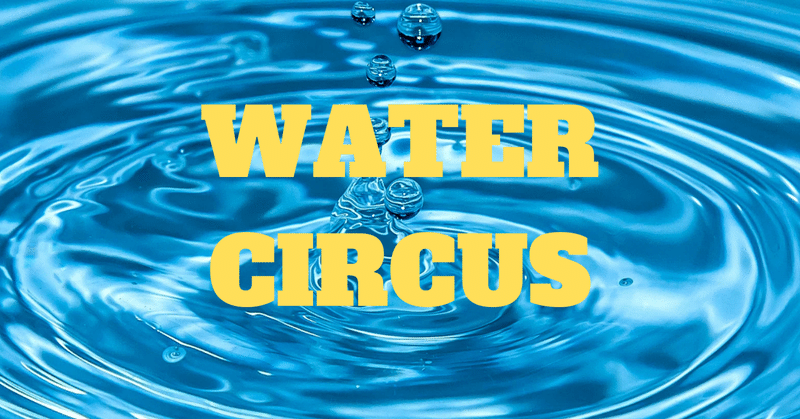
【ショートショート】ウォーターサーカス
ペットボトルの水を飲もうとして、水に飲みこまれたのは初めてだった。飲み口から飛びだしてきた水の塊に、頭からつま先まですっぽりとおさまる。一瞬の出来事だった。
どう考えてもペットボトルの内容量より多い水の中に、ぼくはいた。目の前にたくさんの気泡が浮かぶのが見える。ぼくの口からもれた空気だ。不思議と息苦しさはない。
前方に目をやると、小さな光の粒がゆらゆらと揺れていた。次第に光の粒は大きくなっていく。すると突然、水の塊は水風船が破裂するかのようにパーンと弾けとんだ。
ぼくの全身はずぶ濡れだった。髪の毛から雨降りのようにポタポタと雫が落ちては、乾いた白い地面を色濃く染める。濡れた前髪をかき上げて、顔を洗うように手のひらで顔を拭く。
顔を上げたぼくの目の前に、信じられない光景が広がっていた。
快晴の空の下、その空よりも真っ青な色をした巨大なサーカス小屋の前に立っていたのだ。サーカス小屋の上部には、これまた巨大なクジラのバルーンがテントから飛びださんばかりに乗っかっていた。サーカス小屋の入口では、たくさんの人が列を作っている。さっきまでうちのキッチンにいたはずなのに……この場所は……。
「ようこそ、ウォーターサーカスへ!」
水はたくさん飲んだがまだ状況が少しも飲めていないぼくに、ひとりの女性が話しかけてきた。
「ここはどこですか? というか、あなたは誰?」
「ひとつずつお答えしましょう。ここは『水島』と呼ばれる場所で、私たち水島サーカス団が興行を行うための浮島なの。ウォーターサーカスは完全招待制の公演でね。水のエンターテインメントを心潤うまで楽しんでいってね。改めまして、ようこそ、ウォーターサーカスへ! 水島サーカス団見習いのヨーコよ、よろしくね」
ヨーコさんが話してくれた通り、確かに今いる島はそんなに広くはない円形の浮島のようだった。周りは見渡す限りの青い海だ。こんなあやしい場所でのあやしい公演への招待状がいつ届いて、いつ「いく」と返事をしたのだろうか。ふと、うちの冷蔵庫から取りだして飲もうとした水のペットボトルを思いだした。
「まさか、あのペットボトルの水が招待状だったってこと?」
「そうよ。私たちは『呼び水』と呼んでいて、ほかにも水が関係するものなら、どこへだって招待状を送れるの。プールや海で泳いでいる人が招待されることもあれば、洗濯機に吸い込まれてやってくる人だっているのよ」
洗濯機の中で洗濯物と一緒に目を回しながらここにくるよりは、少しはマシな気もした。
「これって誘拐ですよね?」
「招待だよ」
「ぼくは望んできたわけじゃありませんよ」
「これは超超超ラッキーなことなのに、なんだか君はドライだなぁ」
ヨーコさんはぼくの頬っぺたを指でつんつんと突いてきた。
「さっさと帰してください」
「公演が終われば、みんな無事に元の場所に送っていくってば。約束するよ。けどね、きっとここにきたことを後悔させないから」
ヨーコさんはぼくに視線を合わせるように、まっすぐな目で見つめてくる。その目は光を反射する水面のようにきらきらと波打っていた。
「おーい、ヨーコや。招待客が集まったようじゃ。もうすぐ開演するぞぉ」
大きなシルクハットに黒いタキシード、口ひげを生やした小太りの男が、大声で叫びながら、ぼくらへと近づいてきた。
「団長、ごめんなさい。今、行きます!」
どうやら、この人がこの変な団体のボスらしい。
「やぁ、やぁ、こんにちは、少年。私が水島サーカス団長のミズシマじゃ。君は幸運な子だねぇ」
「別にきたくてきたわけじゃないので」
「こりゃ、ドライなお客さんだ」
「だって、サーカスって子供だましでしょう?」
「ほほう。君みたいなお客さんが一番、やりがいがあるんだよなぁ。よしっ、ヨーコや。この少年と一緒に客席からご覧なさい。あとで、リアクションの報告をよろしく。ほっほっほっほっ!」
ミズシマ団長は豪快に笑いながら、のそのそとサーカス小屋の中へと消えていった。
「さぁ、私たちも中へと入りましょう」
「ここから帰るまでのただの暇つぶしですよ」
「わかった、わかった。はい、行くよぉ!」
ぼくと同じように、突然この場所に招待されたずぶ濡れのお客さんの列に並ぶ。浮き輪をつけたままの人やシュノーケリングの恰好の人もいて、どこから招待されてきたのかは一目瞭然だった。
軽快なジャズミュージックと水音をミックスしたような不思議な音楽が流れる入口を抜けて、サーカス小屋のテントへと入る。テントの中は外から見た大きさよりもさらに広くて天井が高く、まるで巨大ドームのような空間が広がっていた。何よりも目を引いたのが、中央に堂々と設置されている巨大な円形の滝だった。その滝を囲うように、階段状に観客席が設けられている。
「す……」
「すごいでしょ? あれがうちのメインステージよ」
自分が思わず口にだすよりも速くヨーコさんに心の内をいわれたもので、でかかった言葉をゴクリと飲み込んだ。
「た、ただの滝じゃないですか。あれのどこがステージなんです?」
「素直じゃないなぁ。じゃあ、あれはどうだ?」
ヨーコさんの呼びかけに、再び円形の滝へと目をやると、滝の表面を何かがもぞもぞと移動している。目を凝らして見ると、その正体はなんと鯉だった。何匹もの鯉が、絶えず落下する水流に逆らうようにして滝を登っている。
「ほら、鯉の滝登りっていうじゃない。ここに招待された幸運なお客さんをお出迎えする演目なの」
そこで、ちょうど場内に響きわたるアナウンスが始まった。
「お集まりいただきました、紳士淑女の皆々様! ようこそ、水島サーカス団プレゼンツ『ウォーターサーカス』へ。開演の前に、本公演の注意をひとつだけ。会場内の席はすべて水かぶり席となっています。全席です。常時、水がかかりますのでおきがえされてもすぐにびしょ濡れです。メイクを直されても、すぐに落ちます。なので、余計なことは考えず、水のエンターテインメントと水との触れ合いを思う存分に楽しんでいってください。まもなく開演でございます!」
客席からはとまどいの入り交じった拍手がまばらに起きた。そりゃそうだ。一方的な主張のアナウンスに抗議したくもなったが、公演が終われば帰れることだし、おそらく何を言っても水かけ論で終わりそうな気がした。
しばらくすると、テント内の照明が落とされて、円形の滝がライトアップされた。
鯉たちは滝に流されて落ちながらも、少しずつ滝を登っていく。何匹かの鯉は下まで流されてしまったが、ついに三匹の鯉が滝の頂上へとたどり着いた。
雷が鳴ったのは、そのときだった。
テント内にぽつぽつと雨が降りだす。雨足はどんどんと強まっていった。
「ここまで濡れると、なんだか諦めがつきます」
もうぼくがすわる椅子の座面には、小さな水たまりができていた。
「ふふふ。まだまだ、こんなもんじゃないわよ。ほら」
再び滝に目を向けると、なんと滝の上で三匹の鯉が光りながら浮かび上がっていた。天井全体に稲妻が走ると、鯉たちに大きな雷が落ち、なんと三匹の龍へと変身した。緑でも赤でも黄色でもない水色の龍だった。
「水龍様よ。さぁ、メインステージのお目見えよ」
円形だった滝の水が、まるで両開きのカーテンのように左右へとスルスルと消えていく。すると、中からは巨大な円形のプールが現れた。中央には桟橋がかかっている。桟橋が舞台となっているようだ。
「ウォーターサーカスの目玉『ウォーターカーテン』よ」
ヨーコさんの言葉が頭に入ってこないくらいに呆然としていると、舞台上に数名の長い棒を持った団員が登場した。その団員たちを目がけて、三匹の水龍が襲いかかってくる。団員たちは手に持った棒で応戦するも、水龍の気性は激しく、だんだんと押されていく。
やられる、と思った次の瞬間、なんと団員たちは、長い棒を水龍の腹の部分にくっつけて、動きを封じ込めることに成功した。それは、テレビで見たことがある龍舞のようだった。
団員たちが長い棒を操るようにして踊りだすと、水龍も合わせるように、体をくねらせて舞台上を飛び回った。団員たちの棒さばきに合わせて、水龍は円を描いたり、互いの体を絡み合わせたり、舞台上を縦横無尽に舞った。水龍をあやつる団員たちは水龍を跳びこえたり、ほかの団員たちと衝突しないように踊りながら、舞台上に三つの『8』の字を描いてみせた。
「あれが『水龍の舞』よ。とても縁起のよい演技なんだから」
会場内には、最初のまばらな拍手と比べ物にならない大きな拍手が起こった。
すると、桟橋の下から新たな三人の団員がせり上がってきた。三人ともが手にサーフボードを持っている。三人は互いに目で合図をすると、水龍の背中にサーフボードを投げて、なんとその上に飛び乗った。踊り続ける水龍の背中に激しい波が立ち、サーファーたちはバランスをとって完全に乗りこなしていた。
さらに大きな拍手が起こり、会場内の熱気がどんどん増していくのがわかる。
ここで団員たちが、水龍の腹から一斉に棒を外した。解放された水龍たちは、舞台上から客席へと飛んでくる。水龍の舵をとるように、背中のサーファーが波を乗りこなしていく。会場内には、大きなウェーブが巻き起こっていた。サーファーたちは舞台上の団員からバケツを受け取ると、再び水龍とともに客席へと戻ってきた。バランスをとりながら水龍の背中からバケツで水を汲むと、客席へと次々と水をまいていく。
「ぷはぁー!」
ぼくの頭上からも水がどんどん降ってきて、なんだかもっと水をかけてほしい気持ちになってくる。階段状になっている客席の足元には滝のように水が流れ、ばしゃばしゃと足を遊ばせた。
ひとしきり水をまき終えると、サーファーたちは水龍の背中から円形のプールへと飛び降りた。自由となった水龍たちは客席を飛びこえると、真っ青なテントの布地へと吸い込まれ、テントの布地を泳ぎ始めた。
客席はもう総立ちだ。今日一番の大拍手が起こった。指笛を鳴らす人もいれば、大声で叫ぶ人もいたほどだ。
「さすがに驚いたでしょう?」
「まぁまぁだね。もっとすごいのを見せてもらわないと」
笑いながらも、ドライなテンションでヨーコさんにぼくは返した。
一旦、静まり返った舞台上に、今度はスポットライトが照らされる。そこに現れたのは、シルクハットをかぶった人間の大人ほどの背丈の水飲み鳥だった。
ちょこちょこと歩いてきた水飲み鳥は桟橋の端へと移動して、長い首を上下させて水を飲んでいる。何度も首を上下させていた水飲み鳥だが、バランスを崩してプールへと落ちてしまった。観客がどよめく。すると、プールの中に落ちた水飲み鳥が、次第にミズシマ団長の姿に変わっていくじゃないか。
慌てた団員がプールへと飛び込み、ミズシマ団長を救出した。ミズシマ団長はピクリとも動かない。観客が固唾を飲んで見守る中、団員がミズシマ団長を仰向けに寝かせて心臓マッサージをほどこした。ミズシマ団長の口から、飲み込んでいた水がピョーンピョーンと飛びだすと、むくりと起きあがった。
「ウェルカム・トゥー・ウォーターサーカス!」
さっきまで気を失っていたミズシマ団長が大声で叫ぶと、プールからいくつもの水柱がドーンと派手に打ち上がった。なんだか心配して損した気分だった。
「ちょっと喉がかわいたもので、水を飲もうと水飲み鳥に変身したんじゃが、どうも飲みにくくてかなわん。代わりにこれを使いましょう」
そう言って、ミズシマ団長がとりだしたのは長いストローだった。
「すみませんが、ちょっと水分補給だけさせてちょうだいな。大事だからね。あ、客席の皆様は水分足りていますかな?」
とぼけたミズシマ団長の問いかけに、観客がどっと沸いた。
「ではでは、しばし水分補給を」
ストローを口にくわえたミズシマ団長がズズズズーと吸い込むと、なんとプール内の水が一気になくなってしまった。
「ふぅ、やっと喉が潤ったわい。仕切り直して、ウェルカム・トゥー・ウォーターサーカス!」
もう一度、ミズシマ団長が大声で叫ぶも、水のなくなったプールから水柱は上がることなく静まり返っている。
「ありゃ、まぁ。全部、飲み干してしまったわい」
再び、観客は大笑い。
「元に戻さんとな。どれどれ」
ミズシマ団長はシャツをめくると、突然大きく膨れた腹をだした。
団員から何かを受けとったミズシマ団長は、なんと自分のおへそのところにくっつけた。どこからどう見ても、それは蛇口だった。
「ほいとな」
ミズシマ団長が蛇口の栓をひねると、すごい勢いで飲んだ水がプール内へと戻っていき、たぷたぷだったお腹もへこんでいった。
「皆様、このことはどうか水に流してください」
終始とぼけているミズシマ団長の言葉に思わずぼくは吹きだして、会場に拍手と笑いが溢れた。
「それでは、ウォーターサーカスのフィナーレです!」
ミズシマ団長の叫び声で、団員たちが桟橋の舞台へと集合した。一斉にプールへと飛び込むと、団員たちはイルカやオットセイといった海の生き物に次々と変身していく。ヒトデにタツノオトシゴにシュモクザメなど様々だ。
「さぁ、最後は私も行かないとね!」
「えっ?」
隣に座っていたヨーコさんがいきなり立ち上がると、走って客席を駆け下りていき、プールへと飛び込んだ。
すると、円形のプールの水嵩がどんどん増え始めた。プールの縁から溢れてしまうと思ったけれど、不思議と水は溢れることなく、気がつけば大きな円柱型の水の塊となっている。それはまるで、水族館の巨大水槽みたいだった。生き物に変身した団員たちは、気持ちよさそうに水槽内を泳いでいる。
あれ、ヨーコさんはどこだ?
水槽の中を探していると、どこからともなく美しい歌声がきこえてきた。
歌っていたのはなんと人魚だった。
「ヨ、ヨーコさん⁉」
ヨーコさんの歌のリズムやメロディーに合わせて、海の生き物となった団員たちは水槽中を泳ぎ回った。
軽快で力強いリズムのときには、イワシの群れとなって統制された大迫力の泳ぎを見せた。
陽気な歌声のときには、暖かい南の海を思わせるカラフルな熱帯魚たちがにぎやかな泳ぎを。
寂しさを歌っているときには、凍えるような北の海を思わせるクリオネやイッカクがスローな泳ぎを。
深い悲しみを歌っているときには、真っ暗な深海のような水槽内に、チョウチンアンコウの背びれの先端が点滅するだけだった。
巨大水槽内で表現される様々な海のグラデーションに、思わず見入ってしまう。
会場内からは、すすり泣く声もきこえた。
そのすべてを指揮しているヨーコさんの歌声は、圧巻のひと言だった。
ミズシマ団長はというと、ポセイドンの姿で気ままに泳いでいて笑えた。
ヨーコさんが歌いながらゆっくりと回転し始めると、生き物たちが一斉に円柱型の水槽内をぐるぐると回りだした。泳ぐ速度はぐんぐんと上がり、水槽内には巨大な渦が起きている。
一体どうなるのだろう、と思っていると、ヨーコさんの最後の高音が伸びきったところで、円柱型の水の塊がすべて弾けとんだ。客席には大量の水が壁のようになって、ザブーンと崩れ落ちてくる。
同時に、サーカス小屋の屋根も上空へと弾けとんで、快晴の空にクジラのバルーンが打ち上がり、たくさんの潮を吹いた。空からはスパンコールのような水滴が降ってきて、ぼくはしばらく浴び続けていた。
体中がブルブルと震えている。
寒さでも怒りでもない、ありえないものを目の当たりにした歓びの震えだった。
「本日はありがとうございました。これから皆さんを元いた場所へと、無事にお送りいたします」
ミズシマ団長が挨拶すると、名残惜しそうな声や拍手が起こった。
「なかなか面白かったでしょう?」
いつの間にか、ヨーコさんがぼくの隣にいた。
「こんなに面白いものは見たことないよ」
ドキドキやワクワクを隠すことなく、初めて素直に笑って、ヨーコさんに伝えることができた。
「でしょう!」
ヨーコさんは誇らし気な顔で笑っていた。汗なのか水なのかもわからない光るものが頬を伝っていて、その表情が本当にきれいだった。
「この場所って、ずっとここにあるの?」
「また別の場所へと移動させるんじゃ」
ぼくの問いかけには、ミズシマ団長が答えてくれた。
「ほら、こうやってな」
ミズシマ団長が指をパチンと鳴らすと、なんと真っ青なサーカス小屋が大きな球体の水の塊となった。
球体はだんだんと小さくなっていって、やがて手のひらサイズの水の塊になった。
ミズシマ団長は、ポケットから切れた輪ゴムを取りだすと片方を水の塊の端っこに縛りつけ、もう片方の輪ゴムの切れ端を輪っかにして指にはめた。
「水ヨーヨーじゃよ」
ミズシマ団長は無邪気に笑った。
目に映るその笑顔が、だんだんとぼやけていく。そろそろ、帰る時間のようだ。いつの間にか、ぼくは最初と同じ水の中にいた。
たぷん、たぷん。
視界はぼやけてはいるが、ミズシマ団長が手に持った水ヨーヨーで遊んでいることはわかった。
水ヨーヨーのリズムに合わせるように、たぷん、たぷんとぼくの潤った心も弾んでいた。
文章や物語ならではの、エンターテインメントに挑戦しています! 読んだ方をとにかくワクワクさせる言葉や、表現を探しています!
