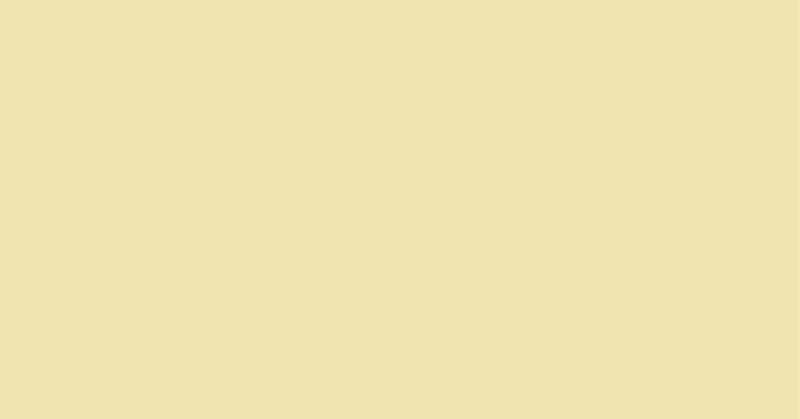
2887文字、日本が欧米文系を乗り越える上で押さえるべき理解について(いらぬ不幸やご都合主義正義に対する教育の責任に触れつつ)
2023-4-001
学問的に欧米からあまり離れてない周縁である日本は、下で言う要請物の持ち込みが欧米文系よりも容易でしょうから、欧米文系の乗り越えを多分に期待できるポジションにあると考えますが、
その優位性を生かせてない(単なるローカル実態主義では近代性に留まるので、乗り越えレベルで生かしてる事にはならない)とも思います。
(この理解を、文系の既存の知的権威の言動に対し下で言う対教育のように付き合うべく、
つまり、内実の確からしさ差異を無視した解釈に付き合わされないよう、押さえましょう。)
例えば、人なり国なりがAをできないせいで一般に不幸と言えるような事態に陥ったとして、これを認識した文系者の為す対象理解に求められるべきものは、
代替不可能な内外事情にしか応じない主体像として歴史を紡いできた結果のできないである、
かつ、具体的扱いが場の疑似でない固有性を阻害なく反映させたものである、
ここ(内外境界意味する有限の与件性とより確からしいものが取って代わる運動性、現象がこれらから成ってるという意味での、帰属の修正余地のなさ)からのズレを、
現象における受容に値しない部分と見なし、前者でのズレを主体の責任、後者でのズレを場の責任に帰する事の正確性についての、その文系者なりの上限化であると思います。
以上を認める場合、文系者の為す現象解釈には、内在性質と外在性質が疑似でない程それらの統合物である現象は受容に値するとの現象観、
および、同種の他との共通要素捨象による個別性検討(代替不可能なもののみ個別性とする処理)が要請されてる事になり、
加えて、この要請物の獲得機会を潰してる形の既存教育(要請物とバッティングしてる近代性の保全)には、
受容に値する不幸だけがある状態へと持ってく上で必要となる、受容に値する不幸と値しない不幸の分別ができない状態のまま社会に送り出し、
また、そのように送り出された人達に社会の歴史を紡がせてきた(どの理念をどれだけの期間伴ってようと、
歴史がいらぬ不幸に許容的であり続けてきた)件についての責任がある事になるはずです。
(この意味で、奪う奪われる現象Aを非難しつつ、同Bには疑問を持たない内容のご都合主義な平和教育に限らず、同内容の秩序観が多様化してるだけと言える現状も、
近代性保全に与し、教育を近代性への特化に矮小化してる教育者の責任と言えます。
ちなみに、引き受ける内在事情外在事情の代替不可能化を上限化させてない人の、何かができるとかできないといった状態は、
その人に帰属してない部分を持つ為、自分に帰属してないものまで帰属してるように扱う帰属操作に等しく、
他方で、自分がその被害者でないケース含め、奪う奪われる現象への否定的位置づけをその人が見せるのなら、
当然、そこには帰属操作に対する抽象化不足故の、ご都合主義な秩序観なり正義感覚なりが言えるはずですし、
また、実存の内実確からしさの不足が対真善美の上限化失敗である事の具体例でもあると思います。)
とはいえ、自力で近代性をできるだけ受容しないよう(特に、個別性が根拠になる局面での個別性捨象である不当合理をもって、
文系事象の理解や文系的局面での論理を展開してしまう事、展開してるケースに遭遇し真に受ける事のないよう)配慮しつつ教育受ける事も理論上可能ですから、
上の主体像から成る実存でない(検証精度の低い検証結果の仮説へのフィードバックの形が自分自身について言えてしまう生、理想を過剰に割り引く現実の意味で対真善美や対無限者を上限化できない生)
という事態の全てが、教育なり教育者なりに帰されるわけではありませんが、
そのような対教育を、というか、いらぬ特化の忌避が与えられたものの受容に先立ってる(いらぬ特化を防ぎつつ受容する)有り様の、対教育に限らない自力保障を可能にするには、
局面と着目無視とが合致してる振る舞いを基準とした過不足(過大反応過小反応)を防いでるならば、その結果に生じるものは受容に値する
(受容しない側に非がある)とする、ある意味自他を突き放す方向に、他の倫理系イメージよりも妥当性を覚え、
かつ、単に場に合わせるだけでなく、場の個別性の検討を大した理由なく閉じないでおく必要が、
つまり、この二つの意味でいらぬ限定を忌避してる必要があって、実際、そこに自由を覚える事自体は小学生でも全然可能でしょうし、
その自由の実現へと教育側が背中を押してあげる(教育への脱近代の取り込みに相当するけれど、
冒頭のような現象解釈の養成の取り込みまでいかないと、脱近代を潰す役回りになってしまってる点は変わらない)に越した事はないと思います。
もちろん、フィードバックが結果的に脱近代へと向かわせるような評価環境でない点は子どもにとっての教育も、教育にとってのパラダイムも同じなので、
認識対象を着目無視枠組みに落とし込む際に局面と着目無視の不一致が、つまりは、差異付与という加工前後での確からしさ保存の失敗が、
実態主義(方法的懐疑はじめ、表層の汚れを拭っただけのものの根拠化)や不当合理の形で生じる近代性を、
パラダイム刷新の対象にしない事で保障する哲学者と、
パラダイムを体現する事で、
個別性が根拠にならない局面では同種の他との差異要素捨象を用いて、個別性が根拠になる局面では同共通要素捨象を用いて、通用の行き渡ってる状態、最も確からしい状態を確保する働きからの、
乖離を哲学者にも刷り込む教育との間の関係を終わらせる必要もあるでしょうから、
文系事象の解釈に先の要請物を持ち込めない人ほど対文系では不利である(より確からしい解釈を選抜する処理にいらぬ限界負う)、
との理解の欠如(前述のズレに相当する)を主体と場が共に持つという教育像や文系学問像を、
どこに修正余地があるのかの理解として押さえましょう。
注、
パラダイム刷新に最も責任負うのは哲学者ですし、近代性の特徴を実態主義と不当合理とした時、近代科学の成功に帰せられるだろう後者
(とはいえ、文理での捨象対象の違いを押さえてれば防げてるはずの、表層次元や内実次元でのいらぬ飛躍を取り除けているいないの無区別の弊害を引き起こしてきた、素朴な領域侵犯)はともかく、
近代始点である方法的懐疑の実態主義的側面(主観の内実確からしさ不問な根拠化を齎した件)が糾弾されてない
(ソクラテス裁判の顛末は冒頭の話が実態主義的扱いの受容へと至ったケースとして解せるなど、
先の主体像が過半でない場合に実態主義と見なせる市場や民主制は近代に限らないけれど、
表層の汚れを拭うだけなのは現象学も同じである事から分かるように、冒頭の話における場が誰かの内面世界である場合のズレは、近代以降では実態主義への理論的保障の側面が加わってる)以上、
前者の責任は哲学者に帰せられる為、その分、先の要請物に即した評価のある教育環境でない、という事態に対する教育なり教育者なりの責任は割り引かれるでしょうが、
哲学者の地平を近代性の枠内に限定してるのも教育を通した特化作用なわけで、ここに共犯関係を見ましょう。
ご支援の程よろしくお願い致します。
