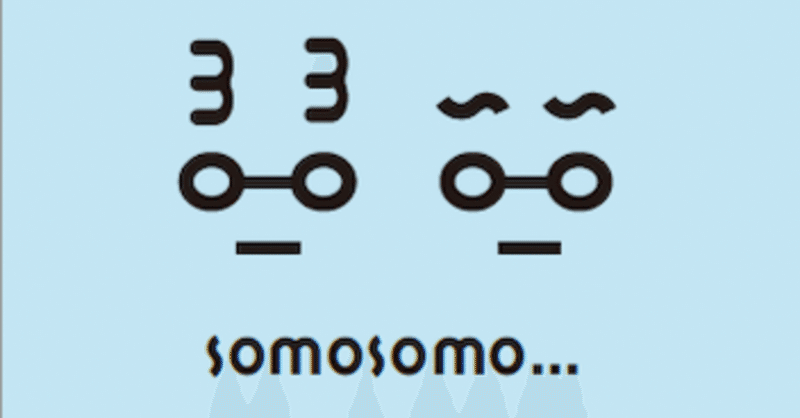
哲学は地域社会の課題解決にいかに貢献できるか〜手を引くこと、撤退すること、離脱することの意味と意義
山梨県立大学の2人の哲学者、橋本憲幸先生と橋爪大輝先生が「哲学は地域社会の課題解決にいかに貢献できるか」について語り合うトークイベントを開催しています。2023年7月に続き、2023年10月27日(金)に開催したイベントで語られたことを書き起こし、読み返し、一部は加筆し、修正しました。最後まで読んでいただけますと幸いです。司会は兼清慎一(山梨県立大学国際政策学部・地域研究交流センター運営委員)が務め、山梨で企業や自治体のブランディングに取り組んでいる斉藤奈央さんにコメンテーターを務めていただきました。
橋本憲幸(山梨県立大学国際政策学部)
福島県田村市出身。2015年4月に山梨県立大学国際政策学部に着任。筑波大学第三学群国際総合学類卒業。筑波大学大学院一貫制博士課程人間総合科学研究科修了。博士(教育学)。主著に『教育と他者——非対称性の倫理に向けて』(春風社、2018年)など。
橋爪大輝(山梨県立大学人間福祉学部)
東京都多摩市出身。2021年4月より、山梨県立大学人間福祉学部講師。東京外国語大学外国語学部卒業。東京大学大学院人文社会系研究科(倫理学専攻)博士課程修了。博士(文学)。著書に『アーレントの哲学』(みすず書房、2022年)。
斉藤奈央(株式会社「DEPOT」プランナー/ディレクター)
山梨県甲斐市出身。山梨県立大学国際政策学部に在学中、(株)DEPOTにインターンとして参画し、そのままメンバーに。山梨県だからこそできるクリエイティブがあると信じ、日々向き合い中。
夏の間、「悪の凡庸さ」について研究していました
ーー橋爪先生、この夏はどのような研究をされていたのですか。
文献の研究が中心で、本を読みながらノートをとり、それに基づいて論文を書く、ということをやっていました。いま翻訳の仕事も抱えているので、それも進めていました。いずれにせよ、基本的に研究室にこもってやる仕事です。
私は博士論文を出すまで、ハンナ・アーレントという哲学者――政治哲学者と呼ばれることも多いのですが――をメインに研究していました。そのアーレントの概念のなかに「悪の凡庸さ」というものがあります。この夏はそれについて考えていました。
アーレントは、1906年にドイツ語圏で生まれたユダヤ人なんです。世界史に詳しい人はこの並びを聞いただけでピンとくるかもしれません。1933年にヒトラーが率いるナチスがドイツで政権を取りました。ナチス政権は、ユダヤ人に対する迫害と差別を公然と政策に掲げていました。それは、アーレントにとって、自身の身も危ないという状況を意味します。彼女はそういうところから逃れてきた人なんですね。
命からがらヨーロッパを逃れて彼女はアメリカに渡りますが、そのアメリカで、自分たちを迫害したナチスや全体主義とは、どのような悪だったのだろうと、哲学的な思索を進めていくんです。
そんな中、ナチスの党員だったある人物が、戦後15年ぐらいたってから、イスラエルに拘束されて裁判にかけられるということが起きた。それが、アドルフ・アイヒマンという人で、ナチス政権の官僚としてユダヤ人の虐殺に大きな役割を果たした人物だったんですね。
その「大きな役割」というのがどういうものだったか。ナチスによるユダヤ人の虐殺は、社会全体レベルで非常にシステマティックに行われた虐殺でした。たとえば、物資を運んでいく物流網を最大限に駆使して、ユダヤ人を移送して効率的に殺戮していく。そういったプロセスを経て、推定も含まれていますが、600万人が殺害されたとも言われています。アイヒマンが果たした役割というのが、まさにその移送でした。交通機関等を使ったユダヤ人の移送を取り仕切っていた人物だったんです。そのアイヒマンが捕えられて、イスラエルのエルサレムで裁かれることをアーレントは知りました。その裁判を傍聴しに行き、彼女が書いたのが『エルサレムのアイヒマン』という本なんですね。そこでアーレントが編みだした表現が、「悪の凡庸さ」という表現だったのです。
この概念が、ありていに言って、たいへん物議をかもしました。凡庸とはどういうことか、これだけ人が死んでいるのに凡庸と言っていいのか、と。それは、アーレントから言うと誤解だという話なんですけど。とはいえ、「悪の凡庸さ」はその意味をめぐって今でも論争がずっと続いている、そういう概念なんですね。
「凡庸さ」とは、文字通りには「普通」という意味になります。「凡庸」の「凡」も、「平凡」の「凡」ですよね。ですから「悪の凡庸さ」も、そういうものとして受け取られてしまった。そうすると、ユダヤ人が大量に虐殺されているのに、それがまるで「つまらない普通のこと」だと言っているかのように、一部の人たちには受け止められてしまったわけです。
システマティックな殺戮は、規範を守る普通の人びとの協働によって行われた
アーレントは、もともと人間と人間が一緒になって何かをやるという協働を理論的に検討して、共同行為のポジティブな可能性をずっと語ってきた人なんです。やや唐突な例に聞こえるかもしれませんけど、例えば大学という場があって、それが機能しているというのも、たくさんの人々がよどみなく連携することによって、ある種の仕組みや制度を生み出していることだと言えます。普段の授業が行われるのも、そういう連携体制あってのことです。
アーレントは、協力して組織や制度を生み出していく人間の能力についてポジティブに語っていたんですけど、このホロコースト(ナチス・ドイツによるユダヤ人の大量殺戮を指す言葉)においては、ひとつの民族を虐殺するという巨悪のために共同行為とか協働が使われてしまった。アーレントにとってこのことは大きな意味があって、自身がポジティブに語ってきたものを逆用されたというか、そういう意味合いを持っていたんじゃないかなと私は思っています。
このとき、その巨悪が実行された仕方が問題で、そこではみんなで協働して犯罪的な行為をやっているわけですよね。こういう悪のなかでは、みんな協調してやっていかなければいけない。普通の社会だったら、残虐な人間とか、自分の剥き出しのエゴを優先して全体秩序を乱す人間とか、そういうパーソナリティのほうが邪悪で悪いやつということになってくると思うんですけど、逆に、この大量虐殺という悪事を果たすうえでは、そういう悪人は邪魔者になるわけです。
ホロコーストにおいてどういう人たちが連携し合っていたかというと、アーレントは、そこである種のノーマルな人々を想定している。ノーマルというのは「普通」という意味でもあるんですけど、同時に「規範(norm)的」という意味があります。だから、普通で、規範というものに則して動けるような人たち。こういう人たちが連携してやっていくことによって、むしろ社会全体で、ある特定の人々や民族を殺戮するという、人類史上稀に見るような悪が行われたことになる。
当時のドイツでは特定の人々を殺戮する体制が成立していて、ものすごく邪悪なことが起きている。でも、ある意味価値観が反転した世界の中にナチス・ドイツの人たちは生きていて、ユダヤ人を殺戮するという目標を共有し、それが“善”だとされてしまうと、そのためにお互いによどみなく連携できてしまう。そういう事態が「悪の凡庸さ」ということで、アーレントが言いたかったのではないか。私自身はこのようにアーレントを読んでいるんです。
例えば、日本社会が全体主義政権に完全支配されていたとしたら、大学で教員をやっているということが、もしかしたら特定の人々を殺害することに加担することもあり得るかもしれない。そういう状況下で言うと、普通に働いているだけでも、悪に加担することになってしまう。当時のナチ政権下というのは、まさにそういうシチュエーションだとアーレントは解釈していました。
では、どうすればよいのか。手を引く、思考する
では、こういう状況で悪に加担しないためにはどうすればよいのか、となります。アーレントは、ひとまず我々にできることはそこから手を引くことだ、と考えました。手を引くというと、簡単というか、実効性があるのかよくわからないことにも聞こえるのですが、社会のいろいろな人たちがいろいろな連携をしている中で、その連携をある程度断ち切るということを意味します。悪しき協働に関与しないことによって、そういう全体の協働を止めたり、分断させたりする。そういう結果には繋がらないかもしれないけど、少なくとも参加はしないということです。
そして、手を引くというのは、積極的にいうと、思考すること、考えることだというのがアーレントの結論です。アーレントの思想的な展開のなかでいうと、彼女はアイヒマン裁判以後、「考えること」について考察を深めていきます。思考がアーレントのテーマになっていく、という変化が起きるんですね。ちょっと専門的な話になってしまいましたが、この夏の間に書いていた一番大きい論文はそういう主題でした。
ーー例えば、私(兼清)は報道機関で働いていましたが、戦時に報道機関で働いていたら、自分は戦争に加担する報道をしてしまっていたかもしれないという思いもあります。
戦時に報道機関で働いていて、いろいろと調査をして報道している場合、政府の通達を広めるみたいなことは、ある種、社会を円滑に動かすための必須のものだと思うんですけど、そのシステム全体が、悪しき目的のために動いているときに、それは個人の倫理観がどうこうということよりも、円滑に動いているシステムをきちんと円滑に動かすという、そのために加担していってしまう。それはまさに「悪の凡庸さ」ということをアーレントが言ったときに考えたことと通底しているんじゃないでしょうか。
共生とは差別に抵抗すること。社会的カテゴリを更新し続けること
ーー橋本先生は、夏の間、どのような研究をされていたのですか?
橋爪先生がよいパスをくださったというか、話を繋げるための手がかりをお示しくださったというふうに思いました。今回のトークイベントのタイトルである「他者と共に生きるとは」というテーマは、まさに私の研究テーマの一つです。「共生」ですね。共生とはいったい何なのか、何をどうすることが共生なのか、あるいは何をどうすることがよりよい共生なのか、ということを考えています。共生は流行り言葉であり、無条件によいことであるかのような印象も与える、そうであるがゆえに、警戒しなければならない、立ち止まってその意味を吟味する必要があると思います。
共生という概念には、いくつか定義があります。一つは、社会的カテゴリを更新し続けることです。これが共生、共に生きることだとされた系譜があります。最初は、どうしてそういう定義になるんだろうと、私もわからなかったのですが、丁寧に追っていくとわかってきます。ちなみに、私自身は「共生」の定義が「社会的カテゴリを更新し続けること」では不十分だと思っています。夏はそのことを考えていました。ただ、今回はこの概念規定に基づいて考えてみます。
社会カテゴリを更新するとは、どういうことか。ひとりの人間というのは、例えば、コーヒーが好きであるとか、男であるとか、大学教員であるとか、第一子であるとか、東北の出身であるとか、いろいろな属性、社会的カテゴリを持っているはずなんですね。でも、ときにわれわれは他者を認識するときに、“この人はこういう人”という一つのラベルを貼り付けて、それだけでおしまいにしてしまうことがある。これって、差別なんです。差別とは何かというと、一つの認識だけ、この人はこういう人というラベルを貼り付けて終わりにすること、一つの社会的カテゴリを割り当てて済ませること、これが差別の意味なんですよね。これはマジョリティからマイノリティに対して非対称的に行なわれやすい。
共生というのは、この、“この人はこういう人だ”と一つに決め付けておしまいにする、この差別に抵抗するために出てきた思想であり、概念なんです。少なくとも日本の文脈にはそういう展開がある。だからこそ、この人はこういう人でもある、でもこういう人であるだけではない。また別の側面を持っている、つまりいろいろな面があるんだということを常に確認し続けることが、この人はこういう人だと認識して終了するという差別から逃れる唯一の方法ではないかということが、この定義の背景にはあります。“社会的カテゴリの更新”という言い方だけでは、共生の意味としてはちょっとわかりづらいかもしれませんが、今言ったような文脈を含めると、理解に向けて少し迫れると思うのです。共生は差別への抵抗、反差別の思想として生まれてきた。反差別として共生があるということです。
その社会的カテゴリを変えていきましょう、その人のいろいろな面、多貌性、多元性、複数性を見ていきましょうねという考え方。しかしそこには“社会的なカテゴリがないと他者を認識することはできない”という前提が潜んでいます。私は、そうなのか? と思っているところがあります。つまりわれわれは、他者を“誰々として、何々として”しか見ることができないんだろうかということなんです。例えば、兼清先生、私は国際政策学部の教員としてしか兼清先生を見ることができないのだろうか。橋爪先生も人間福祉学部で哲学を講じている人、ハンナ・アーレント研究者としてしか見ることができないのだろうか。私は兼清先生その人、橋爪先生その人を知ることはできないのか。いくつもの“⚫︎⚫︎として”を積み重ねることでしか他者を理解することはできないのか、その先に他者を他者そのものとして理解することはどのように可能か、そういう問題意識があるんですね。
ただ、この社会的カテゴリがあるから、他者とも生きられる、つまり国際政策学部の教員として兼清先生を見ることができるからこそ兼清先生とうまくやっていけるという可能性もあります。逆に、社会的カテゴリがあるから、他者と共に生きることが難しくなるということもありうる。私は後者のほうを考えたいわけです。この人はこういう人だ、この人はこの社会的カテゴリに属する、そうしてその人のことを認識することができるのかもしれないけれども、そういうふうに見るがゆえに問題が出てくるところもあるのではないか。これを考えてみたいと今思っているわけです。
おそらく、社会的カテゴリがあったほうが社会ではコミュニケーション——という言葉を使うのが妥当かどうか、ちょっと言い淀むところがありますが——は円滑に進むと思います。私は、そのカテゴリ同士で円滑にやりとりしているときに、見えなくなっているその人の姿っていうのがどうしても気になってしまう。ある社会的カテゴリが現れているということは、それ以外が見えない、いわば排除されてしまっているわけですよね。そこがどうも気になってしまうんです。他者の属性を固定化せずに、その多層性、多面性を常に認識する。それが社会的カテゴリを更新し続けるということです。とはいえ、共生の定義をそこに留めてよいのかなとも思っているのですが……。
道徳と倫理は違う。倫理は反道徳でもある
そうした事柄を考えるための補助線として、「道徳」と「倫理」を区別して捉えてみたいと思います。道徳と倫理は一般的に同じものだって言っている人もいます。私は分けたいと思っていて、実際に分けている人もいます。どういうふうに分けるかというと、どちらも望ましいという意味合いを持っているのですが、道徳は集団に属するものである、対して倫理は個人を単位とするものである。つまり、道徳は集団の中での望ましさ。例えば、この大学という集団だったら、こういうふうに振る舞うのがよいこと、これは道徳です。それに対して倫理は、ときにその集団にある道徳に歯向かうことがあります。自分はそういう道徳には従わない。そのとき個人の中で何が起きるかというと、橋爪先生の話にも関連するのですが、思考です。自分はそういう道徳には従わない、自分はこれがよいことだと考えるから、自分はこういうふうに振る舞うのだ、こういうふうに行為するのだ。それが倫理なんですね。だから倫理は反道徳的なんです。集団の道徳に抵抗する。
みんながよいと言っているからよいのだというのは道徳的です。みんながよいと言っているけど、自分はよいとは思わない、自分は別のこれがよいと思う、これが倫理です。日本社会でマイノリティの人びとが声を上げ始めてますよね。それって、すごく倫理的なんです。日本社会の中で当たり前になっているマジョリティがよいと思っていることに、それは嫌だ、私は苦しいと声を上げる。これは非常に倫理的だと思います。この側面を重視したい、注目したいと今は思っています。
それはなぜか。人間は集団になって活動するときでも、おそらく最初は個人から何かを始めている。例えば、地域の活動にしても、そのときの最初のその個人の思いというのは、やむにやまれぬ思い、例えば、悲しさだったり、憤りだったりとか、そういう思いのはずなんですね。かけがえがない思いがあったはずなんですが、それが集団化していく、いろいろな人と一緒に何かをやっていくということになってくると、その最初のやむにやまれぬ思いというのが薄まるということか、消えていってしまうというか、ないがしろにされていくというか、そういうところがあるのではないか。この考え方に立つと、集団で何かをするということそれ自体はすでに倫理的ではない、というか、何らかのよさをつぶしてしまっている。そういうところがあるのではないか。
個人でやり始めた活動があったとして、そこにいろいろな人が入ってくる。そうすると、元の活動が胚胎していた、内に含んでいた大切なことが抜けていってしまう。全く別の活動として動いていってしまっているというところがあるのではないか。だとすると、その活動それ自体が、もし本当によかったものであるならば、集団化することによってそれが傷ついていってしまう。これを問題だと考えると、何かをするときは、集団でやるというよりは、個人の資格で何かをするということが大事になってくる。そうしないと、そもそも個人がやろうとしたことが、集団によって生まれてしまう何かよく訳がわからない論理、組織の論理、そういうものによって、けがされてしまいかねない。そう考えると、個人として何かをすることの重要性をまずは指摘できるのではないのかなと今思っているわけです。
他者と共に集団を形成して生きざるを得ない私たちに、離脱の自由はあるのか
ただですね、わわれれは他者とともに生きざるを得ないんです。どんなにいやな人とともですね。だから考えなくてはいけないのは、個人の資格を維持したまま、集団を形成するためには、どういった条件を満たす必要があるのか。個人を潰さない集団とはどういうものなのかということです。個人が尊重されるとは、そもそもどういうことなんだろうかということも考える必要があるかなと思います。
これは自分自身の研究としてまとめたわけではないのですが、少なくとも発言の自由と離脱の自由が保証されないと個人の尊重は無理なのかなと考えています。他にもありえますが、ひとまず発言の自由と離脱の自由。発言の自由はひとまず説明を省きます。離脱の自由というのは、そこにいたんだけど、やっぱりやめたと言って出ていくということです。そこから出ていけるということが保証されていないと、その個人の尊重というのは難しいのではないか。例えばが私は今哲学ということで、ここにいて話をしているわけですが、教育学、教育哲学、国際開発学、いわゆる途上国のこと、そうしたことに取り組んでいます。そこに少し引き付けて言うと、学校ではいじめというものがいまだにある。なぜいじめは起こるのかということの一つの説明にもなるかもしれないと思うのがこの離脱なんです。嫌なことがあったから別のクラスに行きます、明日から別の学校に行きます、これは現在できないんですね。だからいじめられている側が学校の外に向けて離脱しないといけない。離脱すれば問題が解決するとは私は言いたくないわけですが、しかしそういう状況を回避するためには、“嫌だから抜ける”ということがつねに可能であるということが大事かなと思います。
ここから「地域」や「地域貢献」にできるだけ接近したいと思っているんですけど、この地域というのは物理的な離脱が困難なんじゃないかなと思うのですよね。私は「地域」というものについて深く考えられていると自分ではまったく思っていないので、これから述べることには誤解や偏見が含まれているかもしれませんが、地域からは脱けられない、少なくとも脱出しづらい、そこではその倫理的な活動というものが不可能なのではないか、そんなふうに思うのです。そうすると、地域貢献と言っているときに、それもその集団の論理にからめ取られてしまうのではないか。元々その地域貢献、この地域のために何かをしたいというふうに思っていた個人のやむにやまれぬ想いというものがうまく出てこないというか、それが活動の中で生きてこないような条件がその地域の中にあるのではないか。そのようなことをちょっと考えたわけです。
地域というのは集団なので、一種の道徳に覆われているわけですね。この地域はこうすることがよいことであるというような。一種の道徳。それに抵抗する個人の大切さという話もしたいというのが、今回の私の報告です。地域が持っている道徳に抵抗する個人というのをどうやって確保しているのかということが課題になるのかなと思ったということです。離脱が困難であり、その場にとどまらざるを得ないような状況で、それでもなお倫理的であることはいかに可能なのか。これが今回の自分の大きな問いだというふうに思っているのです。
集団が個人を尊重することができた場合には、その集団も、もしかしたら倫理的というふうに読めることもできるのかなという気もしながらも、最終的にはその個人を尊重するとは何で、そのためには何が必要なのかというところを考えながら、その地域の中で個人が個人として立ち現れるためには何が必要なんだろうかということを考えることが、共生というところから地域貢献に至る一つの道筋かなと思ったというのが今回の話でした。ありがとうございました。
私たちは集団から離脱することができるのか
ーー個人的な疑問で恐縮ですが、集団からの離脱って難しいのではないかなという感覚があります。最近、私(兼清)は、あるプロジェクトの話し合いから離脱したのですが、すごく罪悪感があったんですね。自分は無責任だなと。あるいは学生があるプロジェクトに取り組んでいるときに、「ちょっと休みたい」とか「別のことをしたい」ということを言ってくるときに、すごく申し訳なさそうに言ってくる印象があります。僕らからすれば、むしろそう言ってくれたことがありがたい側面があるのですが、多分本人はそう思っていないのではないかなと思うんです。言葉で「離脱の自由」というのはわかるんですけど、離脱する際に、罪悪感とか、自己肯定感が低くなるとか、関与しなかった無責任さみたいな思いとくっついてる感じがするのです。
多分それは道徳と倫理がせめぎあっているという状況だと思います。つまりなぜ罪悪感を覚えるかというと、その場、その集団の中にいったん入ったのであるならば、そこに最後までコミットし続けることが責任の果たし方であるという道徳を、その学生が常に内面化してしまっている、身体化してしまっているからですね。だからそこを脱けることに罪悪感を覚えることになる。逆にそういう道徳を身につけていない人だったら特に何も感じずに脱けることができるだろうと思って聞いていました。実際、今の説明が成り立つとすれば、罪悪感を感じるのだがどうしたらよいかということが、今後課題になってくると思います。
でも、その地域に貢献するなり、プロジェクトで何かをするなりというのは、その集団にいなければできないことなのかと考えると、たぶんそうではない。本人が嫌な気持ちを抱えたままその集団の中でなにかをいやいややるということよりは、離脱したうえで、別の形でそこに関わる、あるいは何も関わらないという関わり方をするということが意義として認められるべきなのではないか。遠回りで間接的なことかもしれないけれども、その個人にできることはまだあるのです。見えていないだけで。見えていることしか評価しないというのは間違いです。今の話は、橋爪先生の撤退というか、手を引くことと関わってきそうです。
ーー橋爪先生は、橋本先生のご報告に何かコメントはありますか。
橋本先生がおっしゃった最後の部分は、「悪の凡庸さ」で想定されている状況とは、状況のサイズが違うところもありますけれども、「道徳」と「倫理」という区別って、ちょっと面白いなっていうふうに思っています。アーレントだったら、例えば良心という言葉で説明していることと重なっていると思いました。いま橋本先生が触れたような事例は、集団そのものが倫理的におかしくなっている状況というのには限られないと思うので、そのあたりが微妙な違いになるとは思いますが。
その一方でアーレントも、「悪の凡庸さ」みたいな共同的な悪が現実となっているときに、そこから後退したり撤退した者は「無責任」という評価を受けたのだけれども、むしろそういう政治的共同体に加担しないことが本当の意味で「責任」を果たしていることになる、という話をしています。こういう部分は、橋本先生のおっしゃる「離脱」と結びつけて考えることはできるなと思って、伺っていました。
確かに私は「悪の凡庸さ」みたいな話をして、集団がまるごとおかしくなっているっていうときにそこから脱けるという、そういう倫理性の話を前の発表ではしたんです。ただそれは、“人間が協働しているからこそできることがあるよね”というベースがあったうえで、なんですね。例えば最初に大学の例を出しましたけど、大学というのが多人数の秩序ある協働によって成り立っているから、例えばこういうトークイベントもできる。このイベントも、秩序ある協働に与かっているっていうところも、やはり押さえておきたい点なんです。つまり「悪の凡庸さ」はあくまでエクストリームな、極端な状況であると捉えています。
同時に、私と橋本先生の思考のスタイルの違いも感じました。じつはこの間、橋本先生のご著書を読ませていただいたのですが、橋本先生は、やっぱりどこまでも前提を突き崩すというか、一度立てたものも懐疑によって打ち崩していくようなところがある。さきほど出されていた共生の定義もそうだと思うんですけど、やはり最終的にひとつのカテゴリーの固定化というところには行き着かないで、そのカテゴリーを打ち崩し続けていくところに倫理性を見ていく。ご自身の議論にたいしても、橋本先生がおっしゃる意味での「倫理」的な関わり方をしていると思ったんですよね。これが誉め言葉になっているのかはわからないですけど、批判的なスタンスというのがどこまでも通底した書物だと思って拝読したんです。
私の本は、アーレントの研究でまとめた部分というのは、我々は秩序だった仕組みを作り上げる、その中で安定して生きられている、そういうところを細かく描き出すような研究になっています。これは実はアーレントっぽくないんですよ。アーレント業界の中では結構珍しいタイプだと思っています。そういう意味で言うと、橋本先生と最後の違いが出てるなというのは、私は安定的なものをどう作り上げていくのか、どう秩序を作っているかというところにも関心があって、たまたま秩序自体がおかしくなっているところで、その秩序から外れるということを今回は主題化したのですが、橋本先生の研究ではそちらの方が、どちらかというとメインというところがあると思うんですよ。
そのなかで、伺っていて思ったのが、さきほど「やむにやまれぬ思い」というのが出てきたじゃないですか。これもまさにそういう問題と重なると感じるんですよね。集団では個人の思いをある程度抑えないと、集団的な秩序を作っていけないと思います。その場合、集団だからこそできることと、個人の思いというのが、なんていうかトレードオフ的なところがあるなと思って。逆に言うと、「やむにやまれぬ思い」というのをあまりに強調したまま、それを共同性の次元に持っていくというと、かなり専制的な形の組織形態にしないと実現ができないんじゃないかという気がちょっとしたんです。専制的というのが強すぎれば、「超トップダウン」的というか。ひとつの思いを軸に、それを実現するみたいな様態になっていっちゃいそうな気もして。そこを橋本先生がどう思っておられるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかった点です。
ーー橋本先生、いかがですか。
私は多分そういうふうには考えないです。つまり、共同性を特に志向しない。その個人の資格で活動するっていうのは、そういうところにも関係していて、なぜ人と一緒になにかをするのかという疑問があります。だから、ものすごく力をもった個人がですね、やむにやまれぬ思いを持って突き進んでしまったら、その専制的な状況に行きうるかもしれないと想像はするのだけれども、そもそもやむにやまれぬ思いが、例えば、共に何かをして、共に成し遂げよう、他者を巻き込もう、他者にも自身の倫理に従わせよう、そういうところを目指していない。そういう考え方を持っていたと今、気づきました。
ーー権力関係や上下関係があるなかで、手を引いたり、離脱したりするのは難しいのではないですか。
そうですね。まず大事なことは、離脱することができるということを認識しておくということですね。その人自身が離脱しなくても、しようと思ったらできるという状況が自分には保証されているということをわかってほしい。まわりもそのように認識しているということが重要だと思います。(例えば、学生と地域プロジェクトやるというときに、そういうことをちゃんと最初に確認をしてくれみたいなことですか?)。はい。そのうえで、やっぱり難しいと思うんです。例えば、その地域に家を建てたら、簡単に出ていけないですよね。だから、考えたいことはその離脱が困難な状況の中でも、その個人が倫理的にふるまえるためには一体何が必要なんだろうかということであり、その発言の自由とか離脱の自由のほかに、個人を個人として尊重するために必要なことがあるとするならば、それはいったいどういうことかということを考えたい。
ーー橋爪先生はいかがですか。
権力関係があって、離脱が難しいという点について言うと、私個人の考えとしては、そういう事象はどうしたって人間共同体の一種の自然として絶対起きてくると思います。私自身は、それを見越したうえで、そういうことを防ぐようなメカニズムを仕組みとして入れるという発想を取りたくなります。この点は、橋本先生の考えている対応に通ずる部分も通じない部分もあるかなと感じます。入り口の部分では脱けられるということを認識するべきだというふうにおっしゃったときは、「いや、でもやっぱり脱けづらいシチュエーションってあるんじゃないのかな」「現実に脱けられないってことあるんじゃないかな」みたいなことを思いました。たとえば、脱けることはできるけど、その場合生活の資が立てられなくて生存が難しくなる、ということになったら実際には脱けられないことになっちゃうので、そういう部分を議論の中で確認するというんですかね。そういうのをなにか予防メカニズムの仕組みとして入れていくという発想になってくると思うんです。私はそういう発想になりがちですね。
地域でイベントを開催した経験から
ーーコメンテーターの斉藤さん。これまでの議論でコメントはありますか。
話を聞いていて、自分の経験してきたことを客観的に捉えることができました。最近、先生方のお話をなぞるような感覚をずっとしていました。私は、甲府の中心街で「豊かなウイークエンド」というテーマタイトルでイベントを開催したんです。これは、普段使われない公共空間、道路も含めて普段使っていないものを土日に使おうという趣旨のイベントでした。道路を通行止めにして、道路の真ん中でバーベキューをしたりとか、舞鶴城でブレークダンスをしてみるとか、県庁の噴水広場を開放して子供たちが水遊びをできるようにするとか、芝生広場でサウナをやってみるとか、普段なかなか使う機会がないところを土日に使うイベントをしました。
このイベントは、普段使わない公共空間を使って甲府の魅力を発信しようという、普段やらない非日常的な行動をして甲府でこんな楽しいことがあるんだみたいなものを見つけていこうというのが最初の目的でもあったんです。ただ、もともと街を豊かにしようとか、街を盛り上げようと思って、サウナをやっている人はいないし、バーベキューをする人も地元住民に喜んでほしいからと言ってバーベキューをしているわけではなくて、個人が元々好きとか楽しいという純粋な気持ちでやっていたものが、急に集団になったときに、大義というか、街を豊かにしよう、甲府の魅力を発見しようというようなものが一つの目印になったときに、なんか急に形が変わってしまったり、義務感にかられてしまったり、私達自身が企画したことでさえ、「途中、何のためにやってるんだろうな。なんのためにバーベキューしようと思ったんだろう」となってきてしまって。
他者と共生するっていうのがすごく大切で、切っても切れないような地域というところもそうなんですけど、離脱するのが難しいところで、今回のイベントは、元々イベントがなかったものを、自分たちで企画してやった、自分たちで集団というか、ものを作り上げたという形になるので、離脱という概念がそこにはなかったのか、そもそも、みんなでやろうやろうっていうふうにぐいぐい形を作ってしまったことによって、そこに離脱できるという余白を作れなかったし、目的そのものもだんだん歪んでいってしまう。
ただ、楽しかった。地域の人がふだん使えない公共空間を使えて楽しかったよとか、そういう声はいただいたんですけど、ただ何か、個人ひとりひとりとしてのやる気、モチベーションがだんだん薄れてきて、大義名分のために取り組む形になってしまったというのが、今日の話を聞いて、すごく自分の中で感じるところがあって。地域という文脈で言うと、本当にいろいろな人がいて、年齢もそうだし性別もそうだし職業もそうだし、いろいろな属性の人たちがいる中で、私はこの話を聞いて、街を豊かにするとか、一つの目的のためだけに動く必要はないんだなということに気付かされました。
自分が楽しいからやるというのもひとつの理由だし、誰かとやるのが楽しいというのもひとつの理由だし、街を豊かにするとか抽象的な言葉ですべてをくくろうとしなくていいんだなというふうにおもいました。
組織の中での小さな抵抗
ーー橋本先生、斉藤さんのコメントに対して何かコメントはありますか。
やりたい人が集まって何かをしていくみたいな話があって、それはアソシエーションという言い方もできるだろうし、社会学だとゲゼルシャフトとゲマインシャフトみたいな言い換え、区分で理解することもできるなと思って、何かそのへんを丁寧にみていく必要があるなと思いました。
道徳と倫理の両立という話題に関係するのかもしれないのですが、権力関係があるから組織の中から脱け出せない、その組織にとどまらざるを得ないという状況の中で、組織の中で何か小さな抵抗するということは可能かなと思いました。例えば、ちょっとさぼるとかですね。大学の中でもそういうことがありますね。書類を作って出すとか、やらなきゃいけないことは一応やるのだけれど、そのときに「本当にこれ、やるべきことなんですかね」「他にやり方ないんですかね」って一言添えるとかですね。個の集まりであったはずの集団や組織は、いつの間にか個から離れてまったく異なる論理で駆動し大きな流れを作るということがありますから、それを小さくても短くても少しだけでも攪乱する。そういうちょっとした小さな抵抗をそれぞれの持ち場において行なっていることが意味を持ってくるかもと思いました。それはそれぞれが銘々にやっていかないと、組織全体を変えるというところには行き着かないと思いますし、時間もかかると思うのですが、それでもそれぞれがその場で小さな抵抗を積み重ねていくこと、倫理的であろうとすること、個としてあろうとすること、そういうことは少なくともやっていかないと何も変わらないだろうと思います。
人間と人間を協働させるコスト
ーー橋爪先生はいかがですか。
いま橋本先生がおっしゃっていたことって、ちょっと面白くて、なんかやりたくないけどやるというか、それ確かに大学でもというか、どんな組織でもあると思うんですよね。
アーレントは人間を、たくさんの人が集まることによって――物理的に集まってなくてもいいんですが――いろいろな人が連携することによって制度みたいなものを作り出していくものと捉えています。アーレントはそこに人間の大きな力を見ていて、そういうものを作り出すことができるのは人間特有のパワーだというんですよね。だけど、その裏返しとして、私たち人間って、協働を調整するということにいつもものすごく膨大なコストを割いているなという気はするんですよ。例えば、この場を作るために事前に打ち合わせをする。いや、このイベントの打ち合わせは楽しいんですけどね。でも、これが規模が大きくなると大変で。例えば、今度このイベントをやるために事前の会議をやろうって言って、バラバラに働いている大学教員を10人ぐらい集めようとすると、その日程調整だけでめちゃくちゃたいへんだったりするんですね。「『人間を集める場を作る』ために事前に集まる」コストだけでめちゃめちゃ膨大なんです。人間と人間を協働させるコストってそれだけ大きい、我々の費やしているコスト全体の半分ぐらいはそれに費やしてるんじゃないかって思うぐらいです。大学というのは組織なので、組織をひとつのいわばメカニズムとして動かしていくためには、比喩的に言うと、それを円滑にするために壊れたものを取り替えたり、油をさしたりみたいなことをしなきゃいけない。現実的には、例えばルールを書き換えるとか、そういうようなことが必要だったりするわけです。例えば、授業をやるということは、いろいろな人びとの協働の賜物だと思うんですけど、その場を実現させるための前段階に、膨大にそういうことがある。
“やりたくないけどやる”ことの中には、本当に必要なのかどうかわからないことがいっぱい含まれていると思います。この書類は、“全くいらない”ということにしちゃうと多分いろいろ問題が起こってるんだけど、でもいちいちこれを書くみたいなことが本当に個別レベルで必要なのかというと、よくわからない。こんな面倒な書類、書かなくていいんじゃないみたいに思っちゃうものがあるとかですね。でもその中に本当に必要なものもまぎれ込んだりしてる。それを腑分けするのって、すごく難しい。今は斉藤さんがおっしゃってくださったことは、そういういろいろな思惑を抱えたプレーヤーというのを協働させるということが持っているコストの部分というのもあるのかなっていう気がしたんですよね。
だから最初の橋本先生の言い方じゃないですけれども、何ていうか、やむにやまれぬ思いというんですかね、それがそのままストレートにずっと先まで行くっていうことは、ほぼあり得ないわけですよ。プレーヤーがたくさんいると、それがジグザグしてくることになっていく。そうすると、みんな自分がやっていたことがだんだんわからなくなってくる、みたいな。
でもだからこそ、こういうふうな場を作れているみたいなそういう面も何かあって、そこがすごく両義的な受け止めをしてしまいますね。今日は微妙に保守的な落としどころが多いんですけど、そんなことを思いました。
悪に基準はあるのか
【フロアからの質問】
ーー私は情報学が専門なんですけど、橋爪先生がおっしゃった悪というのがすごく気にしています。いわゆる機械が何かを処理して出した結論は、完璧にローコストで論理的にも問題がない結論を出したときに、それが悪いかどうかという判断は結局人間によるという問題と絡んでいるんじゃないか。情報学は哲学と距離があるように見えるんですが、本当は形而上学の流れで情報学があるので。それで、何かを定格化して発見して出した結論、推論をした結論、あるいは「トロッコ問題」のような問題を考えたとき、悪いという基準は、コミュニティの離脱も同じ問題なんですけど、そのコミュニティだったり、その人が持っている人格だったり、先入観かもしれないかということが気になります。もちろんナチスがよいことをしたという意味ではないんですけど、あの中の組織をまとめるために、いわゆる感情をあおって、そういう結果になったとしたら、あの集団とうまくいくための選択の一つだったかもしれない。例えば、私は4月に山梨に引っ越ししてきまして、どこに住むのか悩んでいたとき、犯罪統計を見て犯罪が少なかった街を選びました。これが差別になるのか。差別とはまた別の問題だと思いますが、そういうことを言うと差別だと思われる。だからバイアスというものが、悪と言っていいのか。橋爪先生と橋本先生はこの悪という基準をどういうふうに思われているのでしょうか。
(橋爪先生)すごく興味深い質問です。今日の話ともアーレントの話とも離れた感じの回答になるかもしれないんですけど、確かに機械が一定のアルゴリズムというか、計算に従って最適な最もローコストな結論を推論するというのは多分おっしゃる通りかなと。それが悪か否かというところには、何て言うんでしょう、その計算結果をどういう価値づけにおいて判断するかというところが大きいのかなという気がしています。
人間存在は生命活動している存在者なので、単純に物質的な存在者とは違って、一定の危害を加えると死んじゃうような存在者でもあるし、それと強く紐づく形で苦痛などを経験する存在者でもある。何を悪とし善とするかは、ある種の規範倫理学的な問いとかメタ倫理学的な問いになってくると思うんですけれど、ひとつにはそういう生物として持っている特性から、あるタイプの悪は特定できそうな気もするんですね。要するに、仮にAIが“人間に危害を加える”みたいな結論を出したら、容認しがたいというところが出てくるんじゃないかなと思いました。つまり、善とか悪というカテゴリーが存在してくること自体が、人間の存在の仕方と密接に結びついて出てくるのかなと思います。
ただし、個のレベルで言うと単純なわけで、例えば、私は急に何か切り付けられたりすると、苦痛が生じたりするし、死んじゃったりするかもしれないので、やっぱりそれは端的に言って私の生にとっては悪なんだけれども、それが社会というレベルになってくると、あることがいいのか悪いのかというのは複雑な判断になってくると思います。それでも、集合的なレベルに行っても基本線はそこなのかなという気がしていて、我々がある種の傷つきやすさみたいなのを抱えた存在であるからこそ、あるものは我々にとって悪として現象してこざるを得ない。さらに苦痛や害悪を社会的に低減させるメカニズムが出来上がってくると、そのメカニズムを打ち壊すようなものも悪として捉えられるようになる。こういう連関はあるような気がしています。
(橋本先生)いや、まとまりませんでした。悪とは道徳に対する挑戦だとすれば、道徳がなければ悪もないことになり、倫理も悪ということになる。ナチスのことを踏まえれば道徳的な悪もありそうで、そのとき倫理こそが正しいことになるのか、そのときの正邪の規準とは何かといったことを考えていましたが、うまく思考を組み立てられませんでした。ただ情報学あるいは存在論からの問題提起は重要だと思っています。そういう存在に関わる議論と、規範的な議論、そして実践の議論というそれぞれの岸壁にどうやって橋を掛けていくのかというところが課題だと思っていて、引き続き宿題にさせてほしいと思いました。
まとめ・謝辞
以上、2023年10月27日に山梨県立大学飯田キャンパスC101教室で開催されたイベントの内容を一部、加筆・修正し、記録しました。このトークイベントは3回シリーズで、次は2024年1月に開催する予定です。もう一度大学で開催したあと、会場を大学から街の中に移して開催してみたいと考えています。
なお、このイベントは、山梨県立大学地域研究交流センターの地域貢献実践事業として開催されました。関係者の方々のご支援に感謝の意を表します。
また、素敵なロゴとポスターをつくってくれた山梨県立大学国際政策学部の折井穂乃花さんにも感謝の意を表します。

